第2章 バングラデシュ国の政治経済情勢と開発計画
2.3 貧困の状況
開発計画では「貧困緩和」を最優先課題と認識し、各ドナーやNGO、および我が国援助計画においても同様である。各セクターの個別計画においても、貧困の緩和は個別開発プログラムが最終的に寄与すべき課題として認識されている。バングラデシュ政府の開発プログラムの他、現地NGOも農村および社会開発の分野で、貧困削減プログラムを積極的に展開している。以下、バングラデシュ国の貧困の要因、状況、および特性について簡潔に述べる。
2.3.1 貧困の要因
バングラデシュ国の貧困の原因や要因については、これまでに数多くのドナーや研究者が議論を行っている。バングラデシュ政府が作成したMemorandum for Bangladesh Development Forum 2002-2003(以下、バングラデシュ政府メモランダム)3やバングラデシュ側の貧困関連文献より、概ね以下の事項が要因として集約される。
【人為的要因】
- 雇用と経済活動機会の不足
- 教育、保健サービス、その他社会的行政サービスの質の低さ
- インフラ(道路、電気、港湾施設、通信および情報伝達手段、貯蔵庫など)の不足
- 社会的資本(住民間のネットワークや互助機能など無形の資産)の機能不足
- 土地や資産など富の不平等な分配構造
- 政府実施機関における開発プログラム間の調整不足
- 民主的政治過程と決定の欠如
- 法と秩序の欠如または弱さ(組織的犯罪、強奪、経済活動妨害など)
- 地方自治と地方分権化の機能不足
【自然要因】
- 肥沃な壌土など人口扶養力(Carrying Capacity)の高さが招く高い人口成長率
- 自然災害に対する脆弱性
Bangladesh: Progress in Poverty Reduction 2002(以下、貧困削減に関する進捗報告)4では、貧困率が非識字層、土地無し層、および賃金農業従事者に高いことが報告されている。貧困の分布をみると、洪水が頻発するような脆弱な地域およびチッタゴン丘陵など少数民族が居住する地域に貧困層の分布が見られる。
問題は、以上の要因が組み合わさることで「貧困の悪循環」過程を生じさせることにある。貧困の悪循環は、貧困層を貧困のまま停滞ときには悪化させ、一方で富裕層には財や資産の蓄積が進む状態を作り出す。政府、ドナーおよびNGOが貧困の緩和に向けての課題は貧困の悪循環の裁ち切りであるが、実施される取組み策は支援者間で多様である。
2.3.2 貧困率の推移
貧困の削減に対する取組みの結果、70年代には約70%を占めた貧困率は、2000年現在で約50%に低下した。90年代に入ってからは、「貧困の削減」が開発計画上で最優先の課題として位置付けられ、ドナーやNGOの直接的な貧困対策支援も格段に増加した。90年代の貧困削減の推移は以下の表のとおりである。
基本的な生活に必要とされる支出以下で暮らす貧困率(Head-count-ratio under upper poverty line by Cost-of-Basic-Needs method)は全国レベルで1991年度の58.8%から2000年には49.8%まで低下した。最低限の生活に必要とされる支出以下で暮らす最貧困発生率(Head-count-ratio under lower poverty line by CBN method)は1991年度の42.7%から33.7%に改善した。
顕著な改善を示したのは農村部であった。貧困発生率は同期間で61%から53%に削減、最貧困発生率については46%から37%に低下した。しかし、農村部には未だバングラデシュ国人口の約4分の3が暮らしており、結果的に貧困者数もおよそ85%が農村部に集中している。
|
表2-3-1 貧困率の推移
|
そして、未だ約6,300万の人口が貧困線以下の暮らしを強いられ、人口の半数が貧困者に分類されている。加えて特筆すべきは、都市部での貧困率の推移である。90年代の前半は大幅な改善基調にあったものが、後半は若干の悪化傾向に転換している。世銀およびADBが作成した「貧困削減に関する進捗報告」では、農村部から都市部への急激な人口流入が主な原因の一つであろうと推察している。農村部と都市部との所得水準の差が、都市部への流入を促す要因であろうと指摘している。
なお、農村部の貧困状況は改善基調にあるが、最貧困率から判断しても依然農村部の貧困発生状況は高い(都市部の2倍)。貧困が絶対的多数存在するゆえ都市部への流入が起こるとすれば、代表的な農村成長地域や中核都市を各地に形成し、農村人口の生計を向上させうる手立てが求められるものと考えられる。
地域間で貧困率の推移状況をみると、90年代のチッタゴン地域の状況があまり芳しくない。チッタゴン地域は近隣の丘陵部にあまり政府の開発プログラムが浸透していないHill Track地域を含んでいること、都市部への他地域からの人口流入が激しかったことが要因として考えられる。
|
表2-3-2 地域(Division)間の貧困改善の推移状況
| |||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3 所得格差の推移
世帯間の経済状態の格差を示すジニ係数によれば、全国的に所得の格差が広がる傾向にあることが判る。農村部の格差拡大は比較的緩やかであったが、都市部の所得格差の拡大が顕著であった。
|
表2-3-3 所得格差の推移
|
全国的な貧富格差拡大の傾向は、概ね富裕層への富の集中によるものである。しかし、農村部では薄く広くではあるが確かに貧困の緩和が進んでいるものと考えられる。徴税制度の徹底を含めた所得分配システムの機能化が望まれる。
なお、下位と上位所得層の支出拡大動向(成長の裨益度合い)は、以下の1人当り年間支出額成長率の所得階層別分布(貧困削減に関する進捗報告より引用)で説明できよう。
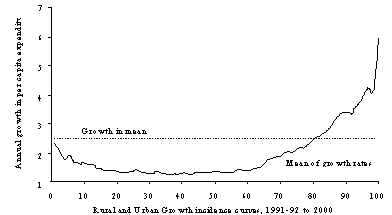
以上より全国平均してどの所得階層も支出額の年間成長率は少なくともゼロ以上ではあったことが判るが、1人当り支出額の年間成長率は最貧層を出発点に、所得水準が高くなるにつれまず低減する傾向にある。そして中間所得層を超えた地点から段階的に増加し、高所得層になると急増している。つまり、成長の裨益効果は特に高所得層に向かい、貧困者層への生活水準は改善はしたものの依然緩やかであったことが伺える。
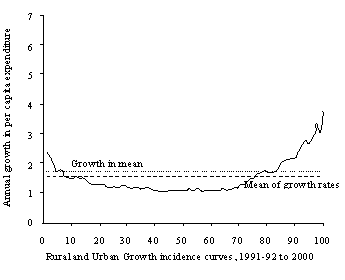 |
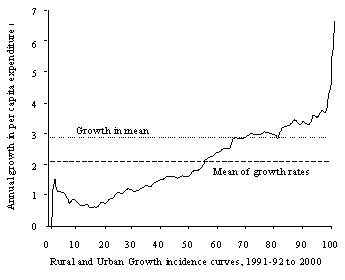 |
| 上図(同じく貧困削減に関する進捗報告より引用)は、支出額成長率の所得階層別分布を都市部と農村部に分けたものである。都市部では成長の裨益度合いが富裕層において極めて高く、裨益分配の偏りを示したのに対し、農村部では比較的公平に行き渡った傾向が推察される。 |
2.3.4 非所得面の貧困状況(基本的ニーズの充足)
貧困は、所得面だけでなく、健康および栄養状態、教育水準などの非所得面からも確かめるべきである。1980年から現在にわたる非所得面の貧困緩和の推移を次表に示す。なお、非所得面の貧困改善を示す基本的ニーズの充足状況は、我が国の重点分野でもある社会開発分野で取組まれる課題であり、詳細は第6章の社会開発分野の項に委ねる。
都市部の貧困悪化に係る説明のとおり、貧困緩和に係る取組み課題は農村部における雇用機会の創出と都市部における行政サービスの拡充およびフォーマル・セクターの成長である。農村部におけるインフラ整備とともに、教育、職業訓練、保健サービスの拡充による人的資源の開発も必要である。次表に示すとおり、1980年代初頭より現在にかけて、全体的に基本的ニーズの充足状況は急激に改善した。貧困指標(非所得面の貧困発生率)が1980年代前半の61%より現在は35%まで低下していることからも明らかである。しかしながら、フォーマル・セクターの経済活動を担える人材が依然不足しているのは事実である。
|
表2-3-4 非所得面での貧困緩和の推移
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、PRSP進捗報告によれば、概して所得貧困より、非所得面の貧困緩和の速度が速く、1990年代に入っても緩和速度が維持されていることが明らかにされている。
2.3.5 貧困削減戦略ペーパー(PRSP)の概要
現在バングラデシュ国では、より包括的な貧困緩和への取組み方策を構築するため、貧困削減戦略ペーパー(PRSP)を策定途中である。2002年6月には中間PRSPがドラフトされる予定にある。2002年3月、パリに於いて行われたドナー会議上発表されたバングラデシュ政府メモランダムでは、以下の4つのアクション・パス(Four Broad Action Paths)からなる戦略を置き、これらに沿った開発プログラムが形成、実施への優先付けがなされる想定にある。
| 1) |
貧困削減に向けた経済成長の増進(以下の事項を促進して実現される)
1-1) マクロ経済の安定 1-2) 農業成長に貢献する新技術の導入 1-3) 農産物の多様化 1-4) 最貧困層の与信サービスへのアクセス拡充 1-5) 農村部における農業外活動と都市農村間のリンケージの拡充 1-6) 道路、電力、通信網の整備拡充 1-7) 技術の革新(情報通信、バイオ) |
| 2) | 貧困層に向けた人的資本開発の増進(教育、保健医療、栄養面サービスの拡充)
|
| 3) | 社会的安全網(Social Protection)の強化
|
| 4) | 参加型行政の展開と女性の進出とジェンダー格差の解消 4-1) 地方行政の強化 4-2) 開発主体間(NGOと政府)の調整 4-3) 不公平さの撤廃につながる政策と制度の準備 |
3 Memorandum for Bangladesh Development Forum 2002-2003, Paris, March 13-15, 2002(Ministry of Finance, ERD and Ministry of Planning, Planning commission, GRD)
4 As Background paper for Bangladesh Development Forum, Paris, March 13-15, 2002(World Bank & ADB)

