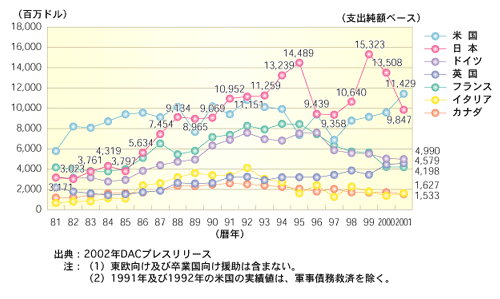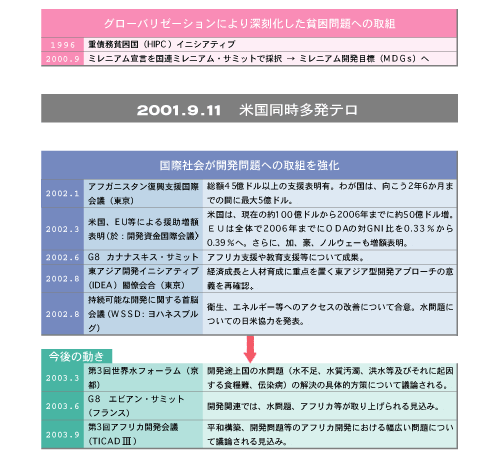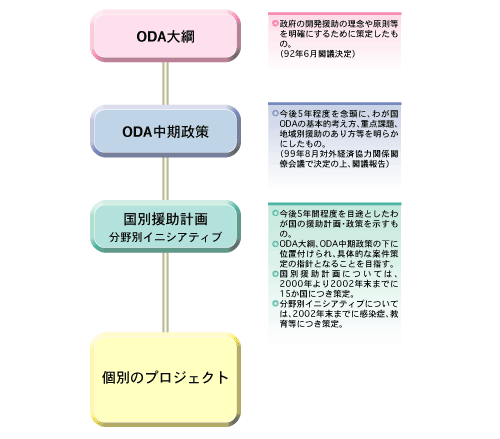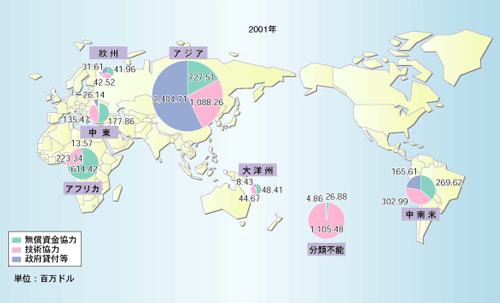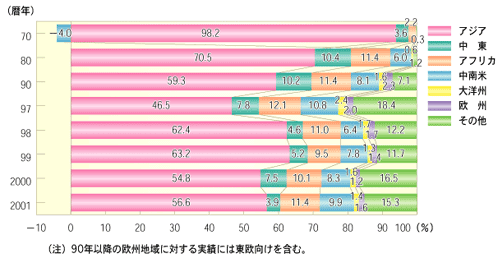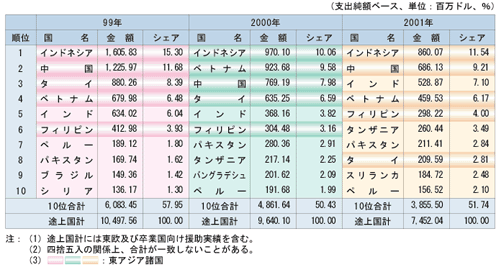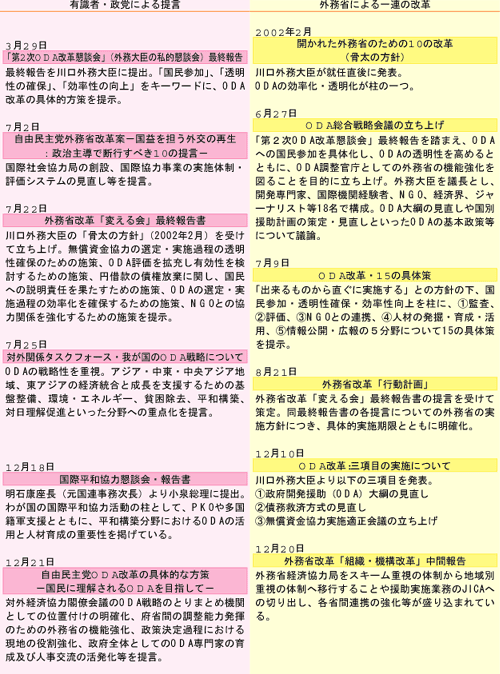政府開発援助(ODA)白書 2002年版の要旨
平成15年4月
|
激変する国際社会におけるわが国ODAの展開 過去数十年の国際社会の努力により、途上国の開発問題は、多くの面で良い方向に推移。しかし、依然として、途上国は多くの困難に直面しており、特に、グローバル化の進展や2001年9月の米国同時多発テロなどを契機に、国際社会の開発問題への関心が増大。 第1節 開発問題への国際的関心の高まり ● グローバル化の進展の中で格差が拡大し、貧困が深刻化。また、環境問題や感染症など地球規模の問題も依然として深刻。さらに、冷戦終了後、紛争、特に国内紛争が頻発し、紛争予防、緊急人道支援、平和の定着と国づくりといった取組が増加。途上国への民間投資等が減少傾向にあることも、途上国の開発に打撃。 ● 国際社会では、開発目標の共有と新たな開発戦略の構築が進展。特に、ミレニアム開発目標(MDGs)は、貧困削減、基礎教育、保健医療などに関する具体的な達成目標を設定。開発戦略に関しては、援助国、国際機関等が貧困削減に直接焦点をあてて協調を活発化。 ● わが国は、経済成長を通じた貧困削減が重要との考え方に立って、経済セクター支援等を通じた貿易・投資の促進にも協力。 2節 開発に関する一連の国際会議 ● 2002年には、開発資金国際会議(3月)、G8カナナスキス・サミット(6月)、持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)(8月-9月)といった国際会議が相次いで開催され、開発が主要議題の一つとなった。 【図表I-2:米国同時多発テロ前後から現在までのODAを巡る動き】(白書案より抜粋) ● これらの会議での主要な議題は次のとおり。
-ODA、民間資金(投資や貿易)等あらゆる手段を通じた開発資金の確保。
-援助手続きの調和化を通じた援助の効率化
-途上国における、民主制、法の支配、腐敗防止といった良い統治(グッド・ガバナンス)の確保
-途上国への選択的な援助の実施
-NGOや民間部門との連携強化
● わが国は、アフリカ、教育、持続可能な開発について、「小泉構想」をはじめ、各種のイニシアティブを発表。また、わが国は、ODAが減少する中で、国際会議における合意を着実に実施するために、援助のさらなる重点化・効率化、債務問題への取組、NGO等とのパートナーシップの強化などを推進。 ● わが国は、経済成長を通じた貧困削減が重要との考え方に立って、経済セクター支援等を通じた貿易・投資の促進にも協力。
国際的に開発問題への関心が高まっていく中、わが国も限られたODA資金をより有効に活用するため、ODA戦略をこれまで以上に明確化し、重点や優先順位を定めていくことが必要。 第1節 わが国ODAの全体像 ● わが国は、地域的にはアジアを、開発戦略としては経済成長を通じた貧困削減と人・制度づくりを重視した援助を実施。その際、わが国の経験やノウハウを活用。 ● 平和と安定へのODAの活用や人間の安全保障、ミレニアム開発目標(MDGs)の達成といった取組も重視。 第2節 アジアを中心に世界に展開するわが国ODA ● 東アジア諸国は、わが国ODAの半分以上が実施されてきた地域。わが国は、貿易・投資と連携したODAを進めることで地域の目覚ましい発展に貢献。 【図表I-11:わが国二国間ODAの地域別配分】 【図表I-12:わが国二国間ODAの地域別配分の推移】 【図表I-16:わが国二国間ODAの10大供与相手国・供与額】(いずれも白書案より抜粋) -中国については、2001年10月、「対中国経済協力計画」を策定。思い切った見直しの結果、2001年度の円借款は、前年度比約25%減。
-東南アジアについては、経済連携の強化に向けて、メコン地域開発や政策支援を実施。
-2002年8月には、地域開発協力を構築し、また、東アジアの経験を世界に発信するため、東アジア開発イニシアティブ(IDEA)閣僚会合を開催。 ● アフリカ地域については、アフリカ自身のイニシアティブである「アフリカ開発のための新たなパートナーシップ」(NEPAD)を支えていく。このため、わが国は、2003年、第3回アフリカ開発会議(TICADIII)を開催する予定。 ● その他の地域についても、それぞれの地域のわが国にとっての重要性、開発ニーズなどを踏まえ、必要な協力を実施。 第3節 平和の定着と国づくりへの協力 ● 2002年5月、小泉総理はシドニーにおける政策演説で、「紛争に苦しむ国々に対して平和の定着や国づくりのための協力を強化し、国際協力の柱とする」との決意を表明。
-わが国は、東チモールやアフガニスタン、スリランカ、インドネシアのアチェ、フィリピンのミンダナオなどにおいて、和平プロセスの促進、治安への支援、人道・復旧支援といった具体的な取組を実施。
第4節 人間の安全保障の推進 ● わが国は、人間の安全保障の考え方に基づいて、難民・避難民、地雷、教育、保健医療、ジェンダーといった分野におけるODAを積極的に推進。
-「人間の安全保障基金」(わが国は、2001年度までに累計約190億円拠出)は、2003年1月末現在で72プロジェクトを実施。
-2003年度より、従来の草の根無償を拡充し、草の根・人間の安全保障無償を導入することとしている。
第5節 ミレニアム開発目標(MDGs)(注)の達成に向けた努力 ● MDGs達成のため、わが国は、経済成長を促す支援を行うと同時に、社会セクターへの直接的な支援を強化。
-教育については、2002年6月、わが国の教育支援策を発表(基礎教育の普及を重点として、向こう5年間で低所得国に対し2,500億円以上の支援を行う)
-感染症については、2000年に発表した沖縄感染症対策イニシアティブを着実に実施していく。
-環境については、2002年8月に「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ(Eco-ISD)」を発表。
-水と衛生については、本年3月の第3回世界水フォーラムや6月のG8エビアン・サミットを見据えて取組を強化。その一環として、ヨハネスブルグ・サミットに際し、日米協力イニシアティブを発表。
(注)ミレニアム開発目標:貧困、教育、保健、ジェンダー、環境等について具体的な達成目標と年限を定めたもの。96年のDACの国際開発目標と2000年9月の国連ミレニアム宣言等を発展的に統合。
第6節 国際連携の推進 ● MDGsの達成に向けて、ますます効率的・効果的な援助が求められる今日、わが国は、被援助国や他の援助国との政策協議を強化するとともに、それらの国々や国際機関などとの連携を推進。
-途上国間の協力である南南協力を積極的に推進。特にアジアの開発経験をアフリカに活かすため、アジア・アフリカ協力を積極的に推進。
-他の援助国とは、政策協議を緊密に実施。さらに、一部の国については、共同イニシアティブや共同プロジェクトも実施。
-世界銀行、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)等国際機関とも政策対話や共同プロジェクトを実施。
第1節 ODAを巡る厳しい国内状況と改革の加速化 ●長引く経済不況と財政状況の悪化もあり、国内のODAに対する見方は厳しさを増している。ODA予算は98年度以降減少の方向にあり、特に2002年度のODA予算は、前年度比10.3%減という大幅な削減。 ●ODAは国民の税金から成り立っており、その実施に当たっては、国民の支持と理解が不可欠。外務省は、2002年、透明性、効率性、国民参加をキーワードに様々なODA改革の具体策を実施。また、ODAの戦略性を高めるための取組にも着手。 【I-27:2002年のODA改革を巡る一連の動き】(白書案より抜粋) 第2節 ODA政策の立案機能の強化 ●ODA関係府省庁間の連携を強化。そのため、「対外経済協力関係閣僚会議」を一層活用するほか、2002年11月、被援助国への資金の流れ全体を見る枠組みとして、資金協力連絡会議が発足。 ●JICAについては、2002年の臨時国会で「独立行政法人国際協力機構法」が成立。これにより、2003年10月1日からJICAはより自律的に事業を実施。 ●2002年6月、外務省は、国別の援助計画、分野別の重点化、他のODAの重点課題について高いレベルで議論するため、ODA総合戦略会議を設置。 第3節 国民参加型援助の推進 ● 政府は、NGOや地方公共団体等との連携強化、人材の発掘・育成・活用、開発教育、情報公開・広報に努力。
-2002年には、NGO・外務省定期協議会を充実し、在外公館とNGOとの定期協議(ODA大使館)を導入。
-2002年度より円借款について「本邦技術活用条件」を導入。
-ODAメールマガジンの発行やODAタウンミーティングの開催。
第4節 DA事業の各過程における透明性・効率性の向上 ●円借款の候補案件リスト(ロングリスト)の公表や無償資金協力実施適正会議の開催等を通じ、透明性を向上。 ●JBICでは、2002年4月、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」を策定・公表。JICAにおいても、環境ガイドラインの改訂作業に着手。 ●調達については、不正が行われた場合には、当該業者を一定期間ODA事業の入札・契約から排除する仕組みを整備。 ●監査については、円借款調達手続きの外部専門家によるレビューの対象国の拡大、無償資金協力の第三者機関による監査の導入、抜き打ち監査の導入等を推進。また、監査結果のフォローアップを行う仕組みを整備。 ●評価については、全ての事後評価に第三者の視点を導入。被援助国の評価能力向上を目指しワークショップを開催。 ●政府としては、今後、更なるODA改革を進めるとともに、アジア地域への重点配分、平和構築の重視、人間の安全保障の重視、国民参加・顔の見える援助を進める。 ●また、わが国の援助理念や援助戦略をより一層明確にする必要がある。そのため、外務省は、2002年12月にODA政策の根幹をなしているODA大綱の見直しに着手。見直しにあたっては、特に次の点を重視する。
-人道的見地等の「普遍的価値」とともに、わが国にとっての安全と繁栄等を加えてODAの基本理念を明確に示す方向で検討。
-アジア重視、平和構築分野へのODAの積極的な活用、人間の安全保障等を中心として、重点化を図る。
-政策立案・実施体制の明確化、国別援助計画の充実など戦略性、機動性、透明性、効率性を確保する方策を盛り込む。
|