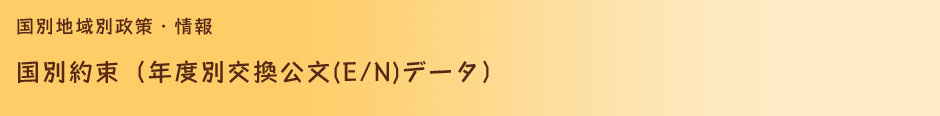国連世界食糧計画(WFP)を通じた食糧援助について
平成18年12月15日
- 我が国政府は、国連世界食糧計画(WFP)を通じ、地域の平和と安定に大きな影響を及ぼし得る国・地域や、不安定な移行期の中で食糧を必要としている国について、合計9億3,000万円の食糧援助を行うこととし、このための書簡の交換が、日本時間12月15日(金曜日)、ローマにおいて、我が方中村雄二駐イタリア国大使と先方シーラ・シスルWFP事務局次長(Ms. Sheila Sisulu, Deputy Executive Director)との間で行われた。
今回の食糧援助の対象内訳(カッコ内は供与額)。
(1)マラウイ社会的弱者 (2億円)
(2)シエラレオネ社会的弱者 (1億7,000万円)
(3)スワジランド社会的弱者 (1億円)
(4)ザンビア社会的弱者 (1億5,000万円)
(5)ジンバブエ社会的弱者 (1億5,000万円)
(6)パレスチナ自治区住民 (1億6,000万円) - マラウイ、スワジランド、ザンビア、ジンバブエを含む南部アフリカ地域は、世界で最も高いHIV/AIDSの感染地域となっており、このことが労働生産者層に影響を及ぼし、その結果、農業生産性低下や食糧生産量減少に繋がり食糧不足の一因となっている。さらに、HIV/AIDS感染者、結核患者等の社会的弱者は極度の貧困であるために、たとえ穀物の生産状況は良好であっても、食糧を購入することができず慢性的な食糧不足の状況となっている。国別の現状については、マラウイでは約80万人が食糧不足であり、5歳未満児童のほぼ半数は慢性的な栄養失調にある。スワジランドでは成人のHIV/AIDS感染率が33.4%であり、国民の12%が栄養失調にある。ザンビアでは国民の3分の2が必要とされる基礎的栄養を満たすことができていない。ジンバブエについては、WFPによれば近く140万人の食糧支援が必要となるとしている。WFPはこれらの国々を含む南部アフリカ地域におけるHIV/AIDS患者等の社会的弱者に対象を絞った食糧支援事業を2005年1月から行っており、2006年11月から2007年3月の期間については430万人の裨益者を目標としている。
- シエラレオネについては、1991年から始まった内戦が2002年に終了した後、本格的な復興に向かっているところであるが、依然として多くの住民は慢性的な食糧不足に直面している。WFPは2005年1月から国内避難民、帰還民やその他社会的弱者を対象に食糧配給事業を実施しており、2007年の裨益目標者数を約10万人としている。
- パレスチナについては、我が国としてはパレスチナ人の生活状況の更なる悪化を防ぎ、和平志向の民意を支える観点から、人道支援を行うものである。WFPは、西岸およびガザ地区に居住する難民以外の住民(孤児、老人、栄養不足の児童、病弱者等)を対象に2005年9月から食糧を配給している。
- 我が国による、以上のようなWFPによる食糧配布事業支援は、これらの地域の食糧不足の軽減及び経済・社会の安定に貢献するものである。