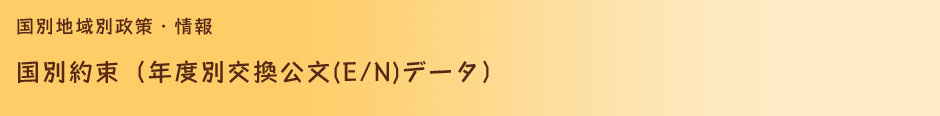ミクロネシア連邦の「ウエノ港整備計画」に対する無償資金協力について
平成18年8月9日
- 我が国政府は、ミクロネシア連邦政府に対し、「ウエノ港整備計画」(the Project for the Improvement of the Weno Harbor)」の実施に資することを目的として、総額7億2,500万円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が8月9日(水曜日)、ポンペイ州パリキールにおいて、総理特使としてミクロネシア連邦を訪問中の沓掛防災担当大臣も署名式に同席の下、我が方滑川雅志駐ミクロネシア連邦大使(フィジーにて兼轄)と先方ローリンS.ロバート外務大臣代理(Mr. Lorin S. Robert, Acting Secretary of Foreign Affairs)との間で行われた。
- ウエノ港は、ミクロネシア連邦最大の人口を抱えるチューク州で唯一の岸壁等の港湾施設を有する港である。チューク州は日常生活品の多くを他国からの輸入に依存しているが、これら輸入品は外航大型船によりウエノ港に持ち込まれ、同港及び州都が位置するウエノ島内で消費されるほか、州内連絡船により離島地域に運ばれている。
他方、ウエノ港の現行施設の基本構造は終戦直後に建設されたものであり、外航大型船用岸壁、州内連絡船用岸壁については、その後我が国無償資金協力により拡張・補強が行われたものの、同港北側に位置する小型船舶用の荷揚げ施設の規模は建設当初のままである。このため、係留スペース及び係留施設の不足から、これら船舶用の港湾は混雑しており、作業効率や安全性の低下といった問題を引き起こしている。
また、2002年にチューク州を相次いで巨大台風が襲い、ウエノ港は高潮により被害を受けた。特に最前面に位置する外航大型船用岸壁は、上部工損傷や防舷材が軒並み剥ぎ取られる等、多大な損傷を受けて使用できない状態にあり、このため、現在外航大型船の貨物積み降ろしは、作業性、操船性、安全性を無視して州内連絡船用岸壁を使用せざるを得ない。外航大型船の船体長は、州内連絡船用岸壁より長いため、貨物の積み降ろしは全て船上のクレーンにより行わざるを得ず、荷役作業の効率が低下しており、このため停泊日数の増加や内航船の沖待ちなどの問題を引き起こしている。さらに、進入口も狭隘であることから、船舶が座礁する危険性も高い。
このような背景のもと、ミクロネシア連邦政府は、小型船舶用荷揚げ施設の整備、外航大型船用岸壁の復旧を内容とした「ウエノ港整備計画」を策定し、我が国に対し無償資金援助を要請したものである。 - この計画の実施により、(1)小型船荷揚げ施設の整備で平均係留隻数が80隻から120隻に増加することにより、混雑化が解消し、それに伴い荷揚げ作業の効率化及び安全性の向上が図られること、(2)外航大型船用岸壁が復旧し、従来の機能分担が達成されることで、寄港日数が現在の3日から2日に減少し、その結果荷役効率の向上が図られること、(3)ウエノ港の機能が回復し、外航及び内航海運がともに活性化することで、チューク州の持続的発展に寄与すること、が期待される。
(参考)
ミクロネシア連邦は、太平洋西部に位置し、東西約2,500kmにわたって広がるヤップ・チューク・ポンペイ・コスラエの4州からなる連邦国家である。面積は約701kkm(奄美大島程度)、人口は約127,000人。