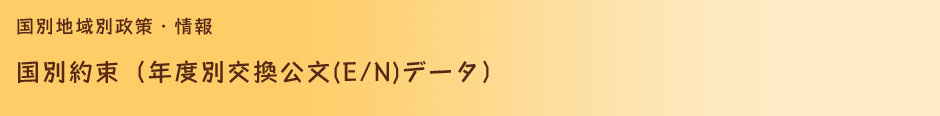貧困農民支援によるウガンダのネリカ米普及・生産促進事業について
(国連食糧農業機関(FAO)経由で実施するもの)
平成18年2月28日
- わが国政府は、国際連合食糧農業機関(FAO)を通じ、ウガンダ共和国におけるネリカ米普及・生産促進事業に1億4,700万円(約137万ドル)の貧困農民支援を実施することとし、このための書簡の交換が、2月28日(火曜日)ローマにおいて、わが方中村雄二駐イタリア国大使と先方デヴィッド・ハチャリックFAO事務次長(Mr. David HARCHARIK, Deputy Director General)との間で行われた。
- わが国は、高収量のアジア稲と病気や雑草に強いアフリカ稲を交配することにより開発されたネリカ米(New Rice for Africa)の普及に向けた協力をアフリカ諸国で行ってきている。アフリカの稲作は、貧しい農民により営まれる粗放的な農業であり、灌漑整備や肥料の多投なく収量の増加が可能なネリカ米の普及は、食糧不足の緩和と、農民の所得向上を通じた農村の貧困削減に寄与するものとして期待されている。わが国は、ネリカ米の普及をアフリカ開発会議(TICAD II、III)の具体的な支援策の一つとして表明し、2005年にはアジア・アフリカ首脳会議、G8グレンイーグルズ・サミットにおいてわが国の対アフリカ開発支援策として紹介した。これまでに西アフリカ稲開発協会(WARDA)に対するネリカ米の研究開発支援や、国際協力機構(JICA)専門家の派遣を通じたネリカ米の栽培試験等の協力を中心に支援を実施している。
- ウガンダにおけるネリカ米普及に向けた課題は、広くその有用性をウガンダの農民に普及することにある。今回の事業ではFAOの農民動員による指導手法(ファーマーズ・フィールド・スクール)を活用しつつ、地元農民に対し幅広くネリカ米の普及と指導を実施する。具体的には現地米と比して単位当たり収量で3割高く、収穫までの期間が2~3割短い稲「ネリカIV」を、東部、中央、西部のサイト合計1,000ヘクタールにおいて耕作し、6,000世帯の農民を対象に、種籾、肥料、足踏み脱穀機等を供与し、播種・施肥等の栽培方法、脱穀等の収穫後処理、種籾の自主生産、流通に関する指導を行うものである。
- ウガンダは、1)国策としてネリカ米を含む陸稲振興を推進していること、2)コメの消費が増えつつあること、3)降雨・土壌に恵まれ二期作が可能であること、4)地下水位が浅いこと等、ネリカ米普及のための条件が揃っている。わが国は、ウガンダとギニアの2ヶ国においてネリカ普及の成功事例を形成し、その成果を他の国に拡げていく方針である。
- こうした協力を通じて、ウガンダにおけるネリカ米普及を通じたコメの生産性の向上と、貧困・飢餓の削減に寄与することが期待される。
 収穫前のネリカ米 |
 農家のネリカ米(1) |
 農家のネリカ米(2) |
 ナムロンゲ農業試験場でのネリカ米 |