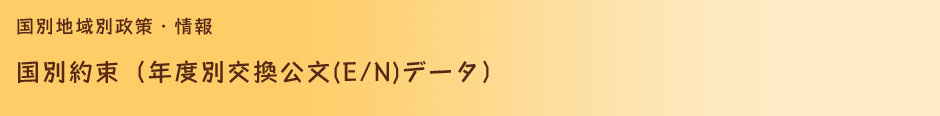世界食糧計画(WFP)を通じたアフリカ諸国に対する食糧援助について
平成17年12月16日
- わが国政府は、世界食糧計画(WFP)を通じ、アフリカのブルンジ、ルワンダ等の大湖地域やシエラレオネなど、紛争から平和へ向かう移行期の中で食糧不足に困窮している諸国の難民や国内避難民を対象として、合計9億4,000万円の食糧援助を行うこととし、このための書簡の交換が、日本時間12月16日(金曜日)、ローマにおいて、わが方高岡望在イタリア国臨時代理大使と先方シーラ・シスルWFP事務局次長(Ms. Sheila Sisulu, Deputy Executive Director)との間で行われた。
今回の食糧援助の対象内訳(カッコ内は供与額)。
(1)ブルンジ国内避難民・難民等 (1億7,000万円)
(2)ルワンダ国内避難民・難民等 (1億8,000万円)
(3)タンザニア滞在難民等 (3億1,000万円)
(4)シエラレオネ国内避難民・難民等 (1億7,000万円)
(5)コンゴ共和国脆弱者等 (1億1,000万円) - 大湖地域の安定はアフリカ全体の安定に大きな影響をおよぼす。2000年に内戦和平合意に至ったブルンジでは、本年8月に大統領選挙が実施され、暫定政権から本格政権への移行が完了し、国家再建に向けて動き出しており、平和の定着は重要な局面を迎えている。このような中、コンゴ民主共和国やルワンダから流入した難民、タンザニアから帰還したブルンジ難民の間で、深刻な食糧不足が発生している。また、ルワンダでは、94年の大虐殺の爪痕を残しつつも、本格的な復興期に入っているが、農業インフラは大きな打撃を受けており、難民や社会的弱者が食糧不足に困窮している。タンザニアは、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国から流入した難民が60万人にのぼり、世界最大の難民受け入れ国の一つとなっているが、こうした難民は、自由に農耕等の生産活動が出来ないこともあり、WFPは、人道的観点から39万人の難民を対象に食糧配給事業を行っている。
- シエラレオネでは、1991年以来、断続的な戦闘行為が展開されて来たが、2002年に国連ミッションが派遣され、本年までに児童兵を含む7万人の戦闘員の武装解除、27万人の帰還難民の再定住が行われた。その一方で、多くの住民は慢性的な食糧不足に直面しており、これまで武装勢力がダイヤモンドを財源に住民に武器と食糧を供給することで紛争が長期化した経緯もあり、食糧支援により住民の不安を解消することが重要な課題となっている。コンゴ共和国も、1997年の内戦発生後、平和プロセスは進展してきているものの、政府軍と一部反政府民兵との間で武力紛争が発生するなどしている。このような中、国内消費の3%しか自給出来ない食糧不足国である同国では、干魃等により更なる食糧不足が発生している。
以上のような状況の下、わが国は、WFPより国際社会に対してアピールが発出されたことを受け、人道的見地から、また地域の安定と復興を支援する観点から、WFPを通じ、米・小麦・トウモロコシと大豆の粉の混合食品を購入するための資金を供与することとしたものである。 - 世界では、8億4,000万人が紛争や干魃等の自然災害によって食糧不足に陥っている。飢えと栄養失調関連の疾患で死亡する人々の数は年間1,000万人を越え、戦争による犠牲者よりも多くの人々が飢餓と栄養失調により命を落としている。食糧問題は、世界が一致して取り組むべき重要課題であり、わが国は、国際社会と協調しつつ、積極的な貢献を行っていく立場である。2005年、アフリカ大陸は、南部及び西部における深刻な食糧危機、スーダン、シエラレオネ、大湖地域等の不安定な移行期で直面する食糧不足などの試練に晒された。わが国は、本年、こうしたアフリカの窮状を踏まえて、集中的な支援を行った。この結果、2005年中に供与を決定したアフリカ向け食糧援助の合計は122.44億円(このうちWFP経由支援は52.74億円)となる。
- 今回の食糧援助により、アフリカの食糧不足が緩和され、同地域の安定にも貢献することが期待される。なお、今回の協力は、本年4月にインドネシアで開催されたアジア・アフリカ首脳会議において小泉純一郎総理大臣が表明したアフリカ支援の一環として実施されるものである。