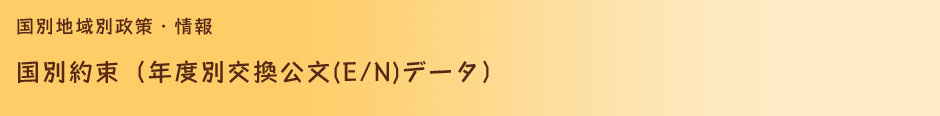ナイジェリアに対する無償資金協力「食糧増産援助」および「地方電化計画(3/3期)」について
平成14年7月11日
- わが国政府は、ナイジェリア連邦共和国政府に対し、「食糧増産援助」および「地方電化計画(3/3期)」の実施を目的として、総額20億9,800万円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が7月11日(木)、アブジャにおいて、わが方池田章在ナイジェリア臨時代理大使と先方マグナス・クパコル大統領首席経済顧問(Dr. Magnus Kpakol, Chief Economic Adviser to the President)との間で行われた。
(1)食糧増産援助(Increase of Food Production):
供与限度額 4億7,000万円(2)地方電化計画(3/3期)(the Project for Rural Electrification):
供与限度額 16億2,800万円
- (1)食糧増産援助
ナイジェリアでは、1960年独立以来のクーデターや内戦、および内戦終結後は石油生産の本格化により、同国の産業構造が原油関連収入に依存する形に移行してきたこと等が原因となり、農業開発が停滞していた。このような状況を受け、ナイジェリア政府は、1986年から農業を重視する政策に転換し、その後GDP(国内総生産)に占める農業の割合は約33%に増加した。しかしながら、農業従事者の多くは伝統的な小規模農業を営んでおり、その生産性は依然低くとどまっている。
このような状況の中、ナイジェリア政府は、持続的な近代農法の確立を目指し、米を増産するため食糧増産計画を策定したが、厳しい財政下生産性向上に必要な肥料の購入に必要な資金が不足している状況にある。
このような状況の下、ナイジェリア政府は食糧増産を図るための肥料の購入に必要な資金につき、わが国政府に対して無償資金協力を要請してきたものである。
(2)地方電化計画
ナイジェリアの地方農村部では、集落ごとに独立電源による電力の供給が行われていたが、燃料費・部品の手当や日常的な維持管理が実施できず、供給電力の質の低下、電力供給の時間制限が著しくなり、電力供給が停止することもみられるようになった。その結果、地方農村部の電化率は極めて低くなっている(ナイジェリア全体の電化率は約35%)。このためナイジェリア政府は、地方農村部に中長期的に質の良い安定した電力供給を行うため、これまでの独立系電源に比して維持管理が容易であり、料金徴収システムが確立されている既存送電網に地方農村部を連結し、電化を行うことを計画しているが、厳しい財政状況のため、実施が困難な状況にある。
このような状況の下、ナイジェリア政府は、特に電化率が低い、ナサラワ州アウェ町およびケアナ町、バウチ州ボゴロ町、ゴンベ州カッシンギ町、ボルノ州ダマサク町の5地区における「地方電化計画」を策定し、この計画を実施するための送配電用資機材の調達に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画の第3期実施により、未電化であったボルノ州ダマサク町が電化され、第1期・第2期において実施されたナサラワ州アウェ町およびケアナ町、バウチ州ボゴロ町、ゴンベ州カッシンギ町とあわせ、対象地区における9万8,300人の住民に対して24時間の安定した電力供給が可能となり、対象地域の経済・社会開発に大きく資することが期待される。