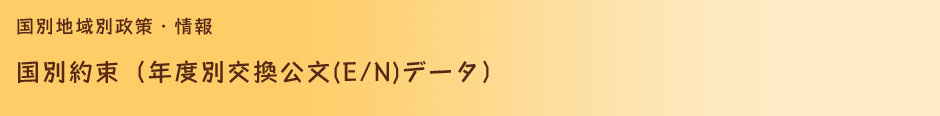アンゴラの「第二次ルアンダ市電話網整備計画」ほか4件に対する無償資金協力について
平成13年4月12日
わが国政府は、アンゴラ共和国政府に対し、「第二次ルアンダ市電話網整備計画」、「ルアンダ州保健センター機材整備計画」および「ルアンダ州給水計画」の実施に資することを目的として、また、「食糧援助」および「食糧増産援助」のため、総額20億5,800万円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が、4月12日(木)、ジンバブエの首都ハラレにおいて、わが方菅野悠紀雄在アンゴラ大使(ジンバブエにて兼轄)と先方ジョアキン・アウグスト・デ・レモス在ジンバブエ・アンゴラ大使(Mr.Joaquim Augusto de Lemos, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Angola to the Republic of Zimbabwe)との間で行われた。
| (1)「第二次ルアンダ市電話網整備計画」 | 5億7,800万円 |
| (2)「ルアンダ州保健センター機材整備計画」 | 3億8,100万円 |
| (3)「ルアンダ州給水計画」 | 2億5,900万円 |
| (4)「食糧援助」 | 5億9,000万円 |
| (5)「食糧増産援助」 | 2億5,000万円 |
(参考資料)
(1)「第二次ルアンダ市電話網整備計画」
(the project for Rehabilitation of Telephone Network in Luanda Phase II)
アンゴラの電気通信設備は、内戦で破壊されたため1992年には電話加入数が72,000台から49,000台に激減し、電話普及率も100人当たり0.49台に減少した。その後復興が始められ、2000年9月末には内戦前の水準に回復しつつある。しかし、電話普及率を南アフリカ開発委員会(SADC)加盟の近隣諸国と比較すると、1998年末現在で南ア11.5台、ジンバブエ1.70台に対し、アンゴラ国は0.56台と、近隣諸国に比べて依然低い水準にある。
電気通信設備が集中する首都ルアンダ市では、旧式の紙絶縁ケーブルを使用しているため、降雨による絶縁不良が生じ、故障の原因となるとともに、通話品質の劣化も甚だしい。また、電話網の配線方法が複雑な配線となっていることも加わって、電話線路設備の劣化が著しい状況にある。
このような状況の下、アンゴラ政府は、ルアンダ市内のサンパウロ局およびテラ・ノーヴァ局地域における「第二次ルアンダ市電話網整備計画」を策定し、この計画の実施のためのそれぞれ約1万回線の電話網整備に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画実施により故障・品質劣化の著しい旧式の電話網が改善され、両地域の必要な需要を満たすサービスが可能となる。
(2)「ルアンダ州保健センター機材整備計画」
(the project for Improvement of Medical Equipment in Primary Health Facilities in Luanda Province)
アンゴラでは、長引く内戦の影響により、保健医療分野において大きな打撃を受けた。同国政府は保健医療支出を削減したため、多数の医療施設では医療従事者、医療機材および医薬品等が不足している。そのため、同国の保健医療事情はサブサハラ・アフリカの中でも劣悪な状況にあり、保健指標は、乳児死亡率(170/1,000出生)、妊産婦死亡率(1,500/100,000出生)とも、同地域平均(87/1,000出生、676/100,000出生)に対し非常に高い数値を示している。アンゴラ保健省は、1999年から2001年までの最優先事項を母子保健医療サービスの向上と位置づけ、一次医療の改善を国民の保健医療問題の中心課題として取り組んでいる。
同国の保健センターは、各郡レベルに配備されているが、とりわけ全人口の約17%(統計局公表202万人)が集中するルアンダ州の保健センターの整備が緊急の課題となっている。
このような状況の下、アンゴラ政府は、ルアンダ州にある27カ所の保健センターのうち、緊急に整備を必要としている13カ所の保健センターのための「ルアンダ州保健センター機材整備計画」を策定し、この計画の実施のための基礎的医療機材の更新および補充に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画の実施により、ルアンダ州内の7郡の約166万人の一次医療サービス、とりわけ母子保健医療の改善が期待される。
(3)「ルアンダ州給水計画」
(the project for Water Supply in Luanda Province)
アンゴラでは、長引く内戦のため、首都ルアンダ市およびその周辺地域(ルアンダ州)に200万人におよぶ避難民が流入し、ルアンダ州の人口は350万人に膨れ上がった。
ルアンダ州に流入してきた国内避難民は、基本的には公共サービスがほとんど期待できない市街地周辺地域に住み着いた。特に、国内避難民の生活安定や都市活動を維持するための重要な要素である生活用水の給水については、既存施設の老朽化や新規施設の建設の遅れにより、安全で衛生的な水を必要量確保できず、慢性的な水不足と水質障害に悩まされている。
アンゴラ政府は、迅速かつ円滑な国内避難民の帰還と再定住を実現するために、「国内避難民帰還再定住化全国計画」の策定を1997年に行い、この中で給水施設・システムの整備を国内避難民の定住の促進に必要不可欠なものと位置づけた。しかし、内戦などの影響により国、州とも財政基盤は脆弱であり、独自でこの計画を実施することが困難な状況にある。
このような状況の下、アンゴラ政府は、ルアンダ州内の国内避難民再定住化計画地域および公共施設のための「ルアンダ州給水計画」を策定し、この計画の給水体制を改善するために必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画実施により、再定住化地域の避難民および公共施設の人々に対して安全な水を供給することが可能となり、対象地域の衛生状態が改善され、水因性疾患の発生率の低減が期待できる。
(4)「食糧援助」(Food Aid)
アンゴラは、農業について高い潜在的生産力を有しているにもかかわらず、1994年の穀物生産が国内需要の3分の1にも満たず、1995年の最初の数カ月には人口の約3分の1に当たる350万人が食糧援助を受けた。
その後もアンゴラ国の食糧事情は停滞しており、アンゴラ政府は、慢性的に続く食糧不足を改善するために必要な食糧(米)を調達するための資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
(5)「食糧増産援助」
(Grant Aid for Increase of Food Production)
アンゴラの農業分野は、1970年代にはトウモロコシを始めとして余剰生産物を輸出し、コーヒーに関しては世界第4位、サイザル麻に関しては世界第3位の生産量を誇っていたにも関わらず、1994年の穀物生産は国内需要の3分の1にも満たず、1995年の最初の数カ月には人口の約3分の1に当たる350万人が食糧援助を受けるほどに食糧生産が落ち込んだ。
アンゴラ政府は、国家復興と和平プロセスの実施を急務としており、特に荒廃した農村の復興は、帰還兵士や帰還難民の雇用機会を創出し、かつ危機的な食糧事情を改善するためにも重要な政策と位置づけられている。農業農村開発省が策定した「2000年/2001年農業生産推進プログラム」では、重点項目の中に、(1)トウモロコシ、キャッサバなどの主食や野菜、家畜の増産を目指す企業・個人農家に対する支援、(2)中央政府による必要な基礎農業資機材の購入販売を通じた農業技術の伝播とフォローアップ、という2点を含めている。
これらの重点項目に関し、アンゴラ政府は、食糧増産に必要な農業資機材を調達するための資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。