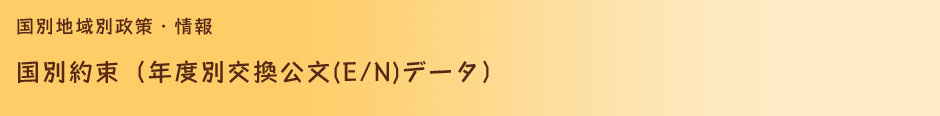マリの「カチ・クリコロ・カンガバ地区給水計画」ほか3件に対する無償資金協力について
平成13年1月6日
わが国政府は、マリ共和国政府に対し、「カチ・クリコロ・カンガバ地区給水計画」、「予防接種拡大計画」、「食糧増産援助」および「債務救済のための無償援助」として、総額15億1,878万2,000円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が1月5日(日本時間6日)バマコにおいて、わが方古屋昭彦在マリ大使と先方モディボ・シディベ外務・在外マリ人大臣(Ministre des Affaires Etrangeres et des Maliens de l'Exterieur)との間で行われた。
- 「カチ・クリコロ・カンガバ地区給水計画」
供与限度額:4億4,600万円 - 「予防接種拡大計画」
供与限度額:4億7,900万円 - 「食糧増産援助」
供与限度額:4億5,000万円 - 「債務救済のための無償援助」
供与額:1億4,378万2,000円
(参考資料)
1.「カチ・クリコロ・カンガバ地区給水計画」
(le projet d'alimentation en eau potable dans les cercles de Kati, Koulikoro et Kangaba)
マリは、全土の大半が砂漠又は半砂漠の内陸国であり、中央部を流れるニジェール川およびセネガル川流域を除いては慢性的な水不足に悩まされていることから、水資源の確保が国家の重要課題となっている。このため同国政府は「水資源開発基本計画」を策定して給水事情の改善に努めている。
しかしながら、いまだに衛生的な飲料水を利用できる国民が全国民のおよそ52%にすぎず、半数の国民が不衛生な水を利用せざるを得ない状況にあり、彼らの多くは胃腸、眼、皮膚等の水因性疾患に悩まされ健康が阻害されている。また、給水施設が少ないために多くの婦女子は苛酷な水汲み労働の負担を強いられている。
こうした背景の下、マリ政府は首都バマコ周辺地域で給水率が著しく悪いカチ、クリコロおよびカンガバ地区(平均給水率約15%)における給水事情改善を目的として、「カチ・クリコロ・カンガバ地区給水計画」を策定し、この計画のためのハンドポンプ付深井戸およびソーラーシステム小規模給水施設建設等の実施に必要な資金につき、わが国政府に対して無償資金協力を要請してきたものである。
本計画の実施により、約10万7,000人が衛生的な水を利用できるようになり、給水率も現状の約15%から87%に大きく改善されることが期待されている。
今回は本計画の第2期目として、ハンドポンプ付深井戸118本を建設するものである。
なお、本計画の第1期目として、既にハンドポンプ付深井戸80本およびソーラーシステム小規模給水施設2カ所の建設について、平成12年度に4億4,500万円の無償資金協力を実施している。
2.「予防接種拡大計画」
(le projet d'appui au programme elargi de vaccination)
マリの母子保健に関する保健・医療指標は、ポリオ、麻疹、破傷風、黄熱病、マラリア、B型肝炎等多数の伝染病や風土病により、5歳未満児の死亡率が1,000人当たり237人、乳幼児死亡率は1,000人当たり144人、また妊産婦死亡率が10万人当たり580人と著しく悪い。そのため、同国政府は保健医療環境の整備に努めると共に、ユニセフ、世界保健機関(WHO)などの協力を得ながら、予防接種活動を推進してきた。
しかしながら、同国政府の財政は劣悪な状況にあるため、ワクチンの購入、輸送車両およびコールドチェーン資機材の不足や老朽化への対応に支障を来しており、そのため予防接種率も低迷している。
このような背景の下、マリ政府は予防接種率向上を目的に、「予防接種拡大計画」を策定し、この計画のための予防接種活動に必要な資機材の購入のための資金につき、わが国政府に対して無償資金協力を要請してきたものである。
なお、本計画の実施により、同国の予防接種活動体制が整備・改善されること、2001年の予防接種対象となる1歳未満児約42万人および妊娠可能女性約230万人の安全な予防接種を可能にすること、また、1歳未満児のB型肝炎予防接種率が65%へ向上することが期待されている。
3.食糧増産援助
マリにおける農業は、国内総生産(GDP)の49%を占め、80%を越える国民の主要な収入源となっており、同国の基幹産業である。しかしながら、同国はサヘル地域に位置する内陸国で、全土の大半が砂漠又は半砂漠であり、耕作可能地域は中央部のニジェール川流域および南部の比較的降水量に恵まれた地域に限定されている。そのため、同国政府は、わが国を含む他の援助国の支援の下、天水を基本とする伝統的農業から、灌漑化、農業技術および改良種子の普及、農業機材の投入等による農業の近代化を図るべく農業政策を推進しており、近年食糧事情は大幅に改善されてきている。
しかしながら、同国は人口増加が著しく(年間約2.8%)、また食糧生産力の地域間格差も大きいため、豊作時においても主要穀物の輸入を行わなければならない状況であり、同国農業にとって灌漑農地の拡大、技術の近代化による更なる生産力の向上は緊急的課題となっている。
このような背景のもと、マリ政府は、食糧自給、持続的農業発展を目標とした食糧増産計画を策定し、この計画に必要な農業機械、肥料および農薬を購入するための資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
4.「債務救済のための無償援助」
この無償資金協力は、マリ政府が1988年4月1日から1998年3月31日までにわが国政府と行った円借款取決めに従って締結された借款契約に基づき負っている債務のうち、平成12年度第2四半期に返済期限の到来した元本および約定利息のうちの返済額に相当する額を供与するもので、債務救済措置の一つである。
この無償資金協力により贈与する資金は、マリの経済の発展と国民福祉の向上のために必要な生産物等の購入のために使用される。
1978年3月、国連貿易開発会議(UNCTAD)第9回特別貿易開発理事会(TDB)閣僚会議閣僚会議が開催され、多くの開発途上国が深刻な債務返済問題に直面していることから、先進諸国がこれらの開発途上諸国に対する過去の二国間政府開発援助(ODA)の条件を調整する措置、またはその他同等の措置をとるよう努力すべき旨の決議が採択された。この無償資金協力は、この決議に鑑み、マリ共和国とわが国の友好協力関係を強化することを目的として、わが国の無償資金協力の一環として実施するものである。