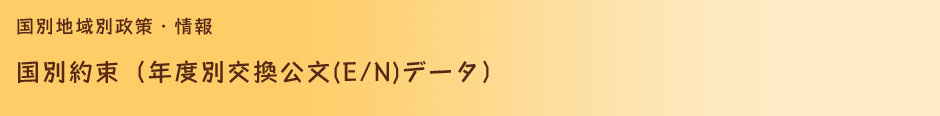WFP(国連世界食糧計画)を通じた無償資金協力(食糧援助)に関する書簡の交換について
平成19年7月31日
- 我が国政府は、WFP(国連世界食糧計画)を通じ、貧困あるいは不安定な移行期の中で慢性的な食糧不足の状況にある社会的弱者(避難民、エイズ患者、女性、子供等)を抱える以下7か国に対し、「食糧援助」として合計32億円の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が、7月31日(火曜日)(現地時間同日)、ローマにおいて、我が方中村雄二駐イタリア国大使と先方シーラ・シスルWFP事務局次長(Ms. Sheila Sisulu, Deputy Executive Director, World Food Program of the United Nations)との間で行われた。
今回の食糧援助の対象内訳(カッコ内は供与額)。
(1)アフガニスタン・イスラム共和国社会的弱者 (3億9,000万円)
(2)パレスチナ自治区住民 (2億3,000万円)
(3)シエラレオネ共和国社会的弱者 (3億5,000万円)
(4)ジンバブエ共和国社会的弱者 (4億8,000万円)
(5)スーダン共和国社会的弱者 (9億7,000万円)
(6)チャド共和国社会的弱者 (3億円)
(7)リベリア共和国社会的弱者 (4億8,000万円) - アフガニスタンにおいては、長年の戦争などによる環境破壊や干魃の影響で十分な食糧を生産することができず、深刻な食糧不足の状態が続いている。極貧のため恒常的に食糧援助を必要とする者が約350万人、食糧が不足する季節に支援を必要とするものが約300万人と言われる。
パレスチナ自治区、特にガザ地区においては2007年6月のハマスによるガザ地区掌握により住民の生活状況は一層深刻となっており、72%が貧困状態に陥っている。
シエラレオネは、2002年に約10年に亘る内戦が終結し、本格的な復興に向かっているところであるが、依然として多くの住民は慢性的な食糧不足に直面している。
ジンバブエは、かつては大規模農業の高い生産性により「アフリカの穀物庫」とも呼ばれていたが、農地改革や干魃等の影響もあり、農業生産量が激減した。2007年春は凶作であったため、特に、社会的弱者にとって食糧入手は一層困難になっている。
スーダンは、アフリカ大陸最大の国ではあるが、20年以上にも亘る内戦のため国土は疲弊し、慢性的な食糧不足の状態に陥っている。2003年に勃発したダルフール紛争により、約20万人のアフリカ系住民が殺害され、難民、国内避難民が約200万人から250万人発生している(国連の報告)。今後、避難民が帰郷したとしても、耕作環境が整わないため、食糧不足は依然として続くと予想される。
チャドは世界最貧困国のひとつで食糧不足に苦しんでいる。これに加え、ダルフール紛争の影響で国内避難民が約14万人発生しているほか、隣国スーダンから難民が押し寄せ、約24万人が難民キャンプで支援を受けて生活している。
リベリアにおいては、2003年に14年に及ぶ内戦の終結と和平、復興への道を歩み始めたが、元兵士の社会復帰、帰還者の生活再建支援などは資金不足もありなかなか進んでいない。そのため、農業の生産性が低く、食糧不足は深刻である。 - 我が国は、このような国々の社会的弱者の置かれた状況に鑑み、WFPの支援要請に応え、人道的見地から食糧援助を実施するものである。今回の食糧援助により、これらの国々における食糧不足の緩和に繋がることが期待される。
(参考)
- 各国基礎データ
国名 面積
(万平方キロメートル)人口
(百万人)2005年一人当たりGDP
(米ドル)2005年アフガニスタン 65.2 25.1 228(2006) パレスチナ自治区 0.6 3.8 802(2006) シエラレオネ 7.2 5.7(2006) 220 ジンバブエ 39.0 12.9(2004) 340 スーダン 250.6 35.5 570(2004) チャド 128.4 9.7 400 リベリア 11.1 3.4(2006) 130 出典:外務省ホームページより
- 被援助国地図(別添)(PDF)

![]() Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。