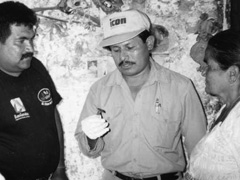| ホンジュラス共和国 -Republic of Honduras- |
| 算数指導力向上プロジェクト | ||
| 案件開始日 | 平成15年4月 | |
| 案件終了予定日 | 平成18年3月 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | ホンジュラス国は現在「2015年までに、男女すべての就学年齢児について、6年間の初等教育の完全普及と修了を達成する」という目標を掲げ、多くのドナーの支援を得て、さまざまな取り組みを行っている。初等教育の現状をみると、純就学率は95%(2000年)と高く男女格差もほとんどないことから、児童の学校教育へのアクセスが改善され、教育の普及が進んでいる様子がうかがえる。 一方、修了率は68.5%(2000年)と低く、教育の質的な側面において十分な改善がなされていない状況が推察される。さらに初等教育修了者のうち、正規の6年間で教育課程を修了できたものは31.9%であり、中退と留年が現在のホンジュラス国における主要な教育開発上の課題となっている。 ホンジュラス国における留年のおもな原因は国語(スペイン語)と算数の成績不振である。また、現職教員の資質が低いことが問題としてあげられている。ホンジュラス国政府は「国家再建計画」の柱の一つである「教育再建計画」に基づき、教員養成・再研修システムの改革に取り組んでおり、現在、国立教育大学を中心として「現職教員研修プログラム」を1998年8月から開始している。 我が国はホンジュラス国に対し、これまで12年間にわたり算数分野の協力隊を派遣し(関連隊員派遣数累積60名)、現職教員研修のための協力を実施してきた。こうした実績が評価され、今般ホンジュラス国政府より「現職教員研修プログラム」のうち、児童の留年率がもっとも高い科目の1つである算数について我が国に協力が要請された。具体的な要請の内容としては、算数の教員継続研修の改善・実施、算数国定教科書教師用指導書、児童用作業帳の作成、児童用標準学力テストを使用した教育評価方法の整備である。 本プロジェクトでは、技術協力プロジェクトとボランティア事業の連携のもと、現職教員の算数指導力の向上を目的として、1年生から6年生までの教師用指導書・児童用作業帳を開発するとともに、「現職教員研修プログラム」を通じ、これら成果品を活用して算数の現職教員研修の改善を図るものである。 |
| 2.協力活動内容 | (1)-1 初等教育における教師用指導書の試案を作成する。 (1)-2 教師用指導書試案を算数科授業で試用する。 (1)-3 試用状況をモニタリングする。 (1)-4 モニタリング結果を教師用指導書にフィードバックする。 (1)-5 教師用指導書試案を完成させる。 (2)-1 初等教育における算数児童用作業帳試案を作成する。 (2)-2 算数児童用作業帳試案を算数の授業で試用する。 (2)-3 試用状況をモニタリングする。 (2)-4 モニタリング結果を算数児童用作業帳にフィードバックする。 (2)-5 算数児童用作業帳試案を完成させる。 (3)-1 算数教員研修のための研修計画をたてる。 (3)-2 作成した教師用指導書・児童用作業帳を活用し、5県において教育大学PFCに則り研修を実施する。 (3)-3 算数教員用学力・指導力テストを作成・実施する。 (3)-4 算数授業評価分析シートを作成する。 (3)-5 算数の授業評価を実施する。 (3)-6 児童用学力テストを作成・実施する。 (4)-1 (1)~(3)の活動を通じ、カウンターパートに知識・技術を移転する。 (4)-2 教育関係者を対象としたセミナー等の開催を通じ、経験をシェアする。 |
|
| 地方女性のための小規模起業支援プロジェクト | ||
| 案件開始日 | 平成15年11月 | |
| 案件終了予定日 | 平成18年10月 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | ホンジュラス国(以下「ホ」国)は中南米諸国の中でも最貧困国の一つであり、総人口の約49%が極度の貧困状態(一日の平均収入が1ドル以下)にあると言われている。こうした状況に加え1998年11月に同国を襲ったハリケーン・ミッチにより、人口の3分の1にあたる220万人が被災するとともに、その経済的被害は約50億ドルにのぼり同国に壊滅的な打撃を与えた。これに対しホンジュラス国政府は、1999年4月に国家再建マスタープラン作成し復興に努めるとともに、同国の最重点課題である貧困削減に向けた取り組みに力を注ぎ、2001年10月には貧困削減戦略ペーパー(PRSP)を策定した。同PRSPでは、同国の貧困層の多くが社会的弱者層(女性、子供、失業者等)であることに鑑み、「特定グループへの社会的保護」として社会的弱者支援を重要課題の1つに掲げている。また「ホ」国は農林水産業を中心としたモノカルチャー型経済であり、特に地方では就業機会・既存の雇用先が限られていることから、「ホ」国政府はPRSPに基づく貧困削減への取り組みとして、中長期的に収入向上に効果のある小規模起業に着目し、関係機関との連携により貧困女性を対象とした小規模起業を支援するプロジェクトを我が国に対し要請してきた。これに対し我が国は、事前評価調査団を派遣し「ホ」側関係機関と協議を重ねた結果、社会的弱者の生活向上を目的として全国13県80箇所以上のサイトでプロジェクトを実施している大統領府直轄機関である「家族支援計画」(PRAF)を本プロジェクトのカウンターパート機関とするとともに、職業訓練分野で長年の経験を持つ職業訓練庁(INFOP)を講師派遣等を行う協力機関とすることで合意した。本プロジェクトでは、現在PRAFが実施している貧困女性を対象とした小規模起業支援事業(Di-Mujer)を通じ、モデルサイトにおいて貧困女性が地域のリソースを活用した小規模事業を起業・運営できるよう、コミュニティ分析、市場調査、各種訓練、および起業支援(マイクロファイナンス、起業後のアドバイス等)を行い、貧困層への直接裨益を目指すとともに、これら一連のプロセスを通じ、カウンターパート機関のキャパシティビルディングを図り、プロジェクト終了後も「ホ」側で継続して貧困削減の取り組みがなされることを目指すものである。なお収入向上などの経済的側面の改善だけでは効果的な貧困削減には繋がらないことから、本プロジェクトでは貧困女性のエンパワメント等ターゲットグループの意識の向上に配慮したアプローチをとる。またプロジェクト成果の普及・拡大を視野に入れ、地方自治体、NGOとも密接に連携する。 |
| 2.協力活動内容 | 0-1. PRAFによる貧困女性の小規模起業支援に関する現状調査を実施する。 0-2. 小規模起業支援にかかる問題の詳細分析を行う。 0-3. プロジェクトサイト候補の貧困状況調査を実施する。 1-0. プロジェクトサイト選定のための検討を行う。 1-1. 物的及び人的資源を把握するための地域調査を実施する。 1-2. 貧困女性のニーズを把握する。 1-3. 地域の資源を発掘する。 1-4. 市場調査を実施する。 1-5. 貧困女性の参加によって計画を策定する。 2-1. 組織化に関する調査・啓発活動を実施する。 2-2. 組織化のための集会を開催する。 2-3. 組織のルールをつくる。 2-4. 持続的な組織運営のための支援を行う。 3-1. 地元のインストラクター・プロモーターへの研修を行う。 3-2. 自己啓発と動機付け(ジェンダー等)にかかる研修を行う。 3-3. 小規模起業(事業運営・マイクロファイナンス・法的手続き等)の研修を行う。 3-4. 職業技術にかかる研修を行う。 3-5. 研修にかかるモニタリング活動を行う。 4-1. 融資制度について改善点を明確化する。 4-2. 地域のニーズに合った融資制度を検討する。 4-3. 小規模起業のための融資制度を改善する。 4-4. 融資制度のモニタリング活動を行う。 5-1. 流通経路に関する調査を実施する。 5-2. 現況の流通経路の改善点を明確化する。 5-3. 地域と業種ごとの流通経路について貧困女性に関する訓練を行う。 6-1. 技術的アドバイスを行う。(特に商品化について)。 6-2. 事業運営についてアドバイスを行う。 6-3. 小規模企業経営に関する情報を提供する。 7-1. プロジェクト各活動の評価を行う。 7-2. 各成果にかかる事例集を作成する。 7-3. 小規模起業支援のための各種ガイドラインを作成する。 |
|
| シャーガス病対策プロジェクト | ||||
| 案件開始日 | 平成15年9月 | |||
| 案件終了予定日 | 平成19年9月 | |||
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | シャーガス病は貧困層の疾病とも言われる。土壁や藁葺き屋根でできた家に住むサシガメは吸血中に排便し、糞便の中にいる原虫トリパノソーマが人の粘膜や掻いた傷口等から体内に侵入する。急性期には治療薬があるが、慢性期になると治療法がなく、心臓疾患等で感染後10~20年後に死亡する。慢性期になると死を待つしかない深刻な病気である。 中南米ではマラリアに次いで深刻な熱帯病とされ、2千万人以上の患者がいると推定されている。中米では、感染者は人口の約9%、約244万人と推測されており、ホンジュラス国では、人口の約7%、約30万人もの人々が感染しているとされている。 シャーガス病予防は、マラリア熱、デング熱等他の媒介虫感染症に比べて恒常的な成果を挙げやすい。シャーガス病を媒介するサシガメは、現在のところ殺虫剤に対する感受性が強く、また、近い将来耐性を発達させる可能性も低いとされている。したがって、(1)殺虫剤散布、(2)住居の改善、(3)住民教育を通して消滅可能な病気であることが実証されている。実際に南米のチリ、ウルグァイでは、感染の断絶が宣言されており、南米での成果を受け、中米7カ国(グアテマラ、ホンジュラス、ベリーズ、エルサルバドル、ニカラグァ、コスタリカ、パナマ)及び汎米保健機構(世界保健機構アメリカ地域事務局(PAHO/WHO))は、「2010年までに中米におけるシャーガス病の伝搬を中断する。」という目標をあげて中米シャーガス病対策イニシアティブを開始した。この目標達成のため、毎年「中米地域シャーガス病対策連絡会議」が開催され、各国の取り組みが評価されている。 我が国は、グアテマラ国において、2000年より協力を開始しており、2002年7月より技術協力プロジェクトとして実施しており、PAHO/WHOにより高い評価を受けおり、中米各国への展開が期待されている。 |
||
| 2.協力活動内容 | 1 4県においてR.prolixus(Rp)消滅が消滅する。 (1)4県におけるシャーガス病の疫学調査の実施 (2)4県におけるRpの昆虫学的調査の実施 (3)サシガメが生息する家屋への殺虫剤散布活動の実施 (4)散布後の状況について疫学的・昆虫学的調査の実施 (5)地域、NGO、他ドナーと連携した住居改善の啓蒙活動の実施 2 4県においてT.dimidiata(Td)が減少する。 (1)4県におけるシャーガス病の疫学調査の実施 (2)4県におけるTdの昆虫学的調査の実施 (3)Td減少に向けた戦略の策定 (4)Tdが生息する村への殺虫剤散布活動の実施 (5)散布後の状況について疫学的・昆虫学的調査の実施 (6)地域、NGO、他ドナーと連携した住居改善の啓蒙活動の実施 3 住民参加型の監視体制が確立される (1)住民参加型監視体制のためのマニュアル、資材の作成 (2)住民に対する啓蒙活動の実施 (3)各保健管区にて住民による監視体制の確立 4 シャーガス病対策にかかる情報伝達体制が確立される (1)情報伝達フォームの作成 (2)地域保健管区から保健省中央に対する情報連絡体制の整備 (3)保健省中央での情報連絡体制の整備 5 サシガメ生息地で14歳未満の陽性者がいなくなる(陰性になる) (1)ホンジュラス側の取組により、14歳未満の陽性者に対し治療を行う (2)治療後12-18ヶ月の間に再試験を行う
|
|||