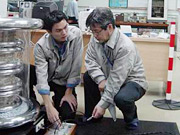| タイ王国 -Kingdom of Thailand- |
| 下水処理場運営改善 | ||
| 案件開始日 | 平成16年5月 | |
| 案件終了予定日 | 平成22年2月 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ国では、急激な経済発展と都市化の進展により様々な環境問題が生じている。内務省公共事業局および科学技術環境省は水質汚濁問題に対処するため、90年代より全国を対象に下水道施設整備を推進しており、1995年までに20箇所の下水処理場が建設・供用された。 その一方で、急速に整備される下水道を適切に運用、管理する技術者が不足していたため、その養成が急務となり、タイ国政府は我が国に対し技術協力を要請した。我が国はこの要請に応え、1995年8月1日から2000年7月31日までの5年間にわたりプロジェクト方式技術協力「下水道研修センター」を実施し、全国の下水道関係者(約1000名、電気、機械、水質分析、下水道設計分野)に対する研修を実施した。 しかしながら、上記プロジェクトにより下水道分野の技術者を養成できたものの、建設された下水処理場の設計が不適切であり、また個々の下水処理場の運営管理体制が不十分なため、現在既存下水処理場の多くが正常に機能しておらず効率が悪い状況に陥っている。このため、タイ国の下水道事業では既存の下水処理場の効率の改善が急務になっている。 かかる状況の下、タイ国政府は、下水道事業、特に処理場の運営改善を目的とした技術協力をわが国に要請越した。 本プロジェクトは、タイ国における下水処理場の効率を改善することを目的に、機能を十分に発揮していないモデル下水処理場(※)の設備を修復・改善した上で、その運転・保守管理の方法を改善し、さらにその過程で得られる知見を他の下水処理場に応用できるよう、参照資料の作成、関係者に対する研修等を実施する。 ※タイ国には全国に下水処理場が70箇所あるが、協力相手先機関である天然環境資源省下水道公社(WMA)が管理する下水処理場はその内7箇所である。本プロジェクトではWMAが管理する下水処理場の内、3箇所をモデル下水処理場とする。 |
| 2.協力活動内容 | 1-1 モデル下水処理場のリハビリテーション計画を見直す。 1-2 モデル下水処理場のリハビリテーションを実施する。 1-3 モデル下水処理場のリハビリテーションの適正さを確認する。 1-4 リハビリテーション工事を終えたモデル下水処理場の運転と保守管理を実施する。 2-1 タイの下水処理場運転・保守管理の改善のために必要なレファレンス・マテリアルを特定する。 2-2 レファレンス・マテリアル作成のための手法を検討する。 2-3 レファレンス・マテリアルを作成するための調査を実施する。 2-4 レファレンス・マテリアルを作成する。 3-1 必要な能力の基準を設定する。 3-2 研修資料を作成する。 3-3 研修を実施する。 4-1 レファレンス・マテリアルを普及用に修正する。 4-2 運転・保守管理報告を収集する。(日報、週報、月報、年報) 4-3 完成図書を収集する。(設計図、仕様書、完成図) 4-4 既存の情報システムを調査する。 4-5 既存のシステムを改良して、所要のシステムを開発する。 |
|
| 国家計量標準機関(フェーズ2) | |||
| 案件開始日 | 平成16年5月 | ||
| 案件終了予定日 | 平成19年11月 | ||
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ政府は、タイ産業の輸出競争力強化のために、タイ国内において国家標準を整備し、国際的同等性を確保した計量標準の体系を確立しようとしている。タイには国家標準の一元的な整備・維持・供給システムがなく、一部の大企業は校正を海外に依頼している。このために、高コスト・手続遅延といった問題が生じており、タイ産業の輸出力強化の阻害要因となっている。 タイ政府は、輸出力強化の阻害要因を解消すべく、1997年8月には国家計量制度整備法を制定するとともに、1998年6月に国家計量標準機関(National Institute of Metrology (Thailand)=NIMT)を設立し、タイ国内の計量標準基盤整備に着手した。1999年5月には国家計量基盤整備マスタープランが閣議了解され、NIMTの整備計画が了承された。 このようなタイ政府の動きに対し、日本政府はNIMTの新建屋建設・機材整備を目的として1999年より国際協力銀行(JBIC)を通じて第24次及び第25次円借款を実施している。一方、タイ政府は、円借款による供与機材を用いた国家標準を維持・供給するためのNIMT技術者の育成を目的として、日本政府に対して1999年にプロジェクト方式技術協力(当時)を要請してきた。 これを受けてJICAは5年間の技術協力プロジェクトを計画し、実施に向けた準備を進めていたが、円借款による新庁舎建設の遅れが予想されたことから、フェーズ1(2年間)とフェーズ2(3年間)に分けて実施することとした。すなわち、フェーズ1においては現有庁舎において技術移転可能な分野を対象とし協力を行い、フェーズ2については新庁舎建設に係る進捗も踏まえ、その実施の時期を判断することとした。 2004年3月に行われたフェーズ1終了時評価及びフェーズ2実施事前評価調査をと併せて行ったところ、フェーズ1協力が予定とおりに成果を挙げていること、及び第25次円借款による新庁舎建設の観光と機材調達の進捗を考えて、フェーズ1終了後継続してフェーズ2を実施することの妥当性が判断されるにいたった。 |
|
| 2.協力活動内容 | 1-1 必要な人員を計画通り配置する。 1-2 予算計画を策定し、適正に執行する。 1-3 活動計画を策定し、計画通りに実施する。 2-1 機材を適切に据付、設定する。 (主に円借款で購入した機材) 2-2 機材を操作・維持管理する。 2-3 機材の操作・維持管理マニュアルを作成す る。 3-1 技術協力計画を策定する。 3-2 C/Pの現在の基礎技術力を査定する。 3-3 技術移転後のC/Pの技術力を評価する。 4-1 計量標準を設定し、維持する。 4-2 校正ラボ環境管理技術を向上する。 4-3 国際比較を実施する。 5-1 国家標準に基づいた参照標準の校正技術を 向上する。 5-2 校正手順書を作成する。 5-3 品質システムを確立する。
|
||
| エネルギー管理者訓練センター | ||
| 案件開始日 | 平成14年4月 | |
| 案件終了予定日 | 平成17年4月 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ国は近年の急速な経済成長に伴い、一次エネルギー消費も年率約10%で伸長してきた。一次エネルギーの多くを輸入に頼る同国にとってエネルギー需要の管理は重要な政策課題となっている。また、地球温暖化ガス(GHG)排出抑制の観点からもその重要性は増している。こうした背景のもと、同国政府は1992年に「省エネルギー促進法」を公布し、一定水準以上のエネルギーを消費する工場・施設においては「エネルギー管理者」の配置を義務づけるなど、省エネルギーの推進を図ってきた。しかしながら、同国におけるエネルギー管理者となる人材の数・能力は不足しており、民間部門における省エネルギーは十分に進展していない現状にある。 このため、タイ国政府は科学技術環境省エネルギー開発推進局(DEDE)の下に「エネルギー管理者訓練センター」を開設し、同センターにおいてエネルギー管理者、及びその指導者の養成・訓練を行うとともに、エネルギー管理者を対象とした資格試験制度を導入することを計画した。 本プロジェクトはかかる制度を機能させる上で必要な制度支援と人材育成を行うものである。 |
| 2.協力活動内容 | ●施設・機材・活動・予算に係わる計画の策定、実行、管理など、組織の運営・管理に関する助言と支援を行う。 ●専門家からカウンターパート(C/P)に対し、国家試験委員会設立・運営、座学及び実習を含む試験前研修の実施・運営、試験問題策定、講師向け研修の開発など、国家試験 制度確立のための助言と支援を行う。 ●省エネルギー知識の最新情報を継続的に提供する手法の確立について助言と支援を行う。 |
|
| 薬物対策地域協力 | ||
| 案件開始日 | 平成14年6月 | |
| 案件終了予定日 | 平成17年6月 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | ヘロイン、アヘン等の薬物問題の中心とも言える「黄金の三角地帯」は、タイ、ミャンマー、ラオス及び中国雲南省の接する地域であり、薬物の問題は国境を越えた地域の問題となっている。この地帯を中心とするインドシナ地域では、近年ヘロイン、アヘン等の薬物に加え、錠剤型覚醒剤の密造、密売、若年層を中心とした乱用が社会問題となっている。 こうした薬物問題に対応するために、タイ政府は首相を委員長とする薬物統制委員会を設置し国を挙げて対策に取り組んでいる。特に、薬物統制委員会事務局(ONCB)は、実質的な薬物専門機関として機能し、タイ警察及び国連機関と連携を取りながら対策を進めている。 しかしながら、タイにおいては薬物鑑定、薬物分析の技術及び法執行機能の確立が求められているため、タイ政府は本分野に関する協力を日本政府に要請した。 タイ及び周辺国における薬物対策は喫緊の課題であり、薬物製造拠点の特定に必要な薬物鑑定・分析技術がタイにおいて向上することは、タイのみならずインドシナ地域にも裨益する案件であることから採択に至った。 |
| 2.協力活動内容 | 1) CLMV諸国の薬物鑑定官に対し定性分析、定量分析の研修を実施する。 2) CLMV諸国の薬物分析官に対し不純物分析の研修を実施する。 3) CLMV各国の捜査官に対し薬物取締りに係る研修を実施する。 4) タイ警察及び保健省医科学局の薬物鑑定官に対し定量分析の研修を実施する。 5) タイ警察及び保健省医科学局の薬物鑑定官に対し不純物分析の研修を実施する。 6) タイ警察の捜査官に薬物取締りに係る研修を実施する。 7) 不純物分析の実践的活用のための薬物情報システム構築にかかる支援を実施する。 8) 薬物取締能力向上に向けた、薬物情報システムの活用に関する指導・提言を行う。(薬物取締における鑑定・分析に関する指導を含む。) |
|
| タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画 | ||
| 案件開始日 | 平成13年12月25日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ及びその周辺国であるカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムにおいては、国境を越えた家畜の移動が増えてきた結果、家畜の移動と共に家畜病気も国境を越えて広がり、この地域内の畜産業にとって重大な損失をもたらしている。こうした現状の改善と病気の発生を防ぐためには、国毎の対策ではなく、国境を越えた広い地域内での対策が不可欠である。 こうした背景から、1998年、タイ国政府から我が国に対して、広域技術協力「タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画」の要請があり、2001年12月から技術協力を開始した。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 家畜病防除のための地域間協力体制の強化 2. 人材開発 3. 疾病調査方法の改善 4. 動物ワクチンの生産及び品質管理技術の改善 5. 家畜検疫技術の改善 |
|
| 鉄道研修センターA/C | ||
| 案件開始日 | 平成13年4月1日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ国では第6次国家経済社会開発計画(1986-1991)以来、陸海輸送力の近代化を重要課題の一つとして掲げ、特に鉄道の近代化には我が国の借款などにより近代設備の導入を強力に進めてきた。こうした新技術の導入に伴うタイ国鉄職員の再訓練のため、タイ政府は1988年我が国に対して技術協力を要請し、1992年5月のR/D締結後、タイ鉄道研修センター(RTC:1940年設立)において1997年5月まで5年間本プロジェクトが実施された。 プロジェクト終了後も我が国により供与された運転シミュレーター等の訓練機器を活用して年間2000人以上の職員教育が実施されているが、その後新型機関車が導入されたこと、また列車走行中の車両故障時に適切に対応するための訓練が必要となったことから、プロジェクトのアフターケアとして新たな分野での技術移転とその為必要な訓練装置の供与を我が国に要請してきた。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 応急処置訓練装置のデザイン指導 2. 応急処置訓練装置の供与 3. 応急処置訓練装置の据付指導 4. 応急処置訓練装置による教育指導 5. 鉄道教育訓練全般にかかる助言 |
|
| 外傷センタープロジェクト | ||
| 案件開始日 | 平成12年7月1日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ国では、都市化にともない交通事故による死傷者数が急激に増加しており、現在では主要な死亡原因のひとつとなっている。また若年層の死亡者数が急激に増加するとともに、交通事故による障害者数も増加の一途を辿っており、大きな社会問題となっている。 我が国は、1991年から1996年までタイ国コンケン県において実施した、公衆衛生プロジェクトにおいて外傷予防のためのモデル的なシステムの開発に対する協力を実施し、高い評価を得たが、タイ国政府は、この分野での更なる強化を図るため、国立コンケン病院での「外傷センタープロジェクト」の実施を決定し、同センターにおいて外傷予防のためのプロジェクトを実施すべく我が国に技術協力を要請してきた。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 病院ケア・外傷ケア改善のための組織計画策定 ・外傷処置ガイドラインの改訂 ・トリアージシステム計画策定・外傷ケアについての病院スタッフ訓練 2. プレホスピタルケア・住民に対する通報及び応急処置訓練・広報 ・救急指令センターの設置 ・救急サブ・ステーションの設計・設置など |
|
| 工業用水技術研究所(フェーズ2) | ||
| 案件開始日 | 平成12年6月1日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ国では、近年の急激な工業化に伴い、工業用水需要の急増による地盤沈下や、不十分な排水処理による水質汚濁が問題となっている。こうした問題を解決するため、タイ政府は工業用水技術研究所(IWTI)を設立したが、我が国はタイ政府からの要請により同研究所の技術的基盤を固めるため、1998年6月から2000年5月まで技術協力を実施した。工場局は、IWTIスタッフの技術をさらに向上させ、実際に技術指導を行えるようになることを目的とし、我が国に対し、フェーズ2プロジェクトを要請した。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 研修サービス実施(工場エンジニア・公害防止管理者・処理施設オペレーター及び工場局検査官を対象とする教材作成、研修コース・セミナー開催) 2. コンサルティングサービス実施(工場調査・実験、概念設計、改善提案作成、マニュアル・ガイドブック作成) 3. 情報サービス実施(IWTI内部の情報共有システム確立、工業用排水に係る情報の集積・提供、ホームページ・年報による広報) |
|
| 国際寄生虫対策アジアセンタープロジェクト | ||
| 案件開始日 | 平成12年3月23日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | 1998年5月、バーミンガム・サミットにおいて、橋本総理(当時)は、アジアとアフリカに寄生虫対策のための「人造り」と「研究活動」の拠点をつくり、WHO及びG8諸国とも協力して、かかる拠点と周辺諸国とのネットワークを構築し、寄生虫対策の人材育成と情報交換等の促進を提案(以下、「橋本イニシアティブ」)した。1998年6月、プロジェクト形成調査団をタイ及びフィリピンへ派遣し、橋本イニシアティブのアジアでの拠点となる施設の選定を行うための調査を行った結果、アジアにおいてはタイ・マヒドン大学熱帯医学部を拠点とすることが適当との判断を得た。この調査結果を受け、関係者間において具体的な案件形成のための検討が重ねられ、1999年5月から7月まで企画調査員をタイ及び周辺国(フィリピン、ラオス、カンボジア、ミャンマー、ベトナム、マレーシア)へ派遣した。その結果、マヒドン大学熱帯医学部でプロジェクト方式技術協力及び第三国研修によりアジアにおける寄生虫対策のための拠点づくりの協力を行い、周辺諸国については、無償資金協力、個別専門家派遣、研修員の受け入れ等により協力を行うことが適当との提案がなされた。 右背景を踏まえ、我が国は保健省との連携の下マヒドン大学熱帯医学部に国際寄生虫対策アジアセンターを開設し、タイ国政府より同センターを中心に人材育成を主眼においた技術協力の要請があった。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 研修カリキュラムと研修教材の開発、研修施設およびフィールドの整備、タイおよび周辺国の寄生虫対策に携わる人材育成研修を実施する。 2. 現場レベルの調査に基づき、寄生虫対策プログラム運営手法、保健衛生教育手法、予防対策手法に関するモデルを開発する。 3. 人的ネットワークの構築のために必要な活動を実施する。 4. 情報ネットワークの構築のために必要な活動(IT UNIT等の設置を含む)を実施する。 5. 各活動のモニタリングと評価を常時実施する。  |
|
| 東北タイ造林普及計画(フェーズ2) | ||
| 案件開始日 | 平成11年12月13日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | 東北タイ造林普及計画(1994.4.1~1997.3.31)では、タイ東北部における森林の急激な減少に対し、地域住民による造林活動を促進することを目的として大規模苗畑管理技術の開発と住民造林活動の普及を主眼とした活動を行ってきた。終了時評価調査の結果、高品質な苗木の生産技術と林業技術の普及体制の強化がプロジェクトの一層の自立発展に必要と判断され、1997年4月1日より1.5年間のF/U協力を実施し、当初のプロジェクト目標は概ね達成された。 これらの協力成果に基づいて、村落林業の発展と農民参加による持続可能な森林経営を確立させることを目的として、タイ国政府はフェーズ2の協力を我が国に要請越したものである。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 情報 (1) 関連情報の収集・分析 (2) データベース管理システムの構築 (3) 情報提供システムの構築) 2. 技術 (1) 苗畑・造林技術の改良・開発 (2) 林産物利用法の改良・開発 (3) 展示林・モデル林の整備・改良 (4) 森林経営ハンドブックの作成 3. 訓練・普及 (1) モデル地域の選定 (2) 訓練・普及の実践 (3) 訓練・普及手法の改良 4. モニタリング (1) モニタリングの実施 (2) (1)の結果分析   |
|
| 金型技術向上事業 | ||
| 案件開始日 | 平成11年11月1日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | 第5次経済社会開発5ヶ年計画(1981~1986)の一環として金属加工機械産業分野の中小企業の育成を目指していたタイ側の要請に基づき、日本政府は、無償資金協力により金属加工機械工業開発研究所(MIDI)を建設すると共に1986年10月より5年間、同施設を利用して鋳造、熱処理、材料試験、機械加工、機械設計、測定を主な協力分野とするプロジェクト方式技術協力を実施した。 その後、タイ国の裾野産業の輸入依存体質を改善するために、自動車産業及び電気・電子産業を対象に、1993年より開発調査「工業分野振興開発計画(裾野産業)」が実施された。 かかる経緯を踏まえ、タイ国政府は、同調査にて作成されたマスタープラン(M/P)に基づき、上述のMIDIを裾野産業開発部(BSID)として改編することとし、以前実施したプロジェクトによりMIDIに付与された基礎的な機能を拡充し、金型分野の地場の裾野産業を育成して国際競争力を強化したいとして、1996年9月、技術協力を要請してきた。 |
| 2.協力活動内容 | 技術研修・セミナー以外に技術の情報サービス、アドヴァイザリーサービス、試作品製造サービスを行う予定。またそれら活動を通じ、プラスティック金型の設計、NCプログラミング、加工、組立・試打、各分野について技術移転を行う。 |
|
| 都市開発技術向上計画 | ||
| 案件開始日 | 平成11年6月1日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイでは急速な経済成長に伴い、バンコク首都圏を中心に都市化が進んだため、無秩序な都市開発がさまざまな都市問題を招いており、特にバンコクにおける都市環境、交通渋滞等は総合的な都市計画の欠如が原因であると言われている。これらの問題を解決するため、タイ政府は都市開発の手法としての区画整理技術を導入するとともに、都市開発技術者及び都市計画担当行政官を育成する「都市開発訓練センター」を設立した。 同センターでは都市計画にかかる研修コースを実施する等独自の対応を行っているものの、都市開発の分野に関しては技術能力の不足から、都市開発の事業が円滑に進められない状況にあるため、タイ政府は、タイの事情に即した都市開発(主に区画整理)の手法を開発し、都市開発にかかる体系的な研修コースを設け、かかる手法を普及することを目的として我が国に対する技術協力を要請してきた。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 「都市開発」手法の開発 (1) タイ国における都市開発の現状・課題、組織・財政・法令及び技術的な枠組みが調査・分析される。 (2) 上記を踏まえたタイ国における都市開発を推進するための方策が検討される。 2. 研修教材の作成 (1) 「都市計画」及び「都市開発」コースに関わる研修教材(基礎・中級)が作成される。 3. 研修コースの開発及びインストラクターの養成 (1) 既存の都市計画研修コースの内容が改善される。 (2) 都市開発の新研修コースのカリキュラムが開発され、インストラクター候補生が養成される。 (3) 「都市計画」及び「都市開発」コースが実験的に実施される。 (4) 実験的研修コースのモニタリング・評価が行われ、レギュラーコースの内容に反映される。 4. 研修コース(基礎)の開始 (1) 「都市計画」及び「都市開発」基礎研修コースが開発され、実施の準備が整う。 |
|
| 水管理システム近代化計画 | ||
| 案件開始日 | 平成11年4月1日 | |
| 案 件 概 要 |
1.要請背景 | タイ農業はチャオプラヤ河の水源に大きく依存しているが、近年のタイ国の経済成長により、工業、土地造成、リゾート等各分野の開発が進み、チャオプラヤ河流域の水需要は著しく増大しつつある。水需要の大半をしめる農業分野では、乾期の農業用水不足、末端圃場レベルの水利用の非効率性等の課題を抱えている。 我が国は、1985年から1997年まで、灌漑排水施設の計画・設計・施工に係わる適性技術の開発整備、水管理技術の確立を目的とした技術協力を実施してきたが、タイ政府は、これまでの技術協力の成果をさらに発展させ、より一層効率的な水管理システムを完成させ末端圃場までの無駄のない精緻な水管理システムを構築するため技術協力を要請してきた。 |
| 2.協力活動内容 | 1. 圃場水管理と営農 (1) 水利組織の強化 (2) 圃場内施設の整備手法の改善 (3) 作物多様化及び作付け率向上に関する普及活動の強化 2. 流域・デルタレベルの水管理 (1) 適切な水管理システムの開発 (2) 灌漑排水施設の改善方法の検討 (3) 灌漑排水の計画及び施設操作手法の改善 3. 研修 (1) RID技術職員、DOAE普及職員、農民リーダーへの研修 (2) セミナー活動による成果の波及 |
|
![]() Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。