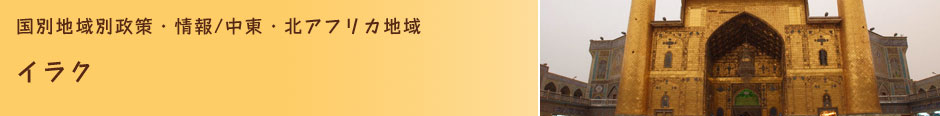イラク復興支援のための無償資金協力に関する説明会(議事録)
1.無償資金協力課長による説明
日本政府は、昨年10月にイラク復興支援のため当面の支援のため15億ドルの無償資金協力の実施をプレッジした。
この実施を円滑に行うため、10月末から昨年末まで、数多くの企業からイラク復興支援のためのプロジェクトについてのヒアリングを行った。外務省に来ていただいた企業は、数十社に上る。各企業からの情報提供に感謝する。関係省庁で行ったヒアリングについても、情報を共有して活用させていただいた。関係省庁、企業の尽力に感謝する。
ヒアリングした案件は数百、あるいはそれ以上にも上ると思われる。また、案件の熟度が高いものもそうでないものもあるが、全部をあわせると数兆円レベルに上ると推定される。そういう意味では、15億ドルの無償資金協力は多額に上るようではあるが、資金のニーズや提案されたプロジェクトの中ではほんの一部であるといえる。また、15億ドルには、すでに実施・決定済みの約9000万ドルの無償も含まれている。
この実施を円滑に行うため、10月末から昨年末まで、数多くの企業からイラク復興支援のためのプロジェクトについてのヒアリングを行った。外務省に来ていただいた企業は、数十社に上る。各企業からの情報提供に感謝する。関係省庁で行ったヒアリングについても、情報を共有して活用させていただいた。関係省庁、企業の尽力に感謝する。
ヒアリングした案件は数百、あるいはそれ以上にも上ると思われる。また、案件の熟度が高いものもそうでないものもあるが、全部をあわせると数兆円レベルに上ると推定される。そういう意味では、15億ドルの無償資金協力は多額に上るようではあるが、資金のニーズや提案されたプロジェクトの中ではほんの一部であるといえる。また、15億ドルには、すでに実施・決定済みの約9000万ドルの無償も含まれている。
15億ドルの無償資金協力は主として4つのチャネルで供与される。
1つは、UNDPが管理する信託基金である。UNDP管理の基金については、ドナーが実施する機関(国連諸機関)と分野を指定することができる。この信託基金に拠出される案件の中には、日本企業が受注し得る案件も含まれると考えられる。
次は、世界銀行が管理する信託基金である。この基金については、ドナーは優先的に資金を回して欲しい分野を指定することができる。
次は、イラクの各省庁、地方自治体、行政機関などに対して直接供与することによって実施される無償資金協力である。今日の説明は主としてこのチャネルの無償資金協力について行われる。
最後に、これまで実施してきたような国際機関に対する緊急無償資金協力(UNDPに対して資金を供与して実施したIREP、ウンムカッスル港緊急浚渫、UNICEFに対して資金を供与したことによって実施したバックツーザスクールプロジェクトなど)である。
これらのチャネルにどのように資金が分配されるか、具体的な点はまだ決定されていない。おおよその目安は検討されているが、治安状況、イラクの政治プロセス、信託基金の活動状況など不確定な要素が多いため、確定的なことは申し上げられない。無償課長として、個人的には、半分以上は、バイの無償資金協力として実施していきたいと考えているが、不確定要素に大きく左右されることについてはご理解頂きたい。
いずれにせよそれぞれのチャネルを通じて資金は供与されるので、イラク(各省庁、地方自治体等)に対して直接供与される無償資金協力は15億ドルの一部である。
日本政府は、2004年以降の中期的な支援として円借款を中心に35億ドルの支援も表明している。したがって、仮に15億ドルの支援が終ったとしても、日本政府の支援が終るというわけではない。
1つは、UNDPが管理する信託基金である。UNDP管理の基金については、ドナーが実施する機関(国連諸機関)と分野を指定することができる。この信託基金に拠出される案件の中には、日本企業が受注し得る案件も含まれると考えられる。
次は、世界銀行が管理する信託基金である。この基金については、ドナーは優先的に資金を回して欲しい分野を指定することができる。
次は、イラクの各省庁、地方自治体、行政機関などに対して直接供与することによって実施される無償資金協力である。今日の説明は主としてこのチャネルの無償資金協力について行われる。
最後に、これまで実施してきたような国際機関に対する緊急無償資金協力(UNDPに対して資金を供与して実施したIREP、ウンムカッスル港緊急浚渫、UNICEFに対して資金を供与したことによって実施したバックツーザスクールプロジェクトなど)である。
これらのチャネルにどのように資金が分配されるか、具体的な点はまだ決定されていない。おおよその目安は検討されているが、治安状況、イラクの政治プロセス、信託基金の活動状況など不確定な要素が多いため、確定的なことは申し上げられない。無償課長として、個人的には、半分以上は、バイの無償資金協力として実施していきたいと考えているが、不確定要素に大きく左右されることについてはご理解頂きたい。
いずれにせよそれぞれのチャネルを通じて資金は供与されるので、イラク(各省庁、地方自治体等)に対して直接供与される無償資金協力は15億ドルの一部である。
日本政府は、2004年以降の中期的な支援として円借款を中心に35億ドルの支援も表明している。したがって、仮に15億ドルの支援が終ったとしても、日本政府の支援が終るというわけではない。
次に、案件の決定についての基本的考え方を説明したい。優先分野としては、先に官房長官が発表したように、電力、保健医療、水・衛生、教育及び治安の改善に資する案件を優先的に考えている。これらの優先分野に入らない案件が排除されるわけではないが、候補案件の中での優先順位が低くなることはある。
イラクの状況に鑑み、現地のニーズに合って、なるべく速やかに調達ができて複雑な据付等が必要でない案件や、効果が早く上がるということを念頭に過去日本企業が手がけた案件のリハビリ案件を中心に考えている。
イラクの状況に鑑み、現地のニーズに合って、なるべく速やかに調達ができて複雑な据付等が必要でない案件や、効果が早く上がるということを念頭に過去日本企業が手がけた案件のリハビリ案件を中心に考えている。
案件を採択した際には、その都度外務省で記事資料などの方法で公表するほか、案件の個別の入札公示については調達代理機関である日本国際協力システム(JICS)のHP上などで公表される。各企業から様々なヒアリングを行ったが、各企業からご提案のあった案件が採用されるかどうかについては、案件があまりにも多岐に上ることもあり個別に回答できない。各企業からのご提案のあった案件は重複していることもあるし、イラク各機関のニーズと必ずしも一対一で合致しているというわけではないので、個別に回答できないという点についてはご理解を頂きたい。
草の根・人間の安全保障無償についても一言言及しておきたい。1億円以内で現地のニーズに速やかに対応できる案件については、今後も実施していく方針である。その際には、現地付近の周辺国で調達できる物資を供与する案件も実施することを考えている。
1月11日からJICAの予備調査チームがアンマン入りして、情報収集に当たることになっている。本調査に関しては、11月に公示が行われ、国内での調査を行ってきた。明10日より、調査団はヨルダンに赴き、アンマン市を拠点とし、イラク国内関係者、ドナー関係者へのヒアリングを通じた案件の緊急性、必要性、イラク国内技術者の技能レベルに関する情報、輸送事情等につき現地コンサルタントの協力も得て調査を行うこととなっている。調査は3月下旬までを予定しており、クウェートでの調査も行う予定。
今後の案件の選定に当たっては、このJICAの予備調査の結果を十分参考にするが、これ以外にも外務省は、通信事情の悪い中、現地のCPA、Coalition Forces、イラク関係機関等と直接連絡を取り、情報を収集して、案件を選定することもあるので、例えばイラクにおいてニーズの高い特殊車両供与などの案件など、この予備調査の対象とならなった案件が、直ちに支援の対象外というわけではない。
草の根・人間の安全保障無償についても一言言及しておきたい。1億円以内で現地のニーズに速やかに対応できる案件については、今後も実施していく方針である。その際には、現地付近の周辺国で調達できる物資を供与する案件も実施することを考えている。
1月11日からJICAの予備調査チームがアンマン入りして、情報収集に当たることになっている。本調査に関しては、11月に公示が行われ、国内での調査を行ってきた。明10日より、調査団はヨルダンに赴き、アンマン市を拠点とし、イラク国内関係者、ドナー関係者へのヒアリングを通じた案件の緊急性、必要性、イラク国内技術者の技能レベルに関する情報、輸送事情等につき現地コンサルタントの協力も得て調査を行うこととなっている。調査は3月下旬までを予定しており、クウェートでの調査も行う予定。
今後の案件の選定に当たっては、このJICAの予備調査の結果を十分参考にするが、これ以外にも外務省は、通信事情の悪い中、現地のCPA、Coalition Forces、イラク関係機関等と直接連絡を取り、情報を収集して、案件を選定することもあるので、例えばイラクにおいてニーズの高い特殊車両供与などの案件など、この予備調査の対象とならなった案件が、直ちに支援の対象外というわけではない。
選定の際の留意点は次の諸点が考えられる。いずれにせよ、イラクの状況に応じ柔軟に対応する方針である。
(1)必要性・緊急性。
(2)治安状況にもよるが、施工(管理)・据付等現地での邦人による作業を必要とするか否か。但し現時点では、邦人(民間の方)のイラク入りは想定していない。
(3)イラク側の優先順位。
(4)工期や調達等、案件の実施に要する期間。
(5)維持管理の難易度。
(6)先方の維持管理能力。
(7)他ドナーによる支援との関係。
(8)技術協力との連携の有無、必要性。
(9)環境や社会問題への配慮。
次に、イラクの各省庁、地方自治体、行政機関、一例として病院に対して直接供与する無償資金協力について具体的な実施方法を説明する。この無償資金協力は、基本的には緊急無償資金協力として実施されるものであり、予算も緊急無償である。
この支援に関しては、イラクにおける特殊な状況を勘案して、今回新たな実施要領を作成した。基本的には一般無償の実施要領をイラクの実情を踏まえて適宜改訂したものになっている。今回の無償資金協力では、原則的に日本企業の契約タイドとなっており、JICSがイラク側機関の調達代理機関として、資金管理にも当たることになっている。
この支援に関しては、イラクにおける特殊な状況を勘案して、今回新たな実施要領を作成した。基本的には一般無償の実施要領をイラクの実情を踏まえて適宜改訂したものになっている。今回の無償資金協力では、原則的に日本企業の契約タイドとなっており、JICSがイラク側機関の調達代理機関として、資金管理にも当たることになっている。
基本的な案件実施の流れは、
- 相手機関等のニーズ、これまでの日本政府の調査、JICAの予備調査、これまでのヒアリング結果などを踏まえて、日本政府において案件の採択を決定する。
- 相手機関の代表者と日本政府(在イラク臨時代理大使を想定)の間の書簡を交換するとともに、実施要領を踏まえた付属文書にも署名してもらう。
- JICSまたは、JICSの下のコンサルタントが入札書類を作成し、入札を行う。入札は一般競争入札となる。なお、既存案件のリハビリ案件など案件の特殊性から競争が成立しないとき、一般競争入札が適切でない場合に、指名競争入札ないし、随意契約になることがあり得るのは、実施要領に明記されているとおりである。
- 落札企業が、物品を納入するあるいは必要なサービスを提供する。この間の資金管理は、JICSが行う。
現在のイラクの情勢に鑑み、当面日本人企業関係者はイラクに入国しないことを前提としている。イラク国内の物品の輸送などについては、基本的に落札業者が現地の業者に委託して実施することを念頭においている。
なお、新政権が発足した場合には、新政権を供与相手先とする無償資金協力を実施することになる可能性も当然あるが、現時点では確たることは申し上げられない。新政権が発足した場合でも、少なくとも当面は今日説明した仕組みで緊急無償を実施していくことになるであろう。
援助の実施のタイミングについて一言言及したい。現在のイラクの状況をふまえれば、できるだけ早く援助を実施することが重要であろう。予算的観点から考えると、可能な限りに今年度中に多くの案件を決定したいと考えているが、イラクにおける状況を考えると、断定的なことは申し上げられない。ただし、来年度予算にもイラク支援の無償予算が含まれていることもあり、今年度中にすべての案件を決定しなければならないと言うわけでもない。また、今回の支援は緊急無償の形式を踏襲しているので、資金を拠出した段階で予算上は実行されたことになるので、たとえば今年度の予算で実施される案件が今年度中に終了しなければならないと言うわけではない。契約書類には当然案件の終了時期が記載されることにはなるが、これもイラクにおける治安の状況などを考えて、工期の延長その他の手続については柔軟に考えていく所存である。
イラク情勢が流動的であることに鑑み、各種リスク要因を如何に織り込むかも、工夫をしていきたいと思っている。具体的には、例えば輸送費、保険費等に関し、実施段階での費用が入札時に想定されたものと比較して著しく高騰した場合は、一義的には、調達代理機関が個々具体的に事情を伺い、協議させていただくこととなろう。基本的な考え方は、一般プロジェクト無償と同様、所要の設計変更、契約額の修正を行うということである。ただし、状況の大きな変化により、輸送費等の著しい騰貴が生じ、残余金の活用や、スペックダウン等の設計変更だけでは対応が困難な場合は、最終的には、財務当局と十分協議した上、被援助機関に対する追加無償の供与を通じた対応も視野に入れている。なお、このような救済措置をとる場合、透明性と公平性を確保するため、当該請負業者よりの要請書を始め変更の根拠を示す関連書類は原則公開することを検討している。
また、事前の調査を十分に行えず、供与限度額の積算の精度が通常より低いことも想定さる。より正確な積算を行うべく、様々な情報収集を行ってきているが、大幅な数量変更や設計変更が生じた場合には、先ほど申し上げた通り、一義的には、調達代理機関が、個々具体的に事情を伺い、協議させて頂くこととなろう。実施段階で数量や、費用項目の増減が生じた場合は、所要の設計変更、契約額の修正を行うということになる。ただし、当初の想定を越える大規模な数量の増加等が明らかになり、残余金の活用や、スペックダウン等の設計変更だけでは対応が困難な場合は、財務当局と協議の上、被援助機関に対する追加無償の供与を通じた対応も視野に入れている。なお、このような追加無償を必要とするような対応をとる場合は、透明性と公正性を確保するため、当該請負業者よりの要請書を始め変更の根拠を示す関連書類は原則公開することを検討している。
また、事前の調査を十分に行えず、供与限度額の積算の精度が通常より低いことも想定さる。より正確な積算を行うべく、様々な情報収集を行ってきているが、大幅な数量変更や設計変更が生じた場合には、先ほど申し上げた通り、一義的には、調達代理機関が、個々具体的に事情を伺い、協議させて頂くこととなろう。実施段階で数量や、費用項目の増減が生じた場合は、所要の設計変更、契約額の修正を行うということになる。ただし、当初の想定を越える大規模な数量の増加等が明らかになり、残余金の活用や、スペックダウン等の設計変更だけでは対応が困難な場合は、財務当局と協議の上、被援助機関に対する追加無償の供与を通じた対応も視野に入れている。なお、このような追加無償を必要とするような対応をとる場合は、透明性と公正性を確保するため、当該請負業者よりの要請書を始め変更の根拠を示す関連書類は原則公開することを検討している。
ガイドラインの中には、入札も交渉も成立しない場合、当該案件の中止を含めて対応を協議するという入札の留保も規定している。この点については、入札の不調によって案件そのものの必要性・重要性が消滅するということではないので、応札価格の詳細なども検討した上で、被援助国との協議も踏まえ、外務省が実施の可否を検討することになる。当初想定されていた事業価格に比べ、正当な根拠をもって大幅な金額の上方修正が必要となるということが判明した場合には、案件の効果などを勘案した上で、案件を中止するということも有り得る。
イラク支援の実施については、公平性と透明性を確保した上で、支援の柔軟性と速度が重要であると認識している。これまでの無償資金協力の制度を踏まえつつも、できるだけ柔軟で、速やかな実施の出来る方法でこれらの無償資金協力を実施していきたいと考えているので、各企業のご理解をお願いしたい。
最後に一つだけ個人的な見解を申し述べることをお許しいただきたい。
皆様よくご承知の通り、昨年11月末にイラクにおいて日本人外交官2名と日本大使館のイラク人運転手が凶弾に倒れ、命を落とした。彼らは、日本の支援をイラク国民の手に届けるために文字通りイラク国内を東奔西走し、案件の発掘、形成、調査、実施に当たっていたのである。彼らの使命は、「日本」のために、イラクを復興し、イラク国民を助けることであった。
無償資金協力課は奥参事官、井ノ上書記官の直接のカウンターパートでもあったし、課員のそれぞれが東京にあって彼らの仕事を一番よく知る立場にあった。また、私個人にとっても奥参事官は公私にわたって最もつきあいの深い無二の親友であった。イラクの治安情勢は引き続き厳しく、また今後の復興支援の実施に際しても様々な障害があると覚悟しているが、我々は彼らが遺した使命、思い、志、事業を引き継いで、イラク復興支援に当たる決意である。
イラクにおける特殊な状況や時間的制約などのため、復興支援の実施については、制度の面などその他でも必ずしも万全とは言えない点もあるかもしれないが、我々なりに全力を尽くしてきたものである。イラクの復興支援においては、今日ご参集の各社を含め、日本の企業の協力と活躍が不可欠と考えているので、今一度、各位のご理解をお願いして、私からの説明を終わることといたしたい。
皆様よくご承知の通り、昨年11月末にイラクにおいて日本人外交官2名と日本大使館のイラク人運転手が凶弾に倒れ、命を落とした。彼らは、日本の支援をイラク国民の手に届けるために文字通りイラク国内を東奔西走し、案件の発掘、形成、調査、実施に当たっていたのである。彼らの使命は、「日本」のために、イラクを復興し、イラク国民を助けることであった。
無償資金協力課は奥参事官、井ノ上書記官の直接のカウンターパートでもあったし、課員のそれぞれが東京にあって彼らの仕事を一番よく知る立場にあった。また、私個人にとっても奥参事官は公私にわたって最もつきあいの深い無二の親友であった。イラクの治安情勢は引き続き厳しく、また今後の復興支援の実施に際しても様々な障害があると覚悟しているが、我々は彼らが遺した使命、思い、志、事業を引き継いで、イラク復興支援に当たる決意である。
イラクにおける特殊な状況や時間的制約などのため、復興支援の実施については、制度の面などその他でも必ずしも万全とは言えない点もあるかもしれないが、我々なりに全力を尽くしてきたものである。イラクの復興支援においては、今日ご参集の各社を含め、日本の企業の協力と活躍が不可欠と考えているので、今一度、各位のご理解をお願いして、私からの説明を終わることといたしたい。
これからは質疑応答のセッションにはいるが、質問のある方は挙手をしていただき、当方の指名によって発言願いたい。また、発言の際には、所属と氏名を明らかにして頂くようお願いする。
2.質疑応答
問:事業の実施にあたっては、日本人は現地に入らず、ローカルスタッフ等を活用して遠隔操作を行うことを想定しているとの趣旨であったが、このようなスタッフの活用のコーディネーションは、民間企業自らが行うのか。或いはJICA等の政府機関がコーディネーションを行うのか。
答:このようなコーディネーションは、原則として契約された企業に行って頂く。書簡の交換などは政府側にて然るべく対応するが、物資の輸送などの調整については、基本的には契約した企業に実施して頂く。但し、当然のことながら、実施にあたっては、様々な情報の提供など、外務省も色々な形で側面支援する。
問:イラク復興支援は時間との戦いでもあるが、迅速な支援を可能にするために、イラク復興支援に限り、一部なりとも契約アンタイドに変更する考えはないか。
答:15億ドルの支援のうち、信託基金経由の支援については、契約アンタイドとなるものもあろう。また、主契約企業が日本企業であっても、通常の無償資金協力同様、サブコントラクターなどは周辺国等第三国の企業を活用することもありうる。
問:実施要領には、支援に先立ち、イラク側からの要請を確認するとの説明がある。通常の無償資金協力の場合、要請状の提出が必要だが、イラク復興支援の場合、誰がどのように要請を確認するのか。
答:先方が必要としないものは供与するべきではなく、そのために先方の意向を確認することが必要である。現在のイラクの状況に鑑み、確認の形式は特に問わない予定で、各省庁と直接連絡を取って確認することもある。
問:今後調査を継続するにつれ、積算に修正が生じる可能性が高いが、この点についてはどう考えるか。
答:イラクの流動的な状況を念頭に置きつつ、輸送費、整備費、保険等については、入札のあり方等柔軟に検討している。例えば、安全面での配慮ということから、警備サービスに対する費用を十分に確保して頂くために、警備費については競争から外すことなどを考えている。
問:周辺国での施設建設は、今回の支援の対象となるか。
答:今回の15億ドルの支援を通じて、周辺国に対して支援を行うことは想定していない。但し、イラク国外での研修や、他の通常の無償資金協力を通じて、従来通り支援は実施していく。
問:予備調査が3月末で終了するようだが、その後すぐに調達が始まるのか。
答:予備調査は、継続的に情報収集を行うことを主たる目的としており、予備調査の終了後、自動的に調達が開始されるということではない。案件の採択は、様々な情報を踏まえ、順次行っていく。
問:自衛隊と関連付けられた形で、ODAが実施される可能性はあるのか。
答:自衛隊が派遣された地域では、ODAの枠組みの中で出来る限りのことは行いたいと考えている。
問:一番最初の案件は、いつ頃実施されるか。
答:出来る限り早く、最初の案件を実施したいと考えている。
問:サマーワでも、この形式のイラク復興支援は実施されるのか。
答:今回ご説明した支援の形式に限らず、これまでバグダッド等で行われてきたように、草の根・人間の安全保障無償や、国際機関経由の支援などもあり得る。
問:現地の電力不足は深刻である。支援を急ぐという観点からは、例えばフェーズ分けの電力案件を実施し、フェーズ1は日本で余っている中古の発電機を少数でも輸送し、フェーズ2で本格的に新品を調達するという考え方はとれないか。
答:発電機については、ごく小型のものについては周辺国で調達し供与した例が既にある。イラクでは、壊れている既存の発電施設を急ぎ修復することが効果的ではないかと考えている。
問:2004年に採択された案件については、必ず2004年中に出荷しなければならないのか。
答:出来る限り早く支援を実施するというのが基本線だが、出荷の時期は、契約によって決定される。2004年に採択された案件について、現地の状況も不確定なことが多いので、絶対に2004年中に出荷しなければならないということではない。予算上は、資金の拠出をもって予算が執行されたことになるので、通常の一般プロジェクト無償のように、予算単年度主義に起因する厳しい工期があるわけではない。
問:米国なども多額の支援を実施するとしており、援助の取り合いという事態は現実に起こりうる。積算作業などについて、慎重になりすぎると出遅れる恐れもあり、案件選定は迅速にお願いしたい。
答:イラク復興支援については、我々としても柔軟性とスピードということを常に念頭において実施していく所存である。
なお、本説明会終了後も、質問やプロジェクトの説明は随時受け付けるので、適宜無償資金協力課に連絡されたい。