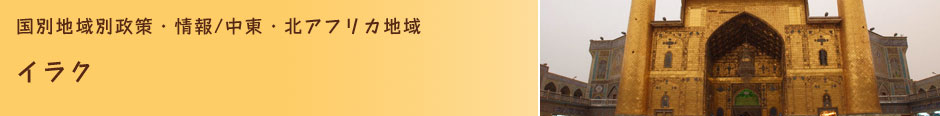イラク復興支援のための二国間無償資金協力に関する実施要領
I.基本事項
1.平成15年10月15日、我が国は、イラクの復興に対する当面の支援として、総額15億ドルの無償資金を供与することを発表した。支援の分野としては、電力、教育、水・衛生、保健、雇用等イラク国民の生活基礎の再建及び治安の改善に重点を置く。なお、イラクの治安状況、通信状況等から詳細な現地調査が極めて困難である中で迅速な支援が必要とされていることから、先ずは、過去に我が国が手がけた案件のリハビリ及び詳細な現地調査を必要としない機材供与案件を中心に選定を行う。
2.我が国は、上記15億ドルの支援の一環として、現在のイラク情勢にも考慮し、イラクの復興開発を迅速かつ効果的に推し進めるべく、イラクの各省庁、地方自治組織の他、病院等イラク国内の適当な実施機関を主たる供与先として二国間無償資金協力を実施することとした。
3.本実施要領は、本件無償資金協力における案件の実施に関する手続きを定め、以てプロセスの公平性・透明性を確保することを目的とするものである。
II.案件の実施要領
1.実施手順概要
(1)案件形成
以下のうち可能な手順を経て案件形成を行う
1)日本国内で外務本省等が日本企業等の国内関係者からのヒアリングを含む関連資料・情報の収集
2)外務本省、JICA(国際協力機構)、JICS(日本国際協力システム)等が行う関連資料・情報の分析
3)JICAの予備調査等(治安状況等に応じて柔軟に実施)
4)イラク側からの関連資料・情報の収集分析
(2)イラク側からの要請
イラクの各省庁、地方自治組織の他、病院等イラク国内の適当な実施機関(以下被援助機関)からの要請を確認する。
(3)案件の採択
案件の採択は外務本省が行う。
(4)書簡の交換
選定された案件実施につき日本政府と当該イラク国内の被援助機関との間で書簡を交換する。右書簡には供与額、案件の内容に加えて以下の手続きが規定される。
1)供与資金の適正使用の確保
2)財・サービスの供与を含む案件実施の主契約者が原則として日本企業となること
3)案件の実施促進のために、日本国政府は独立行政法人国際協力機構(JICA)を実施促進機関として指定すること。
4)案件の実施に当たり、被援助機関と日本政府が推薦する調達代理機関との間での調達代理契約の締結
5)上記調達代理機関が果たすべき業務内容
6)案件の実施に当たり、調達代理機関が契約するコンサルタントの業務内容
7)案件の迅速な実施のために被援助機関が行うべき事項
8)案件完成後の被援助機関の維持管理責任
9)適正な情報の公開
10)残余金の使途を含め案件に係る全ての問題について日本政府と被援助機関が協議すること
(5)調達代理機関との契約
上記(4)の書簡に基づき、被援助機関は、自らの責任において資金の適正使用・管理、案件の維持管理を確保出来るよう、専門的な知見と経験を有するとして日本政府が推薦する調達代理機関と調達代理契約を締結する。
(6)供与資金の管理・移動(詳細は別添)
本件無償資金協力により供与される、資機材の購入や施設の改修等に必要な資金は、銀行取極(B/A)により被援助機関名義で開設される日本の銀行口座に送金される。被援助機関は資金管理関連業務を調達代理機関に委託する。
(7)契約
上記(5)により被援助機関と調達代理契約を締結する調達代理機関は、被援助機関に代わり案件の実施に必要なコンサルティングサービスのためにコンサルタントと、生産物と役務の調達を目的として業者と契約を締結する。
(8)案件の実施
適正な案件の実施のため、コンサルタントは契約に基づき、案件の実施に必要な生産物と役務の調達にかかるコンサルティングサービスを提供し、業者は契約に基づき、生産物及び役務を提供する。調達代理機関はコンサルタント及び業者による案件実施の進捗状況について、必要に応じ、被援助機関に報告し同意を得る。案件の進捗に応じた実施の促進はJICAが行う。
なお、被援助機関による、調達代理機関の利用、コンサルタントの利用及び生産物と役務の調達に際しては、それぞれ、以下2.、3.及び4.に則って行うよう、書簡の交換時に、付属文書によって被援助機関に義務付けることとする。
なお、被援助機関による、調達代理機関の利用、コンサルタントの利用及び生産物と役務の調達に際しては、それぞれ、以下2.、3.及び4.に則って行うよう、書簡の交換時に、付属文書によって被援助機関に義務付けることとする。
2.調達代理機関の責務
(1)調達代理機関
調達代理機関は、被援助機関に対し、十分な勤勉さと適切な知見をもって役務を提供しなければならない。
(2)調達代理業務
調達代理機関の想定される主要な業務は以下のとおりであり、調達代理業務は案件毎に締結される調達代理契約によりその具体的範囲が規定される。
1)被援助機関に代わり贈与による供与資金の管理を行うこと。
2)日本国政府に対し資金管理報告書を提出すること。
3)被援助機関に代わりコンサルタント及び業者と契約を締結し、適正な案件の進捗について、必要に応じ、被援助機関に報告し同意を得ること。
(3)契約の承認
被援助機関と調達代理機関との間で締結される調達代理契約にかかる契約書は、日本国政府により承認される必要がある。
(4)支払方法
被援助機関は日本の銀行と銀行取極(B/A)を締結しなければならない。また、被援助機関は調達代理機関に政府口座から調達口座への資金移動権限を与え、調達代理機関は供与資金の被援助国政府口座から調達口座への移動手続きを行い、適正かつ公正に資金管理を行う(別添参照)。なお、支払いは日本国政府が定める規準により行われる。
(5)調達代理契約の修正
調達代理契約に修正が必要な場合には、修正契約を行わなければならない。修正契約は、日本国政府により承認される必要がある。
3.コンサルタント利用の要領
(1)コンサルタント
調達代理機関は、被援助機関に代わり、案件の設計、入札および調達監理に関し、コンサルティングサービスのための契約を締結する。
(2)適格性
コンサルタントは日本の自然人、または日本の自然人によって支配される日本の法人でなければならない。
(3)推薦
コンサルタントはJICAにより選定され推薦される。
推薦は案件にかかる事前の調査からの技術的一貫性を確保することによって案件の実施を促進するものである。
推薦は案件にかかる事前の調査からの技術的一貫性を確保することによって案件の実施を促進するものである。
(4)コンサルティングサービスのための契約
コンサルタントは、調達代理機関に対し、十分な勤勉さと適切な技術的判断をもって役務を提供しなければならない。コンサルタントにより提供されるコンサルティングサービスの範囲は、次のものを含む。
1)案件の詳細設計調査を実施すること。
2)公正で適正な調達を実施すること。
3)契約業者に対し適切な監理と指導を行うこと。
4)検査機関に委託された船荷検査を含むプロジェクト実施を通じての生産物及び役務に関する検査を実施すること。
5)完了段階及び保証期間満了時における検査を実施すること。
6)進捗状況報告書を作成すること
(5)日本国政府への報告
JICAを通じ、プロジェクト実施の進捗に関する書面での報告が以下の各段階の完了後、日本国政府に対し直ちに提出されなければならない。JICAは、提出のあった書面を、その内容を確認したうえで、確認結果の所見と合わせ日本国政府に送付する。日本国政府は、案件実施のプロセスに問題があると判断した場合には、速やかに所要の措置を講ずる。
1)入札図書作成(入札案内、事前資格審査書類及び詳細設計に係る報告書がある場合にはそれらを含む)
2)入札評価
3)調達代理機関とコンサルタント及び調達業者の契約
4)完了検査
5)瑕疵検査
(6)設計変更
もし予期せぬ事情により以下に例示されているような案件の設計変更が必要となった場合には、調達代理機関はコンサルタントを介し、日本国政府による事前の承認を、JICAを通じて得なければならない。JICAは、設計変更内容を確認したうえで、確認結果の所見等も合わせて日本国政府に送付する。
1)案件サイトの変更
2)建物あるいは施設の主要な構造及び/または強度の変更
3)建物あるいは施設の規模の変更
4)主要機材の規格または数量の変更
5)契約の修正が必要となる変更
4.生産物と役務の調達の要領
(1)総論
1)契約業者
契約業者は、原則として、贈与における生産物及び役務の調達を適正に実行できる日本の自然人、または日本の自然人によって支配される日本の法人でなければならない。
契約業者は、原則として、贈与における生産物及び役務の調達を適正に実行できる日本の自然人、または日本の自然人によって支配される日本の法人でなければならない。
2)調達適格国
イラク復興無償資金協力により調達適格とされる生産物は、原則として日本製またはイラク国内で一般的に流通しているものでなければならない。ただし、日本製またはイラク国内で一般的に流通しているもの以外の生産物の調達も、日本国政府の事前の同意をもって行われうる。
イラク復興無償資金協力により調達適格とされる生産物は、原則として日本製またはイラク国内で一般的に流通しているものでなければならない。ただし、日本製またはイラク国内で一般的に流通しているもの以外の生産物の調達も、日本国政府の事前の同意をもって行われうる。
3)不適正調達
日本国政府は、契約業者に対し、贈与による事業の下では、その事業にかかる調達及び実施に当たり最高水準の倫理を遵守するよう要求する。この点に関し、日本国政府は、当該契約を受注するために、契約業者が腐敗または不正行為に関与したと認めたときは、その契約を認証しない。日本国政府は、他の日本の贈与による、または他の日本のODAによる事業の契約を受注するためまたは実施中に、契約業者が腐敗または不正行為に関与したと認めたときは、日本国政府が定める一定期間、贈与による事業の契約を受注することから失格とする。
また、日本国政府機関が措置を行った企業の製品が調達されることが想定される場合、日本国政府はイラク政府に対し、日本国政府機関の措置の期間内は当該企業の製品を調達対象外とするよう申し入れることが出来る。
日本国政府は、契約業者に対し、贈与による事業の下では、その事業にかかる調達及び実施に当たり最高水準の倫理を遵守するよう要求する。この点に関し、日本国政府は、当該契約を受注するために、契約業者が腐敗または不正行為に関与したと認めたときは、その契約を認証しない。日本国政府は、他の日本の贈与による、または他の日本のODAによる事業の契約を受注するためまたは実施中に、契約業者が腐敗または不正行為に関与したと認めたときは、日本国政府が定める一定期間、贈与による事業の契約を受注することから失格とする。
また、日本国政府機関が措置を行った企業の製品が調達されることが想定される場合、日本国政府はイラク政府に対し、日本国政府機関の措置の期間内は当該企業の製品を調達対象外とするよう申し入れることが出来る。
(2)調達手続
1) 入札方式
入札は一般競争入札を原則とする。ただし、一般競争入札が最も経済的かつ効率的ではないと認められる場合には、一般競争入札以外の方法を採用することができる。
(1) 一般競争入札
贈与は、経済性および効率性とともに、生産物及び役務の提供に適格な入札者間で不公平がないことに関し、然るべき注意がなされて使用されなければならない。一般競争入札は、このような原則を満足させる最良の方法であると考えられる。
(2) 一般競争入札方式以外の調達方法
入札は一般競争入札を原則とする。ただし、一般競争入札が最も経済的かつ効率的ではないと認められる場合には、一般競争入札以外の方法を採用することができる。
(1) 一般競争入札
贈与は、経済性および効率性とともに、生産物及び役務の提供に適格な入札者間で不公平がないことに関し、然るべき注意がなされて使用されなければならない。一般競争入札は、このような原則を満足させる最良の方法であると考えられる。
(2) 一般競争入札方式以外の調達方法
- 資格要件を満たした供給業者の数が限られている場合
- 調達金額が少なく、入札予定者が関心を持つことに疑問があり、一般競争入札の利点がその実務的煩雑さによって阻害される場合
- 入札の全部又は一部が不調となる場合
- 既に調達されている機材等のスペアパーツ及び製造業者が限定されている機材等を調達する場合
- 緊急に調達する場合など一般競争入札が適切でないと認められる場合
上記の場合には、以下の調達方法が適当なものとして適用されうる。なお、その場合においても、一般競争入札の方式に最大限則るよう努めなければならない。
a) 指名競争入札
b) 随意契約
2)契約の形式
契約は、案件毎に適切な契約形式を採用するものとする。
契約は、案件毎に適切な契約形式を採用するものとする。
3)契約の規模
できる限り広い競争を得るため、入札に付される個々の契約は、可能な場合は常に、入札者を引きつけるに十分な大きさであるべきである。一方、もし案件を技術的、実務的に2ないしそれ以上の数の契約に分割でき、かつ、かかる分割が最も広い競争につながると見なされるならば、案件はそのように分割されるものとする。
できる限り広い競争を得るため、入札に付される個々の契約は、可能な場合は常に、入札者を引きつけるに十分な大きさであるべきである。一方、もし案件を技術的、実務的に2ないしそれ以上の数の契約に分割でき、かつ、かかる分割が最も広い競争につながると見なされるならば、案件はそのように分割されるものとする。
4)入札者の事前資格審査
必要と認められる場合は、入札に先だって入札参加希望者に対して、事前資格審査を行うことができる。事前資格審査は、入札予定者が当該契約を実施する能力及び資源を有しているかについて行われ、その際には原則として次の点を考慮に入れて審査が行われるものとする。
必要と認められる場合は、入札に先だって入札参加希望者に対して、事前資格審査を行うことができる。事前資格審査は、入札予定者が当該契約を実施する能力及び資源を有しているかについて行われ、その際には原則として次の点を考慮に入れて審査が行われるものとする。
(1) 同種の契約についての実績
(2) 人材、機器、及び建設又は製造設備に関する能力
(3) 財務状況
特定の契約に係る事前資格審査の案内は、公告、通知されねばならない。契約の規模および資格要件を明確に記載の上、事前資格審査を受けることを望むすべての者に送付されねばならない。事前資格審査の完了の後、可及的速やかに、入札適格者に対して入札書類が発行されねばならない。指定された基準を満たす入札者のすべてに、入札参加が認められなければならない。5)公告
公告は、すべての入札予定者が、入札について知り、また入札に参加するための公平な機会を持つような方法で行われなければならない。入札の公告は可能な範囲で十分な期間を設け、入札参加希望者に周知されやすい適切な媒体を利用して行わなければならない。
公告は、すべての入札予定者が、入札について知り、また入札に参加するための公平な機会を持つような方法で行われなければならない。入札の公告は可能な範囲で十分な期間を設け、入札参加希望者に周知されやすい適切な媒体を利用して行わなければならない。
(3)入札図書
1)総論
入札図書は、調達されるべき生産物および役務に対し、入札者が有効な応札を準備するために必要な情報を盛り込んでいなければならない。一般的には以下が含まれる。
入札図書は、調達されるべき生産物および役務に対し、入札者が有効な応札を準備するために必要な情報を盛り込んでいなければならない。一般的には以下が含まれる。
(1) 入札者心得
(2) 入札書式
(3) 契約書案
(4) 技術仕様書
(5) 必要な付属書等
2)入札図書の明確性
入札図書には、競争性を徒らに阻害する要素が含まれてはならず、また、調達される生産物および役務、契約義務、その履行方法、履行期限、最低履行要求、保証その他の必要条件が記載されるものとする。
入札図書には、競争性を徒らに阻害する要素が含まれてはならず、また、調達される生産物および役務、契約義務、その履行方法、履行期限、最低履行要求、保証その他の必要条件が記載されるものとする。
3)入札の価格と通貨
入札図書は、下記の点につき、明確に記述するものとする。
入札図書は、下記の点につき、明確に記述するものとする。
(1) 入札価格は、日本円または米国ドルで表示しなければならない。
(2) 入札金額は不変で最終のものでなければならない。
4)入札評価の方法
入札図書は、入札評価の方法を明記するものとする。原則として、以下の記述を含むものとする。
(1) 「入札図書に規定されている条件や仕様に合致し、予め設定した見込額以下で、最低価格で応札した入札者が落札者となる」
(2) 入札がいくつかのロットに分割されている場合には、以下の記述を含むこと。
「入札評価はロット毎に別々に行われなければならない」
入札図書は、入札評価の方法を明記するものとする。原則として、以下の記述を含むものとする。
(1) 「入札図書に規定されている条件や仕様に合致し、予め設定した見込額以下で、最低価格で応札した入札者が落札者となる」
(2) 入札がいくつかのロットに分割されている場合には、以下の記述を含むこと。
「入札評価はロット毎に別々に行われなければならない」
5)契約条件
入札図書は調達代理機関と契約業者の権利および義務等の契約条件を明確に規定するものとする
入札図書は調達代理機関と契約業者の権利および義務等の契約条件を明確に規定するものとする
6)仕様書
入札図書に記載される仕様は、生産物と役務の調達に関する重要な事項が明記され、入札の評価を行う際に考慮されるべき主要要素または基準を特定するものとする。仕様書は、できる限り広い競争を確保し奨励するように作成されるものとする。
商標名、カタログ番号もしくはこれらに類する分類に言及することは、特定のスペアパーツの調達の場合、その他特に必要な場合以外は、避けるものとする。
入札図書に記載される仕様は、生産物と役務の調達に関する重要な事項が明記され、入札の評価を行う際に考慮されるべき主要要素または基準を特定するものとする。仕様書は、できる限り広い競争を確保し奨励するように作成されるものとする。
商標名、カタログ番号もしくはこれらに類する分類に言及することは、特定のスペアパーツの調達の場合、その他特に必要な場合以外は、避けるものとする。
(4)開札、入札評価及びアワード
1)開札手続
入札の最終受付日時と場所および開札の日時と場所は、入札公告時に通報されるものとする。入札は、定められた日時および場所で、原則として、入札者もしくはその代理人の立ち会いのもとで開札されるものとする。
入札の最終受付日時と場所および開札の日時と場所は、入札公告時に通報されるものとする。入札は、定められた日時および場所で、原則として、入札者もしくはその代理人の立ち会いのもとで開札されるものとする。
2)入札の補足説明と変更
いかなる入札者も、開札の後には入札の変更を許されるべきではない。入札を実質的に変更しない補足説明については、受け入れられる場合がある。いかなる入札者に対しても提出済みの入札にかかる補足説明を求めることができるが、入札の実質的内容や価格の変更は求められない。
いかなる入札者も、開札の後には入札の変更を許されるべきではない。入札を実質的に変更しない補足説明については、受け入れられる場合がある。いかなる入札者に対しても提出済みの入札にかかる補足説明を求めることができるが、入札の実質的内容や価格の変更は求められない。
3)手続の非公開
開札後、アワードが発出されるまでは、入札の審査、補足説明および評価ならびにアワードにかかる推薦に関係したいかなる情報も、入札者や公式にこれらの手続きに関係していない他の者に対して、公開されるべきではない。
開札後、アワードが発出されるまでは、入札の審査、補足説明および評価ならびにアワードにかかる推薦に関係したいかなる情報も、入札者や公式にこれらの手続きに関係していない他の者に対して、公開されるべきではない。
4)入札審査
開札に続き、(i) 計算上の重大な誤りがないか、(ii) 入札が入札書類に実質的に合致しているか、(iii) 要求されている証明書が添付されているか、(iv) 要求されている保証を伴っているか、(v) 書類が正当に署名されているか、(vi)入札が入札図書の指示に合致しているかどうか、について確認されるべきである。もし、入札が実質的に仕様に合致していない場合、あるいは容認できない留保が含まれている場合、あるいはそのほか入札図書に実質的に応じていない場合、その入札は失格とされるべきである。
開札に続き、(i) 計算上の重大な誤りがないか、(ii) 入札が入札書類に実質的に合致しているか、(iii) 要求されている証明書が添付されているか、(iv) 要求されている保証を伴っているか、(v) 書類が正当に署名されているか、(vi)入札が入札図書の指示に合致しているかどうか、について確認されるべきである。もし、入札が実質的に仕様に合致していない場合、あるいは容認できない留保が含まれている場合、あるいはそのほか入札図書に実質的に応じていない場合、その入札は失格とされるべきである。
5)入札評価
(1)入札評価は、入札図書に記述されている条件にしたがって行われなければならない。技術仕様に実質的に合致しており、かつ入札図書の他の規定に応じている入札は、提出された価格のみに基づいて判定されねばならず、予め設定した見込額以下で最低価格を提示した入札者が落札者とされねばならない。
(2)全ての入札価格が予め設定した見込額を上回った場合、若干の時間的余裕をおいた後、その場で第二回の入札を実施することとする。
(3)第二回の入札においても全ての入札価格が予め設定した見込額を上回る場合、価格交渉が行われるものとする。価格交渉は入札価格の低い者順とする。
(1)入札評価は、入札図書に記述されている条件にしたがって行われなければならない。技術仕様に実質的に合致しており、かつ入札図書の他の規定に応じている入札は、提出された価格のみに基づいて判定されねばならず、予め設定した見込額以下で最低価格を提示した入札者が落札者とされねばならない。
(2)全ての入札価格が予め設定した見込額を上回った場合、若干の時間的余裕をおいた後、その場で第二回の入札を実施することとする。
(3)第二回の入札においても全ての入札価格が予め設定した見込額を上回る場合、価格交渉が行われるものとする。価格交渉は入札価格の低い者順とする。
6)入札の失格
入札の失格は、入札が入札図書に合致していない場合のみ、正当化され得る。
入札の失格は、入札が入札図書に合致していない場合のみ、正当化され得る。
7)入札評価報告書
落札または失格の理由を明らかにした入札評価報告書が、作成されなければならない。
落札または失格の理由を明らかにした入札評価報告書が、作成されなければならない。
8)入札の留保
全ての入札価格が予め設定した見込額を上回った場合であって、全ての応札者との価格交渉が成立しなかった場合は、日本国政府に詳細を報告し、当該入札にかかる対応を協議しなければならない。
日本国政府は、必要な場合、当該案件の中止も含め、被援助機関と対応について協議することができる。
全ての入札価格が予め設定した見込額を上回った場合であって、全ての応札者との価格交渉が成立しなかった場合は、日本国政府に詳細を報告し、当該入札にかかる対応を協議しなければならない。
日本国政府は、必要な場合、当該案件の中止も含め、被援助機関と対応について協議することができる。
9)アワード
アワードは、定められた入札の有効期限内に、入札図書に規定されている条件と仕様に合致した入札者で、予め設定した見込額以下で最低価格を提示した入札者に対して行われなければならない。
いかなる入札者も、アワードの条件として、入札図書に規定されていない責任を負うことや、役務を行うことを要求されてはならない。
アワードは、定められた入札の有効期限内に、入札図書に規定されている条件と仕様に合致した入札者で、予め設定した見込額以下で最低価格を提示した入札者に対して行われなければならない。
いかなる入札者も、アワードの条件として、入札図書に規定されていない責任を負うことや、役務を行うことを要求されてはならない。
(5)契約
1)総則
調達契約は、入札図書に定められた事項に基づき合意され、適切かつ迅速に締結され、履行されるものとする。
調達契約は、入札図書に定められた事項に基づき合意され、適切かつ迅速に締結され、履行されるものとする。
2)契約書
契約当事者間で締結される契約書は、入札図書に添付されている契約書案の内容を基本とし、次の事項が記載されなければならない。
契約当事者間で締結される契約書は、入札図書に添付されている契約書案の内容を基本とし、次の事項が記載されなければならない。
(1)契約日
契約日は契約当事者間で契約書に正式に署名された日とする。
契約日は契約当事者間で契約書に正式に署名された日とする。
(2)契約金額
契約当事者間で合意された契約金額が明記されるものとする。
契約当事者間で合意された契約金額が明記されるものとする。
(3)権利と義務
契約当事者間で分担される権利と義務の内容が明記されるものとする。
契約当事者間で分担される権利と義務の内容が明記されるものとする。
(4)支払条件
支払時期、支払の対象、支払方法(一括・分割払いの別)等の支払条件が明記されるものとする。なお、分割払いを行う場合には、各期に支払うべき金額を明記する。
支払時期、支払の対象、支払方法(一括・分割払いの別)等の支払条件が明記されるものとする。なお、分割払いを行う場合には、各期に支払うべき金額を明記する。
(5)履行期限
機材等の納入期日、完工日等の履行期限が明記されるものとする。
機材等の納入期日、完工日等の履行期限が明記されるものとする。
(6)契約履行保証
契約履行保証金その他契約履行保証が明記されるものとする。契約履行保証金が受注者によって供託される場合には、当該保証額は妥当な金額でなければならない。また、当該契約が履行された場合には、直ちに当該保証金等は受注者に返却されなければならない。
契約履行保証金その他契約履行保証が明記されるものとする。契約履行保証金が受注者によって供託される場合には、当該保証額は妥当な金額でなければならない。また、当該契約が履行された場合には、直ちに当該保証金等は受注者に返却されなければならない。
(7)不可抗力
契約の履行に当たり不可抗力と認められる原因によって、当事者が義務を履行できなくなった場合には、これを不履行とはみなさない旨が明記されるものとする。
契約の履行に当たり不可抗力と認められる原因によって、当事者が義務を履行できなくなった場合には、これを不履行とはみなさない旨が明記されるものとする。
(8)適用される法律及び紛争の解決
当事者間に発生した本契約に係る紛争の解決に関して適用される法律及び処理機関について明記されるものとする。
当事者間に発生した本契約に係る紛争の解決に関して適用される法律及び処理機関について明記されるものとする。
(9)瑕疵担保責任
機材等の引渡後一定期間の瑕疵担保期間が明記される
機材等の引渡後一定期間の瑕疵担保期間が明記される
3)契約の修正
契約に修正が必要な場合には、修正契約を行わなければならない。
契約に修正が必要な場合には、修正契約を行わなければならない。
別添
I.資金移動
1.口座開設及び銀行取極(B/A)
被援助機関は口上書等に記載された口座開設期限までに、または、開設期限が規定されていない場合は可及的速やかに、被援助機関名義の非居住者用円普通預金口座(以下“Account”という。)を日本国内の銀行(以下“Bank”という。)に開設し、口上書等の規定に従って記載された期限までに、または、可及的速やかに、この旨を日本国政府に文書で通知しなければならない。
また、被援助機関は、資金移動にかかる取極をBankと締結しなければならない。
また、被援助機関は、資金移動にかかる取極をBankと締結しなければならない。
2.Accountの目的
Accountの主な目的は、以下のとおり規定される。
(1)日本国政府からの贈与の受け入れ。
(2)Agentとの契約及び業者契約に基づく支払。
(3)使用期限後の残金の日本国政府への返納。
3.贈与の実施
日本国政府は、口上書等の規定にしたがって定められた期日までの間に、または、可及的速やかに、Accountに贈与資金全額を円貨払する。(ただし、日本国政府と被援助機関との間で別途合意される場合には、この贈与の実施期限は延長される。)
4.Agentに対する包括的支払授権の発給
被援助機関は、調達代理契約と同時にAccountのすべての資金を調達用資金(以下"Advances"という)として調達資金口座に移動する権限をAgentに委任するため、Agentに対して包括的支払授権書を発給するか、または、それに代わる手続きを行う。
5.Accountから調達資金口座への資金移動請求
Agentは、生産物及び役務の調達に必要な資金並びに調達代理契約に基づくAgentへの支払金の移動をBankに請求する。この請求には以下の書類を添付しなければならない。
(1)移動資金で調達されるものの詳細な見積書(原本)
(2)括的支払授権書(原本)、または、必要に応じてそれに代わる文書(原本)
(3)調達代理契約にかかる日本国政府による承認書の写し
またAgentは、このBankへの請求書及び見積書の写しを、被援助機関に同時に送付しなければならない。
6.Accountから調達資金口座への資金移動
BankはAgentから提出された資金移動請求について被援助機関に通知する。Bankは、営業日数10日以内に被援助機関より異議が出されなければ、Agentからの請求額全額をAccountから調達資金口座に対し、Advancesの全部あるいは一部として送金する。
II.残余金の使用
残余金(当初計画の生産物及び役務の調達後のAccount及びAdvancesの合計残額(発生利子を含む)をいう)が発生した場合、当該案件の趣旨、内容等に合致し、当該案件の効果的な運営・実施に資するために必要な生産物、役務の調達に対しては、日本国政府による事前の承認を得た上で残余金の使用が認められる。
III.残金の日本国政府への返納
1. Accountからの資金移動は「贈与」振込日から12ヶ月以内に実施されなければならず、期限を超過した後に残金がある場合には、日本国政府へ返納しなければならない(ただし、日本国政府と被援助機関との間で別途合意がなされた場合は、この限りではない)。
2. 必要とする生産物及び役務すべての調達を完了した被援助機関は、日本国政府に調達が完了した旨の完了報告書を提出する。しかし、贈与及び発生利子の一部が使用されずにAccount又はAdvancesに残金があると報告された場合には、日本国政府はこの残金を日本国政府に返納する手続きについて被援助機関に通知する。被援助機関は、この通知に従い残金を日本国政府に遅滞なく返納しなければならない。