ガーナ・学校保健によるマラリア等寄生虫症対策~『貧困の病』制圧の鍵は『人』~
『寄生虫症』と聞いても、現代の日本人にはあまり馴染みがないかもしれない。しかし、日本でも第二次世界大戦後まで寄生虫症が蔓延していた時代があった。また、世界に目を向けると、現在も開発途上国を中心として寄生虫症に感染し、苦しんでいる人がたくさんいる。
寄生虫症とは
代表的な寄生虫疾患には、マラリア、土壌伝播寄生虫、住血吸虫症、フィラリア症などがあり、現在全世界の6分の1の人口である10億人が寄生虫症に感染している(WHOサイト![]() )。なかでもマラリアの発症数は年間1.9-3.3億人、年間死亡者数は100万人を超えていると言われており、その凡そ9割はサハラ以南のアフリカ諸国である。(出典:World Malaria Report 2008)
)。なかでもマラリアの発症数は年間1.9-3.3億人、年間死亡者数は100万人を超えていると言われており、その凡そ9割はサハラ以南のアフリカ諸国である。(出典:World Malaria Report 2008)
寄生虫症は『貧困の病』
寄生虫症が流行する国の多くは開発途上国であり、その原因は媒介動物の生息に適した熱帯の風土に加え、感染症の流行を促進する貧困や劣悪な生活環境などが挙げられる。マラリアをはじめとする寄生虫症は、子供の発育障害、学力低下、働き盛りの労働力の低下を招き、途上国において多大な社会的経済的損失を与えている。例えば、マラリアによるアフリカの経済損失は年間推定120億ドル(約1.2兆円)とも言われている。また、地球温暖化に伴い、従来マラリアの発症地ではなかった地域での流行現象が出てくるという影響も出てきており、地球規模の問題として国際社会が協力して対処するべき、緊急の課題となっている。
日本の経験を世界へ
第二次世界大戦直後の日本は、多くの国民が生存ラインぎりぎりの貧困を経験した。当時の土壌伝播寄生虫の感染率は国民の70%に及び、住血吸虫症やマラリア等の寄生虫疾患が国民の健康に大きな影響を及ぼしていた。そのような困難の中、日本は行政、寄生虫専門家及び民間団体が一体となり、地域住民の積極的な参加の下、全国的な寄生虫対策を展開し、戦後10年程度で制圧に成功した実績がある。また、寄生虫対策を学校保健に統合する新たなアプローチを生み出し、総合的な地域保健活動へと発展させ、地域開発にもつなげた。これは保健システム強化に関する日本独自の経験であり、現在多くの途上国が抱えている地域保健問題の解決に大いに役立つものである。
1997年のデンバー・サミットで、当時の橋本龍太郎首相(当時)は寄生虫症の国際的対策の必要性を訴え、「地球規模の取組」(橋本イニシアティブ)を提唱した。また、翌98年には寄生虫対策の人材養成と情報交換等を向上させていくことを内容とする提案を行い、日本がリードする形で国際寄生虫対策が展開されていくこととなった。これを受け、日本はアジア(タイ・マヒドン大学)とアフリカ(ケニア・中央医学研究所、ガーナ・野口記念医学研究所)に寄生虫対策拠点を設立した。具体的にはタイに、「国際寄生虫対策アジアセンター(ACIPAC)」、ケニアに「国際寄生虫対策東南アフリカセンター(ESACIPAC)」、ガーナには「国際寄生虫対策西アフリカセンター(WACIPAC)」を設立し、寄生虫対策支援を進めてきた。
ガーナ・WACIPACプロジェクト
2004年、日本はガーナにおいて、JICA(国際協力機構)および、野口記念医学研究所を実施機関として、技術協力プロジェクト「国際寄生虫対策西アフリカセンター(WACIPAC)プロジェクト」(2004.01~2008.12)を立ち上げた。日本の経験を踏まえた土壌伝播寄生虫、住血吸虫、マラリアなどの寄生虫対策のための人材育成、学校保健を基盤とした寄生虫対策モデルの試行や、情報ネットワークの構築等に取り組み、成果を上げている。
マンゴーがマラリアの感染源?!
「マンゴーじゃなくて、蚊がマラリアを運ぶんだよ~♪」 ガーナの首都アクラから約90キロ東の町、カセで、小学生たちが町中を歌いながら行進している。驚くべきことに、かつてこのコミュニティの多くの児童や住民の間では、「熟していないマンゴーを食べるとマラリアに羅患する」といった誤った知識が定着していた。そこで、マラリアの正しい知識を広めるため、現地の学校の先生や児童たちが啓発ソングを考案した。こうした人と地域に密着したマラリア撲滅キャンペーン活動は、WACIPACプロジェクトの取組の一環で行われたものである。

マラリア対策のスローガンを掲げ
歌を歌いながらコミュニティを行進する児童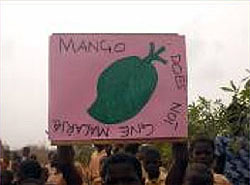
マラリア感染はマンゴーのせいじゃない!!
「橋本イニシアティブ」の日本の寄生虫対策の要は『学校保健』と『人材育成』
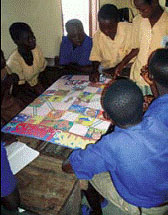
寄生虫ゲームで
盛り上がる児童ら
日本は、学校保健をエントリーポイントとして、寄生虫対策を含む健康教育や人材育成、情報ネットワークの構築を支援している。WACIPACプロジェクトにおいては、小学校で健康教育を実施し、紙芝居や寄生虫ゲームなどの教材を使って寄生虫や衛生に関する正しい知識を学童が習得し、その知識を学童がより親しみやすく理解されやすい形で家族や地域住民に伝えることにより、地域の保健衛生向上にも貢献した。このような学校保健の取組は治療のような即効性はないが、継続的な効果が期待できる非常に有効な支援である。
また、WACIPACプロジェクトでは、メンバー国※の行政官らに対して国際研修を行うことにより、ガーナで検証された寄生虫対策モデルを近隣諸国に拡大することにも重点を置いた。国際研修を受けた延べ人数は137人にも達し、これらのメンバー国では、研修参加者が持ち帰った知識と技術をもとに、保健省、教育省等の省庁横断的な対策委員会の発足、駆虫プログラムの実施、学校保健ガイドラインの策定などの活動が実施され、成果を収めている。さらにはこれらのメンバー国、国際機関、NGOや、タイ・ケニアにおける寄生虫対策プロジェクトとの情報交換も推進し、情報ネットワークを築いている。
※メンバー国 ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、コートジボアール、ガーナ、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、トーゴ (下線は重点支援国)
成功の鍵は『人』
本プロジェクトは、学校保健を通じて学童や地域住民のマラリアを含む寄生虫対策に貢献したのみならず、学校とコミュニティとの連携が促進され、また、寄生虫疾患のみならず幅広い健康教育を実施したことで、公衆衛生の向上にもつながった。さらに、近隣諸国を含む人材育成や情報ネットワークの構築にも貢献し、最終的には各国の保健システム強化へつなげた点は高い評価を得ている。また、本プロジェクトにより、各国の寄生虫対策を実行する責任の『主体』が改めて明確に認識された。つまり、主体となるべきは各国の住民である。このように、プロジェクト成功の鍵は『人』である。モデル国であるガーナでのプロジェクトは2008年12月末に終了しているが、現在、野口記念医学研究所およびメンバー国関係者の間では、今後WACIPACを西アフリカ保健機構(WAHO)へ統合し、同機構の地域センターとして維持していくことに向けた動きを進めている。このプロジェクトの成果が今後も西アフリカの国々によって維持され、各国の『人』を通じて根付いていくことに期待したい。

