アフリカ
- 問1.アフリカと日本にはどのようなつながりがあるのですか。
- 問2.日本はなぜアフリカを援助するのですか。
- 問3.アフリカに対する国際社会の取り組みについて教えてください。
- 問4.日本で開催されているTICADについて教えてください。
現在、日本から約1万キロメートル以上の遠方にあるアフリカは、日本人にとってなかなか親しみを持ちにくいかもしれませんが、実はわたしたちの日常生活の中にも「アフリカ」をたくさん見つけることができます。
例えば、日本人の食卓になじみの深い、バニラ豆(95%)、カカオ豆(80%)、たこ(58%)といった食料品の大半はアフリカから輸入されています。また、日本産業の中核を担う先端産業に不可欠な素材であるレアメタル(白金(73%)、マンガン(61%)、バナジウム(44%)、クロム鉱(34%)等)の多くをアフリカに依存しています(()内は輸入(数量)に占めるアフリカの割合)。その他、蚊取り線香に使われる除虫菊も東アフリカから輸入しています。2008年に日本とアフリカは3兆5609億円に上る貿易を行っており、日本からアフリカへの直接投資は15億ドルにものぼります。
人の交流も次第に拡大しており、日本に暮らしているアフリカ人は9千人近く(2007年末現在)、また5千人ほどの日本人がアフリカに暮らしています(2007年11月)。その中で、900人以上の青年海外協力隊員(2009年7月31日現在)や、多くのNGOがアフリカで活動しています。
アフリカと日本が遠くて近い国になるように、今後も友好・協力関係を深めていきたいと考えています。
アフリカは現在も深刻な貧困、紛争、難民、感染症等の課題を抱えており*、国際社会の大きな懸念事項となっています。そのため、我が国の支援の根底にはまず、「アフリカ問題の解決なくして21世紀の世界の安定と繁栄はなし」という考えがあります。アフリカの抱える問題は、国際社会全体として取り組むべき課題となっており、日本は責任ある国際社会の一員として積極的にその役割を果たすべきであると考えています。アフリカの抱える問題の中でも、テロや犯罪、感染症、環境問題等の課題は国境を越えて影響を及ぼすことが考えられ、それらへの対策としての意義もあります。
また、日本がこうした課題に取り組むことにより、国際社会で評価と信頼を得ることは、国際社会における発言力の強化にもつながります。
次に、国際場裡におけるアフリカの重要性が挙げられます。アフリカには世界の国の約3割にあたる53ヶ国から成ります。そのため、国連総会や国際機関の要職の選挙など、一国一票の投票で過半数や3分の2の多数決で意思決定が行われることの多い国際場裡においては、アフリカの動向は非常に重要です。特に、2002年のアフリカ連合(AU)設立以降は、「アフリカの統一と団結」の下、53ヶ国がまとまった投票行動をとることが多くなり、数の重みをさらに強めています。
さらに、アフリカは資源の宝庫であるとともに潜在的市場として重要です。アフリカには、先端産業に不可欠な素材であるレアメタルが大量に埋蔵されており、日本はその多くをアフリカに依存しています。また、アフリカの有する世界全体の10.0%にのぼる石油の埋蔵量も今後の日本のエネルギー戦略上注目されます。国民の豊かな生活・日本経済の成長に資するこれらの資源の安定的な輸入のためには、アフリカにおける平和の定着のための支援を行うことが必要であると同時に、友好的な日・アフリカ関係を維持していくことが求められます。また、アフリカは世界人口の15%にあたる約10億人を擁するとともに、2005年-2010年の推定人口増加率は世界一の2.3%で、2050年には世界人口の約22%(20億人)を占めるとの推計もあり、アフリカは潜在的に大きな市場と言えます。
こうしたことを背景に、日本はアフリカに援助を行っており、今後も援助の効率性・実効性・透明性を高めるよう努力し、より戦略的な援助を行っていく考えです。
*サブサハラ・アフリカの全人口の半数以上が1日1.25ドル未満で生活をし、全人口の29%が栄養不足、小学校就学率は74%、全世界のHIV/エイズ感染者の約68%(約2250万人)、難民・国内避難民の約4分の1をアフリカが占めるというのが現状です。また、全世界で49カ国の後発開発途上国(LDC)のうち、33カ国がサブサハラ・アフリカに集中しています。アフリカが抱えるこれらの問題に対し、国連安保理の議題の約6割、国連平和維持活動(PKO)の予算・人員の約7割が割かれています。(国連PKO16ミッション中、7ミッションがアフリカで展開)。
冷戦終結後、欧米各国にとって、かつての冷戦の敵であり、地理的にも自国の安全保障に直結する東欧の重要性が高まる一方で、冷戦中は東西陣営の勢力争いの最前線であったアフリカの重要性は低下しました。加えて、当時欧米先進国は経済停滞に悩まされていたこともあり、対アフリカ支援に非常に消極的になっていきました(「援助疲れ」論)。この様に、国際社会のアフリカへの関心が一時低下したまさにその時期、日本は世界の関心をアフリカに呼び戻すことを目的に、アフリカ開発会議(TICAD)プロセスを開始しました。その後、TICADプロセスに加え、G8サミットにアフリカ首脳を招く等の日本のリーダーシップもあり、国際社会はミレニアム開発目標の策定等を通して、対アフリカ支援を強化し、アフリカ向けODAを顕著に増加させてきました(グラフ参照)。英国はグレンイーグルズ・サミットに向け「アフリカ委員会」を立ち上げ、仏は「仏・アフリカ首脳会議」を隔年で開催し、米国は「アフリカ成長機会法」を制定したほか、「米・サブサハラ貿易・経済協力フォーラム」を開催するなどアフリカへの取り組みを強化しています。
特に、2005年は、アジア・アフリカ首脳会議(4月)、グレンイーグルズ・サミット(7月)、国連首脳会合(9月)とアフリカ問題に焦点が当てられた国際会議が数多く行われたいわば「アフリカの年」となりました。これらの会議では、アフリカの開発の重要性と国際社会として、支援を強化していくことが確認されました。
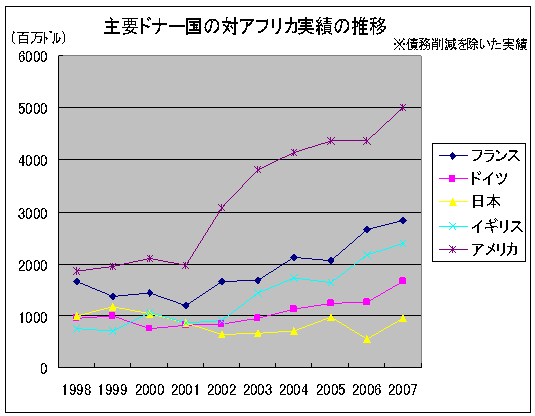
その後のG8サミットでもアフリカは主要議題の1つとして議論されてきており、2008年我が国が主催したG8北海道洞爺湖サミットにおいても、「アフリカ・開発」を主要議題の1つとして大きく取り上げました。
(参考)ミレニアム開発目標
2000年9月の国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言の開発関連部分と90年代の国際開発目標を統合して、とりまとめたもの。貧困削減等について明確な達成期限(2015年)と具体的な数値目標を定めています。
1.アフリカ開発会議(TICAD)を基軸とした支援
日本は、5年に一度のアフリカ開発会議(TICAD(ティカッド)注)の開催を通じて、アフリカ開発を支援しています。日本は、東西冷戦終結に伴って、国際社会のアフリカへの関心が低下していた1993年に、アフリカ問題の重要性を改めて喚起すべく第1回会議を開催しました。
TICADは、日本単独ではなく、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行等と共催して開催してきました。また、TICADは、アフリカ諸国や援助供与国・国際機関、NGO、民間セクターといったアフリカ開発に重要な役割を果たしている開発パートナーが幅広く参加する国際会議です。
TICADでは、一貫して、アフリカ自身の自助努力が重要であり(「オーナーシップ(自助努力)」)、この努力を国際社会が支援していく(「パートナーシップ」)という理念が提唱されてきました。また、アジアとアフリカ間の協力を重視しており、アジア諸国が発展してきた経験をアフリカ諸国と共有しています。
(注)TICADとは、Tokyo International Conference on African Development の略。
2.第四回アフリカ開発会議(TICAD IV(ティカッド フォー))
日本は、最近では、2008年5月に横浜でTICAD IVを開催しました。この会議では、アフリカの 1)経済成長の加速化、2)ミレニアム開発目標(MDGs)の達成、3)平和の定着・グッドガバナンスの促進、4)環境・気候変動問題への対処を重点事項として、アフリカ諸国と上述の幅広い開発パートナー間で活発な議論を行いました。
TICAD IVの特徴は主に次の二つです。
まず、日本による2012年までの 1)対アフリカODA倍増及び 2)民間投資倍増支援をはじめ、多数のアフリカ開発支援策が開発パートナーから打ち出され、「横浜行動計画」としてまとめられたこと。
そして、「横浜行動計画」の履行状況をモニターする「フォローアップ・メカニズム」が創設されたことです。
3.TICAD IVフォローアップ
外務省アフリカ審議官組織は、フォローアップ・メカニズムの事務局として、原則年1回、「横浜行動計画」の開発パートナーから、各支援策の履行状況を取りまとめ、「年次進捗報告書」を作成しています。この報告書は、日本語、英語、仏語で作成し、外務省ホームページで公表しています。
さらに、原則年1回、「閣僚級フォローアップ会合」を開催し、上述の「年次進捗報告書」を基に、「横浜行動計画」の効果的・効率的な実施に向けて、アフリカ諸国、開発パートナーの閣僚級で議論することとしています。
2008年度は、3月にアフリカ南部の国ボツワナでこの会合を開催しました。同会合では、1)「横浜行動計画」が多くの分野で進捗が見られていること(PDF)![]() 、2)TICAD IVで打ち出した支援策を着実に実施し、2008年秋以降の世界的金融・経済危機に直面するアフリカを力強く支援していくことを確認しました。
、2)TICAD IVで打ち出した支援策を着実に実施し、2008年秋以降の世界的金融・経済危機に直面するアフリカを力強く支援していくことを確認しました。
日本は、TICADやそのフォローアップにおけるアフリカ諸国と開発パートナーとの議論を踏まえつつ、G8サミット等の場でアフリカへの支援強化を呼びかけています。
![]() Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
