 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
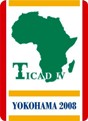
TICAD IV 配偶者プログラム
総理夫人主催ワーキングランチ
- 平成20年5月28日(水曜日)
- 午後12時00分-14時30分
- インターコンチネンタルホテル横浜グランド、シルクルーム
- 日本語・英語・フランス語(同時通訳)
- 主題:アフリカにおける母子保健
アフリカ開発会議に際して開催された昼食会では約20名のアフリカ元首夫人および大臣大使夫人と、ユニセフ、国連人口基金、世界銀行、世界食糧計画のトップが一同に会し、活発で建設的な意見交換がなされた。演説のなかで福田首相夫人や国連機関のトップ, さらに途中参加されたリベリア大統領は、アフリカの元首夫人がアフリカにおいて母子保健を推進するために活躍することを奨励した。また、アフリカにおける母子保健についてのワーキングランチ開催にむけて、ブラウンイギリス首相婦人より福田首相夫人に宛てた激励の書簡が届いた。参加者も今回のワーキングランチはアフリカの発展における重要な問題について語り合う、非常に有意義な場であったとしている。
スピーチ:
福田総理夫人:
- 日本の母親は子供を授かった時に、こうした母子健康手帳をもらえます。ここには母親が出産までの自分と胎児の健康状態を記入したり、出産後の赤ちゃんの成長を記録することができます。
- 今から約60年前、日本は第二次世界大戦後の混乱の中にありました。食糧が不足し、衛生状態も悪い時代に、母胎の健康を守り、乳幼児の死亡率を下げるために、この母子健康手帳が活躍しました。そして今でも日本の母親と子供の命と健康を守るために大切に使われています。
- 日本政府はユニセフなどの国際機関や地元の保健機関、NGOなどの協力を得て、インドネシアやアジア諸国での母子手帳の普及に努めてまいりました。識字率の低い地域や多くの種類の言語を持つ国では、絵を使うことによって、より多くの人に理解してもらえるように工夫もしています。現在はパレスチナの西岸地区で、移動制限のために同じ保健所に通えない場合でも、別の保健所で適切な検診や治療を受けられるよう、この母子手帳を広めようとしています。
- 物理的な隔たりや習慣の違いを越えて、女性と子供達の命と健康を守りたいと願う気持ちは皆同じだと私は信じております。
- 本日は「母子健康手帳」という一つのアイデアを皆様に紹介させていただきました。そして、私どもはこれからも色々なアイデアをご紹介していきたいと思っております。
国連児童基金:
- ユニセフは母子の保健、教育そして保護の分野で活躍しています。これらは元首夫人が主たる擁護者としての役割を担うことができる分野です。
- このすぐ後に発表されるアフリカ子ども白書2008によると、多くの国が子どもの健康に関して成果を出しましたが、いまだに成果の出ない国々が残っています。その主な理由は紛争やエイズです。
- 健康の促進のために元首夫人ができることは、予防接種や蚊帳の使用、経口補水塩や母乳による育児を含めた栄養摂取等、多くの子どもの命を救うことのできる手段を擁護し提唱することです。最近の食料危機を背景に、栄養一般についても重要性が高まっています。
- 教育の分野では是非すべての子どもたちに教育を提唱してください。特に女子への教育が必要です。女子が教育を受けることで賢い母となり、子どもの生存へ一役買うでしょう。
- 保護の分野では、児童労働や子どもへの暴力、その他悪影響のある伝統的慣習、たとえば女性器切除や児童婚等の放棄を擁護し提唱してください。広範囲にわたる性差別の問題も置き去りにはできません。子どもの発育のためにも女性の権利を擁護し促進することが必要です。
- 私は今までに皆様の多くの方がたにお会いしましたが、元首夫人の皆様が母子の保健、教育そして保護の分野で多大なる貢献ができることを確信しています。
国連人口基金:
- 母子保健の改善に向けて私たちは大きな困難に立ち向かっています。
- アフリカの女性と子どもの生命を救うための効果的な保健サービスの提供と資金援助を獲得すべく、元首夫人は大切な役目を負っています。
- 女性は、命を生み出すために自らの命を落とすべきではありません。訓練を受けた専門技能者立会いによる分娩や緊急産科ケア、家族計画等のリプロダクティブ・ヘルスをすべての女性が享受できるようになれば、出産で生命を落とすことはなくなるはずです。
- これらの3種のサービスは一見シンプルなものですが、コミュニティーレベルでこのようなサービスを提供することは難しく、多くはそこまで達していないのが現状です。
- すべての女性に支援が届くようこれらのサービスを拡充し、また児童婚や若年出産などの有害な慣習を撤廃する運動を支援し、思春期の女子の教育普及や若者の健康的な生活習慣の推進が、今、求められています。
- さらに、プライマリーヘルスケアや保健システムの強化、そして保健医療従事者を訓練し、仕事に定着するよう推進することも必要とされています。
- UNFPA は、開発のプロセスにおいてしばしば忘れられがちな女性を擁護するために、元首夫人をサポートするつもりです。私たちが協調すれば、ミレニアム開発目標4と5を達成できるでしょう。
世界銀行:
- 妊婦の死亡の半数がアフリカで起きている事実は到底承諾のできるものではありません。アフリカにおける母子の高死亡率の主たる原因は年齢的に早すぎる妊娠や多すぎる妊娠回数、さらには年齢的に遅すぎる妊娠、また医療施設までの道のりが遠すぎることや、もし医療施設に辿り着けたとしても、適切な処置ができないことにあります。
- これに対処するにはパートナーシップが不可欠です。ですからTICADが今回初めてアフリカの開発における重要課題に焦点を当てるにあたり、元首夫人をその枠組みにパートナーとして位置づけたことをとてもうれしく思います。
- 保健システムの強化や、さらには費用対効果の高い基本的な保健サービスを妊婦や新生児、幼児に、人生の重要な段階において提供することが不可欠です。
- 世界銀行はインフラを通じ、サービスを効果的に提供するための必要とされる保健システムの強化に一役を買っています。保健や教育にかける資源や公的資金を賢く使うことでよりよい成果を出すことができるでしょう。
- 元首夫人の活躍は母子の死亡率を削減するための私たちの努力に欠かせないものです。
世界食糧計画:
- 世界で女性と子どもが危機的状態にあれば、お互いにすぐさま連絡を取り合ってプランを立て、それをともに実施するような‘ホットライン’が国連機関にありますが、ここにお集まりの活動的な元首夫人方がたからも、パートナーシップのもとに手を取り合って、歴史を新しく塗りかえらんとする原動力を見て取ります。
- 女性と子どもはしばしば世界的な飢餓や飢饉の象徴です。そしてまた後進国では70%の女性が食糧生産の象徴です。女性が変化を望んで立ち上がったとき、歴史は変わります。
- フィールドでは、私は何よりもまず女性たちの声を聞きます。女性は知恵を持っているからです。女性はいつも問題解決のため、また育児のための最善策を知っています。
- 大きな夢を持ち、もうこれ以上許容できないことに見切りをつけましょう。学校給食はほんの25セントです。子ども一人たりともおなかをすかしたまま学校で学ぶべきではありません。食糧の価格上昇によって、すべてのおなかをすかした子どもにかかる支援コストが2倍の30億ドルになりました。しかしながら、去年のクリスマスボーナスがウォール街だけで360億ドル支払われているのです。学校給食を優先事項とするならば、その費用を調達することは決して不可能ではありません。
- 世界の2歳以下の子どもが必要とする栄養供給も確保しなくてはなりません。もし時期までに適当な栄養が取れなければ、脳と身体の発育に悪影響を与えます。
- WFPは戦略的な食糧援助を推進しています。たとえばWFP は後進国の農民から、食糧を買っています。それはCash for Foodに当てた資金の80%にものぼります。これは実に革命的なものです。食糧の現地調達は問題を抜本的に解決し、小規模農家を活性化することで、相乗効果が期待できます。
オープンディスカッション:
マリ(Mrs. Toure L. Traore): ここ数年母子保健やHIV/エイズの分野でいくらかの前進がありましたが、乳幼児や妊婦の死亡率がアフリカでは、とくに中央や西部アフリカでは、依然高いままです。ビジョン2010を通じて、アフリカ元首夫人は民間組織や地方政府、中央政府と協力し、死亡率の削減へ向けて母子保健サービス、緊急産科ケア、マラリアの予防と治療サービス、抗レトロウイルス剤の投与等を提供しています。この活動に国連機関の多大な支援も受けてきました。日本政府がこの問題をG8の主要項目として取り上げることを要請します。また、彼らの採択した決定は速やかにメディアを通じて広く周知されるべきです。技術のあるパートナーと組んで、妊婦と子どもの死亡率削減に向けてよりいっそうの努力をしなくてはなりません。わたしも努力を惜しみません。
リベリア (President Ellen Johnson-Sirleaf): 今日のトピックである母子の保健はわが国にとって、とても大きな課題です。というのも、リベリアは内戦によっていまだ統計上最悪の数値を出しているからです。しかしながら、国連機関とのすばらしいパートナーシップによって、リベリアは基本的なヘルスケアや経済成長、教育の普及等、貧困の撲滅に向けて歩んでいます。アフリカと日本のパートナーシップの象徴であるTICADではこのパートナーシップをどのように推し進めようかといった議論が始まりました。また、アフリカの経済的な課題をこなすためへの支援を継続していただけるよう、私たちアフリカの国々がどのように適切な経済政策や良い統治を実施するかといった議論もしています。私は皆さんが女性の参画と福祉を促進するため一致協力して努力をすることを奨励します。
レソト (Mrs. Mathato Mosisili): 新しいタイプの薬剤耐性結核が問題になっていますが、どのようにして、またどのくらい迅速に対処することができるのでしょうか?
世界銀行: 結核はHIV/エイズとともに取り組まなくてはなりません。世界銀行の地域研究所でも統合的な取り組みを必要としています。また、結核患者にサービスが提供されるためには保健システムを強化することも同様に不可欠です。
ナイジェリア(Mrs. Patience Jonathan): 開発のパートナーは母子の死亡率削減のためにどのような援助をしていますか。また開発後進国においては妊婦が出産で死亡した場合、医療従事者の医療責任が問われることはありませんが、このような問題はどのように対処できますか。
国連人口基金: 妊産婦死亡率が高い原因は、医療的な過失というよりはむしろ保健サービスが提供されていないことにあります。政府が国全体にサービスを普及させられない現状の中、コミュニティーにサービスを提供するための資金をいかに調達するか。例えばナイジェリアでは、このようなサービスの需要が高い。ですから、元首夫人がビジネスセクターに声をかけ、企業の社会的責任の遂行を奨励することが大切です。ナイジェリアでは、大きなビジネスセクターがあるので、良き協力体制を築き、資金調達を推進してください。
国連児童基金: 保健サービスの提供には保健システムの強化も同様に大切です。コミュニティーに基づいた統合的な保健システムは不可欠です。ユニセフは女性と子どもに対する暴力の問題にも取り組んでいます。
ブルキナファソ(Mrs. Chantal Compaore):妊婦と子どもの死亡率削減へのユニセフの取り組みに感謝します。資金不足によって、政府はリプロダクティブヘルスの提供をいくらか断念しましたが、国際機関の支援で私たちはビジョン 2010を立ち上げることができました。いまや政府は母子のためのロードマップを持っています。そして状況もいくらか改善されました。しかしながら、すべては資金次第で、特に農村部における深刻な医師不足やHIV/エイズが課題として残っています。政府はビジョン 2010について関係者が対話を持つことを奨励していますが、私たちはビジョン 2010をこえてビジョン2020を立ち上げるべき必要性を感じています。
世界食糧計画: 現在は食糧価格高騰にあり、母子の健康が優先的に配慮されなければなりません。皆さまがお国で、この栄養不良の問題にどのような取り組みをされているのかお聞かせください。
レソト(Mrs. Mathato Mosisili): ワールドビジョンなどのドナーの支援でレソトでは費用対効果の高い野菜の生産方法が推進されています。
ブルキナファソ(Mrs. Chantal Compaore): ブルキナファソではWFPの学校給食を含むさまざまな方法がとられています。また、ビジネスセクターに向けた啓発活動もしています。学校給食を全国的に広げようと努力もしています。
世界食糧計画: 学校給食プログラムは最もコストが低い人道支援活動のひとつです。この活動をより持続的なものにするために、私たちは現地調達した食糧を学校給食に利用ように努めています。例えばガーナでは学校給食に使われる食糧は通常地元で収穫されたものです。子どもたちが学校に通うことは、その国の経済成長に直接繋がっていくため、学校給食プログラムへの投資は各国の財務省が率先して行うべきではないかと私たちは考えております。そういう意味で、学校給食プログラムが社会福祉の一部としてでなく、国の未来の経済成長のための活動と認識されるよう努力しております。すべての子どもにが毎日食事を取れるようにするには何をすべきかについて世界規模での対話がますます必要となってきています。
福田総理夫人: 今から60年前、日本の家庭が貧しく、子どもたちの栄養を十分に確保できなかった時代、私も含めた日本の子どもたちは学校給食に大きな恩恵を受けました。また日本は結核で大変な時期も経験しました。7月24日に日本で結核のシンポジウムが開かれますが、ここで結核への取り組みがさらに促進されることでしょう。そして最後になりますが、現在も母子の健康促進に大きく貢献している母子手帳のような日本の経験を皆様の国でも参考にして頂ければ幸いです。また、我が国は、2005年に、保健分野において5年で50億ドルの支援を行うことを表明し、順次実施しています。
