 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
島国のこぼれ話
-PIF諸国・地域の話題集-
平成21年5月1日
1.キリバス~世界で最初に朝を迎える国~
(広大な海洋国家・キリバス)
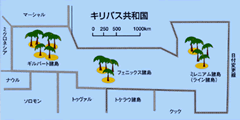
ミレニアム諸島
キリバスは、西からギルバート諸島、フェニックス諸島及びライン諸島の3つの諸島群計33の島から成り立っているキリバス国土の総面積は720平方キロ(対馬とほぼ同じ)であるが、西端のバナバ島(東経169度)と東端のクリスマス島(西経150度)の東西間が3,870キロメートル、北端のワシントン島(北緯5度)と南端のフリント島(南緯11度)の南北間が2,050キロメートルと広大な水域に島が点在し、約335万平方キロに及ぶ世界第3位の広大な排他的経済水域(EEZ)を有している。とりわけ、2000年の到来の際には、それまで国内を縦断していた日付変更線を東端にまで移動させた結果、キリバスは「世界で最初に2000年を迎える国」としてマスコミでも話題となり、現在も「世界で最初に一日を迎える国」とし知られている。
この広大なEEZを利用するために、キリバスの首都タラワには日鰹連(日本鰹・鮪漁業協同組合連合会)の援助を得て運営された漁業訓練センターがある。同センターは、全寮制で日本人インストラクターも数人おり、生徒はエンジンの仕組み・漁の仕方等漁業全般を学ぶ。また卒業後に日本の漁船に乗船し働くことが期待されているため日本語のクラスもある。
2.クック諸島~平和で豊かな最後の楽園~
(黒真珠の養殖)

クック諸島の黒真珠
1980年頃から仏領ポリネシアのタヒチから完全な球形の黒真珠が導入され、クック諸島北部において黒真珠の養殖が始まり、1990年代にはクック諸島の主産業にまで成長し、仏領ポリネシアと並ぶ産地となり、日本、韓国や欧州に輸出している。2000年以降、世界市場での真珠の取引価格の下落により、業者の数も減少し、一時衰退したものの、近年はクック諸島政府も北部離島への振興対策として、クック諸島黒真珠公社を設立するなど黒真珠業の復興に力を入れている。
3.サモア~ポリネシアの伝統を守り続ける国~
(ポリネシア文化のゆりかご)

サモアのファレ
考古学者の研究により、サモアには約3000年前に人類が到達し、サモアを起点にタヒチ、ハワイ、ニュージーランドといった広大なポリネシア海域への移民が進んだと考えられている。このため、サモアは「ポリネシア文化のゆりかご」と呼ばれている。実際、サモアでは昔日のポリネシアの伝統、習慣、生活様式が色濃く残っている。例えば、家屋や集会場には、「ファレ」と呼ばれる壁がなく柱だけの建築様式が多く使われている。服装についても、ズボンやスカートよりも、ラバラバと呼ばれる腰巻きが一般的である。
4.ソロモン諸島~太平洋の植物の宝庫~
(知る人ぞ知る魅惑の楽園)

ソロモン諸島の自然
ソロモンは知る人ぞ知る魅惑の楽園である。その一つがソロモン最南端のレンネル島にあるテガノ湖。1998年に世界自然遺産にも登録された。環状の珊瑚礁が隆起してできたこの島の年間降水量は4000ミリメートルになり、高温多湿地帯で島全体が熱帯雨林に覆われていて人口も少ないため、稀少な動物の楽園となっている。この湖は海とつながっていて、海水と淡水とが混在する汽水湖であるため、特殊なウミヘビやマイマイなどの独特の生態系を持っている。島の2割を占めるテガノ湖は、陸上、淡水、沿岸および海洋生態系と動物植物群集の進化と発達において重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本として注目されている。
世界遺産には登録されていないがソロモン西部に位置する「マロボ・ラグーン」も世界有数のラグーンとして観光スポットになっている。面積約2万9千平方キロメートル、長さ150キロメートルに及び、ラグーン全体が島に囲まれ、深海の深い青、熱帯雨林の緑、浅海のライトブルー、白い珊瑚のコンビネーションは息を飲むほどの美しさである。
5.ツバル~気候変動で注目される国~
(地球温暖化)

ツバルの離島
珊瑚礁の環礁から成るツバルでは、地球温暖化によって海面が上昇すれば国土が水没しかねないとの危機感があり、環境問題には大変敏感である。93年にパエニウ首相(当時)が地球温暖化対策を訴えて米国と日本を訪問したことに始まり、2004年9月には国連総会一般演説の場でトアファ首相代行(当時)はツバル国民が「水」難民(Water Refugees)として特別な地位を与えられるよう国連に要請した。2005年2月には、京都議定書の発効を記念し、首都フナフチに8本(ツバルという国名は8つの島という由来がある)のココナッツの木を植林した。
2006年8月には小池環境大臣(当時)が、2008年1月には鴨下環境大臣(当時)がツバルを訪問し、地球温暖化問題に直面しているツバルの現状を視察した。また2007年9月には石原東京都知事がツバルを訪問した。昨今、世界規模での地球温暖化問題への関心の高まりの中、各国メディアがツバルの現状を取材・報道している。
6.トンガ~南太平洋唯一の王国~
(トンガとソロバン)

トンガの王宮
親日的な前国王トゥポウ四世が日本を何度も訪問したこともあり、王室と日本の皇室との関係は深い。国民も親日的であり、青年海外協力隊(JOCV)による日本語の指導は1986年から続いている。そろばんについては、日本語の指導よりも歴史が長く、1977年頃から大東文化大学の教授が年一回指導を開始したことを契機として、1989年からはJOCV隊員が指導している。現在では、殆どの小学校が授業にそろばんを導入しており、毎年全国そろばん大会が開催される中、2010年に珠算教育が算数に義務履修項目として組み込まれる予定となっているほど、トンガの義務教育に定着している。このように、日本から技術・文化等を学ぼうとする熱い視線が随所に見られる。
7.ナウル~赤道直下に浮かぶ燐鉱石の島~
(燐鉱石)

ナウルの燐鉱石採掘場
ナウルの経済は長年唯一の産業ともいうべき燐鉱石の採掘に支えられてきた。燐鉱石は、化成肥料等の工業原料として利用可能なリンを採取できる有用な鉱物資源である。火山隆起により出来たナウルに、長年珊瑚等の石灰質が溜まり、またグンカン鳥やカモメ等が落とした糞が堆積し化学変化を起こしできたといわれる燐鉱石は豪州、ニュージーランド等に輸出され、ナウルに大きな外貨収入をもたらしたが、その燐鉱石もほぼ枯渇状態にある。
8.ニウエ~世界最大の珊瑚礁隆起島~
("鍾乳洞"の島)

ニウエの渓谷
太古の珊瑚礁が隆起してできたニウエ島は、世界最大の珊瑚礁隆起島である。全体が二層になっており、下の層は平均20メートルほどの高さで、その上の層は一番高いところで65メートルほどある。島には多くの鍾乳洞や小さな渓谷があるが、山や湖、川と呼べるものはない。雨が降ると、そのまま島の内部に吸い込まれ、石灰石がフィルターとなって海にしみ出る。そのため海は透明度が高く、70メートル先まで見通すことができる。
ニウエでの観光の一つとして、島の至る所にある鍾乳洞を巡る洞窟ツアーがある。洞窟ツアーでは壮観な地下の洞窟と驚くべき鍾乳石や石灰岩層をみることができる。洞窟はその昔カヌーなどを保管した場所、あるいは先祖を埋蔵した場所とも言われ、謎の部分も多く残っている。
9.バヌアツ~バンジージャンプの故郷~
(決死のバンジージャンプ)

バヌアツのバンジージャンプ
キリスト教の精霊降臨節を意味する名を持つペンテコスト島では、年に一度の祭で、若者が高いやぐらの上から足に巻いた木のつるだけを頼りに、地面に向かって飛び降りる儀式が行われている。十数年前までは、このランド・ダイビングは成人の儀式であり、これができない若者はいつまでも一人前と認められなかったとのこと。日本でも、テレビのドキュメンタリー番組などで紹介された。ダイバー達は、特にこの日のために訓練を重ねたわけでもない普通の若者であり、中には命を落としたり、大けがをしたりするものも少なくなかったという。現在は単に祭の中の儀式として行われており、観光ツアーの目玉の一つともなっている。かつて、これを見たニュージーランド人がバンジージャンプのアイデアを思いつき、現在では誰もが挑戦できるアトラクションとして世界各地に広まっている。
10.パプアニューギニア~極楽鳥の国~
(国名・国旗の由来)

パプアニューギニアの国旗と極楽鳥
PNGは、元々、豪領パプアと独領ニューギニアとに分かれていたが、1914年に全て豪領となった。「パプア」とはポルトガル語で「縮れ毛」を意味し、16世紀に当地に来航したポルトガル人が命名したとされる。また、「ニューギニア」は、同じく16世紀に来航したスペイン人が、住民がギニアの黒人を連想させたところから「ニューギニア」と命名したとされる。
PNGの国旗は、独立前の1971年に公募され、当時15歳の女学生のデザインが採用された。右側には黄色の国鳥・極楽鳥が、左側には南十字星を表す5つの白星が描かれている。同女学生によれば、極楽鳥はシンシン(PNGにおける伝統的な踊りの一般的呼称)で装飾に使用される羽、南十字星は当国に伝わる5人姉妹の伝説を意味し、南十字星の白い色はブアイ(PNGの一般的嗜好品である檳榔樹(ビンロウジュ)の実)とともに噛む石灰を、赤と黄色はPNGの様々な花の色を表し、黒はその他ポピュラーな色である由。
11.パラオ~エコ&ダイビング・パラダイス~
(日本とパラオとの関係)

パラオのロックアイランド
第二次世界大戦以前は、パラオを含むミクロネシア地域日本の委任統治領となり、コロールには「南洋庁」の本庁が設置された。今でもコロール市内には日本統治時代の建造物が数多く現存している。また日本統治時代に教育を受けた世代も生存しているほか、数多くの日系人が国内の政治経済のリーダーとして活躍している。
第二次世界大戦後、パラオは米国の信託統治領時代を経て、1994年に独立を果たすと、国内の豊かでユニークな観光資源を利用した観光開発に力を入れはじめた。特に1995年11月に日・パラオ間をつなぐ直行チャーター便を就航して以来、日本からの観光客はパラオを訪れる観光客全体の3分の一を占めるまでに至った。国内の観光資源としては、古代の珊瑚礁が何億年も前に隆起して形成された「南洋松島」と呼ばれたロックアイランドや、日本統治時代の史跡や第二次大戦の戦跡等が有名である。また海洋生物が豊富な美しい海は、世界でも有数のダイビング・スポットとして知られており、スキューバ・ダイビングを目的とした観光客にはとくに人気がある。
12.フィジー~南太平洋の十字路~
(南太平洋の十字路)

フィジーのUSP
南太平洋の真ん中に位置するフィジーは、人口約83万人、日本の四国とほぼ同じ総面積を有し、南太平洋ではパプアニューギニアと共に中心的な存在であると同時に、日本からキリバス、ツバル、ナウルを訪れる場合には通常フィジーを経由しなければならないというように、当地域の交通の要衝となっている。このようなことから、フィジーの首都スバにはUNDP、WHO、ILO、ADB等多くの国際機関の代表が駐在、また、太平洋諸島フォーラム(PIF)、南太平洋大学(USP)、南太平洋応用地球科学委員会(SOPAC)といった地域機関も本部を設置している。
13.マーシャル諸島~太平洋に浮かぶ真珠の首飾り~
(マーシャル諸島に根付いた日本語・日本文化)

マーシャルのアミモノ
戦前、30年間にわたる日本の統治下において、 マーシャル人は公学校に学んだこともあって、現在でも年輩者の中には日本語を話す者もいる。また、マーシャル人の生活に根付いた日本語も多く、例えば、アリガトウ、ダイコン、ワサビ、アミモノ、アメダマ、オボン等々がある。マーシャル人の中には、日本人の氏名を名乗っている者も多く(例えば、マタヨシ、イシグロ等々)、中にはモモタロウやチュータロウ等を名前でなく、名字として使っている者もいる。
マーシャル諸島には、日本統治下の習慣が未だに残っており、特に食生活面で顕著に見られる。かつてはマーシャルの主食はタロイモなどであったが、現在は日本統治下にもたらされた米食が完全に定着している。ご飯の炊き方は我が国と概ね同じであるが、マーシャル人はご飯に鶏肉、魚などのほかに、タクアン、キムチなどを一緒に添えて日常的に食べている。また、インスタント・ラーメンやサシミも好物である。
14.ミクロネシア連邦~エメラルドグリーンに輝く4つの楽園~
(ヤップ島の石貨)

ヤップの石貨
ヤップ州では、ミクロネシア連邦を形成する4州(ヤップ州、ポンペイ州、コスラエ州、チューク州)のうちでもっとも伝統的な生活が営まれており、冠婚葬祭や土地の譲渡等の伝統的な取引の際には、現在でも石貨が使用されている。中心に穴を空けた直径1メートル以上の大きな石貨が道ばた無数に並んでおり、無造作に置いてあるが、それぞれ所有者がいる。石貨の引渡時は所有者が変わるだけで石貨そのものは重すぎるため、移動されることは希である。石貨の価値は石の大小ではなく、パラオからヤップに運ぶ道程でどれほどの苦難を乗り越えてきたか等で決められる。現在では国外への石貨の持ち出しは一切禁止されており、ヤップ人の石貨に対する思いがうかがわれる。
