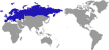 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
米ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙への
核軍縮・不拡散に関する日独外相共同投稿(仮訳)
平成22年9月
(英語版はこちら)
9月4日,核軍縮・不拡散に関する岡田外務大臣とヴェスターヴェレ独外務大臣による英文共同投稿が米ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)紙に掲載されたところ,内容は以下のとおりです。
- 本年5月,180か国以上の代表団がNYに集まって開催されたNPT運用検討会議では,いかにして世界を核兵器から解放できるかについて議論が行われた。オバマ大統領による2009年のプラハ演説を契機とする前向きな機運にもかかわらず,会議は大きなプレッシャーに晒されていた。しかし,すべての代表団による協力と柔軟性の精神により,会議はその期待に報いることができた。
- 我々は外務大臣として,ここから2つの結論を導き出した。第一に,今回の会議では,中東地域における非大量破壊兵器地帯設置を呼び掛ける1995年の中東決議実施のための具体的な措置をはじめ,多くの新しくかつ重要なコミットメントを含む行動計画にすべての代表が合意することができたのは大きな成果である。我々は,この合意の履行のためにできる限りのことをしなければならない。我々の第二の結論は,この合意は極めて脆弱なものであるということである。国際社会による力強い一致した取組なくして,この合意を履行することは困難であろう。イランの核計画や締約国の脱退に関するNPT規則の問題などに関し,会議を通じて表明された相容れない考え方は,消え去ることがないだろう。
- 会議に先立ち,主要な核兵器国はいくつかの重要な措置を講じた。米国とロシアは,自国の戦略核兵器を大幅に削減することに合意した。4月に公表された米国NPRでは,強化された消極的安全保証(非核兵器国に対して核兵器を使用しないという保証)を供与するという新たなアプローチが提示された。
- 我々は,核兵器のない世界を実現し,核セキュリティを強化するというオバマ政権のコミットメントを歓迎し,支持する。我々は米国を含む核兵器国と共に,核兵器の役割をいかに低減させていくか―例えば,核兵器の保有を他国による核兵器の使用を抑止する目的のみに限定することを約束すること―につき議論していく用意がある。仮に,核兵器国が自国の核兵器を放棄することにつき直ちに同意できないとしても,これらの国々は明白かつ現在のリスクを低減させるための実践的な措置を講ずることはできる。
- また,核兵器保有の誘惑に駆られることがないようにすることも必要である。北朝鮮とイランは,自国の不拡散義務に反して核兵器を取得することが決して許されず,国際社会における自らのステータスを高めるものとはならないことを理解しなければならない。
- 気候変動と同様,核軍縮もまた,人類が国境と世代を越える責任感を持つことができるかを問いかける課題である。核軍縮は,人類が「神の火」によって自らを消滅させるリスクを減らすために行動できるか否かを問いかける課題である。我々は,65年前の長崎と広島で人々と建物が激しい熱と光の中で一瞬にして消滅したことを決して忘れてはならない。
- 道徳は近年の対人地雷やクラスター弾の条約を成功させる上で重要な一役を担うこととなった。5月のNPT運用検討会議の最終成果文書において,各国が国際人道法を遵守する必要性が謳われているのは偶然ではない。
- 米国の核抑止に依存している日本とドイツが,なぜかくも精力的に核軍縮を追求しているかと疑問に思う人もいるかもしれない。日独両国はこれまでも長い間,核軍縮の必要性を提唱してきている。第二次世界大戦を通じた完全な荒廃から復興する中で,日独両国は核兵器の廃絶と平和で安定した世界を追求してきた。日独両国はこうした信念を共有しているからこそ,核軍縮に関して共通した役割を見出しているのである。そして,両国とも核軍縮を追求することこそが,核リスクを最も確実に最小化し,国際の安全を強化する道であると信じている。
- 21世紀はいかに人類が地球をマネージできるかが問われる世紀となるであろう。歴史は,地球規模の責任感をもって行動した国を好意的に後世に伝えるであろう。核兵器のない世界に向け,現実的で責任ある道を歩み始めようではないか。これは我々の道義的責任である。
