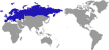 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
青少年に関する日EUセミナー
議事概要
1.開会挨拶
(1)メレセ欧州委員会教育文化総局青少年担当局長
教育分野における共通政策を模索する欧州内の動きは比較的新しいものの、リスボン戦略を進め欧州の成長を達成するためには、青少年と雇用の問題は重要である。
(2)丸山欧州局審議官
日本でも青少年の不適応問題の解決については、社会全体が認識するところとなっており、本日それをテーマとした日本とEU間のセミナーが開催されるに至ったことは誠に感慨深い。
2.基調講演
(1)「学習、社会への取り込み、シチズンシップ-ヨーロッパの戦略」Howard WILLIAMSON(英Glamorgan大学教授)
(2)「日本における「移行期」の課題と自立・参加への支援-ノンフォーマル教育の展開とNPO・ボランティア団体の活動-」佐藤 一子(東京大学教授)
3.各分科会におけるキーノートスピーチ
(1)第1分科会「青少年の就労に関する学校外教育の貢献」
1)Anthony AZZOPARDI(マルタ大学教授)
2)宮本 みち子(放送大学教授)
(2)第2分科会「問題を抱えた青少年の社会への取り込み」
1)Siyka Kovacheva(ブルガリアPlovdiv大学教授)
2)斎藤 環(精神科医、佐々木病院診療部長)
(3)第3分科会「ボランティア活動及び異文化間対話」
1)Nigel Watt氏(英Youth Action for Peace支部長)
2)興梠 寛(世田谷ボランティア協会理事長)
4.各分科会における議論のまとめ
(1)第1分科会
民族の多様性と単一性、経済状況等、日EUでは背景が異なるものの、職業的能力の発展、個人的能力の発展及び市民性の発展という3つの要素を含むアプローチが青少年育成のためには極めて重要である。
(2)第2分科会
青少年育成に不可欠な役割を果たす家族にもより焦点をあて、支援していくことが重要である。ユースワーカーの育成及び認定のための政策を確立させることが必要である。
(3)第3分科会
政府部門、企業部門、民間部門の三者がパートナーシップを形成し、交流を深めていくことが重要である。
5.閉会挨拶
(1)メレセ欧州委員会教育文化総局青少年担当局長
日EUの共通点及び差異について目を向け、いかに協力できるかを議論できた点において極めて有意義な会議であった。
(2)丸山欧州局審議官
青少年に関する日EU間の協力をさらに推し進めるために、今後ともこのテーマにおける対話の継続が必要である。
