| GDP(2009年)(名目)(支出) | 1兆5,277億加ドル | |
| 1人当りGDP(2009年)(名目) | 45,278加ドル | |
| 消費者物価上昇率(2009年)(前年比) | 0.3% | |
| 失業率(2009年) | 8.1% | |
| 政策金利(2010年6月1日以降) | 0.5% | |
| 為替レート | (対米ドル,2009年) | 1加ドル= 0.88米ドル |
| (同,2010年6月) | = 0.96米ドル | |
| 為替レート | (対円,2009年) | 1加ドル= 81.97円 |
| (同,2010年6月) | = 87.49円 | |
 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
カナダ経済と日加経済関係
平成22年7月
カナダ経済
新着情報
(1)カナダ経済は1994年以降基本的に年3%の安定成長であったが,2009年には世界的な金融危機の影響によりマイナス成長に。
(2)ただし,カナダは他国に比し不良債権比率が低く,金融危機による金融市場に対する影響は限定的。
(3)高い貿易依存度(GDPに占める総輸出額の割合は28.6%)。
(4)NAFTA成立以降の高まる対米依存度(輸出の75%,輸入の51%,対加直接投資の52.5%(2009年))。
1.カナダ経済の現況
(1)概況
1994年以降,好調な米国経済の影響を受け,2007年までは年平均約3%の高い経済成長を維持してきた。2001年には米国経済鈍化の影響を受け2000年第4四半期以降減速し,同時多発テロ事件の影響もあり,2001年の実質GDP成長率は1.8%となった。しかし,2001年第4四半期から低金利環境下で個人消費と住宅建設投資等が伸びたことを背景に急回復し,2002年第3四半期の実質GDP成長率は4.4%となった。
しかしながら2003年第2四半期には,SARS及びBSEの発生と加ドル高の影響により,年率マイナス0.2%と,2001年第3四半期以来のマイナス成長となり,2003年通年では年率1.9%の実質GDP成長率であった。その後,同年第4四半期以降回復傾向を示し,2004年に入ってからは,個人消費支出の回復と輸出の拡大を背景に堅調な回復を見せ,実質GDP成長率は3.1%まで上昇し,2005年も同水準(3.1%)を維持した。2006年は,カナダドルの対米ドル高及び米国経済の鈍化の影響で2.8%にとどまった。2007年は米国経済の更なる鈍化及び米国の金融市場の混乱を受けて,最終的には緩やかな成長に止まり,成長率は前年とほぼ同じ2.7%となった(数字はOECDによる)。
2008年は世界的な金融危機の影響を受け,個人消費の鈍化等により,成長率は0.4%となり,2009年には-2.6%となったが,2010年は回復し3.1%となる見通しである。
(イ)消費者物価上昇率は1992年以降安定しており,2001年までコアインフレ率を1~3%の範囲とするという連邦政府の誘導目標の中で推移し(2001年2.5%),2002年は2.2%であった。その後,2002年10月以降2003年3月までは月毎の率が3%以上で推移したが,それ以降は2004年のインフレ率が1.8%,近年では2008年が2.3%,2009年が0.3%になっている。
(ロ)失業率は,過去には10%を超えた時期(1991年~1994年)もあったが,2004年以降7%台から6%台に下降し,2007年には33年間で最低水準の6.0%を記録した。2008年9月以降,再び上昇傾向にあり,2009年は8.33%となっている。
出所:
GDP,1人当りGDP,消費者物価上昇率,失業率
(カナダ外貿省 http://www.international.gc.ca/eet/menu-en.asp#tra ![]() )
)
政策金利,為替レート(カナダ銀行) http://www.bankofcanada.ca/en/index.html ![]()
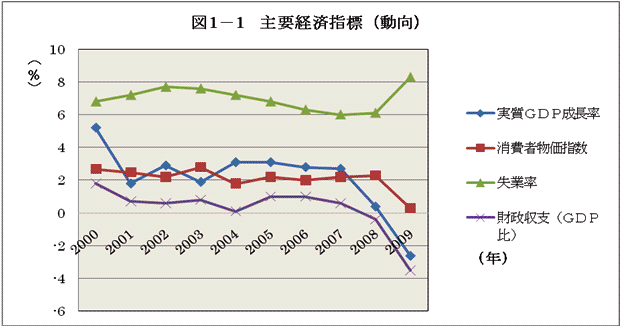
注:財政収支は年度。例えば,2005年は2005年度を指す。
出所:カナダ統計局,カナダ財務省
(2)財政
1970年代以降財政赤字が継続し,1992年度(1992年4月から1993年3月)には対GDP比5.6%を記録。その後政府の財政再建努力もあり,1997年度に均衡財政を達成して以来10年続けて財政黒字を堅持。2008年度以降,再び赤字に転落し,2009年度は5,380億加ドルの赤字を計上するも,G7中では最小。
(3)貿易・投資
半ば恒常的に赤字を記録していた経常収支は,1999年に入り黒字(25.7億加ドル)に転じ,2008年は496億加ドルとなったが,2009年には再び赤字となり,51億加ドルとなった(カナダ統計局)。
2009年におけるカナダの総輸出額は3,600億加ドル,総輸入額は3,652億加ドルとなっている。カナダ経済は経済の対外依存度が高く,総輸出額がGDPの約28.6%(2009年)を占める。特に,対米輸出・輸入はそれぞれ総輸出額の約75%,総輸入額の約51%(2009年)を占める。(カナダ統計局)
対加直接投資(ストック)は,2009年5,494億加ドル(2008年5,408億加ドル)であり,うち52.5%(2008年52.4%)が米国からの投資である。日本の対加直接投資の占める割合は2.4%で第8位を占める。対外直接投資は,2009年5,933億加ドル(2008年6,416億加ドル)であり,うち44%(2008年46.4%)が対米投資となっている。
(4)金融
加ドルは長期下落傾向にあったが(70年代:概ね1加ドル=1米ドル,2002年:1加ドル=0.6368米ドル),2003年に入ってからは対米ドル高傾向が続いており,2010年5月平均は1加ドル= 0.96米ドルとなっている。
1994年よりカナダは翌日物貸出金利を政策金利としており,その上限(+0.25%)が公定歩合となっている。政策金利の誘導目標(target for the overnight rate)については,2005年9月に国内経済の需給バランスを計るとともにインフレ目標の維持のため,0.25%引き上げられ,2.75%となった。その後,10月,12月と利上げを行い,2006年に入ってからも国内需要が堅固であること及びカナダ経済がほぼ生産能力に近い水準で拡大していることを受け,3月,4月,5月と連続して利上げを行ったが,以降は米国経済や国内インフレ状況等を踏まえ以降1年以上にわたり現状維持であったが,消費者物価指数とコアインフレーション指数が4月の予測を上回っていること及びカナダドル高が続いていること等から,2007年7月に利上げを行い政策金利は4.50%となった。しかし,物価上昇は当初の見通しよりも低いと予想されること,サブプライムローンの損失や米国経済の低迷の影響を踏まえ,12月に利下げを行い,政策金利は4.25%となった。その後,米国経済の減速が予測より深刻で更に長期化し,インフレ圧力が低下するとの判断から2008年も政策金利を徐々に引き下げた。2008年~2009年は国際的な金融危機及び米国経済の弱体化を受け,政策金利は0.25%まで引き下げられた。しかし,2010年6月1日は他国に先んじて2年11ヶ月振りとなる利上げを実施し,政策金利を0.5%とした。
カナダ政府は2008年10月以降,市場での信用不安に対応するための金融支援策として,(イ)中長期のインターバンク債務への政府保証,(ロ)住宅ローン債権買取り策の拡充(1,250億加ドル),(ハ)銀行に対する自己資本規制の一部緩和等を実施している。
(5)カナダ経済の今後の見通し
2010年3月4日に公表された2010年予算案「Leading the Way on Jobs and Growth」では,民間調査機関の成長率予想を引用し,今後の経済成長見通しを2010年2.6 %,2011年3.2%とその回復を予測している。中期的には,徐々に経済が回復し労働市場も改善され,また,金利の上昇及び物価の安定も期待されると予測する。
2.カナダ政府の経済政策
(1)国内経済
(イ)2006年1月に発足し,2008年10月には第二次内閣が,2010年1月には第三次内閣が発足したハーパー保守党政権は,以下を「重点5分野」として打ち出している。 1)政治腐敗防止,2)減税,3)犯罪対策,4)育児支援,5)ヘルスケア。
(ロ)2010年度カナダ連邦政府予算は,強固かつ抵抗力のある(strong and resilient)経済の基盤は均衡財政にあり,出口戦略を模索するとともに,均衡財政を目指す方針と発表。2011年度内に財政赤字を半減,2014年度内に180億ドルまでに減少することを目標に,財政赤字の縮小に向け,政府の直接支出に関し規律ある抑制を図っていくこととしている。ただし,増税はせず,地方への移転支出は抑制しないこととしている。
さらに,昨年度に引き続き,190億加ドルの景気刺激策(Economic Action Plan)を実施することとしている(内訳は,減税32億加ドル,雇用保険拡充等40億加ドル,インフラ整備77億加ドル,研究開発支援等19億加ドル,経済危機による影響を受けた産業支援等22億ドル)。
(ハ)2008年1月に,カナダ連邦政府はGST(連邦財貨サービス税)を6%から5%とし,減税を行った。カナダではPST(州売上税)が課される場合もあるが,ノバスコシア州,ニューブランズウィック州及びニューファンドランド・ラブラドル州ではHST(統一売上税)を導入しており,連邦部分の5%を含む13%の税率としている。2010年7月より,ノバスコシア州では税率を15%に引き上げ,オンタリオ州(13%)及びブリティッシュ・コロンビア州(12%)でHSTの導入を行う。
(2)対外経済
(イ)北米自由貿易協定(NAFTA)・その他の自由貿易協定等
1)カナダは米国との間で,関税・非関税障壁の撤廃,内国民待遇原則等を設定した米加自由貿易協定(FTA)を締結し(1989年1月発効),その後,メキシコを加えた三ヶ国間で北米自由貿易協定(NAFTA,1994年1月発効)を締結した。NAFTA締結により,カナダ経済は,米国経済の恩恵を十分に受けて拡大した。2009年のカナダと米国・メキシコとの間の商品貿易総額はおよそ4,783億加ドルであり,カナダの商品輸出額の76.4%はNAFTA向けである。カナダの対米商品輸出は,1994年から2008年までの間に年率平均5.6 %で増大した。また,米国の対加直接投資(ストック)は1,129億加ドル(1995年)から2,883億加ドル(2009年)に伸び,カナダの対米直接投資(ストック)も同時期に846億加ドルから2,613億加ドル(2009年)に増大した。
2)貿易依存度の高いカナダは,WTOなど多国間の枠組みでの自由化の推進等を経済外交の柱にしている一方,NAFTAを始め,地域レベルや二国間での自由貿易協定の締結にも積極的である。また,近年,新興市場経済圏(BRICs)との関係強化も目指している。
カナダはイスラエル(1997年1月発効),チリ(同年7月発効),コスタリカ(2002年11月),ペルー(2009年8月発効)との間で二国間自由貿易協定を締結している。2009年7月には欧州自由貿易連合(EFTA)とのFTAが発効。また,コロンビア(2008年11月),ヨルダン(2009年6月)及びパナマ(2010年5月)とのFTAに署名している。
更に,韓国(2005年4月に第2回交渉),シンガポール(2007年8月第8回交渉),カリブ共同体(CARICOM)(2008年10月交渉開始),ドミニカ共和国(2007年6月交渉開始),中米四ヶ国(エルサルバドル,グアテマラ,ホンジュラス,ニカラグア)(2010年3月第12回交渉),ウクライナ(2010年6月開始)との間でFTA交渉を行っている。2009年10月にモロッコとの間でFTA交渉可能性の検討を行い,2009年11月にはインドとの間で包括的経済連携協定(CEPA)交渉可能性の検討を行っている。
なお,EUとの間では,加EU貿易投資促進協定(TIEA)の基本的な枠組みを2004年3月に合意していることに加え,2009年5月に包括的な経済・貿易協定(CETA)の交渉開始を公表。2010年4月には第3回交渉を行い,次回交渉を7月に予定している。
(ロ)カナダの貿易政策
2009年6月にカナダ政府が発表した2009年版市場アクセス報告書では,カナダ経済が貿易に大きく依存していることを踏まえ,多数国間,地域,二国間における開かれた貿易関係に利益を受けていることから,地域及び二国間貿易協定の活性化を課題とするとしている。
日加経済関係
(1)日加経済関係は基本的に良好。貿易収支も概ね均衡。
(2)日加間貿易は相互補完的。対加主要輸入品目は石炭・木材・銅鉱などの原材料,菜種・豚肉などの農産品,輸出品目は自動車・自動車製品を中心とした製造業品。
(3)2005年11月に日加首脳により署名された「日加経済枠組み」文書で合意された「共同研究」が2007年10月に終了し,二国間の貿易・投資及びその他協力案件の更なる促進のため,2008年11月に第1回貿易投資対話を開催。
1.貿易動向
(1)日加間の貿易収支は概ね均衡しており,2001年までは恒常的に日本の赤字基調となっていたが,2002年,2006年及び2007年は日本の輸出超過。近年は再び,日本の赤字基調となっている。2009年は輸出入ともに減少しており,日本の対加輸出額は7,228億円(対前年比35.24%減),同輸入額は8,575億円(対前年比35.18%減)であり,貿易収支は日本の1,347億円の出超となった。
(2)カナダにとって,日本は輸出入とも米国に次ぐ第2位の貿易相手国であったが,貿易額では2002年以降,中国,英国及びメキシコが日本を追い抜き,2009年は第5位となり,シェアは2.8%である。輸入では米国,中国,メキシコに次ぎ,日本は第4位(2009年3.4%),輸出では米国,英国,中国に次ぎ,日本は第4位(2009年2.3%)である。
他方,日本にとってカナダは14番目の輸入相手国(シェア2009 年,1.7%)であり,16番目の輸出相手国(2009 年,1.3%)である。
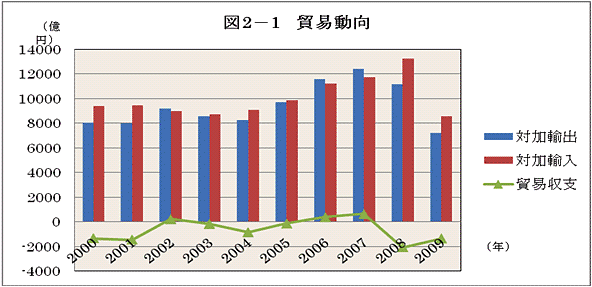
| 対カナダ輸出 | 金額 (1,000円) |
構成比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動車(1500-3000cc以下) | 169,288,352 | 23.4% |
| 2 | 自動車(3000cc超) | 73,956,552 | 10.2% |
| 3 | ギヤボックス及びその部分 | 42,798,509 | 5.9% |
| 4 | 自動車(1000-1500cc) | 31,471,895 | 4.4% |
| 5 | テレビ・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラレコーダー | 26,056,521 | 3.6% |
| 6 | 飛行機・ヘリコプターの部品 | 23,285,132 | 3.2% |
| 7 | 再輸出品 | 22,422,572 | 3.1% |
| 8 | 車輌用ガソリンエンジン(1000cc超) | 16,209,018 | 2.2% |
| 9 | ゴム製乗用車用新品空気タイヤ | 14,497,699 | 2.0% |
| 10 | 縦方向サブマージアーク溶接輸送管(外径406.4mm超) | 11,333,580 | 1.6% |
| (1-10までの合計) | 431,319,830 | 59.6% | |
| 輸出総計 | 722,761,037 | 100.00% | |
| 対カナダ輸入 | 金額 (1,000円) |
構成比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀝青炭(強粘結性のコークス用炭) | 163,453,376 | 19.1% |
| 2 | 菜種(低エルカ酸のもの) | 81,913,261 | 9.6% |
| 3 | 豚肉(冷凍したもの) | 62,513,895 | 7.3% |
| 4 | 銅鉱(含精鉱) | 55,449,343 | 6.5% |
| 5 | 熱帯産でない針葉樹木 | 54,303,399 | 6.3% |
| 6 | 豚肉(生鮮・冷蔵のもの) | 27,762,247 | 3.2% |
| 7 | メスリン,その他の小麦 | 24,654,511 | 2.9% |
| 8 | 大豆 | 22,859,205 | 2.7% |
| 9 | さらした針葉樹の化学木材パルプ(ソーダパルプ等) | 17,815,898 | 2.1% |
| 10 | 塩化カリウム肥料 | 16,041,453 | 1.9% |
| (1-10までの合計) | 526,766,588 | 61.6% | |
| 輸出総計 | 857,526,049 | 100.00% | |
(財務省貿易統計より作成)
(3)日加間の貿易関係は相互補完的関係にある。カナダは,近年,ハイテク・IT関連といった,より付加価値の高い製品輸出の拡大に積極的であるが,日本との関係においては,カナダからの主要輸入品目は原材料・農産品,カナダへの主要輸出品目は製造業品。
(4)カナダ経済は対外依存度が高く,総輸出額がGDPの約28.6%(2009年)を占めており,国際競争にさらされることはカナダの経済に活力を与え,イノベーションの加速,外国投資の増加をもたらし,多くの雇用を創出するとの立場から,カナダ政府は主要市場から障壁を取り除くと共に,国際貿易投資をめぐる制度と規則を強化し,新しいパートナーとの関係を構築することを重視している。
2.投資動向
(1)日本の対加直接投資は,1990年代は1,000億円前後で推移し,1999年には大型M&A案件(約2,400億円)があり急増したが,2000年以降は停滞していた。しかし,2006年以降,邦人自動車企業の製造プラント拡大や金融・保険分野での伸びにより,投資は増加。2009年は輸送機械器具の分野における投資回収が影響し,再び停滞傾向にある。
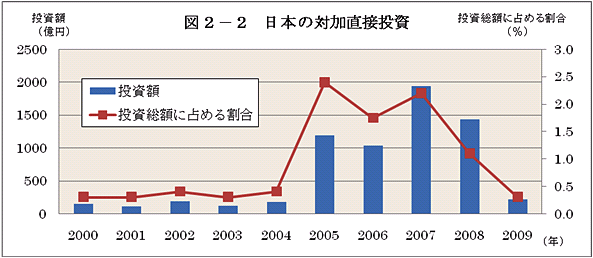
出所:「対外及び対内直接投資状況」「国際収支状況」(財務省)
(2)カナダの対日投資は,1998年には11件17億円(対内直接投資全体に占める構成0.1%)と低い水準にあったが,1999年には,大型の資本提携(約1,400億円)があり大幅に増加した。しかしながら,2000年以降は停滞しており,2006年には金融・保険の分野などでの投資引揚げにより,-3,209億円となっている。2009年の投資総額は-111億円であり,対日投資の増加が課題のひとつとなっている。
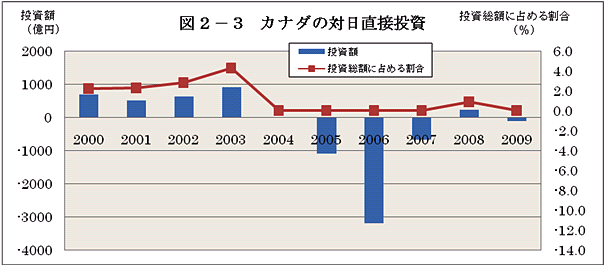
出所:「対外及び対内直接投資状況」「国際収支状況」(財務省)
3.個別事項
(1)「日加経済枠組み」
2005年1月,マーティン前首相の訪日に際して行われた日加首脳会談において,日加両首脳は日加経済関係強化をはかるべく,「創造的な日・カナダ経済枠組み」を立ち上げることで合意。(イ)日加経済関係を総攬する次官級経済協議(JEC)の強化,(ロ)優先的協力分野の特定,(ハ)日加貿易・投資関係の現状を分析し,種々の関係強化策について検討する1年間の共同研究,の3点を柱に,日加経済関係の潜在力を最大限引き出すための取組について検討することとした。その後,日加両国間での協議を経て作成され,2005年11月の日加首脳会談において小泉総理とマーティン前首相により署名された「日加経済枠組み」文書では,投資,観光促進,社会保障協定,税関協力等15の優先的協力分野を特定,列挙するとともに,二国間の貿易・投資及びその他協力案件の更なる促進のための「共同研究」を行うことが合意され,両国間で共同研究を実施し,2007年10月に報告書を取りまとめた。
この報告書は,これまでの日加間の経済分野での協力を総括し,今後両国が経済関係の強化のために取るべき手段として,(イ)規制改革対話,(ロ)投資促進,(ハ)租税条約の改正,(ニ)食品安全,(ホ)エネルギー,(へ)科学技術,(ト)航空サービス,(チ)知財,(リ)電子通信機器の相互承認の各分野における協力の促進を提示している。現在,これらの報告書の内容を踏まえてカナダとの間で具体的な協力につき,検討しているところである。
なお,協力の優先分野については2008年10月に改訂を行い,新たに貿易投資対話の開催や知的財産権が盛り込まれた。
(2)日加間の経済分野での定期的協議
現在,日加間の経済分野での包括的な定期協議としては,政府間のものとしては日加次官級経済協議(JEC)がある。また,2008年1月に東京で開催されたJECでの合意を受け,同年11月,貿易・投資及びその他の協力案件の更なる促進のため,貿易投資対話(TID)を初めて開催し,ビジネス環境の整備,規制協力及び貿易政策についての意見交換を行った。民間間の協議としては日加経済人会議(JCBC)が年に一回開催されてきたが,同会議は第25回会合(2002年5月,仙台)をもって終了し,2004年9月に「新たな対話」の形として日本経団連のカナダ委員会とカナダ経営者評議会(CCCE)によって第1回日本カナダ経済会議(東京)が開催された(第2回会議は2005年11月トロントにて開催)。これらの他,分野別協議として,日加財務金融協議,日加漁業協議,日加情報通信政策協議,日加官民観光定期協議,日加菜種協議,建築専門家委員会(日米加の三ヶ国で構成)等がある。
4.日加間で最近締結された協定等
(1)日加独占禁止協力協定
2005年1月,カナダ政府と交渉中の競争分野における日加独占禁止協力協定について,主要点に関し大筋合意に達し,同年9月6日に署名が行われ,10月6日に発効した。この協定によって,(イ)国際的な広がりを有する反競争的行為に対する両締約国の競争法の執行の強化,(ロ)日・カナダ競争当局間の協力関係の一層の発展,(ハ)域外適用をめぐる摩擦の回避等の効果が期待される。
(2)日加社会保障協定
日加両国の年金制度への強制加入による二重加入等の問題の解決のため,2004年10月に日加両政府間で社会保障協定の締結交渉を開始し,その後2回の協議を経て,2006年2月に東京において署名が行われ,2007年11月外交上の公文の交換を経て,2008年3月に発効した。この協定によって,(イ)原則として就労地国の年金制度にのみ(ただし,派遣期間が5年以内の場合は派遣国の年金制度にのみ)強制加入することが原則になるとともに(二重加入の問題の解消),(ロ)両国での保険期間を通算し,それぞれの国における年金の受給権が確立される(保険料掛け捨ての問題の解消)。
(3)日加AEO(認定事業者)制度の相互承認
2010年6月25日,日加当局間でAEO(認定事業者)制度の相互承認に合意。AEO(Authorized Economic Operator)制度とは,貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して,迅速化・簡素化された税関手続を利用することを認める仕組みであり,相互承認により,それぞれのAEOに対し,相互に便宜を与えることとなった。
![]() Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
Adobe Systemsのウェブサイトより、Acrobatで作成されたPDFファイルを読むためのAcrobat Readerを無料でダウンロードすることができます。左記ボタンをクリックして、Adobe Systemsのウェブサイトからご使用のコンピュータのOS用のソフトウェアを入手してください。
