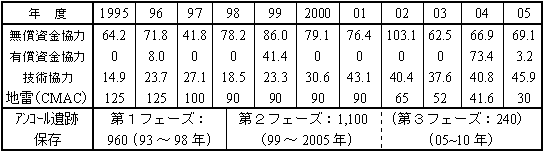アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
カンボジア和平及び復興への日本の協力
平成19年1月
我が国は、1980年代末よりカンボジアの和平、復興、内政安定、国造りに積極的に協力してきた。
こうした我が国の和平プロセスへの深い関与を通じて形成されたカンボジアの日本への信頼感を基礎にカンボジアとの関係を強化することは、我が国の対ASEAN外交推進の上でも重要であり、我が国は今後もカンボジアの国造りを支援していく方針である。
カンボジア和平及び復興への日本の協力の概要は次の通りである。
1.カンボジア和平への協力
(1)パリ和平協定締結に向けた外交努力
(イ)1989年の第一回カンボジア問題パリ国際会議に日本は招かれて参加(和平会議に日本が参加したのは戦後初)。復旧・復興と避難民の祖国帰還を担当する第三委員会にて豪州との共同議長を務めた(日本側議長は今川幸雄元在カンボジア大使)。
(ロ)1990年2月の河野南東アジア第一課長(当時)による未承認政権・ヘン・サムリン統治下のカンボジア訪問を踏まえ、カンボジア問題の解決には、カンボジア人自身の直接対話が極めて重要との認識の下、1990年6月に「カンボジアに関する東京会議」を開催した(カンボジア各派が参加)。これは地域紛争の解決を目指した和平会議の開催という我が国外交史上例を見ない試みであった。同会議で、暫定期間の主権の源泉となるカンボジア最高国民評議会(SNC)にプノンペン政権と三派連合政府が対等参加することについての合意及び、SNC第一回会合と軍事活動の自粛の同時実施など和平プロセスにおける重要な点につき合意された。
(ハ)1991年には包括的政治解決に向け、日本の非公式な考えを各派に打診したり、病気治療の目的でフン・セン首相を訪日招待した際に、包括的和平文書に関して、小和田外務審議官と意見交換の機会を設定する等、積極的な外交を展開し、1991年10月のパリ和平協定の締結に向けた国際社会の努力の一翼を担った。
(2)国連カンボジア暫定機構への要員派遣
パリ和平協定を受けて、明石康国連事務総長特別代表が統括する国連カンボジア暫定機構(UNTAC)による暫定統治が開始された。日本では、1992年6月に「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」が成立し、同年9月以降、日本から自衛隊施設大隊、停戦監視要員、文民警察官及び選挙要員等延べ人数1300人余りがUNTACの活動に参加し、人的貢献を行った。(我が国による初のPKO派遣)
こうした中、1993年4月、国連ボランティアの中田厚仁氏が何者かに銃撃され死亡し、更に5月には文民警察官等の一行が何者かに襲撃され、高田晴行警視正が死亡、その他4名の文民警察官が重軽傷を負う等尊い犠牲を払ったが、総選挙の成功に貢献した。
(9月24日、新憲法に基づきシハヌーク殿下が国王に再即位し、「カンボジア王国」は再出発した。)
2.カンボジア経済復興への我が国の外交努力
我が国は、カンボジアの復旧・復興は同国の和平の維持と表裏をなすものと考えて、復興支援に積極的な外交を展開した。
1992年6月に我が国は国連開発計画(UNDP)と共同で議長を務め、「カンボジア復興閣僚会議」を開催した。この会議において、カンボジアに対する中長期的な復興援助の調整メカニズムとして「カンボジア復興国際委員会(ICORC)」の設立につき合意がなされ、我が国が議長を務めることとなった。ICORCは計3回開催されたが(1993年9月、1994年3月、1995年3月)、1996年からはICORCに代わり「カンボジア支援国会合(Consultative Group Meeting for Cambodia, CG会合)」が開催された。CG会合は、その後継続され、2006年3月には第8回会合が行われた。我が国は、過去3回CG会合の開催国を務める等、同会合に積極的に貢献している。
3.新生カンボジアの政治的安定・民主化のための支援
(1)1997年7月、翌1998年の総選挙を控えて対立してきた二大与党(人民党及びフンシンペック党)の間で武力衝突が発生し、ラナリット第一首相(フンシンペック党党首)は国外へ逃れた(いわゆる7月事変)。これに対し、我が国事変発生以前には橋本総理(当時)のイニシアティブで事態沈静化のため仏と共に特使(今川元大使)を派遣した他、事変発生後においても訪日したフン・セン首相への働きかけや停戦とラナリット殿下の選挙参加に関する4項目提案を行うなどして、自由・公正な選挙実施による事態の正常化のために貢献した。1998年7月の総選挙に対しては、選挙費用21百万ドル(当初見積もり)の内、912万ドルを支援し、選挙専門家1名及び監視員32名を派遣した。
その後も次の通り選挙支援を実施している。
- 2002年2月の地方選挙:選挙費用約18百万ドルの内、3百万ドルをノンプロ無償見返り資金により支援。NGOによる有権者教育活動等を草の根無償で支援。我が国現地大使館員を中心とする18名により選挙監視活動を実施。
- 2003年の総選挙:国家選挙管理員会に226万ドル、NGOに草の根無償で13.6万ドルの支援を実施。選挙監視団25名を派遣。
4.カンボジアの法の支配及び人権状況改善への協力
(1)法整備支援
司法関係者の能力向上を図り、カンボジアの司法体制の整備・向上を図ることを目的に、民法・民事訴訟法の起草作業及び司法制度改革支援を中心とした協力を1999年3月から実施している。民事訴訟法は2006年7月に公布され、民法も閣僚評議会での審議を終え、法案として国会に提出されることが閣議決定された。
(2)クメール・ルージュ裁判への協力
クメール・ルージュ(KR)裁判特別法廷は、1970年代後半に国民大虐殺を行ったKR政権の幹部を裁くため、国連の技術的・資金的協力を得てカンボジア国内裁判所に設置される特別法廷である。我が国は、同裁判がカンボジアの「法の支配」や「良き統治」の確立に資するとの考えから、国際社会において主導的に協力をしてきている。
我が国は本裁判実施への国連の協力を確保するために国連総会における決議の提案など国際社会において主導的な外交努力を行った。また、我が国は同裁判の国連負担分予算(43百万ドル、3年分)の約半分(21.6百万ドル)の資金を拠出した。今年7月、我が国候補の野口元郎検事が上級審の国際判事に任命された。
(3)国連カンボジア人権決議の主提案国としての役割
我が国は、1999年より2005年まで、国連人権委員会、乃至、国連総会第3委員会において「カンボジアの人権状況決議案」の主提案国となっている。同決議案はこれまで全て無投票採択されており、右は我が国がカンボジア側と西側諸国間の意見調整に努力した成果として双方から高い評価を得ている。
同決議案は、カンボジアの人権状況を公平な視点から評価しつつ、更なる進展を慫慂するバランスの取れた内容となっている。
5.近年の日本のカンボジアへの経済協力
我が国は、2002年1月に対カンボジア国別援助計画を策定し、同国の持続的な経済成長の達成及び貧困対策を中心に、1)持続的な経済成長と安定した社会の実現、2)社会的弱者支援、3)グローバル・イシューへの対応、4)ASEAN諸国との格差是正のための支援の4分野を重点分野として支援を行っている。
我が国は、対カンボジア援助では最大の援助供与国であり、2005年度までの援助実績は円借款133.09億円、無償資金協力1,090.65億円(以上、交換公文ベース)、技術協力392.47億円(JICA経費実費ベース)である。
【参考】我が国の経済協力(無償・有償・技協:億円、地雷・アンコール遺跡:万ドル)