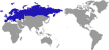 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
日墺21世紀委員会第10回会合
【会議概要】
2006年10月30日及び31日、日墺両国の委員によって構成され、両国の共通の利益に関わる長期的課題について意見交換を行うことを目的とする賢人会議である「日墺21世紀委員会」第10回会合がウィーンにて開催された。
オーストリア外務省のヨハネス・キルレ外務次官は開会の挨拶において、過去12年に渡って委員会が存続したことが日墺関係の重要な一部となっている旨を述べ、2006年4月24日、東京で行われたシュッセル・オーストリア首相及び小泉首相との日墺首脳会談において、本委員会についても言及されたこと等について触れた。
1.ワークショップ『エネルギー問題』
委員会の前半では、エネルギー安全保障をテーマとするシンポジウムが行われた。
(日本側発言)
中国とインドの経済成長を契機とするアジアにおけるエネルギー需要(2003年から2030年の間に倍増することが予想されている)の増加傾向によって、石油輸入依存度はさらに高まることとなる(現在、消費量の約60%であるが、2030年には約90%に達すると予想)旨を述べ、また、特に中東からの石油輸入が大幅に増大する可能性が極めて高いことを指摘した。現時点では各国ともそれぞれ自国のエネルギー供給の確保に努めており、エネルギー補給の多様化(石油、原子力発電等)、輸入国の分散、外国油田開発への投資、戦略的石油備蓄の用意等を行っているが、その際、各国間における競争や関係の緊迫化等が生じる恐れがあり、より大きな需要を確保するためにはアジアの主要輸入国の間で協力関係が構築されることが望ましいという見解を示した。さらに、安定したエネルギー需要を必要とする石油輸出国との間には相互依存関係が生じるため、これらの国々と協力関係を結ぶことも検討の余地がある旨を述べた。
(オーストリア側発言)
エネルギー安全保障問題の複雑さについて言及し、資源、輸送方法、エネルギー変換能力(精製等)、さらには分配(エネルギー輸送キャパシティ等)の保障について述べた。この中で、EUは“Green Paper : Towards a European Strategy for the Security of Supply”(2000)と“Green Papger on Energy Efficiency”(2006)の2種類の戦略文書を公表していることに触れ、EUのエネルギー総消費量においても熱発電所においても、今後は特に天然ガス使用の増加が予想されており、2030年には、EUの石油輸入依存は約87%、天然ガスでも約80%とされていることを述べ、EUは2020年までに省エネの可能性を一般家庭において約27%、事務所において約30%、交通において約26%、産業において約25%と見積もっている旨を報告した。
その上で、概要以下の見解を示した。
1)新しい化石エネルギー源の開発よりもエネルギー効率化の方が経済的である、
2)ある一定の分野においては、化石エネルギーを再生可能エネルギーで代用する方策が有望である、
3)建物暖房・冷房等に受動型太陽工学を使用することで、多大な省エネが可能となる、
4)個人的交通手段においては今後も化石エネルギー源に依存することとなるであろう、
5)そのため、オーストリアは将来的にも石油、天然ガス及び石炭を大量に輸入する必要がある。
(日本側発言)
次に、「代替戦略」というテーマに関して、2006年5月に発表された日本の新・国家エネルギー戦略について報告があった。日本は、2030年までに石油依存の割合を約40%(現在は約70%)にまで下げ、原子力発電の割合を約30~40%まで引き上げ、さらにエネルギー効率を約30%向上させることを計画しているという。また、外国の油田・天然ガス源の開発を促進し、「自主開発」原油輸入の比率を40%にまで引き上げる予定であるという。その際に予期されるリスクとして同委員は、エネルギー消費増加に伴う需給の構造的逼迫、中国など新興の大消費国とのエネルギー源を巡る競争、地政学的緊張感の高まり、油田・天然ガス源開発などにおける投資リスク等を挙げた。
その際、聴講者からの質問に答えて、日本の車輌メーカーがハイブリッドエンジン搭載車両(一部で再生可能エネルギーを使用)の開発・販売においてあげた実績について説明された。これによって2030年までに日本の交通において約20%の省エネ効果が見込まれるという。今後はガソリンだけに頼らないハイブリッドその他の技術革新により、更なるエネルギーの効率化が期待される、と述べた。
(オーストリア側発言)
オーストリアにおける新しいエネルギーシステムの必要性を強調した上で、高いエネルギー効率、化石エネルギー割合、温暖ガスの削減、供給保障、革新技術の開発等を促進するEUのエネルギー戦略は、持続可能なエネルギーシステムにとって良い出発点をなすであろうが、これには政治レベルだけでなく、生産者および消費者のレベルにおいても変革への意志が不可欠である旨を述べた。
2.委員会会合『国際情勢:日・米・EUの役割』
(日本側発言)
緊張を孕む東アジアにおける日本の外交政策の特徴に関して、中国と北朝鮮の一党独裁体制と日本及び韓国の民主主義とを対比した上で、大量破壊兵器拡散の脅威(北朝鮮によるミサイル及び核実験)、中国の軍事費増大によって脅かされる東アジアの軍事面の均衡等について言及し、日本は米との安全保障体制強化に努めると同時に、インド、オーストラリア、韓国及びASEAN諸国との関係や中国との協力関係の強化に努めている旨を述べた。また、東アジアには現在、効果的な地域的安全保障の機構が欠けているが、それには冷戦期のCSCEがモデルとなり得ること、日本外交は民主主義、人権、法の支配及び市場経済等の価値を重視し、価値を共有するEU,OSCE等との協力関係を発展させている旨を述べた。
(オーストリア側発言)
欧州の米に対する関係を解析し、両国が2003年のイラク戦争の際の意見の相違を乗り越え、再び協力関係にあるという結論を述べた。ただし、基本的な見解の相違(単極主義・多極主義、軍事化・人民法と国際機関へ重点を置くこと)はまだ解決をみていないとし、米も欧州もともにパートナーシップのための前提条件を満たす意思がないため、本物の対等な欧米パートナーシップへの見通しはいまだに立っていない。EUは加盟国の意見を一本化し、その防衛政策を作成せねばならず、米国は指導的役割及び責任をEUと分かち合うことに前向きにならなくてはいけないという。
(日本側発言)
航空産業の見地からグローバルな国際システムについて報告し、アジアの高い経済成長率は空輸の増加をもたらし、2006年から2025年までの間にさらに約10%の増加が見込まれるが、世界全体での増加率は約6.1%にとどまる旨を述べた。特に空輸によって行われる商業活動(特に電子部品分野)は、東南アジア諸国間において非常に活発であり、最終生産物は、同様に空路で欧州や北米へと輸出される。旅客機分野ではアジア・欧州・北米を結ぶ空路が緊密になっており、2004年には、欧州・北米間を約4000万人が往来し、欧州・アジア間では約1600万人、アジア・北米間では約1200万人であった。東アジアにおいては東京・ソウル・上海間(予定)で定期的にシャトル飛行が行われているという。
(オースリア側発言)
世界商業の主要部分を構成するEU・米国・日本の経済関係について概要を述べ、2006年はEU25カ国の占める割合が12.2%、米国が8.9%、日本が5.9%、さらに、中国の割合は1986年から2006年の間に1.6%から9.4%にまで増加したという。これによると、EUと米は互いに最大の取引相手であるが、商行為の約4分の1が国際企業によって行われ、うち2%を係争問題が占めている。日本はEUの5番目に大きな輸出市場であり(4.1%)、EU全体に対する輸出割合において約6%を占めている。アジアに対する商業関係について同委員は、多角的経済連携協定(EPA)と、中断したWTOドーハラウンドの前向きな進展が必要である旨を強調した。
外交アカデミーにおける公開のシンポジウムの開催によって、委員会はより公開された形式で行われた。優れた専門家によるハイレベルな貢献により、委員会は両国にとって意義深いものとなった。
【第10回会合の委員】
| 氏名 | 現職 | |
|---|---|---|
| 委員長 | 石坂 芳男 | トヨタ自動車相談役 |
| 委員 | 進 和久 | エー・エヌ・エー総合研究所顧問 |
| 植田 隆子 | 国際基督教大学教授 | |
| 小山 堅 | 財団法人 エネルギー経済研究所研究理事 | |
| 梅津 至 | 駐オーストリア大使 |
| 氏名 | 現職 | |
|---|---|---|
| 委員長 | ゲアハルト・ブルックマン | 元下院議員 |
| 委員 | マックス・コートバウアー | 元郵便貯金銀行総裁 |
| ハンスペーター・ノイホルト | ウィーン大学教授 | |
| ヴァルター・コレン | 墺・産業院外国貿易局長 | |
| ニコラウス・シェルク | 墺・外務省アジア・大洋州局長 | |
| ピーター・モーザー | 墺・駐日大使 |
(敬称略)
