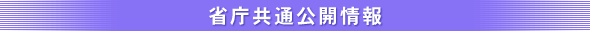
II. 重点外交政策を中心とする外交のレビュー
(重点外交政策評価ダイジェスト)
平成17年度我が国の重点外交政策は、「国民を守る日本外交~安全保障と邦人安全対策~」、「先頭に立つ日本外交~新たな国際秩序の構築に向けて~」、「主張する日本外交~戦略的な情報発信」、「底力のある日本外交~情報収集、ODA、文化、外交実施体制~」の4本の柱の下、各施策が実施されている。以下は重点外交政策として位置づけられている施策、またはそのような事務事業を含む施策に関し、概括的にレビューしたものである(具体的な評価については各項目参照)。
1.国民を守る外交(我が国の安全保障の強化と邦人安全対策)
(1)日米安保体制の維持・強化
日米安保体制の信頼性の向上と在日米軍の円滑な駐留の確保を実現することは、我が国の安全保障を確保する上で不可欠であり、平成17年2月に「共通戦略目標」が日米両国により確認されたことを踏まえ、10月の日米安全保障協議委員会(「2+2」会合)において、日米がどのような役割や任務を担い、そのためにどのような能力を備えるべきかに関する検討や、「抑止力の維持」と「地元の負担軽減」という二つの大きな目標を実現するための兵力態勢の再編に関する検討の結果を取りまとめた共同文書を出した。また、弾道ミサイル防衛分野では日米共同開発の着手を発表し、在日米軍駐留経費負担については新たな特別協定に署名するなど、平成17年度は日米協力の深化が特に顕著に現れた。
評価シート:2-3「米国との安全保障分野での協力促進」
(2)北朝鮮問題への対応
核問題については、平成17年7月から9月にかけて行われた第4回六者会合において六者会合で初めてとなる「共同声明」の採択に成功した。「共同声明」の中で北朝鮮はすべての核兵器及び既存の核計画の検証可能な放棄を約束した。
これにより、北朝鮮の核問題の平和的解決の重要な基礎を築くことができた。
拉致問題については、17年11月の日朝政府間協議において、生存者の早期帰国、真相究明、容疑者の引渡しを改めて強く求めた。12月の同協議では、拉致問題に関する協議、安全保障協議、国交正常化交渉の3つからなる日朝包括並行協議の立ち上げに合意した。18年2月の同協議では、具体的な進展は得ることができなかったが、拉致問題をはじめとする我が方の広範な懸念や要求を直接伝えたことには一定の意義があった。また、国連総会における「北朝鮮の人権状況」決議の採択は、拉致問題解決へ向けた国際的な圧力となっている。
評価シート:1-2 「朝鮮半島の安定に向けた努力」
(参考)1-3 「未来志向の日韓関係の推進」
11-3 「国際社会のおける人権の保護・促進のための国際協力の推進」
12-2 「政治・安全保障分野における国際約束の締結・実施」
(3)領土問題への対応、経済安全保障の強化
(イ)ロシアとの平和条約交渉の推進
日露関係においては、北方領土問題が戦後60年を経ても依然として未解決であり、最大の懸案となっている。日露関係を進展させるためには、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して早期に平和条約を締結するという一貫した方針の下、精力的に平和条約交渉を行っていくとともに、幅広い分野で日露関係を発展させていくことが重要である。平成17年度には、3度の首脳会談をはじめ、外相会談や事務レベルでの会談等、あらゆるレベルで協議を行い、ロシア政府要人等による北方領土問題に関する強硬な発言が目立った中、同年11月の日露首脳会談では、両首脳が平和条約締結問題につき、これまでの様々な合意及び文書に基づき、日露両国が共に受け入れられる解決を見出す努力を行うことで一致した。また、政治対話、貿易経済分野の協力、国際舞台における協力や人的交流・文化交流等、「日露行動計画」の着実な実施を通じて幅広い分野で両国関係が進展した。
評価シート:4-5 「ロシアとの平和条約締結交渉の推進及び、幅広い分野における日露関係の進展」
(ロ)竹島問題への対応
平成17年2月の島根県議会の「竹島の日」条例の上程を機に盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の3・1演説、国家安全保障会議(NSC)常任委員会の声明等、竹島問題を巡って日韓関係は悪化した。我が国は、外務大臣談話を発出し、竹島の領有権を巡る我が国の立場は一貫していることを明確にした上で韓国国民の過去を巡る心情を重く受け止め、和解に基づく関係構築を呼びかけた。その後、4月、5月の外相会談及び6月の首脳会談を経て、日韓関係は平静に向かった。今後も、韓国側の理解を得るための粘り強い働きかけと日韓関係全体の強化を併せて進展させる必要がある
評価シート:1-3 「未来志向の日韓関係の推進
(ハ)経済安全保障の強化
エネルギー、漁業、海洋問題、食糧問題等への効果的な対応を通じ、これらの資源の持続可能な形での安定供給を確保するため、様々な国際協力を推進した。
エネルギーについては、米国ハリケーン・カトリーナの被害により不安定化した国際石油市場に対して、国際エネルギー機関の協調行動として、我が国の石油備蓄の放出を行った結果、世界的な原油の安定供給及び国際原油価格の安定を確保した。
漁業については、我が国にとって最も重要な水域を扱う、中西部太平洋まぐろ類条約が国会承認され、また、公海における魚類(たら、かれい、まぐろ、かつお等)の保存管理のための一般的措置に関する国連公海漁業協定の国会提出が閣議決定され、国際協力を推進した。また、我が国の働きかけにより、国際捕鯨委員会に我が国の立場を理解する6ヶ国が新規加盟した。
海賊問題については、アジア海賊対策地域協力協定を他国に先駆けて17年4月に締結し、同協定の早期発効をめざし、関係各国に対し、同協定の早期締結を働きかけた。
国際海洋法裁判所選挙に際し、我が国が候補者として指名した柳井俊二中央大学教授が同裁判所裁判官に選出された。また、大陸棚延長に関するシンポジウムを開催し、各国の大陸棚限界延長申請準備の促進を図った。
評価シート:10-4 「経済安全保障の強化」
(4)対アジア外交
「安定しかつ繁栄した東アジア」を築くためには、自由、民主主義、市場経済、法の支配、人間の尊厳の尊重を促進し、偏狭なナショナリズムを排除することが重要である。米軍による抑止力の維持を前提としつつ、日中共益の分野での中国との協力を深化し、韓国とも拉致問題を始めとする様々な分野で協力し、東南アジア諸国、インドとの協力も推進した。
(イ)対中外交
様々なレベルにおける率直な間断なき対話を実施。対話を通じた懸案の適切な処理を行うとともに、幅広い分野において未来志向の協力関係を推進。日中経済関係の拡大は続いており、前年に引き続き、日中貿易総額(含む香港)は、日米貿易総額を超過した。人的往来が年間417万人(1日1万人以上)と国民交流も一層の深化を遂げた。
また、「日中21世紀交流基金」の立ち上げ等は、日中間の国民交流を強化し、今後の日中関係を下支えするものとなることが期待される。
評価シート:1-4 「未来志向の日中関係の推進」
(ロ)対韓外交
政治分野での緊密な対話が行われ、竹島問題や、靖国神社参拝問題等で日韓関係がぎくしゃくした時期においても、外交当局間の対話は維持された。人的交流の拡大については、国交正常化40周年を記念した「日韓友情年2005」の下で700件を超える記念行事を成功させ、羽田―金浦直行便の倍増、短期査証の無期限免除等を通じ年間400万人を超える日韓間の往来を実現し、交流の流れは高まった。北朝鮮問題に関しても日韓連携の下、六者会合において朝鮮半島の非核化へ向けた重要な基礎となる共同声明の採択に成功した。また、過去に起因する問題への対応についても具体的措置がとられ、未来志向の日韓関係の基盤構築の一助となった。
評価シート:1-3 「未来志向の日韓関係の推進
(ハ)東南アジア諸国
ASEANの後発加盟国であるベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーに対する支援を通じて、ASEAN域内の格差を是正し、ASEANの統合を促進することにより地域の平和と安定に貢献することを目的として、メコン地域開発支援(総額630億円)を行った。日本の企業の進出が盛んで、経済的発展を遂げつつあるタイとは日タイ経済連携協定締結に向けて平成17年度だけで閣僚級を含む様々なレベルで計13回の交渉を行い、平成18年2月には協定条文を基本的に確定するに至った。マレーシアとの経済連携協定については、12月に署名が行われ、インドネシアとの間でも早期協定締結を目指して強力に交渉が進められた。また、スマトラ沖大地震の被災国であるインドネシアに対し、様々な復興事業への支援を行い、インドネシア側からも様々な機会に謝意が表明された。東南アジア諸国との要人往来も盛んに行われるなど、二国間関係を新たな高みに引き上げるための外交が積極的に展開された。
評価シート:1-5 「タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーとの友好関係の強化」
1-6 「インドネシア及びマレーシア等との友好関係の構築強化」
(ニ)ASEAN地域フォーラム(ARF)を中心とする地域的安全保障協力の推進
アジア太平洋地域の平和と安定の確保のための多国間の枠組みとして、ASEAN地域フォーラム(ARF)を活用している。信頼醸成の促進→予防外交の進展→紛争へのアプローチの充実の3段階のアプローチを設定して漸進的な進展を目指している。そのため種々の会合、ワークショップに参加するとともに、12月には東京において海上安全保障に関するワークショップを開催した。また、第12回ARF閣僚会合の議長声明では、朝鮮半島の非核化に向けた平和的解決を探求する重要性に言及されるなどの成果があった。
評価シート:7-1 「日本の安全保障政策に関する外交政策」
(ホ)対印外交
17年度は、5年ぶりとなる総理のインド・パキスタン訪問及びそれに続く麻生外務大臣のインド・パキスタン訪問が実現する等、特に日印関係にとって大きな節目となる年となった。具体的には、17年4月の総理訪印の際に今後の二国間関係の戦略的方向性に関する具体的指針となる「8項目の取組」に合意した。18年1月の外相訪印の際には、「8項目の取組」のフォローアップとして、外相間の戦略的対話の立ち上げ、経済連携協定(EPA)の真剣な検討、今後3年間で4000人の人的交流の実現を目指す「麻生プログラム」の立ち上げ等に合意した。
評価シート:1-7 「南西アジア諸国との友好関係の強化」
(5)海外邦人の安全の確保
平成17年における日本人海外渡航者は年間1700万人(国民の8人に1人)、在留邦人は100万人に達するなど、海外に渡航・滞在する日本人は増加する一方であり、海外において事件・事故等のトラブルに遭遇する邦人も増加している。このような中、「自分の身は自分で守る」ための国民自身による安全対策・危機管理意識の醸成・強化は海外邦人の安全対策の基礎となるものであり、17年度において、外務省危険情報を201国・地域に対し305回改訂・発信、スポット情報(渡航先別事件・事故速報)を487回改訂・発信、安全対策基礎データを200国・地域に関し改訂した。電話相談は9370件、ホームページへのアクセスは約4148万件に急増した。スマトラ沖大地震及びインド洋津波の未曾有の悲惨な被害に関する国民の記憶は鮮明であり、ホームページのアクセス数からみても、邦人の安全対策・危機管理意識が高まったといえる。
海外邦人援護・危機管理体制の強化に向けては、休館時の緊急電話対応サービスの拡充、緊急事態対応マニュアルの更新等に加え、大規模緊急事態対応の強化のための安否確認システムの整備・拡充に取り組んだ。
評価シート:15-2 「海外邦人の安全確保・危機管理体制の強化」
(6)国際テロ対策
我が国は、テロ対策に係わる国際的な基準づくりに積極的に参画し、我が国の立場を反映させると共に、途上国等におけるテロに対する脆弱性の克服、国際的な法的枠組みの強化の観点からODAを活用し、研修員受入れ等途上国に対するテロ対策能力向上支援を推進した。また、日米豪、日・EU、日・印のテロ協議を行ったほか、東南アジア地域テロ対策協議を東京で行った。
ODAを活用した途上国のテロ対処能力向上支援を進めた結果、参加国の国内法整備や人材育成を通じてテロ対策における経験と知見を共有し、重要な課題として克服しようという共通の意思が強化されつつある。また、国連、G8等の枠組みへの参画及びより多くの国との多国間協議及び二国間協議の実施によって、様々な分野での情報交換や政策協調を行うことは、幅広く実効的な協力体制の強化につながった。
また、9.11テロ後、我が国は、テロ対策特別措置法に基づき、海上自衛艦をインド洋に派遣し、テロリスト捕捉のための作戦(「テロとの闘い」)を継続しているコアリション各国艦船への補給活動を実施しているが、平成17年には同特措法を延長し、テロとの闘いへの積極的な姿勢を引き続き示した。
旅券の偽変造防止により、テロリスト等国際犯罪人の国際間の移動を制限するため、国際的基準に準拠し、名義人の顔画像をICチップに記録したIC旅券の導入を行った。IC旅券の申請受付を開始した3月20日から31日の間に1日あたり約2万4千冊(導入1ヶ月前は1日あたり約1万4千冊)を発給した。
評価シート:7-3 「国際テロ対策協力」
7-1 「日本の安全保障政策に関する外交政策」
15-1 「領事サービスの改善・強化」
(7)国際犯罪対策の強化
国際犯罪対策を防止するための国際的な法的枠組みとして、平成17年度は通常国会において人身取引議定書及び密入国議定書について締結の承認を得、18年6月には、国連腐敗防止条約の締結につき国会の承認を得た。人身取引については、上記議定書のほか、4ヶ国に政府協議調査団を派遣し、実態面での対応も行った。これらを背景として、日本国内での人身取引の公的シェルターでの被害者保護数は104人(16年度は24人)に急増した。外務省の取組が国内の対応と連携し成果をあげたといえる。
評価シート:11-4 「国際組織犯罪への取組」
(8)軍縮・不拡散に対する取組
北朝鮮、イラン等の核問題や非国家主体による大量破壊兵器を用いたテロの脅威が懸念されている現在、国際社会として軍縮・不拡散に関する目標及び達成手段を共有することが重要である。我が国が国連総会における核軍縮決議案を出して12年目の平成17年は、決議案を新たに構成し直し、簡潔で力強い決議案を国連総会に提出、過去最多の168ヶ国という圧倒的支持で採択され、核兵器の全面的廃絶に向けた国際社会の意思形成の進展に貢献した。
また我が国は、グレンイーグルズ・サミットにおいて「不拡散に関する首脳声明」の採択においても貢献した。その他、我が国は包括的核実験禁止条約(CTBT)、化学兵器禁止条約(CWC)、生物兵器禁止条約(BWC)、国際原子力機関(IAEA)追加議定書等の軍縮・不拡散関連条約の普遍化、国際的輸出管理レジームの強化、PSIへの貢献、アジア不拡散協議(ASTOP)の開催等のアジアアウトリーチ活動等を中心に貢献した。
評価シート:8-1 「大量破壊兵器及びその運搬手段の軍縮・不拡散
2.先頭に立つ日本外交(新たな国際秩序の構築)
(1)国連安保理改革
日本が国連安保理の常任理事国になることは、国際的貢献に見合った発言力の確保、安全保障に係る重要な情報の迅速な入手等日本の安全保障の確保の点から重要な課題であり、過去約10年間にわたり安保理改革に取り組んできた。そのような中、平成17年7月、長い安保理改革における歴史上初めて、我が国は、ブラジル、インド、ドイツ(G4)と共に、常任理事国の拡大を含む安保理決議案であるG4枠組み決議案として総会に提出し、この決議案には、各国の厳しい利害が対立する中、32ヶ国が共同提案国となり、各国ハイレベル間で真剣かつ広範な議論が行われた。G4の取組は、決議案の採択には至らなかったが、改革実現に向けた機運を未だかつてないほど高め、平成17年9月の国連首脳会合で採択された成果文書において、早期の安保理改革を「国連改革の不可欠な要素」と位置付けられるに至った。また、平成17年12月に発出された総会議長発書簡は安保理拡大の必要性について幅広い合意があることを確認し、2006年に協議が再開されるべきであると言及した。今次第60回総会においても、既に2本の安保理決議案が提出されており、改革の機運は維持されている。
評価シート:7-4 「国連における我が国の地位向上」
(参考) 1-8 「大洋州地域諸国との友好関係の強化」
(2)多角的貿易体制の維持・強化と経済連携の推進
WTOの香港閣僚会議において、農業、非農産品市場アクセス、サービスなど主要分野においてメンバーが合意できる事項を閣僚宣言に盛り込むことに成功し、交渉を進展させた。宣言の中では、我が国の利益(「攻め」と「守り」の双方)を着実に確保し、今後の交渉につなげることができた。
また、WTOを補完する二国間/地域的な経済的枠組みが構築されつつある。具体的には、平成17年4月にメキシコとの経済連携協定(EPA)が発効し、平成17年12月にはマレーシアとのEPAが署名され、タイについては、平成18年2月に条文が基本的に確定し、署名に向けて調整を行っている。平成18年2月現在、比、タイ、韓国、ASEAN全体、インドネシア及びチリとの間でEPA交渉中である。我が国は高い水準の貿易自由化を目指すとともに、投資、知財、協力等幅広い分野を含むEPAを推進している。
評価シート:10-1 「多角的自由貿易体制の維持・強化と経済連携の推進」
(3)「人間の安全保障」の推進
我が国の働きかけにより、平成17年の国連総会首脳会合の「成果文書」には国連総会文書としては初めて「人間の安全保障」の文言が織り込まれ、今後の概念普及の基礎を確保した。
具体的な事業として、「人間の安全保障基金」に対する支援を通じ、紛争・感染症といった人間の生存、生活、尊厳に対する様々な脅威から途上国の住民や地域住民を保護し、個人・地域社会が自立するための能力向上に取り組む国際機関のプロジェクトを支援した。また、「草の根・人間の安全保障無償資金協力」により、在外公館が実施主体となり、草の根レベルに直接裨益するきめ細かい援助を1633件(約144億円)実施した。
評価シート:11-1 「人間の安全保障の推進」
(4)イラク復興支援
我が国は、自衛隊派遣による支援とODAの連携により、イラクの復興のために主体的かつ積極的な貢献を続けており、自衛隊が行ってきた医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備といった人道復興支援を中心とする活動は、ODAによる支援との連携により、現地の人々の生活基盤を回復、充実させると共に雇用も生み出してきた。学校の改修を例にあげれば、ムサンナー県内の学校のうち、陸上自衛隊により22校、ODA(国連-HABITAT経由)により59校が改修された。
ODAについては、2003年10月のマドリッド会議で、2007年までに最大50億ドルの支援を行う旨表明し、このうち、総額15億ドル分の無償資金協力による「当面の支援」については、2005年5月に全額につき実施が決定された。このようなODAと自衛隊派遣による支援(人的貢献)は、イラクをはじめ各国より高い評価を得た。
評価シート:7-1「日本の安全保障政策に関する外交政策」
5-2「イラクの平和と安定のための支援」
(5)東アジア共同体
平成17年12月の第一回東アジア首脳会議(EAS)では、初会合であるにもかかわらず、東アジア共同体形成に向けた、地域協力の基本的原則について首脳レベルで意見集約が図られる等の成果がみられた。日本外交にとっての成果としては以下があげられる。
-
ASEAN+3以外の国にも首脳会議参加の道を開くという日本の考え方を様々な交渉プロセスを経て最終的な合意に持ちこんだ(豪、NZ、インドが初回会合より正式に参加国として参加)。
-
「開かれた地域主義」や普遍的価値の尊重とグローバルな規範の遵守など日本が主張してきた地域協力の基本的原則が首脳宣言で概ね合意された。
評価シート:1-1 「東アジアにおける地域協力の強化」
3.主張する日本外交
(1)情報発信の強化
平成17年は戦後60周年の節目の年であった。我が国の歴史認識や周辺外交、戦後日本の歩みに関し、外務省ホームページの活用、広報資料の配布、講演、報道機関へのブリーフィング等を通じて情報発信に努めると共に、事実誤認に基づく報道がなされた際には反論投稿を行い、諸外国における対日理解を増進させた。
評価シート:13-1 「海外広報」
14-1 「効果的な外国報道機関対策の実施」
14-3 「効果的なIT広報の実施」
(2)愛・地球博
「2005年日本国際博覧会」を同年3月25日から9月25日まで、「自然の叡智」をテーマに開催した。121ヶ国、4国際機関が参加した。この機会に日本と参加国との間の様々な交流を促進するため、期間中参加国・機関が行うナショナルデー、スペシャルデーに出席する要人を「博覧会賓客」として、日本側負担により招請し、接遇を行った。
博覧会の来場者は、当初目標の1500万人を大きく上回る2200万人で、外国企業に対する日本でのビジネスチャンスの場としても機能した。また、王族、大統領等元首をはじめ数多くの閣僚が訪日し、交流を深め、外交的にも意義が大きかった。
評価シート:10-3 「重層的な経済関係の強化
(3)日本企業支援と対日投資の促進
近年、模倣品・海賊版がアジア地域を中心に広く流通し、その被害は拡大しており、日本製品についてもその例外ではなく、日本企業は、海外における潜在的な利益の喪失も含め、深刻な悪影響を受けている。このため、日中、日米、日EU間の対話を継続し、在外公館に知的財産担当官を任命するなどの対応を行った。また、模倣品・海賊版拡散防止のための法的国際枠組み構想につき議論していくことについてサミットメンバー国(G8)の専門家レベルでの理解を得た。日本企業支援については、個別企業の支援や在外公館施設の効果的活用等を通じて、これまで以上に積極的な対応を行った。対日投資支援については、在外公館のネットワークを活用し、対日投資に関するセミナーやシンポジウムを開催し、投資を支援した結果、2005年末の対日直接投資残高は、前年比4000億円増の10.5兆円(一次推計値)まで伸びた。
評価シート:10-5 「海外の日本企業支援と対日投資の促進」
(参考)10-2 「グローバル化の進展に対応する国際的な取組」
4.底力のある日本外交
(1)文化外交
(イ)国民の世論が外交に与える影響力が大きくなっている今日、日本文化の発信を通じ、対日理解を促進し、親日感を醸成することは、外交を展開する上での良好な基盤となる。我が国は、日本文化の紹介、人物交流の強化、日本語教育・日本研究の推進、知的交流の促進など、様々な事業を世界各地で展開した。日韓友情年、日・EU市民交流年事業、日豪交流年等の周年事業においても、多面的な日本の姿・心を伝えることにより、文化理解の増進を図った。
(ロ)在外公館や国際交流基金が実施している文化事業の稗益者の満足度も高く、日本語学習者数や海外からの留学生数等一部のデータについては前向きな統計が得られている。
(ハ)開発途上国のアイデンティティーを支える文化の分野における支援を行うことにより親日感の醸成を図り、日本として国際的な文化・教育などにおける環境の向上に向け主要な責任を果たすために、ユネスコを通じた協力(無形遺産条約の策定を含む)や、文化無償資金協力を実施し文明間対話を促進した。
評価シート:13-2 「国際文化交流の促進」
13-3 「文化の分野における国際協力」
(2)組織強化
前年度までの外務省改革の検討、実践を踏まえ、能動的・戦略的な外交を展開するための体制強化、在外公館の警備体制の一層の強化、緊急事態の発生に備えた体制整備により、外交実施体制基盤の整備、強化を行った。経済連携協定関連、在外公館における邦人保護、情報収集担当をはじめとして外務省の定員は118の新規増を達成(純増5、在外公館のアタッシェを含めた増員は19)した。
また、在外公館の警備体制の一層の強化のため、警備強化措置、専門家研修、警備関係講義、警備訓練等を予定どおり行った。
緊急事態の発生に備えた体制整備については、本省連絡体制の更新、対応マニュアル作成、設備の保守・整備等の実施により、緊急対策本部を短時間に設置、初動体制を整えた。
評価シート:17-3 「外交実施体制基盤の整備・強化」
