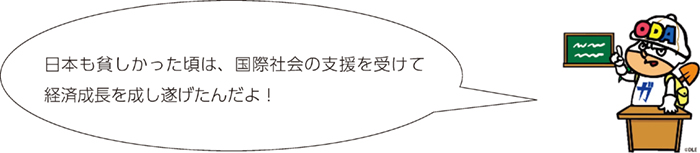はじめに:日本の国際協力の意義
日本が2018年に実施した政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)の支出総額は、約1兆9,051億円となりました。財政状況が厳しく、少子高齢化対策や自然災害の復旧・対策など、日本国内で様々な課題が山積する中で、なぜ日本はODAで開発途上国を支援するのでしょうか。
現在、世界の人口は約70億人ですが、世界銀行によれば、このうち7億人以上の人が、1日の生活費が1.9ドル(200円)にも満たない水準で暮らしています。こうした人々は、食べるものや飲み水がなかったり、学校に行きたくても行けなかったり、病気の時に病院に行けなかったりと、ギリギリの暮らしをしています。困っている人がいる時は、助け合わなければならない、それは国としても同じことです。
また、そもそも日本も、第二次世界大戦後、戦後の荒廃の中から復興しました。そうした苦境から復興し、経済成長を成し遂げ、先進国の仲間入りを果たすにあたり、日本の復興・経済成長を支えた柱の一つとして、戦後間もない時期から開始された、米国などの先進国や世界銀行をはじめとする国際機関などからの支援の存在がありました。東海道新幹線や東名高速道路、黒部ダム、そして愛知用水など、日本の再建と発展のため必要不可欠であった基礎的なインフラは、これらの支援によって整備されました。したがって、日本は、その「恩返し」として、途上国の経済発展を後押しするため、ODAを活用して支援を進めてきました。実際、日本に対して世界各国から寄せられる期待は非常に大きなものです。
さらに、広く世界を見渡せば、気候変動、自然災害、環境問題、感染症、難民問題など、一国では解決が難しい地球規模課題が山積し、深刻化しており、その影響も一国内にとどまらず、世界中に広がっています。2015年には、国連において持続可能な開発目標(SDGs)が採択され、2030年までに「誰一人取り残さない」社会を構築すべく、国際社会が取組を進めています。そのような状況の中では、誰かのために行う善意は、巡り巡って自分に戻ってくるものです。たとえば、どこかの国で温暖化ガスの排出や海洋プラスチックごみの削減に協力することは、巡り巡って日本を取り巻く環境を良くすることにつながります。日本が産業化を支援した結果、途上国からタコやサーモンが日本に輸出され、私たちの食卓に並べられています。一方で、自然災害や気候変動に伴う影響、国境を越えるテロや感染症などの脅威にさらされていることも事実です。私たちは、世界中の様々な主体と協力してこれらの課題に取り組まなければなりません。
日本がODAを開始して、65年以上が経ちました。これまでの日本のODAを通じた途上国への様々な分野での支援や人材育成は、今の日本に対する信頼につながっています。こうした信頼は、たとえば、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の招致や2025年大阪・関西万博の誘致の際、日本が各国から多くの支持を集めたことにも少なからずつながったと言えるでしょう。ODAは貴重な税金により実施していますので適切に活用し、途上国のために役立てていくことは言うまでもありません。そして、日本は、世界が抱えている課題を解決することが、日本の平和と安全、そして繁栄につながるものとなるよう、これからも開発協力を行っていきます。