|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
D.社会保障及び児童の養護のための役務の提供(第26条、第18条3) 社会保障
192. 我が国では、条約第26条1に規定する社会保障として、医療保障の面においては、各種医療保険制度及び養育医療、育成医療の公費負担制度があり、所得保障の面においては、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、遺族年金、生活保護等がある。
193. 児童に関する社会保障の給付のうち、医療保障の面においては、児童を含め国内に居住するすべての者が、公的医療保険制度に加入することとなっている。また、身体に障害のある児童に対して生活の能力を得るために行う育成医療の給付、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付、及び結核にかかっている児童に対して療養に併せて学習の援助を行うための療育の給付については、その給付に要した費用を支弁する都道府県は、本人又はその扶養義務者の負担能力を考慮してその費用の全部又は一部を負担することとなっている。
194. 社会福祉の面における児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の給付については、それぞれ適用対象となる児童を監護する者等受給資格者の扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める所得の制限限度額に従って支給されることとなっている。
(a)児童手当制度
195. 児童手当制度は、児童の養育に伴う家計の負担を軽減し、家庭生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的として、1972年度から実施されている。
児童手当制度については、1994年、最近の出生率の低下など、児童や家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、就労と育児の両立支援などを目的とする改正が行われた。改正においては、各種育児支援サービスの充実を図るため、福祉施設を児童育成事業と改称し、新たに児童育成事業に充当するための事業主拠出金を徴収することとして安定的、継続的にこの事業が実施できるようにした。
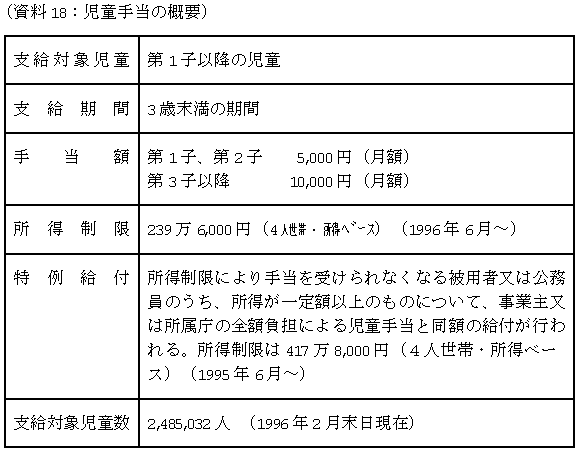
(b)児童扶養手当制度
196. 離婚による母子世帯等、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当を支給している。
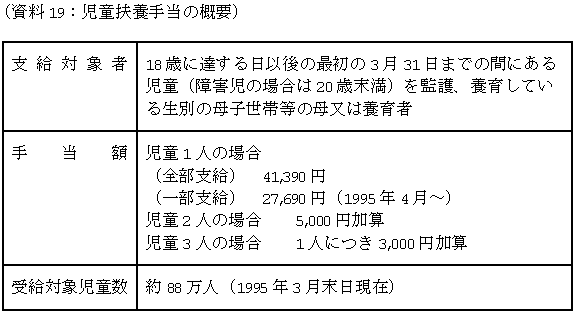
(c)特別児童扶養手当
197. 20歳末満で精神又は身体に中程度以上の障害を有している児童を家庭で監護、養育している父母等に特別児童扶養手当を支給している。
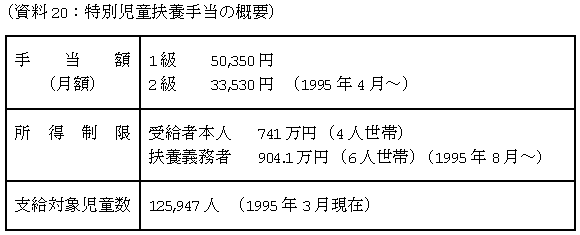
198. 更に、生活保護法は、児童についても適用される。ただし、同法においては、保護の基準を要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別、その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとされているほか、保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとすることとされている。
児童の養育のための役務の提供
199. 我が国では、次のような措置により、児童の養育のためのさまざまな役務の提供を行っている。
(a)保育所200. 我が国においては、保護者たる父母のいずれもが昼間労働することを常態とするなど、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合には、市町村が当該児童を保育所に入所させて保育する措置をとることが義務づけられている。保育所は、1994年4月現在、施設数は22,532ヵ所、入所児童数は1,593,161人となっている。
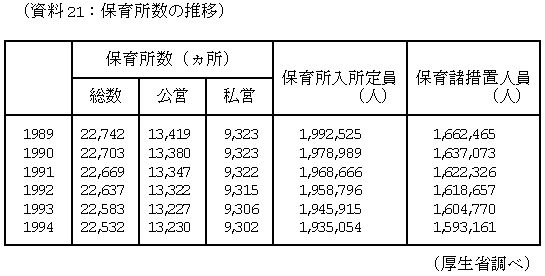
201. 保育所の運営費には、人件費、事業費、管理費等が計上され入所児童の年齢区分に応じて、それぞれの児童1人当たりの保育単価が設けられ、適切な保育が実施されるよう配慮されている。なお、保育所の整備については、保育ニーズに対応して、毎年積極的な整備が進められた結果、全国的にほぼ必要な水準に達しているものと思われるが、今後、大都市近郊の人口急増地域等に重点を置き、新設を図るとともに、災害や新しいニーズに対応できるように老朽施設の改築整備を促進していく必要がある。
(b)事業所への助成
202. 児童手当の拠出金を拠出する一般事業主によって当該事業所の従業員の児 童を対象とした保育施設の設置がなされる場合には、これに対し助成を行っている。
203. この他、女性の社会進出等に伴う多様な保育ニーズに対応するため、乳児保育、延長保育等の特別保育対策を積極的に実施している。
(c)乳児保育
204. 乳児(0歳児)については、安全を保持し、その心身の順調な発達を保障するため、設備や職員配置等の保育条件に配慮した保育を行う必要があり、このような観点から、所定の設備及び運営基準に適合する保育所に対し、保母の加配を行っている。1994年度実績は、7,645ヵ所。
(d)時間延長型保育サービス事業
205. 従来からの延長保育と長時間保育を統合し、1994年度から時間延長型保育サービス事業を創設し、A型(2時間延長)、B型(4時間延長)、C型(6時間延長)の3類型による延長保育を実施している保育所に対し、補助を行っている。1994年度実績は、1,649ヵ所。
(e)夜間保育
206. 概ね午後1時頃からおおよそ午後10時頃まで開所している夜間保育所に対し、補助を行っている。1994年度実績は37ケ所。
(f)障害児保育
207. 保育所での集団保育が可能で日々通所できる障害児(特別児童扶養手当の支給対象児童)を受け入れている保育所に対し、保母の加配を行っている。
1994年度実績は、4,381ケ所。(g)一時的保育事業
208. パート就労など女性の就労形態の多様化に対応するため、週3日程度の弾力的な保育サービスや、保護者の傷病等に対応した緊急保育サービスを実施している保育所に対し、補助を行っている。1994年度実績は、387ケ所。
209. 放課後児童対策事業として、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(放課後児童)の育成・指導、遊びによる発達の助長を行い、児童の健全育成の推進を図っている。
210. 更に、近年の少子化の一層の進行や女性の社会進出など児童を取り巻く環境の変化に対応し、1994年12月16日、文部、厚生、労働及び建設の4大臣の合意により、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)が策定され、子育て支援のための施策について総合的、計画的に推進されることとなった。このエンゼルプランの一環として、1994年12月18日、大蔵、厚生及び自治の3大臣の合意により、「緊急保育対策等5カ年事業」が策定され、低年齢児(0歳から2歳までの児童)保育や延長保育等について計画的に推進されている(詳細は、19.参照)。
211.また、家庭環境を奪われた児童や虐待からの保護を図るため、児童福祉施設入所等を実施している(詳細は、V.F.参照)。
212. 更に、乳幼児の健康保持のために各種母子保健対策が実施されるとともに、障害を持つ児童のために各種福祉サービスの提供の推進が図られている。(詳細は、Ⅵ.A.,B.及びC.参照)。
児童委員
213. 児童委員とは、児童福祉法第12条に基づき、市町村の区域に置かれている民間奉仕者であり、担当区域内の児童及び妊産婦について、常にその生活及び環境の状態を把握し、その保護、保健その他福祉に関し、援助や指導を行う一方、児童相談所、福祉事務所等の行政機関の業務(児童・母子・精神薄弱者の福祉)の遂行に協力することを職務としている。児童委員は、厚生大臣から民生委員・児童委員として、全国の市町村で約21 万人が委嘱されている。また、1994年1月からは、地域において児童や妊産婦の福祉に関する相談・援助活動等を専門に担当する者として約1万4千人の主任児童委員が委嘱されている。
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||