|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
B.障害を有する児童(第23条) 166. 我が国の障害者基本法では、すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有し、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参与するよう努めなければならない、また、その家庭にあっては自立の促進に努めなければならない旨規定している。更に、児童福祉法は、すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない旨規定している。
167. 我が国では、身体障害児は、1987年には92,500人であったのが、1991年には、81,000人であり、毎年減少傾向にあり、また、精神薄弱児は、1990年に100,000人となっている。身体障害児又は精神薄弱児を以下「障害児」という。
(資料11:障害児数)
(単位:人)
総 数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~17歳 身体障害児
(1991年)81,000 12,100 23,300 24,700 18,900 精神薄弱児
(1990年)100,000 10,300 25,300 36,500 27,800
(厚生省調べ)
168. 政府は、上記に述べた国内法等に基づき、ハンディキャップをできる限り軽減し、一般の児童と同様の生活が営めるようにすることを基本とし、福祉、保健・医療、教育、雇用等の広範な分野にわたり、主に以下のような各種施策を行っている。他方、我が国における障害児(者)を取り巻く社会環境として、未だ、交通機関、建築物等における物理的な障壁、点字、手話サービスの欠如による文化・情報面の障壁等があるところ、これらの障壁を除去し、障害児(者)の自立を促進し社会活動を自由にできるような平等な社会づくりをめざしていくことが必要である。このため、政府においては、1995年12月に障害者プランを策定し、具体的な施策目標を明記し、保健福祉施策を強力かつ計画的に推進していくこととしている。
福祉、医療
(a)健康、保健施策
169. 身体や精神の発達遅滞や障害を早期に発見し、早期に適切な措置を講ずるために、乳幼児に対する健康診査を行っているほか、新生児を対象にフェニールケトン尿症等の先天性代謝異常やクレチン症のマススクリーニング検査を行っている。
(b)在宅福祉サービス
170. 障害児やその保護者からの相談に応ずるため、保健所等により母親(両親)学級等の集団指導や家庭訪問等の個別指導による保健指導が行われているほか、身体の機能に障害のある児童や機能障害を将来起こすおそれのある児童に対して、早期に適切な治療や福祉の措置が受けられるように療育の指導が行われている。 また、障害児に対して、児童福祉法に基づく援助として児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業の実施や日常生活用具の給付等が行われている。
(i)日常生活用具の給付等
日常生活を営むのに支障がある障害児に対し、日常生活の便宜を図るための日常生活用具の給付又は貸与を行っている。
(ii)児童居宅介護等事業(心身障害児(者)ホームヘルパー事業)
重度の心身障害のため独立して日常生活を営むのに著しく障害のある心身障害児(者)を抱えている家庭に対し、ホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって重度の心身障害児(者)の生活の安定に寄与する等その援護を図っている。
(資料12:ホームヘルパー数の推移)(単位:人)
(厚生省調べ)
1994年度 1995年度 59,005 92,482 (iii)児童デイサービス事業(心身障害児通園事業)の実施
障害児に対し、家庭から通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を実施している。
(資料13:心身障害児通園事業数の推移)(単位:ヶ所)
(厚生省調べ)
1994年度 1995年度 292 297 171. また、家庭の経済的負担の軽減を図るため、特別児童扶養手当や障害児福祉手当を支給しているほか、1996年度には、国営の郵便貯金事業において、寝たきりの児童をかかえた世帯の自助努力による経済的負担の軽減を支援するため、定期郵便貯金の金利の優遇等を行うこととしている。
(c)施設福祉サービス
172. 児童に対して積極的な治療訓練を行う場として、また、障害の重度化に対応した生活の場として、あるいは就労支援、社会参加促進を図る場として、精神薄弱児施設、肢体不自由児施設、育児施設、ろうあ児施設及び難聴幼児通園施設及び重症心身障害児施設等が設けられている。なお、これら児童福祉施設への入所等についても父母等の所得が一定水準を下回る場合には、無償で行われることとなっている。
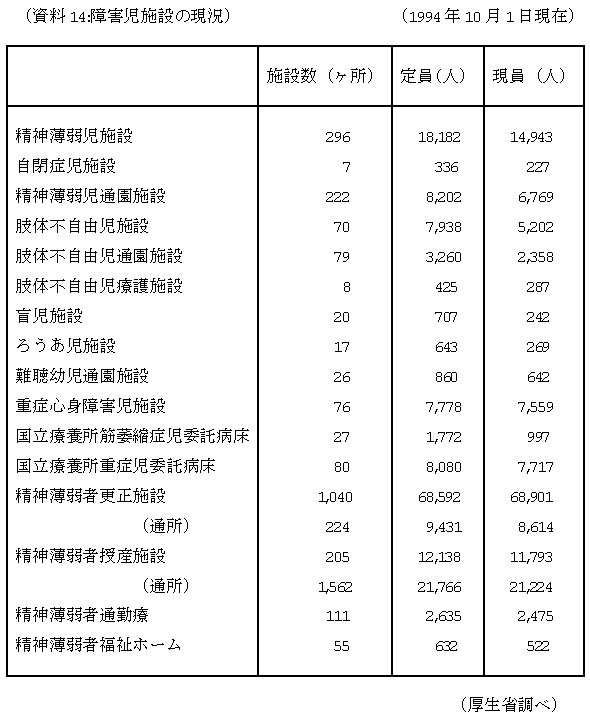
教育
173. 障害により、通常の学級において指導を受けることが困難な、又は通常の学級における指導のみによっては十分な教育効果が期待できない児童生徒については、その能力を最大限に引き出し、社会的自立及び参加を可能な限り実現することを目的として、障害の種類、程度等に応じ、特別な配慮の下に、より手厚く、さめ細やかな教育を行っている。具体的には、盲学校、聾学校若しくは養護学校、小・中学校の特殊学級又は通級指導教室において、障害に応じた特別な教育課程、小人数の学級編制、専門的な知識・経験のある教職員、障害に配慮した施設設備等により教育を行っている。
(資料15:盲・聾・養護学校数及び在学者数)
(文部省調べ)
盲学校 聾学校 養護学校 70 107 791 (単位:校) 4,696 7,557 74,966 (単位:人) (資料16:特殊学級数及び在学者数)
(文部省調べ)
小学校 中学校 14,835 7,014 (単位:学級) 44,319 22,632 (単位:人) (資料17:通級による指導を受けている児童生徒数)
(文部省調べ)
小学校 中学校 13,628 441 (単位:人) 174. 政府では、このような特殊教育を更に充実するため、各種施策を行っており、例えば、1993年度からは、特殊教育の新しい形態として、通級による指導を制度的に実施し、比較的軽度の障害のある児童生徒は、授業の大部分は通常の学級で受け、障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で受けている。
175. また、教育の機会均等の趣旨及び盲・聾・養護学校等への就学の特殊事情に鑑み、保護者の経済的負担を軽減し、その就学を奨励するため、保護者の負担能力に応じて、就学のため必要な諸経費の全部又は一部を助成する特殊教育就学奨励費が支給されている。1994年度においては、諸単価の引き上げ及び帰省費の支給対象回数の増等その他支給対象の拡充を図っている。
雇用
176. 障害者の雇用の促進等に関する法律、障害者対策に関する新長期計画、障害者雇用対策基本方針及び障害者プランに基づき、公共職業安定所、障害者職業センター等において、児童を含め、すべての障害者に対し、職業指導、職業訓練、職業紹介等の職業リハビリテーンョンを実施している。
レクリエーション
177. 児童も含め障害者が障害のない者と同じように、スポーツや文化活動を楽しむことができる機会を提供するために、全国身体障害者スポーツ大会や精神薄弱者の全国規模のスポーツ大会(ゆうあいピック)の開催等スポーツの振興に努めるとともに、障害者による各種文化活動の支援、障害者にも配慮した劇場やコンサートホールの設置等を推進している。
障害児の治療の分野における国際協力
178. これらの分野で蓄積してきた技術、経験などを政府開発援助(ODA)や民間援助団体などを通じて開発途上国の障害児対策に役立たせることは、国際協力上極めて有効であり、かつ重要である。我が国の政府開発援助大綱は、「子ども、障害者、高齢者等社会的弱者に十分配慮する」ことを掲げており、例えば、国際協力事業団を通じて、開発途上国に対して障害者との関係でリハビリテーション指導員養成等のための研修員受け入れや専門家及び青年海外協力隊の派遣等の技術協力を行っている。この他、障害児も含めた障害者対策に関する新長期計画、障害者雇用対策基本方針及び障害者プランに基づき、国際セミナー、アジア諸国における職業リハビリテーンョン専門家研修等を実施している。
179. また、障害の予防及び効果的リハビリテーンョン等「障害者に関する世界行動計画」(1982年の第37回国連総会において採択)の目的を実現するために開発途上国や障害者組織からの要請に応えることを目的とする「国連障害者基金」に、1994年までに累計90万ドル(世界第3位)の資金拠出等を行っているほか、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)に対し、1994年度は約20万ドル相当のプロジェクト支援を行っている。
180. 更に、開発途上国における民間援助団体の活動も近年活発化していることから、障害児の保護に携わるNGOに対し、NGO事業補助金及び草の根無償を通じて、障害の予防、リハビリテーンョン等の領域における諸国間の情報交換、技術及び専門的知識の移転の促進のための国際協力を行っている。
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||