|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
Ⅰ.条約の諸規定の実施のための一般的措置
A.国内法及び国内政策と条約の諸規定を調和させるためにとられた措置 12.我が国は、条約の批准に当たっては、国内法制度との整合性を確保することとしている。児童の権利に関する条約は、条約上の「児童」を「18歳未満のすべての者」と定義した上で、児童の人権の尊重、確保を目的として、表現の自由、思想・良心の自由等の自由権的権利や社会保障、生活水準についての権利等社会的権利等を広範に規定している他、児童の養育と発達における父母又は保護者の第一義的責任等児童の保護に資する事項並びに麻薬、性的搾取及び虐待からの保護、難民の児童の保護等現代社会の問題に対応した事項をも規定しているが、これらの内容の多くは、我が国も既に1979年に締結している経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定されていること、また、憲法を始めとする現行国内法制によって保障されていることから、この条約の批准に当たっては、現行国内法令の改正又は新たな国内立法措置は行っていない。
13.なお、我が国は、国内法との整合性を保つために、以下の留保を付している。
「日本国は、児童の権利に関する条約第三十七条(c)の適用に当たり、日本国においては、自由を奪われた者に関しては、国内法上原則として二十歳未満の者と二十歳以上の者とを分離することとされていることにかんがみ、この規定の第二文にいう「自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離される」に拘束されない権利を留保する。」
これは次の理由によるものである。
この条約第37条(c)は、「自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるもの」とする旨規定している。ところで、この条約上、「児童」については、18歳未満のすべての者、ただし、その者に適用される法律によりより早く成年に達した者を除くと定義されている(第1条)が、「成人」についての定義はなく、右規定が、「児童」という若年者をそれ以外の年長者から分離することにより有害な影響を受けることを防止し、かつ、保護しようという趣旨であることにかんがみれば、ここでいう「成人」とは「児童」以外の者、すなわち18歳以上の者をいうものと解される。我が国においては、少年法上、20歳未満の者を「少年」として取り扱うこととし(少年法第2条)、20歳以上の者から受ける悪影響から保護するとの観点から、自由を奪われた者については、基本的に20歳未満の者と20歳以上の者とを分離することとされている。したがって、条約の定める分離の基準の年齢とは明らかな差異が存在するため、同規定に関し、留保を付すこととした。14.なお、上記のとおり、条約の批准に当たっては、国内法の改正は行っていないが、児童の人格の完全なかつ調和のとれた発達が確保され、社会の中で個人として生活できるようにするためには、国内法制の下に、実体面において児童の保護及び福祉をより一層充実させていくことが重要である。児童の権利に関する条約の批准は、その効果的な実現に向けた施策の充実を図る契機となっている。
児童の人権擁護
15.この条約に認められる権利を含めて、児童の人権を保障する行政上の措置の一つとして、1994年度より、「子どもの人権専門委員」制度が開始された。「子どもの人権専門委員」は、児童の人権が侵害されないように監視し、もし、人権が侵害された場合は、その救済のため速やかに適切な措置をとり、また、地域住民や親子を対象とした座談会を開催するなどの啓発活動を行い、この条約の意義、内容や趣旨についての適切な理解を得ること、並びに、児童の人権を尊重する意識の一層の高揚を図ることをその職務としている。「子どもの人権専門委員」は、児童をめぐる人権問題に適切に対処するため、弁護士、教育関係者等である人権擁護委員が指名されており、児童の人権問題を主体的、重点的に取り扱っている。1996年1月1日現在、「子どもの人権専門委員」は、全国で515名が指名されており、すべての都道府県に設置されている。また、「子どもの人権専門委員」が指名される母体である人権擁護委員は、一般から選ばれた市民のボランティアが法務大臣から委嘱されたものであり、法務局・地方法務局の人権相談室や自宅などで人権相談を受けるなどの活動を積極的に行っている。
16.更に、法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局、法務局人権擁護部、地方法務局人権擁護課及び人権擁護委員)は、1994年度、95年度、96年度の啓発活動重点目標をそれぞれ、「子どもの人権を守ろう」と定めた。この目標の下で、人権擁護機関は、学校その他の関係各機関と協力し、児童、家庭、地域社会に対して、児童の権利を尊重する意識の一層の高揚を図るための広報活動を重点的に行っている。
児童の虐待対策等
(a)都市家庭在宅支援事業
17.都市部における家庭内の育児不安、虐待及び非行等の養育上の諸問題に対応するため、民間施設の専門性を活用して近隣地域の家庭から相談を受け、必要に応じて家庭訪問を行う等による即時的継続的な在宅支援を行い、児童の権利擁護、健全育成及び資質の向上に寄与することを目的として、1994年度より開始された。1995年度は20ヶ所の民間施設で実施されている。
(b)児童虐待ケースマネージメントモデル事業
18.1996年度より、児童虐待ケースマネージメントモデル事業を開始した。児童の虐待の早期発見と迅速な対応、継続的なフォローアップのために、地域虐待対応ネットワークを構築し、虐待の早期発見に努めるとともに、ケースマネージメントを実施し、福祉事務所、医師、弁護士、警察等の関係者を含めたチームとの連携により、困難な事例に対応することとしている。
子育ての総合支援等
(a)エンゼルプラン
19.近年の少子化の進行や女性の社会進出等に対応して、1994年度に、今後10年間における施策の基本的方向と重点施策を盛り込んだ「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン)」を策定し、社会全体による子育て支援の機運を醸成するとともに、子育て支援のための施策を総合的に展開していくこととした。エンゼルプランは、子どもを持ちたい人が安心して出産や育児ができるような環境を整備するため、家庭における子育てを社会全体で支援し、その施策の促進において児童の最善の利益が最大限尊重されることを基本的視点としている。そして、重点施策として次の事項を掲げている。
(i)仕事と育児との両立のための雇用環境の整備
(ii)多様な保育サービスの充実
(iii) 安心して子どもを生み育てることができる母子保健医療体制の充実
(iv)住居及び生活環境の整備
(v)ゆとりある学校教育の推進と学校外活動・家庭教育の推進
(vi)子育てに伴う経済的負担の軽減
(vii)子育て支援のための基礎整備なお、エンゼルプランの具体化の一環として、保育対策の計画的整備を図っていくため、以下の「緊急保育対策等5カ年事業」が定められている。
緊急保育対策等5カ年事業における整備目標等
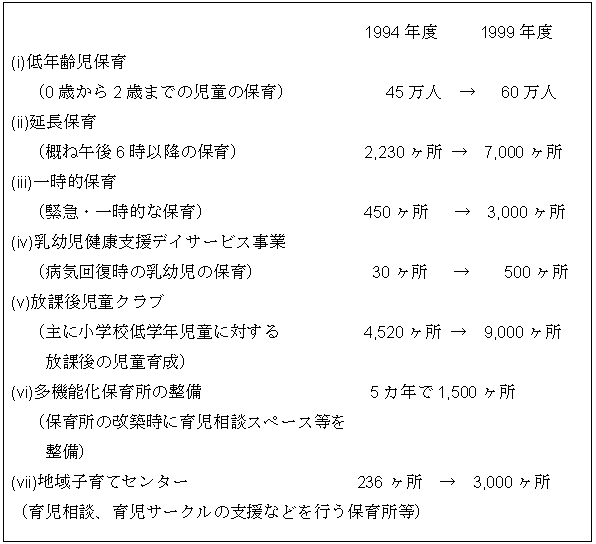
また、文部省では、子育てや教育に係る経済的負担の軽減や家庭教育の充実に努めるとともに、受験競争の緩和を図り、学校内外を通じた「ゆとりある教育」を実現させるため、(i)子育てに伴う経済的負担の軽減、(ii)子育てに関する相談体制の整備等による家庭教育の充実、(iii) 体験的活動機会の提供等による学校外活動の充実、(iv)ゆとりある学校教育の推進に係る施策を積極的にかつ総合的に推進している。
(b)児童手当法の改正
20.児童手当制度は、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に資することを目的とし、現金給付である児童手当を支給することをその内容として1972年から実施されている制度である。他方、児童や家庭を取り巻く環境の変化に対応するため、きめ細やかな育児支援サービスや児童の健全育成のための事業の充実を図ることとする改正が1994年度に行われた。
(c)こども未来財団の設立
21.1994年7月、育児支援事業や児童の健全育成事業を支援することを目的として民法に基づく財団法人である「こども未来財団」が設立された。同財団は、公的なサービスのみでは対応が容易でないサービスの実施を支援することとしている。
教育
22.文部省からは、各学校において、この条約の趣旨、原則の周知徹底を図るとともに、条約の趣旨を踏まえ、教育活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の一層の徹底を図るよう教育関係機関に通知した。
国際協力
23.児童の人権の尊重及び保護のための国際協力についても一層の強化を図っている。特に、二国間協力としては、学校校舎・教室建設、母子保健、小児病院整備等教育、保健・医療分野を中心とした協力を行った。これらを含む社会インフラ分野に対し、1994年は約34億ドルの援助を行っている。近年、我が国の二国間ODAに占める社会インフラ分野のシェアは順調に伸びてきており(91年12.3% → 94年23.2%)、今後ともこの分野への協力を積極的に進めていくこととしている。なお、この分野において、地方公共団体が独自に行う国際協力にも積極的な展開がみられるところであり、政府としてもこうした地方公共団体の活動を支援している。
24.また、政府は、国際機関と協調した国際協力も実施しており、児童救済機関の指導的機関である国連児童基金(UNICEF)に対しては、毎年拠出額を漸増させており、1995年度は2,943万ドル(世界第5位)を拠出しているほか、世界保健機関(WHO)を通じ、結核対策事業、ポリオ対策事業、エイズ対策事業等母子保健の向上等のために積極的な貢献を行ってきている。
25.更に、国際協力においては、NGOの活動も高く評価されるところであり、政府は、NGO支援として、1989年よりNGO事業補助金制度及び草の根無償資金協力の制度を導入し、毎年その支援の強化を図っている。NGO事業補助金の交付に当たっても、母子健康に関する事業等を積極的に重視している。1995年度に保健衛生及び医療事業に対し交付した補助金は、それぞれ25,100千円(対前年比16,700千円増)、229,900千円(対前年比55,787千円増)であり、1995年度におけるNGO事業補助金全体のうち、保健衛生及び医療分野の占める割合は約40%にのぼる。1995年度の草の根無償についても、医療保健分野で、約10.1億円、全体の3分の1にのぼる協力を行っている。
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||