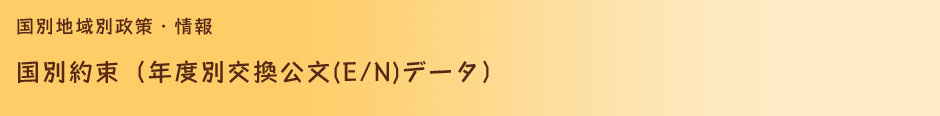インドネシアの「森林火災対策機材整備計画」ほか3件に対する無償資金協力について
平成13年6月5日
- わが国政府は、インドネシア共和国政府に対し、「森林火災対策機材整備計画」、「新生児破傷風対策計画」、「国立公園森林火災跡地回復計画」の実施に資することおよび「食糧増産援助」として、総額20億800万円を限度とする額の無償資金協力を行うこととし、このための書簡の交換が、6月5日(火)、ジャカルタにおいて、わが方竹内行夫在インドネシア大使と先方マカリム・ウィビソノ外務省対外経済関係総局長(Mr. Makarim Wibisono, Director General for Foreign Economic Relations, Department of Foreign Affairs)との間で行われた。
(1)「森林火災対策機材整備計画」 供与限度額 3億900万円 (2)「新生児破傷風対策計画」 供与限度額 1億4,000万円 (3)「国立公園森林火災跡地回復計画」 供与限度額 1億5,900万円 平成13年度 4,800万円 平成14年度 1億1,100万円 (4)「食糧増産援助」 供与限度額 14億円 -
(1)「森林火災対策機材整備計画」(the Project for Improvement of Forest Fire Equipment)
インドネシアでは、1997年に大規模な森林火災が発生し、煙霧は国内に留まらずマレーシア、シンガポール等の周辺国へも到達し、住民の健康、輸送機関、観光産業等に深刻な影響を与えた。焼失面積は26万haに及び、火災は11月頃からの降雨により一旦鎮火したが、翌年1月からの厳しい干ばつのため東カリマンタン州一帯で再燃し、同州内で約50万haが焼失し、損害額は9兆ルピア(約1,300億円)に及んだ。これは全世界に報道され、自然環境保護や地球温暖化等全世界的な観点からも国際社会の注目を集めた。
これに対し、わが国は、消火機材などの緊急供与を行った上、2度にわたり国際緊急援助隊を派遣し、消火活動等を行った。さらにわが国は、1998年10月、森林火災対策に係るプロジェクト形成調査を実施したところ、消火機材、輸送・連絡機材等の絶対的な不足が明らかとなったことから、森林火災対策機材の整備の必要性をインドネシア政府に対し提言した。
このような状況の下、インドネシア政府はスマトラ島およびカリマンタン島の4国立公園を対象とした森林火災の警戒・監視、消火体制の整備を行うため、「森林火災対策機材整備計画」を策定し、この計画の実施のための消火機材(ポンプ、ホース等)等の購入に必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画の実施により、対象4国立公園における森林火災監視体制および初期消火体制の強化による森林火災の減少、国立公園内の貴重な動植物の保全およびプロジェクト方式技術協力「森林火災予防計画」の協力による消火訓練が実施されることにより、他の国立公園の森林火災対策のモデルとなることが期待される。(2)「新生児破傷風対策計画」(the Project for Neonatal Tetanus Control)
インドネシア政府は新生児破傷風対策として、衛生で安全な出産の確保のための助産婦の各村への配置を進めるとともに、1986年から妊婦を対象に破傷風ワクチンの2回接種の普及を開始した。このため、新生児破傷風は1995年には1歳未満時の死亡原因の第5位(3.7%)にまで低下(1986年は死亡原因の第1位(19.3%))した。
しかしながら、破傷風菌は土壌常在菌であるため常に感染の危険性があり、ひとたび感染すれば死亡率が高い。このため、インドネシア政府は2000年までに新生児破傷風の罹患率を出生千人あたり1人以下にすること、および不衛生な注射器による予防接種の低減を目標とし、これらを達成するため、WHO(世界保健機構)の推奨する妊娠可能な女性(15~39歳)に対して計5回の予防接種を実施するプログラムを1996年から開始している。また、当面は、高危険地域に居住する妊娠可能な女性に対し8割程度の抗体レベルが獲得できる2回接種を実施することとしている。
このような状況の下、インドネシア政府は12州を対象として新生児の破傷風を防止するため「新生児破傷風対策計画」を策定し、この計画のための医療機材(オートディスエーブル注射器、破傷風ワクチン、セーフティボックス)の整備のために必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画の実施により、対象12州における妊婦(約295万人)および母体経由の免疫獲得を通じて新生児が破傷風の発症を免れることができ、また、オートディスエーブル注射器およびセーフティボックスを利用することにより安全な予防接種の実施が可能となる。(3)「国立公園森林火災跡地回復計画」(Project for Rehabilitation of the National Park Degraded by Forest Fire)
インドネシアは世界屈指の熱帯林保有国であり、種の多様性が高く、多くの貴重動植物が生息し、全国に39カ所の国立公園が指定されている。しかしながら、同国では度々異常乾燥により、森林・農地等において大規模な火災が発生し、貴重な動植物にも多大な影響を及ぼしている。特に1997~98年に発生した大規模な森林火災は、マレーシア、シンガポール等の周辺国への煙霧害に加え、自然環境保全や地球温暖化等、地球規模の環境問題として国際社会の注目を集めたところである。スマトラ島東部に位置するワイカンバス国立公園においても、公園面積13万haのうち8,500haが森林火災の被害を受け草地化し、森林の自然回復には長い年月が必要と言われており、国立公園の生物多様性を維持し、絶滅の危機に瀕している種や自然生態系保全のためにも在来種による早期の森林復旧が求められている。
このような状況の下、インドネシア政府はワイカンバス国立公園の自然植生を回復するため、「国立公園森林火災跡地回復計画」を策定し、この計画のための植林に必要な資金について、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。
この計画の実施により、ワイカンバス国立公園の森林火災被害地のうち約360haについて、森林の復旧が図られ、また、在来種による森林回復の経験が少ないインドネシアにおいて、在来種による森林回復の経験が蓄積され、在来種による森林回復のモデルが構築されるとともに、計画予定地域内外に生息する野生動物(特に法律により保護対象とされている26種)の生息環境の回復が図られることが期待される。
なお、今回は、1999・2000年度同計画(計2億6,600万円)の3期分として、植林を実施するものである。(4)「食糧増産援助」(Grant Aid for Increase of Food Production)
インドネシアの農業は、1984年にコメの自給目標を達成したことを対外的に宣言した後、1997年までは経済の著しい成長もあり、主に2次食用作物が増産の対象となっていた。しかし、1997年のアジア経済危機に加え、同年夏の厳しい干ばつのため食糧不足が深刻な状況に陥った。このためわが国が1998年に70万トン強のコメの緊急援助を行なったが安定的な供給体制はいまだに確立されていない。インドネシア政府は食糧政策を2次食用作物に加えて、主食のコメに再度重点を置いた政策を取ってきている。
このような状況の下、インドネシア政府は、スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島、スラウェシ島等を対象に、コメ、大豆、トウモロコシの増産を目的とした「食糧増産計画」を策定し、この計画のための肥料の購入のために必要な資金につき、わが国政府に対し無償資金協力を要請してきたものである。