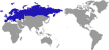 アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
アジア | 北米 | 中南米 | 欧州(NIS諸国を含む) | 大洋州 | 中東 | アフリカ
最近のロシア経済概観
平成17年9月15日
1.ロシア経済のこれまでの推移
(1)ソ連解体後ロシアでは、エリツィン初代大統領の下で92年1月から市場経済に向けた急進的な経済改革が開始されたが、ハイパー・インフレに見舞われるなど多くの問題が生じ、生産も大きく落ち込んだ。
(2)95年頃からようやくインフレが鎮静化し、97年にはGDP成長率も僅かながらプラス(0.9%)に転じ、回復の兆しが見られたが、97年に発生したアジアでの経済危機の影響を受け、また、国際石油価格の低迷などもあって、98年8月にはロシアでも金融危機が発生し、ルーブルの大幅切り下げや支払い停止等を余儀なくされ、経済も再び落ち込んだ。
(3)しかし、99年には国際石油価格が高騰したことやルーブル切り下げの効果により国内の輸入代替産業が復調し始めたことなどを背景に、経済は大幅に成長に転じ、2000年にはGDP成長率は10%と近年にない高い成長を記録した。また、インフレ率も年20%程度まで下がり、急速に改善された。
2.最近のロシア経済の動向と見通し
(1)2001年以降は、ルーブル切り下げの効果が徐々に薄れて、国内産業の復調に限界が見え始め、GDP成長率は01年は5.1%、02年は4.7%と鈍化が見られたが、幸運にも国際石油価格がその後も比較的高値で維持されてきたことから、エネルギー関連産業の好調が続き、これが牽引車となって経済成長が維持されてきたと言える。このため、ロシア経済は、エネルギー産業への依存を益々強める状況になった。
(2)2003年に入って、イラク情勢などの影響で国際石油価格が高騰したことを背景に、ロシア経済は非常に好調に推移し、GDP成長率は7.3%を記録。鉱工業生産、設備投資など他の指標も前年に比べ大幅に改善された。石油の輸出で稼いだ資金が投資や国民の所得を引き上げて内需を拡大し、GDPを引き上げるという好循環が生まれている。この高い成長テンポは、昨年前半まで続き、同年上半期の成長率は7.4%に達した。
(3)しかし、昨年後半に入って、成長率は少しではあるが再び鈍化し始め、昨年後半の成長率は6.8%、本年第一四半期(対前年同期比速報値:4.9%)にもこの傾向は続いている。この間、国際石油価格は1バーレル当たり50ドルを超えかつてないほど高騰したにもかかわらず、成長の鈍化がみられたことは、これまでの石油輸出に依存した成長がもはや限界に来ていることを示すものと思われ、注目される。
| 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP | -5.3% | 6.4% | 10.0% | 5.1% | 4.7% | 7.3% | 7.1% |
| インフレ(CPI) | 84.4% | 36.5% | 20.2% | 18.6% | 15.1% | 12.0% | 11.7% |
| 鉱工業生産 | -5.2% | 11.0% | 11.9% | 4.9% | 3.7% | 7.0% | 7.3% |
| 設備投資 | -12.0% | 5.3% | 17.4% | 8.7% | 2.6% | 12.5% | 10.9% |
| 実質可処分所得 | -16.3% | -14.2% | 9.3% | 8.5% | 9.9% | 13.7% | 8.2% |
| 小売り取引高 | -3.3% | -7.7% | 8.7% | 10.7% | 9.2% | 8.4% | 12.1% |
| 貿易収支(億ドル) | 164 | 360 | 602 | 481 | 463 | 605 | 871 |
| 外貨準備(年末・億ドル) | 122 | 120 | 283 | 362 | 478 | 778 | 1228 |
(出典:金外貨準備はロシア中央銀行、それ以外はロシア統計国家委データ。)
(4)このような状況を受けて、ロシア政府は、本年の経済成長を6.5%程度と見込んでいる。また、本年4月に承認した「06-08年の中期経済発展計画」では、06年から3年間は、楽観的なシナリオでさえ6%前後と控えめな成長を想定しているほか、「成長の新たな源泉を開発し、経済の多様化を促進する施策」の重要性を指摘している。
プーチン大統領は03年の教書演説で、今後10年間でGDPを倍増(そのためには年率7%以上の成長が必要)することを目標に掲げ、その後も折に触れ同目標を達成することの重要性を強調している。しかし、経済の多様化が迅速に進められなければ、この目標の実現は難しいと思われる。
3.経済改革の現状
(1)上述したように、ロシア経済はエネルギー産業への依存度が高く、その基盤は未だ脆弱である。ロシア経済が持続的に成長するためには、経済全体の多様化が急務であるが、そのためには、国内経済の改革が不可欠である。プーチン大統領は、そのような改革の必要性を認識しており、1期目の大統領就任当初から改革の努力を行ってきた。
(2)具体的には、2000年には13%の一律所得税の導入など税法の改革が行われ、2001年には、一連の規制緩和措置がとられたほか、土地法典、労働法典、年金・社会保障制度の改革など長年懸案となっていた一連の改革法案を成立させるなど、法整備面で大きな成果があった。その後も、大きな課題であり改革が遅れていた鉄道や電力分野の改革について、2002年末から2003年始めにかけて一連の法案が採択された。
(3)これらの一連の改革により、ロシアの経済環境は徐々に改善されてはいるがまだまだ不十分である。また、昨年には行政改革により、省庁の大規模な再編が行われたが、行政の効率化など意図された効果は今のところ出ておらず、むしろ混乱を招く結果に終わっているとの指摘がなされている。さらに、当面の重要な課題である銀行制度の改革、ロシアの天然ガスの生産、輸送、販売を独占する企業「ガスプロム」の改革、住宅、医療など一連の公共サービス分野の改革などは、いずれも当初の予定よりかなり遅れており、難航している模様である。
(4)また、公共サービス分野の改革の一つとして、バスなどの無料乗車や医療機関の無料利用などいわゆる「社会的特典」を現金化する法案が昨年採択され、本年1月より施行されたが、その施行に際しての準備が十分でなかったことなどから、年金生活者などを中心に一般市民が、ロシア各地で大規模な街頭デモを展開し、プーチン大統領の支持率が10%近くも一挙に下がるというような事態が生じた。政府は、現金化の一部停止や年金の繰り上げ増額などにより対処し、事態を一応鎮静化させたが、政府の実施能力の低さと国民生活に直結する公共サービス分野の改革の困難さを示す結果となった。
4.ビジネス環境の悪化が懸念される動き
(1)2003年の秋にロシアの巨大石油企業「ユコス」社のホドルコフスキー社長が脱税などの容疑で逮捕され、その後、同社に対して巨額の追徴税が課され、資産が差し押さえられるという事件が起きた。また、その後も一連の外国資本が参加した企業(例えば電話会社のVimpelcom、「日本たばこ(JT)」の子会社など)に対して、同様の巨額の追徴税が課される事例が相次いでおり、ロシアの財界ではこのような明確な基準が不明な追徴課税の動きに対して懸念が示されている。
(2)また、上記「ユコス」社の差し押さえられた資産のうち、同社の主要資産である石油生産企業が当局により競売に付され、競争相手のないままに国営石油企業である「ロスネフチ」に事実上売り渡されたが、これは石油企業の再国有化の動きと見ることもでき、不透明な競売のプロセスとあいまって米国などが懸念を表明している。さらに、最近では、石油などを含む一連の戦略産業分野における外国企業の参加を制限する法律(地下資源法改正法案)が提案されるなど、経済に対する国家の管理を強めようとする動きが見られ、懸念されている。
(3)上述したような最近の当局による一連の動きは、ビジネス環境に、未だ深刻なものではないが、悪影響を与えていると見られており、例えば、ロシアからの資本の逃避額は一昨年に20億ドル程度まで減少したが、昨年は80億ドルまで一挙に4倍も増加したのは、その影響ではないかと指摘されている。
(注)他方、ロシア経済の好調を受けて、昨年のロシアへの外国直接投資は、一昨年の約60億ドルから90億ドルに50%も増加しており、上述した当局による一連の動きは、ビジネス環境にそれほど影響を与えていないとの見方もある。
