本編 > 第III部 > 第2章 > 第2節 > 3. 地球的規模の問題への取組
3. 地球的規模の問題への取組
地球温暖化をはじめとする環境問題、感染症、人口、食料、エネルギー、災害、テロ、国際組織犯罪といった問題は、一国だけの問題ではなく、国境を越えた地球的規模の問題であり、人間の生存にかかわる脅威となっています。国際社会の安全と繁栄の確保に資するため、日本は国際協力を通じてこの問題に取り組み、同時に国際的な規範づくりに積極的な役割を果たしていく方針です。
(1)環境問題
実績
2007年度の実績は、以下のとおりです。
- 有償資金協力(円借款):約4,158億円(10か国)
- 無償資金協力:約240億円(34か国)
- 技術協力
- 研修員受入:2,511人
- 専門家派遣:189人(注84)
- 協力隊員等派遣:431人
現状
環境問題は、未来の人類の繁栄のためにも、国際社会全体として取り組んでいく決意が必要です。1970年代から国際的に議論されている環境問題ですが、1992年の国連環境開発会議「地球サミット(UNCED(注85))」、2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD(注86))」での議論を経て、その一層の重要性が国際的にも確認されています。また、環境・気候変動については、2008年7月に開催されたG8北海道洞爺湖サミットにおいても主要テーマの一つとして、建設的な議論がなされました。
気候変動問題における日本のリーダーシップについては、第I部第1章を参照してください。
日本の取組
地球温暖化対策
2008年1月、福田総理大臣(当時)は「クールアース推進構想」を発表し、2013年以降の枠組み構築へ積極的に参加し、温室効果ガスの排出削減と経済成長を両立させ、気候の安定化に貢献しようとする途上国を支援するクールアース・パートナーシップを提案しました。また、米国や英国とともに主導して世界銀行の下に「気候投資基金(CIF(注87))」を創設し、日本は最大12億ドルを拠出することを表明しました。
環境汚染対策
日本は、国内の公害問題に取り組む過程で多くの経験と技術を蓄積しており、それらを活用して開発途上国の公害問題への対応に協力しています。特に、急速な経済成長を遂げつつあるアジア諸国を中心に、都市部での公害対策および生活環境改善(大気汚染、水質汚濁、廃棄物処理など)への支援の重点化を進めています。2007年度には、モンゴルのウランバートル市で急速な人口増加などによりゴミの排出量が急増し、大きな問題となっていたことから、処分場の新規建設、ゴミ収集運搬用機の無償供与などを行い、住民の生活環境の改善に貢献しました(注88)。また、同市において、JICA、地球環境ファシリティ(GEF(注89))、フィンランド政府などによる技術支援と連携し、導入設備の運用、維持管理の支援を行うことで、実施機関の能力強化を図っています。加えて、アジア地域においてはいまだ十分な対策が講じられていない石綿について、その使用状況などの調査を行い、アジア地域における石綿対策の推進のための取組を進めています。
自然環境保全
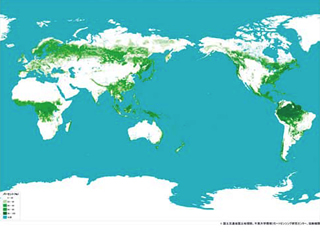
日本は、住民の貧困削減を考慮しつつ開発途上国の自然保護区などの保全管理、持続可能な森林経営の推進、砂漠化対策および自然資源管理に対する支援を実施し、それらの支援を通じ、途上国における生物多様性の保全を図っています。生物多様性条約の下では、2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させるという「2010年目標」が設定されており、この目標達成に向けてさらなる努力が求められています。例えば、エチオピア国南西部地域に位置しているベレテ・ゲラ地域は、クロヒョウやブルーモンキーが生息する貴重な森林生態系を有する地域ですが、近年では農地開発や違法伐採などにより、森林が減少・劣化しており、早急な対策が求められています。日本は技術協力として、エチオピアに対して、2003年度から3年間かけて、住民による森林管理組合の組織化、州政府との森林管理契約によって住民参加型の森林管理体制の整備支援を行ってきました。2006年度からは、住民参加型の森林管理体制をベレテ・ゲラ森林地域全体に普及するための活動に取り組んでいます。森林保全と地域住民の収入向上への取組の一環として支援してきたコーヒー豆栽培については、2007年、国際NGOであるレインフォレスト・アライアンスによる「森林コーヒー認証」の取得に成功し、市場価格よりも高価で販売することが可能になりました。このように日本は、自然環境保全と地域住民の収入向上の両立にも貢献しています。
また、日本は、地球環境の現状と変化を把握するために各国の国家地図作成機関が協働して地球全体の地図を整備する「地球地図プロジェクト」に主導的役割を果たしています。地球地図は環境モニタリングや食料対策、水資源、土地利用などにおける各種将来予測のほか、大規模災害発生時の利用など様々な分野での利用が可能です。2007年度は昨年度に引き続き、アフリカにおいて地球地図の活用などに関するセミナーを開催するとともに、2008年3月には教育関係者や環境・防災NGOなどを対象にした「地球地図シンポジウム」を開催しました。
国際社会との協調
世界的な取組として、国際的な資金メカニズムであるGEFや「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」に基づく多数国間基金(MLF(注90))などが設立・運営されています。日本は、これら国際的な基金の活用や国際熱帯木材機関(ITTO(注91))などの国際機関を通じて積極的な取組を進めています。例えば、ITTOを通じてアジア・大洋州や中南米、アフリカの熱帯林の持続可能な経営の促進および熱帯木材の国際貿易の発展のために、2007年度は27のプロジェクトに対し、約742万ドルの支援を行いました。また、モントリオール議定書に基づく多数国間基金を通じ、中国やインド、モンゴルなどに対して、オゾン層破壊物質の全廃に向けた政策立案支援、代替物質・代替技術への転換や技術者の訓練などを行っています。
(2)感染症
実績
感染症に関する日本の実績については、保健医療・福祉分野の実績を参照してください。
現状
HIV/エイズ、結核、マラリアの三大感染症をはじめとする感染症は、開発途上国の国民一人ひとりの健康問題にとどまらず、今や開発途上国の経済・社会開発への重要な阻害要因となっています。2007年のエイズによる死亡者数は全世界で約200万人となり前年に比べ減少したものの、新規のHIV感染者数は引き続き拡大傾向にあります(注92)。また、世界のHIV感染者の3分の2、エイズによる死亡者の4分の3以上がサブ・サハラ・アフリカで発生しています(注93)。結核は、世界の人口の約3分の1に当たる20億人が感染しており、2006年には166万人が死亡しています(注94)。また、全体の半数はアジアで発生していますが、サブ・サハラ・アフリカにおける発症・死亡率が増えています。さらに、世界の約2億4,700万人がマラリアの感染リスク地域に居住し、年間死亡者数は80万人を超えるといわれています(注95)。感染症は、グローバル化の進展に伴い人やモノの移動が容易になったことから、国境を越えて他国にも広まる可能性が高くなり、地球的規模の問題として、国際社会が協力して対処するべき課題となっています。
民間企業との連携については、こちらも参照してください。
日本の取組
2005年、日本は、保健分野に関連するMDGs達成への貢献を目標にした「『保健と開発』に関するイニシアティブ(HDI(注96))」を発表し、このイニシアティブに基づき、感染症対策を含む保健医療分野に対し、2005年度から2009年度末までに50億ドル程度の包括的な支援を行っています。また、日本は、HDIをアフリカで具現化するため、2006年に策定された「アフリカ感染症行動計画」に基づいて、アフリカにおける三大感染症対策、寄生虫対策などの分野におけるアジア・アフリカ協力などを推進しています。
感染症対策への国際社会の取組は、G8九州・沖縄サミットを契機として、2002年の世界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM(注97)、以下世界基金)の設立につながりました。日本はこれまでに総額8億4,618万ドルを拠出し、また世界基金の設立当初から理事として世界基金の効果的、効率的運営のためにも貢献しています。
また、国連の「人間の安全保障基金」、国際NGOである国際家族計画連盟(IPPF(注98))の「HIV/エイズ日本信託基金」、国連教育科学文化機関(ユネスコ(注99))の「人的資源開発信託基金」および「エイズ教育信託特別基金」、世界銀行の「日本社会開発基金」など、日本が資金拠出して設置した基金を通じてもHIV/エイズをはじめとする多くの感染症対策を実施しています。
HIV/エイズ
日本は、保健医療全体のシステム強化を念頭に置きつつ、HIV/エイズの感染予防、検査とカウンセリングサービス(VCT(注100))の強化、検査・治療・ケア体制整備支援などに貢献しています。2007年度には、HIV推定感染率や患者数がアフリカ諸国の中でも上位にあるタンザニアに対して、無償資金協力を通じ、HIV検査キットの供与を行いました(注101)。タンザニアにおいては、JICAの技術協力を通じて、国家エイズ対策プログラムに対する組織能力強化支援も行っており、相乗効果が期待されています。また、2007年度は、ザンビア、セネガル、ジャマイカで新たな支援を開始しました。例えば、ザンビアでは、ザンビア大学教育病院ウイルス検査室や第三次病院、州立病院の検査室に対し、ザンビア政府が作成した「国家検査精度管理戦略」に沿ったHIV/エイズ検査精度管理システムの確立の技術協力を行っています。さらに、円借款による大規模インフラ整備事業の実施においては、移動労働者の雇用などによるHIV感染リスクの増大を踏まえた対策にも取り組んでいます。
結核
かつて結核は日本の感染症対策の中心であったことから、日本は、結核分野での研究・検査・治療技術の水準が高く、長年の蓄積を活かした開発途上国支援を行ってきました。2007年度には、直接服薬指導による短期化学療法を中心とした手法の普及を中心として、結核分野の国際的な協調に基づき策定された「Global Plan to Stop TB 2006〜2015」に沿った協力を目指し、抗結核薬や検査機材の供与をWHOの結核対象重点国( HighBurden Countries)など結核被害の深刻な国に対して重点的な協力を実施してきました。また、これまでにも、アフガニスタン、パキスタン、ミャンマー、バングラデシュ、ザンビア、カンボジアなどに専門家を派遣し、現地の結核対策プログラムの運営体制の強化、検査能力向上のための研修・指導や指針作成支援などを実施しています。日本の協力はそのほかの国においても着実に成果を上げています。世界の80%の結核が集中している22の結核高負担国のうち中国、ベトナム、フィリピンの3か国が国際的な目標を達成していますが、これらは、日本がこれまで技術協力や無償資金協力などで協力してきた国々です。2007年度においても、NGOを通じて、ザンビアに対して結核対策の強化のための支援を行うなど、引き続き、結核問題に取り組んでいます。
マラリア
深刻なマラリアに対する支援として、2007年度、日本は、ブルキナファソに対して約23万張の蚊帳を供与し、マラリア罹患率や死亡率を減少させるための支援を行いました。また、国連児童基金(ユニセフ(注102))などとも連携を推進しており、2007年末までに計約1,030万張を配布しました。ユニセフの試算によると、日本の支援による1,000万張の蚊帳配布によって、アフリカの5歳未満児(子ども)16万人の命を守ることができるといわれています。そのほかの2007年度の日本の取組としては、大洋州のソロモンに対し、効果的なマラリアの疾病管理体制が確立されることを目指し、適切な臨床および公衆衛生体制の確立とマラリア情報システムの利用、医療従事者の能力や技術の向上に向けた協力を行っています。
ポリオ
ポリオについては、全世界のポリオ根絶に向けた取組は最終段階を迎えています。西太平洋地域で2000年に世界保健機関(WHO(注103))によるポリオ根絶宣言が出され、ポリオ流行国に指定されている国は、ナイジェリア、インド、アフガニスタン、パキスタンの4か国にまで減少しました。WHOは、これらポリオ流行国に集中的支援を行いポリオの根絶を目指しています。日本は、このWHOのポリオ撲滅戦略を踏まえ、ユニセフなどと協力しながらポリオ・ワクチン供与の支援を行っており、これら4か国を柱にこれら諸国からの感染拡大リスクが高い国などにおいて重点的取組を行いました。特に、2007年度は、ナイジェリアがアフリカで唯一の流行国であることや全世界のポリオ輸入株症例の8割以上が同国を原因とすることを踏まえ、ナイジェリアにおけるポリオ対策への取組を強化しました。
寄生虫症
最近は、シャーガス病、ギニア・ウォーム症、フィラリア症、住血吸虫症などの「顧みられない熱帯病(注104)」への対策の必要性について再び注目が集まっています。日本は、世界に先駆けて中米諸国でのシャーガス病対策に本格的に取り組み、媒介虫対策体制確立に向けた支援によって感染リスク減少の大きな成果を上げています。また、人体に寄生虫がとどまり、長期的に健康や社会生活に被害をもたらすフィラリア症についても、WHOとの協力の下、2010年をめどとした大洋州地域、2015年をめどとしたバングラデシュでのフィラリア症撲滅に取り組み、駆虫剤と啓発教材の供与および青年海外協力隊員による啓発予防活動により、大幅な新規患者数の減少や非流行状態の維持に成果を上げてきています。
新興感染症、新型インフルエンザ
新興感染症の一つである鳥インフルエンザは、特にアジアにおいて深刻な被害をもたらしていますが、ウイルスが変異して新型インフルエンザが発生すれば、世界的な大流行をもたらすおそれがあります。日本は、2007年度、新たに6,900万ドルの鳥および新型インフルエンザ対策への支援を表明しました。その一環として、世界で最も鳥インフルエンザによる被害が大きな国の一つであるインドネシアに対して、日本は、鳥インフルエンザ診断能力向上のため、国立家畜疾病診断センターの改修および新設、診断機材操作説明および安全保護に関する指導を行うための無償資金協力を行っています(注105)。また、保健所と連携して患者発生を監視、情報を共有する体制を築くための協力も行っています(注106)。そのほかの取組としては、ASEAN、ASEM(注107)と協力して、150万人分の抗ウイルス薬などを備蓄するとともにWHO、ユニセフなどの国際機関を通じて、住民啓発活動や早期警戒システム、迅速な封じ込め体制構築の支援などを行うとともに、国際獣疫事務局(OIE(注108))を通じてアジア各国連携の下、家きん段階における鳥インフルエンザ防疫体制の強化を行っています。
(3)人口
現状
世界の人口は増加の一途をたどり、2050年には92億人に達することが見込まれています(注109)。世界の人口平均増加率が年1.1%であるのに対して、一般的に開発途上国の中でも貧しい国ほど人口増加率が高く、人口増加が貧困・失業、飢餓、教育の遅れ、環境悪化などの問題に大きな影響を与えており、対応が急務となっています。例えば、一人当たりのGNIが700ドル前後のブルンジ、コンゴ民主共和国、ギニアビサウでは、人口増加率はそれぞれ3.7%、3.1%、2.9%、となっています。人口問題には、人口の構成要因である一人ひとりの人間が、妊娠・出産にかかわる健康状態・権利を確保し、どのように子どもを産み育てるかという個人レベルの問題と、人口数の増加・減少による貧困、食料・水・エネルギー不足、環境劣化問題、人口移動といった国家レベルの問題の両面への対応が求められます。
日本の取組
日本は2007年度には国連人口基金(UNFPA(注110))に対して約40億円、国際家族計画連盟(IPPF(注111))に対して約15億円の拠出を行いました。これらの機関は、妊産婦の健康改善、母子保健の推進のために支援を行うほか、開発途上国の国勢調査など人口関連のデータ収集・分析、女性の能力強化、世界全体で12億人を超えるといわれる思春期の若者を対象とした啓発活動などを行っています。
また、2008年3月には、アフガニスタンの国勢調査実施準備のための設備支援を行ったほか、コートジボワール、シエラレオネ、エチオピアのUNFPA緊急支援プロジェクトに対し、緊急産科治療に必要な器具などを供与し、女性に対する医療・社会的心理支援を行いました。これは、出産への支援という妊娠・出産にかかわる健康状態・権利の重要な局面に関する支援といえます。
(4)食料
実績
2007年度の実績は、以下のとおりです。
- 食糧援助:約160億円(35か国)
- 貧困農民支援:約57億円(18か国)
- 水産無償の実績:約46億円(6か国)
- 技術協力
- 専門家派遣:1人(注112)
現状
世界には約8億5,000万人の飢餓にひんする人がいます(注113)。このうち約3億5,000万人は子どもであり、6秒に1人の子どもが飢餓に関係する理由で亡くなっているといわれています(注114)。ミレニアム開発目標(MDGs)では、2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合を1990年の水準の半数に減少させるとの目標が掲げられています。紛争、自然災害、経済危機の発生などにより、食料支援の必要性は高まっています。世界では、栄養不良に陥っている子どものうち、約1億7,000万人が学校で食事をとることができず、約1億3,000万人が学校に通っていません。
さらに、昨今の食料価格高騰は、途上国においてさらに飢餓・栄養不足に苦しむ人々を増加させています。FAOは、2007年の段階で7,500万人が新たに飢餓にひんしたと指摘しており(注115)、世界銀行も、食料価格上昇により新たに貧困に陥った人口は約1億人に上るほか、飢餓人口も2008年段階で4,000万人増加すると推計しています(注116)。また、食料価格の高騰によって、飢餓人口の減少だけでなく、保健、教育、水・衛生などの分野においても深刻な影響が出ると危惧されています。したがって、食料価格高騰問題においては、食糧配給支援にとどまらず、社会的セーフティ・ネットの確保や食糧増産による需給バランスの改善など、多面的な施策につき包括的かつ一貫性のある取組が求められています。
日本の取組
食料不足に直面している開発途上国に対して食糧援助を行うとともに、開発途上国の食料生産性の向上に向けた努力を中長期的に支援する取組を並行して進めています。
食糧援助については、飢餓への対応として人道的見地から実施しており、アフリカなど食料不足に直面している国を対象として、2007年度には、食糧援助(KR(注117))により、総額約160億円の支援を行いました。このうち、二国間支援を通じて、ネパール、エリトリア、カーボヴェルデ、ブルキナファソ、ハイチなどに対して72.8億円の支援を実施し、国連世界食糧計画(WFP(注118))および国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA(注119))経由では、東ティモール、ギニアビサウ、シエラレオネ、スーダン、パレスチナ自治区などに対し86.8億円の拠出を行いました。特にWFPに対しては、2007年度はWFP経由で実施した二国間の食料援助を含め約1億2,000万ドルの拠出を行い、第5位の援助国となっています。
また、農業生産量の増大のためには、かんがい施設の整備や食料生産技術の向上のための技術協力なども重要です。最近では、ザンビアにおいて、干ばつ常襲地帯における地域・世帯レベルの食糧安全保障を強化するための食用作物の多様化に協力しています(注120)。また、ウガンダでは、水資源を有効利用した持続的なかんがい農業技術を導入し米の生産量の増大を図る支援を行っています(注121)。
食糧価格高騰問題
2007年の後半に入ってから特に顕著となった深刻な食料価格の高騰は、WFPなどの食糧支援事業などにも大きな影響が与えるほどになりました。この課題に対応するため、日本は積極的に緊急食糧支援に乗り出すとともに、G8議長国として、またホスト国として、様々な外交機会においてこの問題を取り上げ、国際社会による一致団結した対応を求めてきました。
(5)資源・エネルギー
実績
2007年度の実績は以下のとおりです。
- 有償資金協力(円借款)
- 約1,298億円(8か国)
- 無償資金協力
- 約56億円(9か国)
- 技術協力
- 研修員受入:356人
- 専門家派遣:114人
現状
エネルギー問題は、貧困、持続可能な開発、環境問題といった様々な問題と関連する地球的規模の課題です。開発途上国では、電力など近代的なエネルギー・サービスを享受できない人々が約25億人いるといわれています(注122)。近代的なエネルギー・サービスの欠如は、産業の未発達とそれに伴う雇用機会の喪失による貧困化、医療サービスや教育を受ける機会の制限など、経済・社会における生活の質的向上を妨げる要因となります。
今後、世界のエネルギー需要はアジアをはじめとする開発途上国を中心に増大することが予想されています。これに対し、エネルギーの安定供給や環境への適切な配慮なしには、エネルギー需給のひっ迫と価格高騰、二酸化炭素排出の増加といった問題が顕著になる可能性があり、ひいては開発途上国の持続可能な開発並びに日本および世界の経済・環境に影響が出ることが懸念されます。
日本の取組
開発途上国の持続可能な開発および日本自身のエネルギー確保の観点から、開発途上国におけるエネルギー供給のための協力を各国の事情に合う形で実施しています。具体的には、開発途上国に対する近代的エネルギー・サービス提供による貧困対策や、産業育成のための電力の安定供給に取り組んでいます。また、同時に、エネルギー・ロス改善、エネルギー利用効率化および再生可能エネルギーを活用した発電施設などのエネルギー関連インフラの整備といった、環境に配慮したエネルギー分野の協力も積極的に進めています。
日本の気候変動対策については、第I部を参照してください。
鉱物などの資源の大部分を海外に依存している日本においては、長期的かつ安定的な資源調達は将来の繁栄のためにも大変重要です。このような資源調達の多くは民間企業を通じて実施されています。このため、これらの企業の資源開発や生産などが円滑に行えるよう、政府開発援助を積極的に活用し、連携していくことが期待されています。
資源国に対しては、その国の外貨獲得源である資源開発を支援し、自立的発展の促進を図り、資源分野における関係強化を図っています。2007年度は、カンボジアのモンドルキリ州における小水力発電設備や送配電設備などへの無償資金協力を2006年度から引き続き実施しています(注123)。カンボジアは過去の内戦の影響によって電力の発展が遅れたこともあり、この支援によって電力が安定的に供給され、州全体の経済発展を牽引することが期待されています。また、日本は、地方電化を通じた貧困削減と地域経済活性化を目指し、電化プロジェクトの契約管理、太陽光発電システムの運用手法能力の移転、エネルギー局地方電化課の業務運営・管理能力の開発などのための技術協力も行っています。例えば、マラウイでは、人口の約8割が生活する地方の世帯電化率がいまだ1%に満たない中、配電線の延伸や太陽光発電システムの普及によって地方電化を推進していくための技術移転や資金の管理運営能力向上支援に引き続き取り組んでいます。
(6)防災と災害復興
実績
2007年度の実績は以下のとおりです。
- 有償資金協力(円借款)
- 約673億円(6か国)
- 無償資金協力
- 約226億円
- 技術協力
- 研修員受入:338人(注124)
- 専門家派遣:34人(注125)
- 国際緊急援助
- 総額:約3億8,100万円
- 援助隊派遣:1件
- 緊急援助物資供与:22件
現状
地震、火山噴火、津波、暴風、豪雨、洪水、土砂災害、干ばつなどの災害は世界各国に様々な形で毎年のように発生しています。大規模な災害では、多くの人命や財産が奪われるだけでなく、経済や社会システム全体が長期にわたって深刻な影響を受けることがあります。特に、開発途上国の多くは災害に対してぜい弱であり、極めて深刻な被害を受けます。また、一般に貧困層が大きな被害を受けて災害難民となることが多く、衛生状態の悪化や食料不足などの二次的被害が長期化することが大きな問題となっています。
また、大規模災害への予防対策に万全を期すべく準備しても、大地震などの大自然の猛威に対しては、人類は無力である場合があります。このような大規模災害が起こると、多数の被災者が発生し早急な災害救援活動が必要となりますが、海外の地域には、災害の規模などにより自国のみでは適切な対応を行えない場合があり、国際協力が重要になります。
日本の取組
自らの過去の災害経験から培われた優れた知識や技術に基づき、緊急支援と並んで災害予防および災害復旧分野の重要性を強く認識しており、積極的な国際協力を行っています。特に、2005年に神戸で開催された国連防災世界会議において、国際社会における防災活動の基本的な指針となる「兵庫行動枠組2005―2015」が採択され、日本は国連と協力してその世界的な実施を推進しています。この会議において日本は政府開発援助による防災協力の基本方針などを「防災協力イニシアティブ」として発表し、制度構築、人づくり、経済社会基盤整備などを通じて、開発途上国における「災害に強い社会づくり」への自助努力を引き続き積極的に支援していくことを表明しました。日本は、同イニシアティブの着実な実施に努めています(2005年度:8.4億ドル、2006年度:8.2億ドル)。また、2005年のアジア・アフリカ首脳会議では、防災分野に対して、5年間で25億ドル以上の支援を行うことを表明しました。防災・災害復興支援の強化を目的として創設された「防災・災害復興支援無償資金協力」を通じ、2007年度には、4地域7か国に対し支援の実施を決定しました。例えば、バングラデシュ北東部のモウルビバザールにおいて洪水の予報精度の向上、暴風雨・鉄砲水の適切な予警報発表を実現するための気象レーダー塔の建設、整備などの支援実施を決定しました(注126)。2006年度も日本の無償資金協力により同国のコックスバザールにおいてレーダー整備を実施しており、これと併せてバングラデシュ気象局におけるサイクロンの監視能力のさらなる向上が図られることとなります。一方で、2007年11月にバングラデシュを縦断した大型サイクロンによって、南部沿岸部を中心に大きな被害が発生し、被災民に対する緊急無償資金協力として、約4億2,600万円の支援を実施しました。2007年度の災害に対する緊急援助としては、ソロモン諸島(地震、津波)、メキシコ(大規模洪水、土砂災害)などにそれぞれ、緊急無償資金協力を行いました。
2004年のインド洋大津波により死者・行方不明者合わせて約8,500人に上る甚大な被害を受けたタイには、国家災害警報センターなどに対して、中央省庁と地方行政、コミュニティレベルにおける連携強化と災害対応能力向上を目的とした技術協力を2006年度から2年間実施しました。その成果として、タイで初の「防災白書」の発行、国家防災計画の改訂、e-ラーニング教材の開発などが行われました。また、村レベルでも、コミュニティ防災マニュアルなどが整備され、ワークショップなどを通じて村人の災害対応能力の向上に活用されています。
国際緊急援助隊
日本は、海外で大規模な災害が発生した場合、被災国政府または国際機関の要請に応じ、迅速に緊急援助を行う体制を整えています。人的援助として、被災者の捜索・救助活動を行う救助チーム、被災者に対して医療活動を行う医療チーム、災害応急対策などについて専門的な助言・指導などを行う専門家チーム、また特に必要があると認められる場合に派遣される自衛隊部隊の4つがあります。また、物的援助として、緊急援助物資の供与があり、被災者の当面の生活に必要なテント、発電機、毛布などを海外4か所の倉庫に常時備蓄しており、大規模災害発生時に、迅速に被災国に供与できる体制を整えています。
最近では、2008年5月2日から3日にかけて、ミャンマー南部にサイクロンが上陸し、未曾有の被害をもたらしました(死者84,537名、負傷者19,359名、行方不明者53,836名(6月24日ミャンマー外務副大臣発表))。日本は、5月9日に当面の支援として、1,000万ドルを上限とする緊急支援を行うことを決定しました。また、ミャンマー政府からの国際緊急援助隊の派遣要請を受け、人道的観点から援助隊の派遣を決定し、医療チーム23名(5月29日〜6月11日)をミャンマー南部のエーヤワディー管区ラブッタに派遣するとともに、3回にわたり合計約1億800万円相当の緊急援助物資を供与しました。医療チーム活動中は、テイン・セイン首相などミャンマー首脳が活動現場に視察に訪れ、激励と謝意表明がなされ、また、日本の医療チームの評判を聞きつけ、遠方から診療に訪れる患者が増えるなど、評価の高い活動となりました。
ミャンマーにおける国際緊急援助隊医療チームの活動については、コラム10も参照してください。
また、中国の四川省では、2008年5月12日にマグニチュード8.0の大地震が発生し、死者約7万人の甚大な被害が出ました。翌13日、日本は当面の支援として、総額5億円相当の無償資金協力および緊急援助物資の供与を決定しました。その一環として、中国政府による派遣要請を受け、日本政府は、救助チーム61名(5月15日〜21日)および医療チーム23名(5月20日〜6月2日)を中国四川省に派遣するとともに、約6,000万円相当の緊急援助物資の供与を行いました。救助チームは、四川省青川県および北川県において捜索・救助活動を行い、16名の遺体を収容しました。また、医療チームについては、四川大学付属華西病院において中国医療関係者とともに医療活動を行い、中国側医療スタッフとともに救急外来253名、入院患者283名の患者を診療しました。中国が歴史上初めて受け入れた海外からの救助隊である日本の救助チーム、さらに医療チームの活動は、中国や日本のメディアで大きく取り上げられました。これらに加えて、中国側からテントなどの救援物資について要請がなされたことから、5月30日には総額5億円を上限とする追加的支援を決定しました。なお、医療チームの活動中には、温家宝首相や楊潔外交部長がそれぞれ視察に訪れ激励と謝意表明がなされたほか、G8北海道洞爺湖サミットの際に訪日した胡錦濤国家主席からも日本の緊急援助隊に対して直接感謝の意が表明されました。
中国との関係については、こちらも参照してください。
国際機関との連携
日本は、2006年に設立された世界銀行防災グローバルファシリティ(注127)への協力を行っています。このファシリティは、災害に対してぜい弱な低・中所得国を対象に、災害予防の計画策定などの能力向上および災害復旧を目的としていますが、日本は、同ファシリティに対し、3年間で600万ドルの資金を拠出しています。
防災の重要性への認識の深まりを背景に、2006年の国連総会においては、各国と防災に関与する国連や世界銀行をはじめとした国際機関が一堂に会して防災への取組を議論する場として、防災グローバル・プラットフォームの設置が決定され、2007年6月に第一回会合が開催されました。日本は、このプラットフォームの事務局である国連国際防災戦略(UN/ISDR(注128))事務局の活動を積極的に支援しており、2007年10月には、兵庫事務所も設置されました。
また、日本は、大規模災害発生時に、地球地図データを利用して被災地域の周辺図を作成し、国連人道問題調整部(UNOCHA(注129))やJICAに提供しています。この地図により、開発途上国など地図整備が不十分な地域においても、災害発生初期において被災地域の地理的特徴を広域的に把握し、災害対策などに利用することが可能となります。2008年度には、ミャンマーのサイクロンや中国四川の地震などの被災地域周辺について、地球地図データの道路、鉄道、土地利用、標高などの情報を組み合わせて作成した地図を提供しました。
(7)テロ・海賊
現状
テロは、国境を越えて引き起こされ、国際社会全体に直接影響を及ぼす重大な地球的規模問題です。世界各国で頻発するテロ事件に見られるように、国際テロの脅威は依然として深刻です。また、テロは主体や手口が多様化する傾向にあり、その対策には、以前にもまして国際的な協調が必要です。テロの頻発は、観光、海外直接投資、貿易などを通じて、テロが発生した国の経済活動に重大な影響を与えます。そのため、開発途上国にとって、テロ対策を強化し、テロを未然に防止することは、開発を進める上でも重要です。
また、海賊行為についての対策も講じる必要があります。特に日本は、石油や鉱物などのエネルギー資源の輸入のほとんどを海上輸送に依存しており、周辺諸国における海賊対策は日本自身の平和と安定に直結します。
日本の取組
テロとの闘い
国際的なテロを防止するためには幅広い分野において国際社会が一致団結し、息の長い取組を継続することが重要であるとの考えのもと、テロ対策の国際的な取組に積極的に参加しています。特に、テロリストにテロの手段を与えない、テロリストに安住の地を与えない、テロに対するぜい弱性を克服するという観点から、テロ対処能力が必ずしも十分でない開発途上国に対し、出入国管理、交通保安、テロ資金対策などの能力向上支援を実施しています。
日本と密接な関係にある東南アジア地域におけるテロを防止し、安全を確保することは、日本にとっても重要であり、重点的に支援を実施しています。具体的には、出入国管理、航空保安、港湾・海上保安、税関協力、輸出管理、法執行協力、テロ資金対策、CBRNテロ(注130)対策、テロ防止関連諸条約などの分野において、セミナーの開催、研修員の受入などを実施しています。
2007年7月には、東南アジア諸国などの危機管理能力向上を目的として、クアラルンプールにて日本主催による「化学・生物テロの事前対処および危機管理セミナー」を実施しました。さらに、東南アジア諸国などの出入国管理業務に携わる職員の能力向上と相互交流を図るため、1987年以来毎年「東南アジア諸国出入国管理セミナー」を開催しています。
また、2006年以降、テロ対策等治安無償資金協力が創設され、開発途上国でのテロ対策の支援を強化しています。さらに、2008年1月、タイ・ベトナム・カンボジアの税関職員に対し、テロ対策などの能力向上のための技術協力を行っています。これにより、テロ対策等治安無償資金協力によりカンボジアに供与された大型X線検査装置の運用強化が図られる見込みです。
海の安全

フィリピン沿岸警備隊関係者に対して
海図の取扱いなどを指導をしている海上保安庁職員
(写真提供:JICA)
海に囲まれている日本にとって海の安全を保つことは、日本の繁栄という観点からも不可欠です。海賊活動の防止のためには、沿岸国の取締り能力向上を図るとともに、情報共有強化や人材育成が重要です。2007年度には、テロ対策等治安無償資金協力を通じ、国際的な主要航路の一つであるマラッカ海峡を含むマレーシア海域の海上保安体制を強化するため、マレーシアの海上法令執行庁に対し、レーザーカメラシステムなどの警備機材を補強するための支援(注131)を行うとともに、引き続き、海上取締り能力の向上を目的とした専門家を派遣しています。
フィリピンとの間では、頻繁に発生する海難事故、タンカーなどの座礁による環境汚染、海賊行為、薬物の洋上取引に対する取組として、日本は、2002年度から2007年度までの間、フィリピン沿岸警備隊の強化支援を行いました。具体的には、フィリピン沿岸警備隊の約2,000名に対し、逮捕術などの訓練、日本の海上保安庁との合同演習を含む海上救難能力強化セミナー、流出油防除技術の訓練、落水者の救助、全員退船訓練、自船・他船消火訓練などを行いました。
(8)国際組織犯罪
現状
グローバル化やハイテク機器の進歩、人の移動の拡大などが進むに伴い、国境を越えて大規模かつ組織的に行われる国際組織犯罪は、治安維持に深刻な影響を及ぼしています。薬物や銃器の不正取引、詐欺・横領などの企業・経済犯罪、通貨などの偽造や資金洗浄(マネー・ロンダリング)などの金融犯罪、不法移民、女性や児童の人身取引などが挙げられ、近年、国際組織犯罪の手口は以前よりも一層巧妙化しています。このような国境を越える犯罪に対しては、一国のみの努力では対策に限りがあるため、各国による対策強化とともに、開発途上国に対する司法・法執行分野におけるキャパシティ・ビルディングなどにより、法の抜け穴をなくす努力が必要です。
日本の取組
麻薬対策支援
麻薬などの薬物問題は人々の生活や生存を直接脅かし、経済・社会の健全な発展を阻害する危険性を有する地球規模の問題であり、国際社会が協調して取り組んでいかなければなりません。また、国内対策の観点からも積極的に薬物対策支援を推進していく必要があります。
二国間支援としては、日本への薬物の供給源となっている薬物の密造地域などにおける薬物関連犯罪の防止や取締り能力向上への支援を行っています。日本は、NGOを通じた協力などによって、これらを支援しています。例えば、2007年度には、ベトナムに対して、薬物常習者の治療を行うためのセンター建設に協力しました。また、中南米のコロンビアでは、麻薬代替作物導入のための職業訓練所の建設を行いました。
さらに、日本は、薬物・犯罪分野における国際的取組を促進するため設立された国連薬物犯罪事務所(UNODC(注132))への支援を毎年行っており、薬物分野に対しては、2007年度は約195万ドルを拠出しました。この資金を利用し、東南アジアの国境における不正薬物取引の取締り強化、ケシ栽培を停止したミャンマーの農村地域の開発などのプロジェクトに対する支援を行いました。
人身取引問題対策支援
日本は、2004年に策定した人身取引対策行動計画に沿って様々な施策を実施しています。これまでに、14か国の先方政府、国際機関、NGOなどと人身取引の効果的な防止および撲滅に向け協議を行っており、2007年度は、ラオス、カンボジア、タイ、インドネシア、ルーマニアなどと協議を行いました。
また、人間の安全保障基金などを通じて、人身取引撲滅に向けた様々なプロジェクトを支援しています。さらに、2007年度には、国連薬物犯罪事務所(UNODC)の犯罪分野に拠出した5万ドルの中からタイの人身取引被害者対策を支援しました。
不法な人の移動の対策支援
国際組織犯罪における不法な人の移動に際しては、偽変造旅券が使用されるケースが多く見られます。日本は、東南アジア諸国・地域などの関係者による相互の協力関係の発展、技術向上、関係諸国・地域の出入国管理行政の的確化と円滑化を目指しています。1995年以降2007年度においても、各国の出入国管理機関における偽変造文書の鑑識技術者の間でのセミナーを開催し、文書鑑識技術などについての意見交換や偽変造旅券の動向などについての情報共有を行っています。
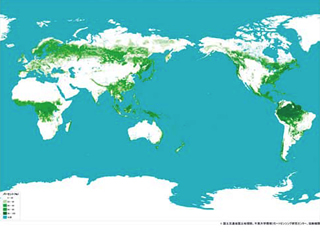

 .
.