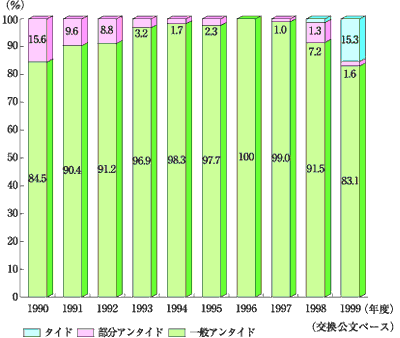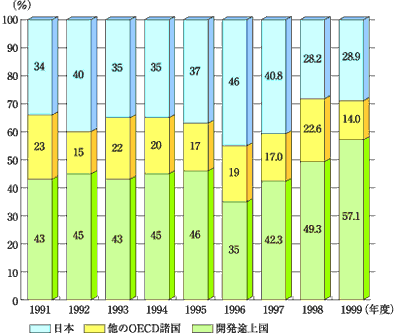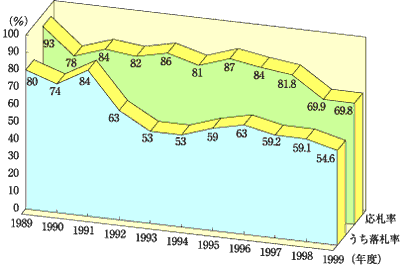第2章 開発協力に関する日本の考え方
21世紀をスタートするに当たって、開発協力は大きな転換点を迎えている。世界有数の援助国として、ODAを外交政策の重要な手段として活用する日本としては、変化に的確に対応し自ら改革を進めるとともに、その考え方を積極的に提示し、開発パートナーシップの構築に努め、また、国民のODAに対する更なる参加と理解が得られるよう努める必要がある。そうした観点から、まず開発協力の世界で現在盛んに議論されているいくつかの問題について日本の考え方を簡潔に述べておきたい。
第1節 グローバル化と開発
ヒト、モノ、カネ、情報の地球規模での自由な移動は、情報通信技術(IT)をはじめとする科学技術の飛躍的な発展等を背景に、近年その加速度を増しており、国際社会に劇的な変化をもたらしている。例えば、経済面では、国境を越えた経済活動の増大は、各国の経済発展を促すのみならず、財やサービス、巨額な資金の地球規模での移動を通じ、世界全体としてひとつの経済(グローバル・エコノミー)を形成するに至っている。また、特に冷戦後、市場経済や民主主義といった経済・社会の仕組みや基本的価値が世界的規模で広く共有され始めており、人々の生き方や、社会と個人の関係、政府と市民社会との関係にも目覚ましい変化をもたらしている。
こうしたグローバル化は、今や不可逆的な流れとなり、その中で生じた富や様々な技術、アイデアは、世界規模で広範な人々に裨益し、進歩の機会を提供するという「光」の側面を有している。
その一方で、グローバル化はすべての国々、人々に熾烈な競争や変化への適応を迫るものであり、一部の国や人々がグローバル化の荒波に十分対応し切れないという事態を生み出したり、変化から取り残された者と進歩の機会を掴んだ者との間の格差が拡大するという可能性を孕んでいることも否定できない。一国内における貧富の差や、先進国と途上国の間の格差の拡大が、紛争や感染症、
統治(ガヴァナンス)の欠如などとあいまって悪循環を形成し、グローバル化の成果を享受しえない国々、人々の出現を引き起こしている。
更に、グローバルな資本の移動に伴い、世界各地の金融市場が緊密化する中、97年の
アジア通貨・経済危機は、短期資本の急激な集中・逆流に伴う影響が世界的規模で瞬時に波及することを明らかにし、こうした金融システム全体に係わる(システミックな)危機に備える必要性を顕在化させた。
このようにグローバル化は、世界的規模での発展の可能性を秘める一方、様々な不安定性を孕んでいる。日本が議長国を努めたG8
九州・沖縄サミットにおいても、すべての人に対しグローバル化の利益を最大化するために創造的であり続けることの重要性とともに、グローバル化に関連した様々な懸念を認識し、その負の側面を最小化する必要があることが強調された。グローバル化が提供する様々な機会を途上国が自らのものとすることができるような環境を整備することが、日本を含む先進諸国、更には国際社会にとっての利益であるとの認識を反映していると言えよう。
グローバル化が一部の国や人々を疎外することなく、包括的なものであり、多くの国や人々が裨益できるようにするためには、開発協力の観点からいくつかの点が重要であろう。
第一に、先進国、途上国、国際機関や市民社会等のあらゆる当事者が連携・協力して、即ち国際社会全体が
パートナーシップを発揮して取り組んでいくことが重要である。
第二に、グローバル化の進展を、単に市場原理に委ねるだけでなく、その負の側面を克服するために必要な国際的な制度や枠組みの構築(グローバル・ガヴァナンス)に国際社会全体として取り組んでいくことが重要である。
第三に、各々の国においてもグローバル化への対応に不可欠な法整備などの
制度構築(インスティテューション・ビルディング)、政策実施・運営能力(
キャパシティ・ビルディング)を育成・強化していく必要がある。
第四に、発展の促進に大きな役割を有する貿易や投資など各分野での対応能力を構築するとともに、各分野を通じた政策の一貫性を確保することも重要である。
第五に、ITとその活用に対する積極的な取り組みが不可欠なことは論を待たない。
第六に、環境保全や感染症問題など地球規模の課題や、紛争など、開発の基盤を崩しかねない問題について、途上国からの主体的取り組みが不可欠であるのみならず、従来にも増して国際社会が関心を深め、支援をしていく必要性が増している。
第2節 貧困削減と経済成長
このようなグローバル化の進展の中で、貧困の克服が経済・開発上の問題としてのみならず、国際的な安定を損ないかねない問題と認識されるようになっている。そうした認識の下に、90年代の後半に入って貧困削減が途上国援助の最大の課題とされるに至った。但し、その方途をめぐっては、国際的に異なった考え方が存在する。
まず、貧困問題に直接的な対応をすべきであり、援助の焦点を貧困削減に絞るべきであるとの議論があり、
世銀や
アジア開発銀行といった国際機関の援助方針にもそうした考え方が色濃く反映されるようになっている。他方、貧困削減と成長は不可分の関係があり、貧困問題への直接的対応だけでは不十分であり、成長が不可欠であること、同時に、その成長が所得格差を縮小するような形で達成されることが重要との考え方がある。
日本は、後者の立場をとっており、DACの場や世銀関係者との意見交換の場でも、こうした議論を積極的に行っている。
九州・沖縄サミットのコミュニケにおいては、成長と貧困削減がバランス良く扱われることとなった
(注1)。
貧困削減に向けた取り組みにおいては、アジアにおける開発の経験が示すとおり、持続的な経済成長が重要である。そのためには、途上国側が主体性を発揮して開発に取り組むこと、民間部門の活力を引き出す方向での政策・体制整備を進めること、農業・農村開発の重視、教育・社会投資の促進を通じての人材の育成、制度造り等能力構築に努め、成長の展望を切り開いていくことが重要と考えられる。しかも、経済成長はあくまで貧困削減のための必要条件であり、成長は貧困層にも裨益する衡平なものでなければならない。そのためには、成長によってもたらされた資源が、国民の保健や教育の向上に向けられ、それが更に成長の礎となるという好循環を築くことが重要である。
成長を阻害し、貧困問題への対処を困難にする課題として、
累積債務、
HIV/AIDS等の感染症の問題、
紛争と開発の問題が注目されている。貧困に苦しむ途上国の中には、極めて深刻な債務問題に直面している国もある。
重債務貧困国への債務救済を実施するに当たっては、これら諸国における貧困削減戦略の一部をなすものとして、社会開発分野への適切な取り組みや債務管理能力の向上が確保される必要があるが、これらの貧困削減、債務救済の努力も、成長の展望なしには持続が困難となろう。
また、HIV/AIDS等の感染症の問題も深刻である。途上国においては健康な生活の欠如は直接的に貧困に通じやすい。途上国における保健・医療の問題は、人々の生存の根元に係わるものとして「
人間の安全保障」(
囲み3.参照)の観点からも重要な取り組み課題となっている。加えて、感染症の問題は、途上国の経済・社会の運営を担い、開発を進めていく主体となる社会の中堅層や青年層を蝕むことになり将来の成長の展望をも奪うものとなっている。
更に、紛争、
対人地雷等の問題は、経済・社会基盤などそれまで営々と築き上げた開発の成果を損ない、途上国の人々の生活に直接的な脅威を与えるものであり、「
人間の安全保障」の観点からも深刻な問題を惹起している。今後、紛争の予防、紛争発生後の諸困難の緩和、再発の防止に資する開発協力の視点を更に強化していくことが求められている。以上は、成長を可能とする基盤を整備する上でも、早急な取り組みが不可欠である。
こうした開発課題は、九州・沖縄サミットにおいても、国際社会の様々な主体が
パートナーシップを発揮しつつ一致して取り組むべき課題として議論された。これら各課題への日本の具体的対応については第3部「主要援助国としての日本の課題別取り組み」において詳細に述べる。
「 人間の安全保障」とは、人間の生存・生活・尊厳に対する様々な脅威を除去し、一人ひとりの人間が自由で創造的な価値ある生活を送ることができるよう取り組んでいくとの考え方である。具体的には、貧困、環境破壊、薬物、国際組織犯罪、HIV/AIDS等感染症、紛争、難民流出、対人地雷等の問題が人間の安全保障に係わる脅威と考えられる。こうした多様な脅威に対し効果的に取り組むためには、各国政府、国際機関、市民社会が連携・協力( パートナーシップ)することが求められる。
98年12月、小渕総理(当時)はヴィエトナムのハノイにおいて「アジアの明るい未来の創造に向けて」と題する政策演説を行い、「人間の安全保障」を日本外交の中に明確に位置付けた。更に、99年6月、東京の国連大学にて、人間の安全保障の視点から改めて開発問題を議論する国際シンポジウムが開催され、保健・医療、貧困撲滅、アフリカ開発が議題として取りあげられた。
また、99年3月、日本は国連に「 人間の安全保障基金」を設置し、人間の安全保障にかかわる脅威を克服するために必要な人々の能力向上及び自立促進に資するような事業を支援することとした。
同基金による事業として、99年9月、「セミパラチンスク支援国際会議」を開催し、旧ソ連時代の核実験場であったセミパラチンスク地域において被爆の後遺症に苦しむ住民たちへの支援のため国際社会の今後の取り組み強化の方途を検討した。
また、フィリピン・カピス州において、「性と生殖に関する健康」( 第3部第1章第1節参照)に携わる保健・医療の専門家等の能力強化と、この分野での地域住民の意識向上とを目的とした活動が国連人口基金(UNFPA)と日本のNGOであるJOICFPの協力を得て実施されている。なお、第3部第5章「紛争と開発」の項目で触れる緊急人道支援分野でのNGOの能力強化等を目的とする国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)による「 アジア・大洋州地域国際人道支援センター」事業も同基金の支援によるものである。
|
途上国における開発の問題は、途上国自らの努力を中心として、援助国のみならず、国際機関、NGOなどが知恵を出し合いながら効果的に協力・連携して取り組むべき課題である。各援助国はそれぞれ開発協力に対する歴史的な背景や独自の経験、考え方、更には得意な分野を有する。また、国際機関は、所掌分野における専門性や、国際機関としての中立性という利点を有する。更に、開発の受益者である途上国の人々に資する支援を進める上でNGO等市民社会との連携は重要な要素である。
こうした各援助国、国際機関の比較優位を活かしつつ相互に補完し合うことによって、援助の重複を回避すると共に、相乗効果を上げることは、援助の効率的、効果的な実施にとって不可欠である。日本としてもこのような開発パートナーシップ構築の試みを歓迎しており、途上国の現場で具体的な成果として結実していくよう知的な貢献を行っていく考えである。
開発パートナーシップのうち、他の援助国や国際機関との援助協調については、日本としてもすでに相当の実績を積み上げてきている。例えば、他の援助国との協調では、日米間で既に「
日米コモン・アジェンダ」の枠組みの下、保健・医療分野等において緊密に協力・連携を実施する等実績を着実に積んでいる
(注2)。また、日仏間でも96年に合意された「
日仏協力20の措置」に基づき援助協調が実施されており、99年12月には「
開発援助に関する日仏共同コミュニケ」が採択され、日仏間で幾つかの重点国を特定し協調案件を具体的に進めていくことが合意されている。更に、日本は主要な援助国との対話を定期的に実施しており、99年度は豪州、加、仏、英、米、北欧諸国との間で援助政策に関する協議を実施している。
国際機関との協調に関しては、国際機関を通じた多国間(マルチ)の援助と日本の二国間(バイ)援助の相互補完・連携を図るべく、マルチ・バイ協力を促進している。例えば
国連開発計画(UNDP)との間で、日本の拠出により設置した「
人造り基金」を通じて、UNDPの経験や組織を活用しつつ日本あるいは日本人の貢献が認識されるような形で援助が行われるよう努めている。
また、保健・医療分野では、
国連児童基金(UNICEF)と定期協議を行い連携強化に努めているほか、実施体制が十分でない国に対し人道的観点から医薬品、ワクチン、注射器等の供与を行う必要がある場合には、「
子どもの福祉無償」
(注3)を活用しUNICEFを通
じて援助を実施している。更に、西太平洋地域での
ポリオ根絶運動の進展を踏まえ
(注4)、同地域での保健・医療分野の協力を強化するため、WHO西太平洋地域事務局との間で2000年2月に第一回の定期協議を開催し、同年12月には第二回定期協議を行った。
世界銀行等の国際開発金融機関との間では、主要な出資国
(注5)として、定期協議の開催や職員派遣等人事交流を含め、各方面において積極的に交流、意見交換を行っている。特に、
重債務貧困国(HIPCs)を中心とする途上国が策定し、
世銀理事会の承認を求める
貧困削減戦略ペーパー(PRSP)については、当該国の今後数年間に亘る開発戦略の骨格を決定するものであり、日本としても積極的にその策定・実施・モニタリング過程において支援を行っている。加えて、世銀をはじめ国際社会が取り組むべき開発課題への対応についても継続的に意見交換を行い、日本の考え方が反映されるよう努めている。
また、日本がその策定に指導的役割を果たしたDAC
新開発戦略においては、
開発パートナーシップの推進が謳われているが、その具体化努力の一つとして、途上国で援助国・国際機関が協力して、保健や教育などの個別の分野(
セクター)毎に中長期的計画を策定し、連携して開発協力に取り組む「
セクター・ワイド・アプローチ」がアフリカ諸国等一部の地域で盛んに試みられている。こうしたアプローチは、様々な開発パートナーが開発の目的と情報を共有し、効果的に協力を進めることを目指すものとして評価しうる。
このセクター・ワイド・アプローチの実施に際しては、資金動員の方法としてセクター毎に共通基金を設立し、各国が資金を拠出するという「
コモン・ファンド」方式の導入や、調達・契約制度をはじめ援助資金の支出・モニター・監査・評価など援助手続きをすべて共通様式にて実施すべしとの主張も一部に見られる。
もとより、援助協調は重要であるが、あくまで被援助国側の開発への主体的取り組み姿勢
(オーナーシップ)を尊重し、これを育むものでなくてはならない。この観点から、
セクター・ワイド・アプローチの実施に際しては、被援助国が
共通基金(コモン・ファンド)方式や援助手続きの急進的かつ厳格な共通化といった手法に対応できるだけの能力構築(
キャパシティー・ビルディング)を十分に成しえているか、日本をはじめとする援助国が援助資金の使途に関する自国民への説明責任をいかに確保しうるか等を良く吟味する必要があろう。
特に財政支援に等しい共通基金方式の実施は、実施のやり方次第では援助国が主体性を発揮する余地を狭める可能性があるものであり、また、「
顔の見える援助」の実現を困難にする可能性を秘めている。そうなれば、国民の援助に対する理解と支持を得ることも難しくなる。また、このような方法は、いまだ試行段階のものであり、効果的か否かが明らかになるには更に時間と検証が必要であろう。途上国の開発を一定の手法の実験の場とすることは援助国としては慎まなくてはならない。
途上国側の直面する援助課題や援助吸収能力が様々であることを踏まえれば、これらの国がたどる開発の道筋も多様であるべきではなかろうか。そのためにはドナー側が提供しうる多様な経験や援助手法から途上国が適切なものを選択する余地を残すべきであり、画一的な解決策を提示し、途上国の主体性発揮の余地を狭めるようなことは好ましくない。援助協調が途上国側の真の開発への主体的取り組み姿勢の強化に寄与するよう努めていくことが求められよう。
なお、開発への取り組みにおいて、その意義と役割の重要性が益々認識されているNGOとの連携については、別項で詳しく述べたい。
日本の資金を使っての援助であるにも拘わらず、相手国に日本の援助だと十分認識されていない、いわゆる「顔の見える援助」が行われていないとの批判がある。これまで以上に国民の理解と支持を得てODAを進めていくためには、日本の援助について相手国国民によく知られ、理解してもらうことは当然と言える。このため被援助国の人々に対して、また援助の現場において日本の援助についての認識と理解を深めてもらうため一層の努力が必要である(
第1部第3章第4節(3)「被援助国における理解の促進」参照)。
「顔の見える援助」が、人と人との交流を通じ、自国の経験に根ざした優れた技術やノウハウを活用しつつ相手国の開発努力を支援するため現場で知恵を絞り汗を流すことを通じて実現しうるものであるとすれば、途上国の国造りを支える人造りへの支援において、専門家派遣、青年海外協力隊及び
シニア海外ボランティア派遣といった事業を通じて、国内の有為の人材を活用し日本の人的な貢献を強化することは、「顔の見える援助」を実現していく上で極めて有益となろう。また、研修員受入や、
国費留学生制度をはじめとする留学生支援、あるいは
日本語学習支援等は、日本人と直接交流したり、現代を生きる日本人の姿や日本の文化に触れる機会を提供し、人的交流に基づく途上国と日本との間の相互理解促進や、国民レベルでの二国間関係増進に極めて重要な役割を果たしている。更には、地方自治体やNGOの協力活動も活発になっており、「顔の見える援助」の観点からもこれを支援していくことは意義深い。
途上国が直面する開発課題への取り組みに必要な人材育成を進める上で、今後ともODAを通じた貢献の余地は大きい。
まず、人材育成については、行政、農林水産、鉱工業、エネルギー、保健・医療、運輸・通信のほか市場経済化、法整備支援、中小企業育成、職業能力開発といった幅広い分野で、専門家派遣、研修員受入を通じて行われている。特に、アジア経済危機に際しては、アジア諸国の金融部門の脆弱性、経済・開発政策の立案・実施に必要な人材の不足等の構造的な問題が指摘され、日本はこれらの国々の金融セクター支援の拡充のために、99年度には7ヶ国に対して合計87名の専門家を派遣している。この他、 円借款を通じても、97年12月より、日本への留学・研修、日本よりの専門家派遣及びこれらのプログラム実施に必要な施設の整備に対して、金利0.75%、償還期間40年(据え置き期間10年を含む)という国際的に最も優遇された条件を適用し、積極的に支援している。
次に、現地における日本語学習支援は、途上国の人材育成や留学生派遣事業を効果的かつ円滑に進める上で、優れた効果を期待しうる。また、日本語学習を通じて途上国の人々が日本への関心と理解を深めることは、まさに日本の「顔の見える援助」の強化にも資するものである。この関連で、ヴィエトナム、ラオス、モンゴル等市場経済移行期にあるアジア諸国において、若手人材をビジネス教育と日本語教育等を通じ育成し、日本との相互理解を深め、人的絆を幅広く形成するための人造りの拠点として「 人材協力センター(日本センター)」建設に向けた支援が進められている。また、現在158名の青年海外協力隊員及び10名のシニア海外ボランティアの方々が途上国の日本語学習支援に従事している。
更に、日本は、留学生等への援助、留学生宿舎の整備等、渡日前から帰国後まで体系的な留学生受入れのための施策を総合的に推進している。99年度には、137の国・地域より計8,774人の国費留学生を受け入れるとともに、私費留学生9,690人に対し学習奨励費(奨学金)を給付している。加えて、99年度からは「 留学生支援無償」が新たなスキームとして導入された。これにより、市場経済への移行に対応すべく法整備、経済・経営等の分野で人材育成への需要を抱えている途上国に対して、政府による組織的・計画的な日本への留学生派遣事業計画を支援することが可能となった。当面はアジアの体制移行国であるインドシナ諸国及び中央アジア諸国を中心に実施することとしており、初年度については、ラオス及びウズベキスタンより各々20名の留学生受入を支援している。
|
また、「顔の見える援助」は、日本企業の有する技術や経営上のノウハウの活用、円借款事業への日本企業の事業参加のあり方といった側面にも係わる。この点に関連した具体的問題として、援助国からの財・サービス調達を義務付けるタイド援助問題がある。限られた援助資源を効率的に使用するためには、国際競争入札を原則とする
アンタイド化の推進を図ることが国際的な流れであり、また、借入国である途上国もアンタイド化を望む場合が少なくなく、そうした背景の下に日本の円借款も96年には100%アンタイド化されたが、その後国際ルール上許される範囲で一部タイド化がなされている。その背景には、アンタイド化が完全に実施された結果、本邦企業の有する技術やノウハウが発揮・移転される機会が著しく減少したという事実がある。こうした状況が続けば国内における援助に対する理解や支持基盤を弱めることになりかねない。援助の効率性を妨げないよう配慮しつつ、援助国自身が有する技術・ノウハウ・人材の活用が開発の視点から有効な場合は、これを使うことが考えられて良い。タイド化を通じた「顔の見える援助」の推進については、まさにこのような要素をバランス良く考慮した対応が必要となろう。
囲み5.日本の技術とノウハウの活用
円借款の調達条件(関連の財やサービスをどこの国から調達できるかの条件)については相手国が世界中から良質・安価な資機材・サービスの調達を行い、効率の高い援助であるようにするとの観点から、調達条件として一般アンタイド化を基本としており、途上国を含め国際社会から高い評価を得ている。こうしたアンタイド化の原則の下で、ODA事業への日本企業の参加機会を拡大し、途上国から求められている日本の固有の技術や経営ノウハウ等の積極的な活用を図るために、特定の分野・目的については、国際ルールに反しない形でタイド化を行っている (注1)。
日本政府は、環境、人材育成、中小企業育成及びコンサルタントによるソフト面での支援を重点分野とし、これら分野に対する支援を強化するため、97年9月に円借款金利の大幅な引き下げを実施し、金利0.75%、償還期間40年(うち据置10年)の最優遇条件を適用することとした (注2)。これらの分野における円借款については、日本の援助であることを相手国国民に良く理解してもらうため、日本人に事業に参加してもらい、日本企業の有する技術や経営上のノウハウの活用を進めるため、国際ルールに反しない範囲で、原則として日本と被援助国二ヶ国のタイドとしている。
更に、98年12月に発表された 経済構造改革支援のための 特別円借款 (注3)については、アジア諸国等が経済の構造改革を進め、早急に経済回復を図れるよう支援することを目指し、金利、償還期間とも極めて緩やかな供与条件を適用している(2000年1月以降、金利0.95%、償還期間40年(うち据置10年))。この供与条件の下では、国際ルール上タイド性の借款供与が可能であるため、原則として契約者を日本企業に限定し、アジア経済再生に向けての貢献が期待されている日本企業の参加機会の拡大を図り、日本の有する技術とノウハウの活用を促進することとしている (注4)。
近年、円借款事業における日本企業の受注率が低いとの指摘がなされている。一般に日本企業の受注率が低いとされる場合の根拠は、円借款による総事業に対する受注率の過去5年間の平均が約2割となっていることであるが、円借款の約3割を占める現地通貨建て費用(現地労働者の賃金や現地で調達される低廉な物資等であり、日本企業の主要関心部分ではない。)を除いた場合、日本企業の受注率は4割程度となる。更に、円借款のうち、日本企業が特に関心を有する規模の大きな契約(10億円以上)に限れば、日本企業はそのうち約8割に応札して、その約6割を落札しているのが実情である。
(注1)OECD輸出信用アレンジメントでは、公的輸出信用や援助信用によって貿易歪曲効果が生じないよう、タイド条件でODA借款を供与するには、商業借款と比較して一定の水準以上に優遇された貸付条件であることが必要とされている。現行の円借款の供与条件では、一部の環境案件、人材育成、中小企業育成、コンサルタント案件に適用される最優遇条件(金利0.75%、償還期間40年(うち据置10年))及び特別円借款に適用される供与条件(金利0.95%、償還期間40年(うち据置10年))のみが右水準をクリアできる。
(注2)具体的に最優遇条件(金利0.75%、償還期間40年(うち据置10年))が適用される範囲(中進国には適用なし)は以下の通り。
 地球温暖化等の地球環境問題対策案件及び公害対策のための環境案件。
 日本への留学・研修、日本からの専門家派遣及びそれらに必要な施設の整備を含めた人材育成案件。
 中小企業のうち特に零細なもの等に対して創設される低利融資制度の支援(但し、 ツーステップローンによる支援の性格上、調達条件は一般アンタイドとする)。
 環境配慮が必要な案件のコンサルタント部分。
(注3)アジア諸国等における景気刺激・雇用促進及び経済構造改革に資するインフラ整備への支援等を目的とし、99年度以降3年間で6,000億円を上限とする特別枠が設けられた。
(注4)特別円借款については、内外の関心が高く、当初対象としていた国や分野以外への適用可能性につき強い関心が寄せられたことを背景として、2000年1月、対象国はこれまでの「経済危機の影響を受けているアジア諸国」から「経済危機の影響を直接または間接に受けたアジア諸国を中心とする開発援助国」に拡大され、また、対象分野に情報通信、輸送基地送配電、下水道、廃棄物処理、工業団地等が新たに追加された。
|
更に、国際的な援助協調の流れの中で、
貧困削減戦略ペーパー(PRSP)策定やセクター・ワイド・アプローチの推進などの作業に積極的に参画し、これらの作業を主導していくことが「顔の見える援助」の推進に繋がることは論を待つまい。
こうした援助協調を巡る新たな動向の背景に、日本が援助の重点地域として支援してきたアジアが金融・経済危機を乗り越えて着実に回復過程にあるのに対して、アフリカにおいては困難を増している点があることに注目しておきたい。2回にわたり
アフリカ開発会議(TICAD)を国連や
アフリカのためのグローバル連合(GCA)と共催してきた日本として、明治以降及び戦後の日本自身の復興・開発の経験やアジアにおける開発協力の経験を活かして、アフリカの開発に貢献することが今程求められている時はないかもしれない。TICADの流れを着実に育み、具体化していくことが日本の「顔の見える援助」となることは間違いない。
こうした様々な分野における取り組みを進める一方、国際社会における開発協力を巡る議論において、日本自身の経験に裏打ちされた援助に関する考えを一層明確化することは「顔(理念)」の見えるODA推進の観点からも重要である。この意味で総理大臣の諮問機関である「
対外経済協力審議会」が2000年9月に答申した「『人間を重視した経済協力』の推進について」に関しては、
国連開発計画(UNDP)の「人間開発報告書」や「ODA中期政策」に謳われる「人間の安全保障」や「人間中心の開発」といった考え方を開発協力を通じ具体化するための提言として活かしていきたい。
囲み6.「人間を重視した経済協力」
総理大臣の諮問機関である「対外経済協力審議会」は、各界の有識者による意見交換の成果として、2000年9月に「『人間を重視した経済協力』の推進について」と題する意見をとりまとめ総理に提出した。
提言では、開発分野において国際的に主流な概念となっている「人間中心の開発」に基づき、経済協力の目的が被援助国の地域住民や人間一人ひとりの開発にあることを常に明確に意識する必要があることを強調した上で、21世紀におけるODAのあり方について、  人間開発を中心とし、開発途上国の 良い統治に留意しつつ、社会開発及び経済開発をバランス良く推進すること、  基礎生活分野(BHN)の充足を図ること、  地域社会・地域住民、特に女性の自主的な参加を重視すること、  環境と開発との両立を図ること、  情報技術(IT)を経済社会発展に結びつけること、が重要であるとしている。
その具体的施策としては、貧困撲滅に向けた重点的取り組みが重要であり、そのためにはインフラ整備等を通じた持続的経済成長により、貧困層の経済活動への参加を可能にし、持続的な人間開発を図る必要があるとしている。また、「人造り」に対する協力を支える基礎教育、保健医療等に関する社会組織の整備の重要性、「人間の安全保障」の観点からも問題となる紛争やグローバル化に伴う様々な悪影響を除去するために経済協力を通じて寄与することの必要性、NGO等との連携をはじめ国民各層の参加を得た経済協力推進の重要性等が指摘されている。
|
トピックス:1.モザンビーク洪水災害派遣、国際緊急援助隊・医療チーム
|
モザンビークでは2000年1月中旬からの降雨、特に2月の豪雨とサイクロンにより、中部及び首都マプトを含む南部5州において過去50年間で最悪の水害が発生し、推定千人規模の死者と約300万人の被災者が出ることとなった。
モザンビーク政府の緊急援助要請を受け、日本政府は直ちに2度に亘る緊急援助(緊急無償資金70万ドル及びテント、浄水剤等の物資3,750万円相当:総計約100万ドル相当)の他、19名の国際緊急援助隊・医療チームを派遣した。
今回の洪水災害でホクウェに入る初めての外国チームとなった日本の国際緊急援助隊・医療チームは、3月18日から3月26日の間、モザンビークの首都マプトから北東へ約200kmに位置するホクウェという村で緊急医療活動を行った。ホクウェは住民2万人のところへ約3万人が流入した避難民村の一つで、電気・水道もなく、洪水で道路も寸断されたため、医療チームは4輪駆動車で何とか通れる泥と砂の悪路を毎日2時間かけて通うこととなった。患者数が日々増加する中、村には衛生士1人と看護婦1人がいるヘルスセンターがあるのみで、医療チームはその庭先にテントを張り診療所を開設した。
医療チームは、一日平均250名という膨大な診療をこなし、9日間の診療患者総数は2,611人に及んだ。診療所のテント内は最高で41度を記録、日々の悪路の移動と暑さのため隊員は体力を消耗し、最初の2日間はほとんどの隊員が昼食を取れない状況であった。しかしながら隊員たちは次第に厳しい環境にも慣れ、病気や怪我もなく無事任務を全うすることができた。
また、現地のボランティアの方々にも、患者の整理や受付業務に精力的に貢献して頂いた。中でも左腕を失ったボランティアの方には、活動初日から最終日まで休むことなく活動に従事して頂くこととなった。
診療患者には、マラリア、下痢症が多く見られたが、子供の発熱患者の殆どはマラリアであった。残念ながら死亡した患者も6名を数えたが、重症の脱水を伴う下痢症等で救命を行ったケースも多く、またマラリアに関しても早期治療による防疫活動に寄与できた。その後、医療チーム活動中にはホクウェの周りの水も引き始め、避難民も元の村に帰りはじめることとなり、救急医療の一応の終息を見ることができた。
洪水被害は一段落したが、飲料水をはじめとする衛生問題や洪水で上流から流れ出た地雷の問題等、復興への課題は山積している。日本としては今後、中・長期的な視点からの同国への援助を検討していくべきであろう。
 子供を診察する医療チーム
診療を待つ人々
|
(注1)
資料編第5章第4節「G8コミュニケ・沖縄2000」参照。
(注2)
第3部第1章第1節「人口・エイズと日米コモン・アジェンダ」を参照。
(注3) 「人間の安全保障」推進の観点から、途上国において生存の危機にさらされている子どもの福祉改善に総合的に取り組むために設けられた無償資金協力の枠組みであり、これまで医薬品・微量
栄養素等の供与を実施してきた「子どもの健康無償」を発展的に拡充し、2000年度より導入されたもの。具体的には、

子どもの健康、

人口・エイズ、

婦人・家庭の役割、

基礎教育・識字の問題、に関する対策を講じるために必要な消耗品・資機材(医薬品、微量
栄養素、避妊具、エイズ検査試薬、婦人職業訓練機材、教材、識字キット等)を購入するための資金を途上国政府に対して又は国際機関を通
じて支援するもの。
(注4)
第3部第1章第3節「地球上からのポリオ根絶に向けて」を参照。
(注5) 日本の
世銀への出資額は第2位、
アジア開発銀行への出資額は第1位
である。
前ページへ 次ページへ
 地球温暖化等の地球環境問題対策案件及び公害対策のための環境案件。
地球温暖化等の地球環境問題対策案件及び公害対策のための環境案件。 日本への留学・研修、日本からの専門家派遣及びそれらに必要な施設の整備を含めた人材育成案件。
日本への留学・研修、日本からの専門家派遣及びそれらに必要な施設の整備を含めた人材育成案件。 中小企業のうち特に零細なもの等に対して創設される低利融資制度の支援(但し、ツーステップローンによる支援の性格上、調達条件は一般アンタイドとする)。
中小企業のうち特に零細なもの等に対して創設される低利融資制度の支援(但し、ツーステップローンによる支援の性格上、調達条件は一般アンタイドとする)。 環境配慮が必要な案件のコンサルタント部分。
環境配慮が必要な案件のコンサルタント部分。