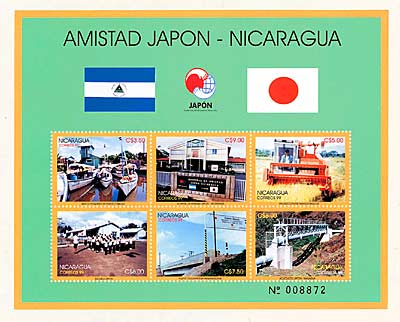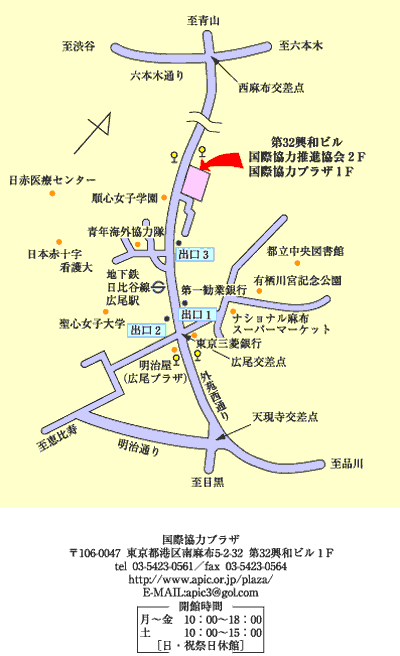国民の幅広い参加を得てODAを実施し、また、ODAに対する国民の支持と理解を得ていくためには、十分な情報公開に基づき国民に対する説明責任を果たすとともに、内外に対し適切な広報努力を行うことが極めて重要である。特に、現在のように厳しい経済財政事情の下でODA予算に対し納税者の理解と支持を得ていく上で、このことは従来にも増して重要である。
ODAは大半が海外で行われる事業であり、また、日本は極めて多くの途上国においてODAを実施していること、更には、多様化する途上国の開発上の課題に対応して日本のODA事業も広範かつ専門化・複雑化しているため、一般の国民にとって、個々の事業のみならずODAの全体像を簡単に把握することは容易ではない。これは日本に限らず主要援助国に共通の問題である。それだけに、政府としても、十分な情報をできるだけわかりやすい形で国民に提供することが不可欠となっている。そうした努力の一環として、99年度からは、海外にあるODAの現場に国民が直接触れる機会を提供することを狙いとして、「ODA民間モニター制度」を導入した。モニターは全国各都道府県にて募集・選出され、数チームに分かれてアジア各国の経済協力プロジェクト現場を視察した後、報告会、国際協力フェスティバル及び報告書を通じて視察の印象、意見等の報告を行う。
99年度は各都道府県から選ばれた計47名のモニターが6チームに分かれてフィリピン、タイ、中国、バングラデシュ、ヴィエトナム、ラオスにあるODAプロジェクト現場を視察、2000年3月に山本一太外務政務次官(当時)に報告書を提出した。(注1)
2000年度は参加募集人数を104名に増やしたのに対し、全国より5,440人の応募があった。また、視察国も上記にインドネシア、ネパール及びマレイシア及びモンゴルを加え、10カ国とした。
ODAに関する情報公開と主として国内を念頭に置いた広報については、政府は従来より囲み14.にまとめたような公刊文書を通じた広報努力のほか、「国際協力の日」を記念した「国際協力フェスティバル」等、広く国民が参加し、ODAを通じた日本と途上国との関わりをより身近に感じられるような行事を開催し、ODA広報に努めている。なお、87年に10月6日を「国際協力の日」と定め、この日を中心に毎年、全国各地で様々な行事を開催している(注2)。
そのほか、93年10月には、「国際協力プラザ」がODAに関する市民への窓口として開設された(注3)。同プラザはODAの資料・情報の整理、公開を行うほか、NGOの情報交換の場として、また、最近は学校の課外授業やグループ学習にも広く利用されている。更に、地方メディアや地域社会への情報発信のため、地方展開にも取り組んでおり、これまでに国内38ヶ所に「国際協力プラザコーナー」が設置されている。
また、外務省は、ホームページによる情報発信に積極的に取り組んでおり、97年より「我が国の政府開発援助」上下巻、「経済協力評価報告書」概要版を、98年よりは「我が国の政府開発援助の実施状況に関する年次報告」も掲載し、動画映像と音声によりプロジェクト視察の擬似体験ができる「ODAバーチャルツアー」なども設けた。ODAコーナーへのアクセスは着実に増加してきており、99年度は80万件以上に達し、外務省ホームページ(注4)上でも最もアクセス数の多い項目の一つとなっている。ODAコーナーを一層拡充し、ODAに関する総合的なホームページの機能を持たせるべく、99年度にODAコーナーの拡充が行われた。現在、本書や「年次報告」のみならず、各論部分を含む「経済協力評価報告書」なども掲載し、提供情報が大幅に拡充されるとともに、構成や検索機能などの利便性の向上も図られている。
九州・沖縄サミットの主要テーマの一つとして議論された情報技術(IT)の重要性は益々高まっている。外務省としても、ホームページを開設し、我が国でも急速に普及しているインターネットを活用したODA情報の提供を進めている。
従来、ODA情報は外務省ホームページの1コーナーとして掲載されていたが、掲載内容が飛躍的に増加したことなどから、平成11年度には、ODAについての総合的ホームページの機能を持たせ、かつ、利便性を向上させるため大幅な拡充を行った。改装したODAホームページは、ODAニュース、ODA政策、ODA資料、みんなのODAの4つから構成されている。
「ODAニュース」では、メディアなどで話題になったテーマについて背景情報や実情を提供するトピックス、最新情報、国際協力に関する採用情報などを提供している。「ODA政策」では、ODA大綱、ODA中期政策などの基本的資料、具体的案件策定の指針となるべく作成された国別援助計画などの情報、NGO支援、緊急援助に関する情報を掲載している。「ODA資料」の部では、ODA白書、ODA年次報告などの基本資料のほか、過去7年分の経済協力評価報告書を利用しやすい形で提供している。更に、最新のODA予算や無償資金協力や有償資金協力などODA案件情報も掲載している。最後に、「みんなのODA」では、ODAの基礎や開発教育についての情報、ODA民間モニターに関する情報及び平成11年度の報告書全文、在外公館からの援助案件の報告、ODAプロジェクトの擬似体験ができるバーチャルツアー(タイなどアジア5ヶ国)、日本及び世界の援助機関へのリンク、などを見ることができる。
今回の改訂では、掲載資料等の充実に加え、機能面の拡充も行った。ODAホームページを読みながら、ODAの用語を探すことができるODA用語集や、ODAコーナーの内部で調べることができる文字検索機能などが追加された。
アドレス:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html
従来、ODA情報は外務省ホームページの1コーナーとして掲載されていたが、掲載内容が飛躍的に増加したことなどから、平成11年度には、ODAについての総合的ホームページの機能を持たせ、かつ、利便性を向上させるため大幅な拡充を行った。改装したODAホームページは、ODAニュース、ODA政策、ODA資料、みんなのODAの4つから構成されている。
「ODAニュース」では、メディアなどで話題になったテーマについて背景情報や実情を提供するトピックス、最新情報、国際協力に関する採用情報などを提供している。「ODA政策」では、ODA大綱、ODA中期政策などの基本的資料、具体的案件策定の指針となるべく作成された国別援助計画などの情報、NGO支援、緊急援助に関する情報を掲載している。「ODA資料」の部では、ODA白書、ODA年次報告などの基本資料のほか、過去7年分の経済協力評価報告書を利用しやすい形で提供している。更に、最新のODA予算や無償資金協力や有償資金協力などODA案件情報も掲載している。最後に、「みんなのODA」では、ODAの基礎や開発教育についての情報、ODA民間モニターに関する情報及び平成11年度の報告書全文、在外公館からの援助案件の報告、ODAプロジェクトの擬似体験ができるバーチャルツアー(タイなどアジア5ヶ国)、日本及び世界の援助機関へのリンク、などを見ることができる。
今回の改訂では、掲載資料等の充実に加え、機能面の拡充も行った。ODAホームページを読みながら、ODAの用語を探すことができるODA用語集や、ODAコーナーの内部で調べることができる文字検索機能などが追加された。
アドレス:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html

ODAホームページ(トップページ)