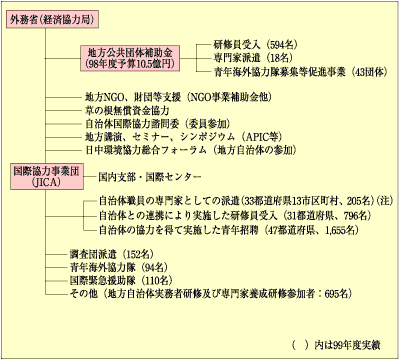国民参加型援助の典型として、第2節で述べたNGOによる活動に加え、JICAが実施する青年海外協力隊とシニア海外ボランティアの派遣事業が挙げられる。
「青年海外協力隊」の99年度の派遣実績を見ると、農林水産、保健衛生、教育文化等の7分野、60ヶ国に2,498人の青年海外協力隊員が派遣されている。1965年の事業開始以来の累計は20,141人に上る。青年海外協力隊は20~39歳の日本の青年男女を開発途上地域に派遣し、地域住民と一体となってその地域の経済・社会の発展に協力することを目的とする事業であり、途上国への技術移転、友好親善の増進、更には日本青年の広い国際的視野の涵養に寄与しており、日本の「顔の見える援助」の一つとして、内外の高い評価を得ている。
シニア海外ボランティア制度は、豊富な経験と知識をもつ熟年世代に、途上国支援の一翼を担ってもらおうと、91年度から派遣が開始されたものである。年齢は40歳から69歳が対象であるが、99年1月までに派遣された215人のうち、45%が60歳以上と、元気なお年寄りが目立つ。しかしシニア海外ボランティアはとにかく健康が第一条件。気候も環境も日本と違う途上国での1年以上にわたる生活は、熟年層にとって予想以上に厳しいものとなる。書類による技術審査は、条件さえ合えば比較的通過しやすいが、2次の健康診断では、1次合格者の半数近くが不合格になるという。また、派遣後に体調を崩し帰国を余儀なくされた例もある。
そのような厳しい状況の中、マレイシアに派遣された元保母の女性は、現地の地方開発省に勤務、幼児教育指導やカリキュラム立案などを手がけている。だが、彼女はオフィス内だけの仕事に飽き足らず、合間をぬって高等専門学校にある保育所での指導を買って出ている。彼女とのふれあいに無邪気に喜ぶ子供たちに、ふと手を伸ばし頭をなでてやりたくなるが、決してそうはしない。マレイシアでは頭は神聖なところとされており、不用意に触れることは許されない。相手の価値観や文化の違いを尊重することも、シニア海外ボランティアにとって不可欠な認識なのである。
また、最近までJICA総裁を務めていた藤田公郎氏も、本制度に応募した一人である。これまでは日本における技術協力実施機関のトップとして技術協力の陣頭指揮をとってきたが、2000年10月サモアに赴任、現在は政府の政策アドバイザーとして経済協力の現場に直接携わっている。
高齢社会の到来を背景に、シニア海外ボランティア事業は広い世界での活躍の場を中高年層に提供するという意味で、貴重な存在だ。経験豊かなシニアの方々に対する途上国側の評価も高く、現在17ヶ国の受け入れ国も大幅に増加する見込みだという。また、第2の人生を途上国で過ごし、帰国後はその経験を糧に第3の人生を日本国内でのボランティア活動で過ごす人も増えているという。中には小学生や中学生に自らの体験を伝える語り部として活躍している方もいる。こうした人々が生き生きと活動できる体制づくりの一環として、本制度の一層の充実が期待されている。
そのような厳しい状況の中、マレイシアに派遣された元保母の女性は、現地の地方開発省に勤務、幼児教育指導やカリキュラム立案などを手がけている。だが、彼女はオフィス内だけの仕事に飽き足らず、合間をぬって高等専門学校にある保育所での指導を買って出ている。彼女とのふれあいに無邪気に喜ぶ子供たちに、ふと手を伸ばし頭をなでてやりたくなるが、決してそうはしない。マレイシアでは頭は神聖なところとされており、不用意に触れることは許されない。相手の価値観や文化の違いを尊重することも、シニア海外ボランティアにとって不可欠な認識なのである。
また、最近までJICA総裁を務めていた藤田公郎氏も、本制度に応募した一人である。これまでは日本における技術協力実施機関のトップとして技術協力の陣頭指揮をとってきたが、2000年10月サモアに赴任、現在は政府の政策アドバイザーとして経済協力の現場に直接携わっている。
高齢社会の到来を背景に、シニア海外ボランティア事業は広い世界での活躍の場を中高年層に提供するという意味で、貴重な存在だ。経験豊かなシニアの方々に対する途上国側の評価も高く、現在17ヶ国の受け入れ国も大幅に増加する見込みだという。また、第2の人生を途上国で過ごし、帰国後はその経験を糧に第3の人生を日本国内でのボランティア活動で過ごす人も増えているという。中には小学生や中学生に自らの体験を伝える語り部として活躍している方もいる。こうした人々が生き生きと活動できる体制づくりの一環として、本制度の一層の充実が期待されている。

マレイシアの保育所で子供たちとふれあうシニア海外ボランティア