|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
C. 少年司法の運用(第40条) 少年司法
256. 我が国においては、少年法上、20歳末満の者を「少年」として取り扱っている。少年が罪を犯した場合については、以下のとおり少年法等により成人(20歳以上の者)とは異なる手続を定め又は措置を講ずることにより、その年齢を考慮し、将来社会において建設的な役割を担うことを促進するものとしている。なお、我が国の刑法は、14歳末満の者の行為は罰しない旨定めており、14歳末満の者は、原則として、児童福祉法に基づき、教護院や養護施設への入所等の措置がとられることとなっている。
(i)一般に、少年は、人格が未熟である反面、可塑性に富んでいるので、罪を犯した少年に対しては、刑罰による非難を加えるよりも、保護、教育を行うことが少年の健全育成に役立つと考えられている。そのため、我が国では、少年が罪を犯した場合等には、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整を図るとの観点から、これらの少年事件は、すべて家庭裁判所に送致、通告される。
(ii)家庭裁判所は、非行事実の有無について判断する司法的機能を有するとともに、再非行防止の観点から、人間関係諸科学の専門職である調査官の補助を得ながら、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について医学、心理学、教育学、社会学等の専門知識を活用して調査を行い、非行の原因、再非行予防のための諸要素に関する要保護性の判断を適切に行う福祉的機能を有している。そして、この二つの機能を十分に生かすためには、検察官が被告人を弾劾し、その刑事責任を追及するという刑事手続のような対立構造は好ましくなく、関係者の協力を得て、裁判官が直接少年に対し語りかけ、教育的な働きかけを行うことのできる非形式的な審問構造の方がふさわしいことから、少年審判手続では、家庭裁判所が自ら事件を調査し、審問を行い、少年にとって最も適切、妥当な措置をとり又は処遇を決定する職権主義的審問構造を採用している。
(iii)上記のように、すべての事件を家庭裁判所に集中させるため、まず第一に家庭裁判所が、保護処分に適するか否かを判定することになる。その結果、少年の過去の保護処分歴等にかんがみて、保護処分によってはもはや矯正される見込みがない場合や、犯罪の内容が重大で、社会に与える影響等を考慮すれば、刑事責任を問い、その罪責を明らかにするのが相当な場合のみ(ただし、いずれも死刑、懲役又は禁錮に当たる罪に限る。)、成人と同様の刑事手続に移行させる。しかし、16歳末満の者については、刑事手続に移行できないこととし、低年齢の少年に対して特に配慮がされている。
また、刑事手続に移行し、刑に処せられる場合でも、少年の特性を考慮し、18歳末満の児童に対する死刑・無期刑の緩和、収容時の成人との分離、仮出獄を許可するまでの期間の短縮等種々の特例が認められている(詳細は、277.及び281.参照)ほか、少年に対し、罰金が言渡された場合、換刑処分としての労役場留置は禁止されている。
更に、一般に、刑に処せられた者は、その刑の執行を受け終わり、あるいは執行の免除を受けてから一定期間経過するか、執行猶予の判決であれば、その期間が経過した時点で、その刑の言渡しは効力を失うこととされる。他方、少年の場合には、刑の執行を受け終わり、あるいは執行の免除を受けた場合には、人の資格に関する法令の適用について、その時点から将来に向かって刑の言渡しを受けなかったものとみなされ、また、執行猶予の判決であれば、猶予が取り消されない限り、猶予期間中であっても、同様に取り扱われるなど、資格の制限が小さくなるように配慮されている。このほか、選挙権、被選挙権についても、公民権停止の効果が生じない場合があるなど有利な扱いがなされている。257. 我が国には、非行少年の鑑別機関としての少年鑑別所と犯罪を犯した少年のための矯正機関としての少年院及び少年刑務所がある。これらの少年を収容している矯正施設においては、少年の健全な育成を期するとする少年法の目的に沿って、人の尊厳及び価値を尊重する意識の促進も、少年の健全な育成の内容として十分考慮に入れ、収容されている者の処遇を実施している。
少年鑑別所
258. 少年鑑別所は、家庭裁判所の観護措置の決定により送致された少年を収容するとともに、家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学等の専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設である。
少年院
259. 少年院は、家庭裁判所において少年院送致の保護処分に付された少年を収容し、これに矯正教育を行う施設であり、初等、中等、特別及び医療と異なる少年院が設けられ、短期(一般及び特修)及び長期の処遇課程に分かれている。少年院では、在院者を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え、規律ある生活の下に、矯正教育として教科並びに職業の補導、適当な訓練及び医療を授けるものとされており、形式的な年齢と共に、それぞれの対象者の実質的な心身の発達の状況等を考慮しながら、その者が社会生活に適応し、社会において建設的な役割を担うことを促進するために必要な生活指導、教科教育、職業補導、医療措置等の処遇を実施している。更に、集団生活を通じて、他の者の人権及び基本的自由を尊重しながら、社会生活における対人関係を調整していくことや社会生活における自己の役割を洞察させる指導等も併せて実施されており、人の尊厳及び価値についての意識の促進に資する取扱いをしている。なお、少年院の長は、在院者に対する矯正教育のうち、各教科を修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができ、右証明書は学校教育法により設置された各学校と対応する教科課程について、各学校の長が授与する卒業証書その他の証書と同一の効力を有する。
少年刑務所
260. 刑事裁判において懲役又は禁錮の実刑の言渡しを受けた少年は、刑の執行のため、原則として少年刑務所に収容される。
これらに収容された者に対しても、少年院と同様に、それぞれの対象者の年齢、実質的な心身の発達の状況、資質等を考慮に入れて、その対象者が社会生活に適応するために必要な生活指導、教科教育、職業訓練、医療措置等の処遇を行い、人の尊厳及び価値についての意識の促進に資する取扱いをしている。保護観察
261. また、少年に対する保護観察としては、家庭裁判所の決定により保護観察に付された者、少年院からの仮退院を許可された者、少年刑務所からの仮出獄を許された少年及び少年の保護観察付執行猶予者に対する保護観察がある。これらの保護観察は、保護観察所の保護観察官及び保護司によって、少年が遵守事項を遵守するよう指導監督するとともに、必要な援助をすることにより実施され、非行の傾向等を考慮し、例えば家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年に対しては、標準的に実施される保護観察のほか、短期保護観察、交通事犯関係者に対する保護観察及び交通短期保護観察といった複数のメニューを設けるといった配慮がなされている。また、遵守事項の設定や保護観察の実施(生活指導、交友関係指導、就職指導、家庭環境調整、学校関係調整等)に当たっては、対象少年の年齢、経歴、心身の状況、家庭、交友その他の環境等を十分斟酌しつつ、対象少年が社会の順良な一員となり、社会において建設的な役割を担うことを促進するために最もふさわしい方法が採られている。また、少年の健全な育成を期するとする少年法の目的に沿って、人の尊厳及び価値を尊重する意識の促進も少年の健全な育成の内容として十分に考慮に入れ、保護観察対象者の処遇を行っている。
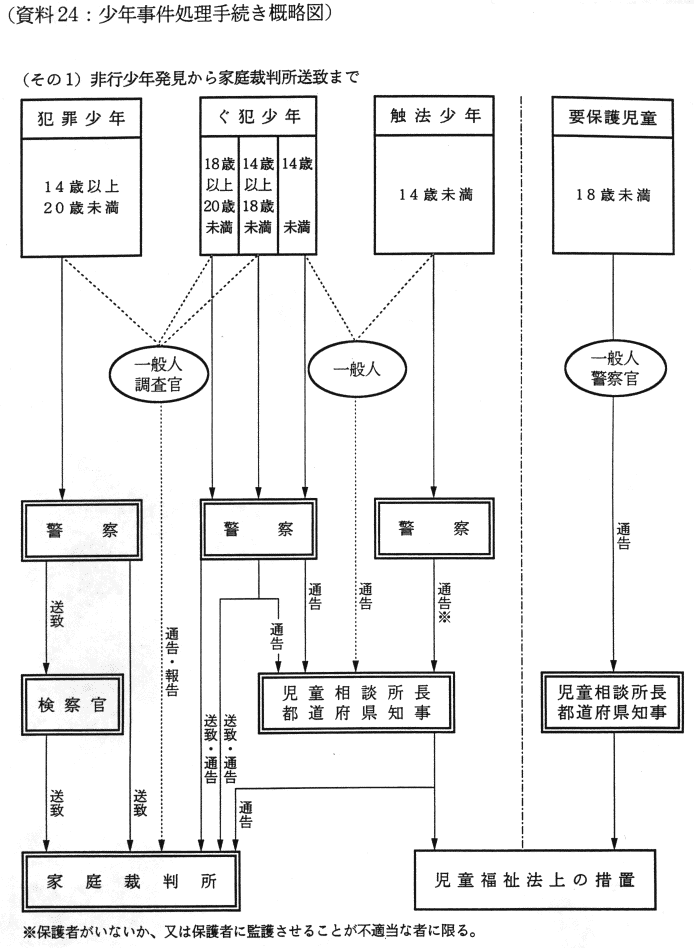
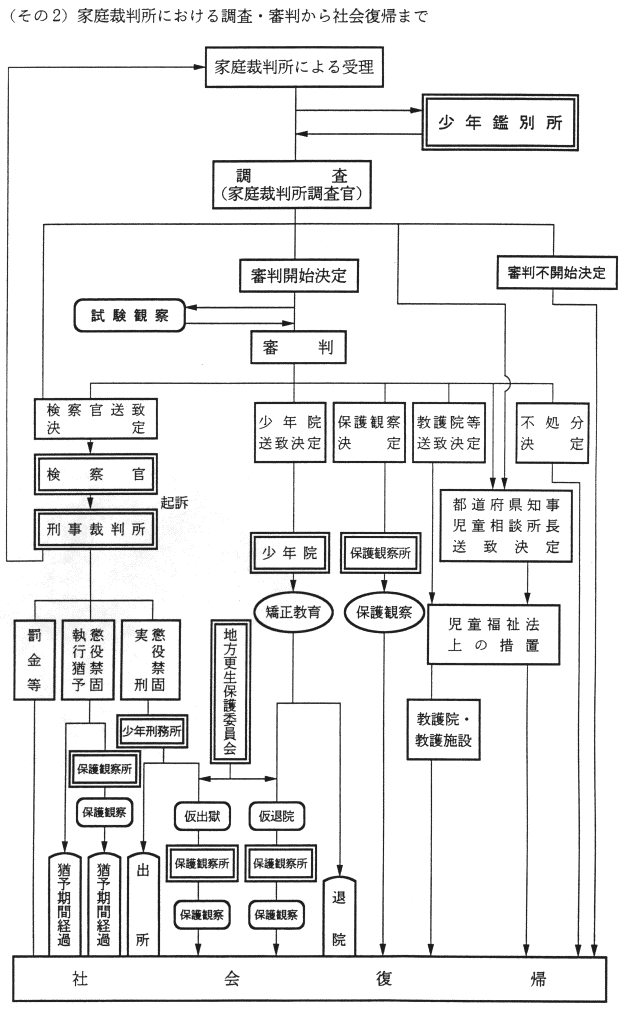

遡及処罰の禁止
262. 憲法は、何人も、実行の時に適法であった行為については、刑事上の責任を問われない旨規定し、遡及処罰の禁止を定めている。少年審判手続においては、少年審判の対象となる少年のうち犯罪少年(14歳以上20歳末満で罪を犯した少年)及び触法少年(14歳末満で刑罰法令に触れる行為をした少年)については、その前提となる行為は、その実行の時に犯罪構成要件に該当する違法な行為である。
無罪推定
263. 我が国の憲法、刑事訴訟法等の現行法令上明文の規定は存しないが、無罪推定は刑事裁判の基本原理とされており、検察官が公訴事実について挙証責任を負い、裁判官は、合理的な疑いを入れない程度に証明された、と認める場合にのみ有罪の判決をしている。
少年審判手続においては、職権主義的審問構造(256.(ii)参照)を採用している。したがって、非行事実について挙証責任を負う検察官は存在しないが、少年が、非行事実の不存在について挙証責任を負う訳ではなく、裁判官が、その取調べた証拠により、非行事実の存在の心証を得た場合に限り、保護処分に付することができることとされており、その心証の程度は、合理的な疑いを入れない程度に達することを必要とするのが一般的理解であって、刑事手続における無罪推定と同様の原則を採っている。罪の告知及び法的その他の援助
264. 罪の告知については、刑事訴訟法が、公訴の提起は公訴事実及び罪名等を記載した起訴状を提出してこれをしなければならない旨規定している(同法第256条)ほか、裁判所は公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならないと規定している(同法第271条第1頃)ことから、被告人は起訴状の送達を受けることにより、いかなる犯罪事実により訴追されているのかを知ることができる。
少年審判手続においては、審判開始前の家庭裁判所調査官による調査の段階でも罪の告知を行い、また、少年審判開始決定があった場合には、第1回審判期日に家庭裁判所の裁判官から告知する運用が定着している。
法的その他適当な援助としては、刑事訴訟法が、被疑者又は被告人の弁護人選任権を認めている。また、少年法は、児童及びその保護者に附添人選任権を認めているほか、少年審判については、保護者の立会いの下に審判が行われることとなっている。公平な審理
265. 我が国憲法は、独立かつ公正な裁判を確保するため、「すべて裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(憲法第76条第3項)と規定し、更に、裁判官の身分を保障している(憲法第78条、第79条、第80条)。また、刑事訴訟法は、被告人、被害者と一定の身分関係を有するなど、審理の公平につき疑いを生ずべき事由のある裁判官等が職務の執行から除斥される旨定めている。
少年審判に関しては、少年審判規則により、「裁判官は、審判の公平について疑を生ずべき事由があると思料するときは、職務の執行を避けなければならない。」(第32条)とされており、また、運用上、少年及びその附添人は裁判官の回避を求める申立てをなしうる。更に、審判の公平につき、疑いを生ずべき事由のある裁判官が関与してなされた保護処分決定に対しては、少年法に基づく抗告が認められている。供述又は有罪の自白の強要
266. 憲法は、公務員による拷問及び不利益供述の強要を禁止し、強制、拷問、脅迫等による自白の証拠能力が否定される旨規定するとともに、刑事訴訟法は、被疑者、被告人の供述拒否権を明記し、取調べを行う警察官、検察官、審理を行う裁判官に、被疑者、被告人に対する供述拒否権の告知を義務づけ、強制、拷問、脅迫等による自白その他任意にされたものでない疑いのある自白の証拠能力を否定している。上記の憲法の規定は、少年審判手続においても尊重されている。
警察における取調べについては、犯罪捜査規範により強制、拷問、脅迫など任意性について疑念をいだかれるような方法を禁止するとともに、特に、少年の場合は、少年の健全な育成を期する精神を基本に、他人の耳目に触れないようにし、取調べの言動に注意する等温情と理解をもって当たり、その心情を傷つけないように努めなければならないことを規定し、少年の特性が考慮されている。反対尋問、証人出席及び証人尋問
267. 刑事訴訟手続については、憲法第37条第2項が「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する」と規定しており、これを受けて刑事訴訟法は、被告人又は弁護人の証人尋問請求権、証人尋問の立会権及び証人尋問権を保障するとともに、反対尋問を経ない供述調書の証拠能力を制限している。
少年法は、刑事訴訟法中の証人尋問に関する規定は保護事件の性質に反しない限り、少年審判にも準用される旨定めており、少年審判においても少年の証人尋問権及び反対尋問権は十分保障されている。
また、証人出席を求めること等について、少年法は職権主義的審問構造(256.(ii)参照)をとっていることから、少年及び附添人からの直接的な証人尋問請求権に関する規定はないが、少年及び附添人は、証人尋問に関し、裁判官の職権発動を求めることができる上、一定の場合には家庭裁判所に職権証拠調義務が生じ、裁判官が合理的な理由なく証人を尋問せず、それが保護処分の決定に影響を及ぼす場合には抗告理由となる。上訴
268. 刑事訴訟法は、被告人の上訴権を保障し、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認、法令の適用の誤り、訴訟手続の法令違反や量刑不当等の事由がある場合には、第一審の判決について高等裁判所に控訴することができると定めるとともに、憲法違反、最高裁判所の判例違反等の事由がある場合には、高等裁判所がした第一審又は第二審の判決について最高裁判所に上告することができる旨定めている。
少年法は、保護処分の決定に対し、法令の違反、重大な事実の誤認、処分の著しい不当を理由とする抗告を認めており、また、憲法違反、最高裁の判例違反等を理由とする再抗告をも認めている。通訳の援助
269. 我が国裁判所においては、日本語を用いることとされており、刑事訴訟法上、刑事裁判において、国語に通じない者に陳述させる場合には、通訳人に通訳させなければならないとされ、その場合、通訳人は、裁判所に対し、旅費、日当、通訳料等の請求ができ、その支払いは国庫からなされる。また、少年法上、少年の保護事件については、家庭裁判所は通訳を命ずることができるとされ、刑事訴訟法の通訳に関する規定が準用されるとしている。なお、最高裁判所の判例は、公判廷で被告人に供述を求め、また、証人等を尋問する場合のほか、被告人に対し裁判等の趣旨を了解させるためにも通訳人を用いなければならないとしており、実務では、国語に通じない被告人のいる法廷ではすべて通訳人が用いられている。
プライバシーの尊重
270. 刑事訴訟法は、基本的人権の保障を全うしつつ、公共の福祉の維持と事案の真相を明らかにすることを目的とする旨規定し、また、少年審判手続については、手続は非公開とされ、記録の閲覧・謄写について一定の制限が課されている。更に、少年法は、家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならないと規定している。実際にも、家庭裁判所では、情報開示という社会的要請に配慮しつつも、少年事件の秘密性の保持を図るよう努めている。例えば、少年及び被害者が特定してしまうような表現は避ける、少年の情操を保護し、その更生の妨げにならないようにするために、動機や犯行経緯、態様などは簡潔で抽象的な表現にとどめる等の配慮をしており、これらの措置を通じて、少年のプライバシーの尊重に努めているところである。
271. 観護措置として少年鑑別所に収容された者については、明るく静かな環境に置くように努め、入所当初はなるべく単独室に収容することとしている。共同室に収容する場合には、その者の性格、経歴、入所度数、年齢等を斟酌して同一室に収容する者を決定し、トイレを区画して遮蔽する等の配慮をしている。また、衣類、寝具及び日常生活に必要な物品は貸与又は給与されるが、規律及び秩序の 維持上又は衛生上問題がないものについては、自弁の物品の使用が認められる等、居室を生活の場所としてふさわしいものとする種々の配慮をし、収容されている者のプライバシーを十分に尊重した取扱いに努めている。
272. また、拘置監に勾留された者に対しても、少年鑑別所と同様な種々の配慮をし、収容されている者のプライバシーを十分に尊重した取扱いに努めている。
司法上の手続に代わる措置
273. 少年審判手続開始後の措置としては、少年法に基づき、児童福祉法の規定による措置を相当と認める場合に事件を都道府県知事又は児童相談所長に送致した上で、児童を指導し、又は施設に入所させる等の措置をとっている。
| BACK / FORWARD / 目次 |
![]()
|
| ||||||||||