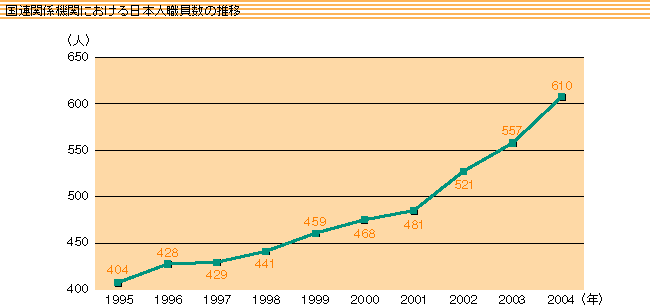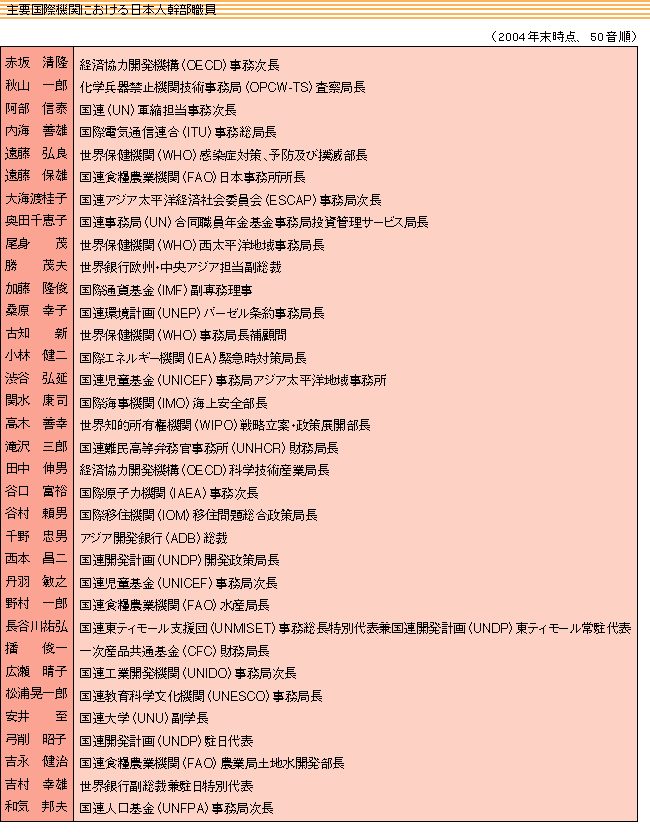2 国際機関で活躍する日本人
冷戦後の新秩序を模索する中でテロや紛争が頻発するなど、国際社会全体が政治・安全保障体制を脅かす諸課題への対応を迫られており、また、グローバル化が急速に進展する中で、環境、人権・人道問題、貧困、感染症等地球規模の諸問題への対応がますます重要になってきている。こうした中で、個々の国家から独立して、国際社会全体の共通利益のために活動している国連等国際機関の果たすべき役割はさらに重く、そこで働く国際公務員の任務と責任もますます重要なものとなってきている。
日本は、国連等国際機関における日本人職員数を増強すべく、優秀な人材の発掘や日本人職員の採用・昇進に向けて、国際機関に対して働きかけを行っている。また、若手職員のためのAE/JPO
(注3)等派遣制度の活用、国連事務局などの採用ミッションの受け入れを通じ、日本人職員の増強に努めている。その結果、国際機関の日本人職員は、着実に増加傾向にあり、その中には、選挙で選出された国際機関の長や、国際機関に就職し、生え抜きで活躍している職員など様々な職員がいる。また、若手から幹部職員に至るまでイラク周辺やアフガニスタンなどの紛争地域を含む世界各国の様々な分野において活躍している
(注4)。しかしながら、国際機関に勤務する日本人の職員数は610人(2004年現在)であり、これらの機関に占める日本の財政的貢献の大きさと比べて、依然として望ましい水準を満たしていない。引き続き、更なる人材発掘と働きかけを行っていく方針である。
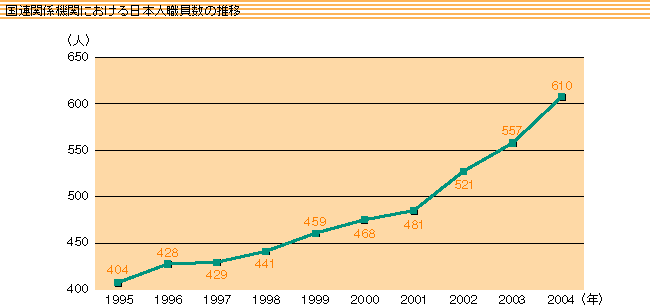
Excelファイルは
こちら
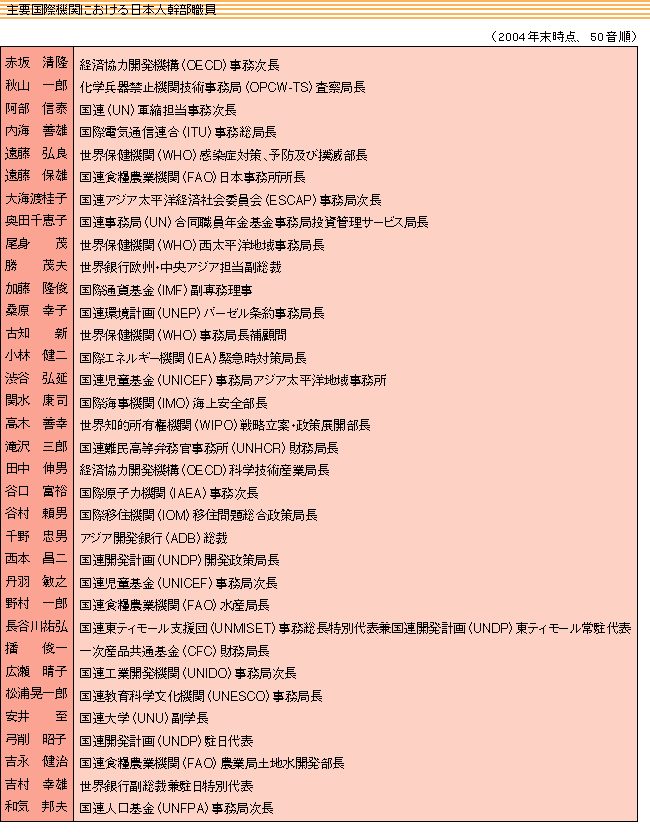
Excelファイルは
こちら
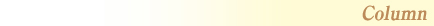
親善大使として開発の現場を訪ねて
現在、私はUNDP※1の親善大使として各国を視察しています。これまで、カンボジア(1999)、パレスチナ(2000)、ブータン(2001)、ガーナ(2003)、東ティモール(2004)を視察しました。初めは、このような大役を全うできるか不安もありました。しかし、私が親善大使を務めることで、少しでも国際協力を身近に感じてもらえればと思い、一生懸命取り組んでいます。
2003年に訪れたガーナでは、エイズ孤児の多いマンヤクロボ地区を視察しました。そこには、クイーンマザーと呼ばれる女性たちがいて、1人で6人もの孤児を引取って自分の子供と同じように育てていました。ガーナには「1人が富を得たら、それを貧しい人みんなに分け与える」という習慣があるのです。私は、先進国が失いかけている「心の豊かさ」について考えさせられました。また、エイズという深刻な問題を自分たちの手で解決しようと協力しあっている姿にとても感動し、私達としても、更に支援の手を差し伸べていくべきと感じました。
2004年には東ティモールを訪問しました。2002年に独立したばかりで、道路、学校、病院などの基本的なインフラがまだ整っていません。印象的だったのは、こうした環境下でも無邪気に遊ぶ子供たちの笑い声があることです。内紛が絶えなかった時期、子供は外で遊ぶことすらできませんでした。この光景を見て、平和を実感している人も多いでしょう。しかし、実際に子供たちに将来の夢を聞いても返事がありませんでした。子供たちの明るい未来のために、私達もできる限りの支援を行い、様々な産業を根付かせることが早急に必要だと感じました。
子供たちの無邪気さや可愛さは万国共通です。しかし、彼らの生活や未来はとりまく環境によって大きく左右されます。私は同じ子供を持つ母親として、世界の子供たちのために私達が何をすべきか、訴え続けていきたいと思います。
開発援助は、地味で時間がかかるという点で子育てに似ています。結果を出そうと焦らず、その国に相応しい開発を確実に進めていくことが大事です。これからも草の根の目線で見たことや感じたことを分かりやすく伝えて、国際協力の裾野を広げていきたいと考えています。
UNDP親善大使 紺野美沙子
※1 国連開発計画(UNDP:United Nations Development Programme)は、アフガニスタンのように紛争後の復興を支援したり、開発途上の国や地域が自立できるまでの援助活動を行っている。
テキスト形式のファイルはこちら
|
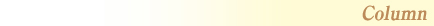
国際機関で活躍する日本人職員 ~長谷川UNMISET代表兼事務総長特別代表~
今世紀最初に誕生した国、東ティモールの地を踏んだのは、その独立から約2か月後の2002年7月15日でした。空港から政府庁舎に着くまでの約15分間、暴動によって荒廃した街中で、将来への不安を見せつつも自由を勝ち取った希望に充ちた人々の顔が印象的でした。24年間、平和を願い続けてきた人々の笑顔を絶やしてはならないと痛感した瞬間でした。
国連東ティモール支援団(UNMISET)は、同年5月に新しく誕生した政府の民主的かつ持続可能な政治行政基盤づくりを支援する任務を与えられています。また、法の支配を確立するため、警察官に対して、人権を擁護するための治安維持活動を行うだけでなく市民に信頼されるように訓練を行っています。このほか、新政府が円滑に機能するよう各省庁に専門家を派遣し、腐敗のない行政機能づくりを支援しています。
国連事務総長特別代表の重要な役割の一つは、東ティモールがより良い統治(ガバナンス)を行うための枠組みを形成する上で、国際社会の基準を満たすよう見守り助言する事です。私は、毎週、アルカティリ首相と会談し、日々直面する様々な問題や将来の国づくりについて助言をしています。また、中央政府の役人と地方の人々との対話にも参加し、市民社会のニーズを把握するよう努めています。復興開発の進捗と必要な支援を国連安保理に報告するだけでなく、現地の人々に国際社会の声を伝えるという大役を任されています。
私は国連開発計画(UNDP)常駐代表も兼任しているため、様々なプロジェクトの視察や鍬入れなどを理由に、グスマン大統領をはじめ政府要人と共に地方へ行く機会を作っています。ヘリで現場に向かう機中は、ディリにおける公務中には聞けない本音や忌憚ない意見を聞く事ができる絶好の外交の場となっています。
そんな私の国連外交を日本政府はいろいろな形で支えてくれました。例えば、インフラや公共施設、電力・水道供給施設の復旧と整備など、東ティモールの人々が人間らしい暮らしができるよう支援してくれています。また、自衛隊は平和維持活動の一貫として、主要幹線道路の維持補修を行い、地元の人々の経済波及に寄与しました。このほかにも、元兵士およびコミュニティのための復興・雇用・安定プログラム(RESPECT)などは、元兵士の不満を和らげる重要な役割を果たしました。これらの貢献によって築き上げられた東ティモール政府を含む多くの人々の日本人への信頼感は、多大に私の外交努力を支えてくれてきていると思います。
現在、国連安保理において、東ティモールでの国連平和維持活動を継続させるか否か討議されています。まだまだ山積する課題やハイチの教訓(※1)を心に留め、5月の安保理に臨みたいと思います。
執筆:国連東ティモール支援団代表兼事務総長特別代表 長谷川祐弘
※1 1991年に起きた軍事クーデターに対し、国際社会は国連安保理決議に基づく経済制裁を実施、多国籍軍が国連ハイチミッション(UNMIH)を展開した。民主主義が取り戻されたが、2004年武装勢力が活発化し、再び安保理決議による多国籍軍の介入が行われた。
テキスト形式のファイルはこちら
|
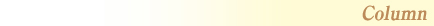
国際機関で活躍する日本人職員 ~和気UNFPA事務局次長~
私の国連職員としての生活は今年で35年目になりました。27歳のときユニセフに就職し、インドのニューデリーに赴任したのは1971年の1月でした。結婚したばかりで、その上ユニセフもインドも何も知らないで私の国際公務員としての生活がはじまりました。当時私はただ一人の日本人職員として、また将来の幹部候補生として上司から大変大事に扱ってもらったのを憶えています。すぐに北インド代表として一か月のうち10日間は州政府との交渉や村や保健所や学校を訪問し、援助プロジェクトの実施現場を見て回ったりしていました。
それから26年間ユニセフで勤務し、任地もバングラデシュ、ニューヨーク本部、バンコク東アジア地域事務所、パキスタン、ナイジェリア、東京事務所と変わり、緊急援助や物資の調達から長期社会開発計画に関連した仕事や資金の調達まで色々な経験をしました。
1997年にはアナン国連事務総長が新しい国連改革構想を打ち出したことを受けて、その実施のために国連開発グループ(UNDG)の事務局次長として出向することになりました。各国連機関が協力しチームワークで仕事をすることになり、新しいことばかりで私のアイデアも取り入れてもらうこともありました。
2000年の2月からは日本政府の推薦で国連人口基金(UNFPA)の事務局次長として働くことになりました。それから5年間が経ちますが国連最後の仕事を楽しんでいます。私が今重点的に押し進めているのは妊産婦の死亡率を下げることです。子どもの死亡率を下げることにはこの20年間かなり成果を上げてきましたが、最貧国で妊産婦の死亡率を下げることは失敗しています。男が最優先、そして子ども特に男の子、それから女の子、最後にお母さんという順番で妊産婦はいつも後回しというのが現状です。
妊産婦の死亡率を下げるのには、緊急産科ケア、妊娠中・出産時・産後の資格のある保健スタッフによるケアが重要です。それから家族計画を普及して望まれない出産を避ける事も大切です。出産の15%は危険が伴うと考えられていますので近くに医師と設備が整った病院があることも死亡率を下げるのに不可欠です。電話もなく交通機関も限られていて、手遅れで死んでいく母親がまだ沢山いるのは我々にも責任があると思っています。
それからHIV・エイズに感染する女性、特に若い女の子が多いので、HIVの感染予防に力を入れています。大変難しい仕事ですが手遅れにならないように世界中で特別の努力が必要です。
国連は自分の良心と信念を曲げないで自由に仕事の出来るよい職場だと思います。世界中から能力のある人が集まっていますし、競争はあっても地味に成果を上げている人もその貢献を認めてもらっていると思います。私はあと二年がんばって退官し、そのあとは後輩に任せ、次の世代の国際人の養成に力を入れたいと思っています。
執筆:国連人口基金事務局次長 和気 邦夫
テキスト形式のファイルはこちら
|