日本を含め世界の国々は国際社会が直面する様々な課題に対して、個別にあるいは地域協力を通じて国際機関とも協力しつつ対処してきているが、そうした中で近年、NGOをはじめとする民間レベルの活動の幅は拡がりを見せてきている。日本のNGO等も開発援助、緊急人道支援のほか、環境、人権、貿易、軍縮・不拡散等の分野において様々な活動を行ってきている。このようなNGO等は、地域社会や住民に密着したきめ細かい活動や迅速かつ柔軟な対応に適しており、その意味で国際社会においてますます大きな役割を果たすことが期待されている。
政府としても、このようなNGO等による活動の利点とNGO等の存在と役割の高まりを認識し、「開かれた外務省のための10の改革」において、NGOとの連携の強化を方針の一つとして掲げた。また、NGOとの関係強化は、一連の改革において常に論点となっており、「変える会」や「第2次ODA改革懇談会」の提言においてもその必要性が指摘されている。
このような動きを踏まえ、外務省はNGOとの連携を推進するために、2002年11月よりNGO担当大使を設置した。NGO担当大使はNGOと外務省の意見交換・情報交換の機会に双方の橋渡し役として参加するとともに、NGOとの対話・協力の機会が多く予定される国際会議等に関しても、NGOに対する側面支援を行っている(注5)。
一方、日本のNGOの多くは、主要先進国のNGOと比べ財政的・組織的基盤が脆弱であることから、NGOが国際協力において、より一層の活躍をするためには、その専門性や組織運営能力の強化が必要である。このような観点から、NGOの組織強化や人材育成などを支援するために、外務省や国際協力機構(JICA)、国際開発高等教育機構(FASID)が、様々なプログラムを実施している。
<開発援助分野>
NGOによる国際協力活動は、開発途上国・地域の多様なニーズに応じたきめ細やかな援助や、迅速かつ柔軟な緊急人道支援活動を実施できるという観点から、また、日本の顔の見える支援という観点からも、極めて重要である。
そのような認識に基づき、外務省は、1996年以来、基本的に年4回実施されていたNGO・外務省定期協議会について、2002年度より、全体会議に加え、ODA政策協議会と連携推進委員会の2つの小委員会を設立した。
「ODA大使館」については、日本のNGOが比較的多く活躍する開発途上国において、日本大使館、JICAや国際協力銀行(JBIC)の海外事務所とNGO等との間で2002年度より開始し、これまでに、カンボジア、バングラデシュ、ケニアなど12か国において実施している。
こうしたNGOの活動を支援するための資金協力形態としては、従来NGO事業補助金、草の根無償資金協力などがあったが、2002年度に日本NGO支援無償資金協力及び草の根技術協力を新設し、2004年度にはそれぞれ27億円、15.8億円の予算額を確保するなど、NGO支援の充実を図ってきている。このうち、日本NGO支援無償資金協力については、従来認められていなかったNGO本部経費も一部支援対象として含めるなど、支援対象経費を拡充した一方、資金の適正使用の確保のため全対象事業について外部監査を義務づけている。
また、NGOが行う緊急人道支援活動については、ジャパン・プラットフォーム(JPF)(注6)の枠組みを通じて、政府とNGOとの連携を深め、日本のNGOが迅速かつ効果的な活動を行うことができるよう2001年度より政府資金を拠出している(政府は2003年度には計27億円を拠出)。米英軍による対イラク武力行使の開始に際しても、JPFに参加する複数のNGOで構成する合同チームが、いち早くイラク・ヨルダン国境地帯で難民等に対する緊急医療体制を整えたほか、イラク国内においても、参加のNGO数団体が国内避難民支援(生活必需品等の配給)、病院、学校の修復などの活動を行ってきており、現在も支援活動を実施している。
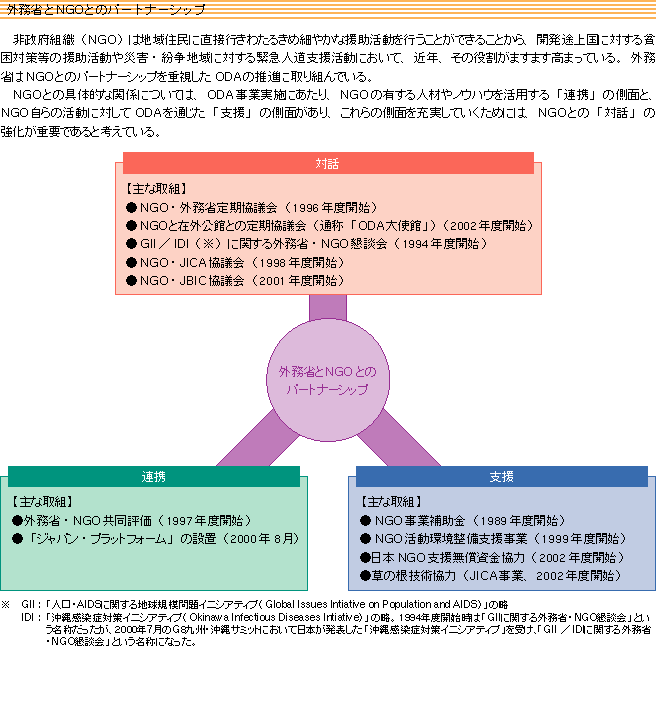
<その他の分野>
環境分野については、例えば、環境教育に関する率直な意見や情報の交換を行う機会を提供するという観点から、6月に東京で行われたアジア協力対話(ACD)のプライム・ムーバー・プロジェクト>(注7)として開催された「環境教育」推進対話では、各国政府関係者から学校教育を中心に政府が実施してきている措置や制度に関する報告が行われたほか、国際機関からは持続可能な開発のための教育に関する取組が紹介された。これに対し、NGOからは地域社会における活動が発表された。その上で、環境教育における政府やNGOのほか様々な主体の役割、連携、情報や知識の蓄積・交換、訓練、モニタリングや評価等について有益な議論が行われ、結果として、アジアにおける環境教育の問題点や今後の方向性が明確となり、参加各国の間で本件の取組の重要性が確認された。
人権分野では、児童の問題についてのNGOとの対話が例として挙げられる。外務省は、国際連合児童基金(UNICEF)との共催により、児童の権利条約の意義や目的について広報するとともに、現在日本で大きな社会問題となっている児童虐待、不登校、いじめ、少年犯罪等の問題について条約に基づいて議論する目的で、東京の国連大学において3月に「児童の権利に関する条約批准10周年記念シンポジウム」を開催したが、パネリストとして参加した有識者やNGO等からは、日本の児童を巡る問題の実態について率直な意見表明がなされた。その結果、同問題の解決にあたっては、政府だけでなく、市民社会など各種の部門が一丸となって取り組まなければならないとの共通認識が得られ、これを踏まえ、政府として同条約のより一層の実施に努めることとなった。
また、現在、将来新たな人権条約となることが見込まれる「障害者権利条約」(仮称)の交渉が国連の場で行われているが、各会合への日本の政府代表団には障害者自身が顧問として加わっているほか、日本の障害者にもNGOも国連の交渉の場に参加するとともに関連セミナーを主催するなど国際的にも顕著な活動を行って評価されている。
貿易面では、現在進められているWTO新ラウンド交渉を政府として成功裡に導くためには民間団体等の理解と協力を得ることが不可欠であるとの認識に基づき、9月に外務省主催で民間団体等を対象に7月のWTO新ラウンド交渉一般理事会決定に関する説明会を行うなど、昨年に引き続いて本件に関してNGOとの連携をとってきている。
軍縮・不拡散分野においても、外務省は「日本NGO支援無償資金協力」の助成を通じて、カンボジア、タイ、スリランカにおいて実際に地雷除去に携わっているNGOを支援している。また、大洋州諸国における小型武器問題の解決に取り組むべく、NGO等の参加も得て、8月に南太平洋地域小型武器セミナーを開催し、小型武器の非合法取引の防止に向けた法整備、武器の安全な保管や廃棄といった問題の解決に向けた地域協力及び市民社会との協力等について活発な議論を行うなど、小型武器の問題への取組にあたって、NGO等と緊密な連携をとってきている。