4 青年海外協力隊・シニア海外ボランティア
日本は、国民参加による国際協力活動を促進するために、青年海外協力隊派遣事業や、シニア海外ボランティア派遣事業の推進に取り組んでいる。これらは、現地の人々と共に活動しながら、途上国の経済・社会の発展に自らの技術、知識を役立てたいとする国民を途上国に派遣する事業である。
20歳から39歳を対象とした青年海外協力隊派遣事業は、1965年にフィリピン、マレーシア、カンボジア、ラオスのアジア4か国へ26名の隊員を派遣して以来、これまでに78か国に2万6,510名を派遣し、40歳から69歳を対象としたシニア海外ボランティア派遣事業は、1990年の事業発足以来54か国に2,101名を派遣(2004年12月末現在、青年海外協力隊員を69か国に2,654名、シニア海外ボランティアを53か国に775名、それぞれ派遣)している。
青年海外協力隊の協力活動は7分野142職種、シニア海外ボランティアの協力活動は9分野64職種にも及び(2004年12月末現在)、農林水産、土木建築、保健衛生、教育文化などの幅広い分野で活躍している。また、2003年からエイズ対策を新たな職種として設けるなど、途上国の要請に基づき、国際社会の課題に応えるきめ細かな活動を行っている。
青年海外協力隊やシニア海外ボランティアは、途上国の発展に貢献するとともに、現地の人々と共に考え、共に実践することにより、「顔の見える援助」として、日本と途上国との相互理解や友好親善の促進に大きな役割を果たしている。また帰国後は、その生きた経験を、教育の現場やコミュニティレベルで共有するなど、様々な形で社会に還元しており、そのユニークな活動は受入国をはじめ国内外から高い評価を得ている。
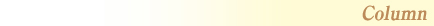
災害時にこそチャイルド・プロテクション(子どもの保護)活動を
スマトラ沖大地震・インド洋津波で大被害を受けたアジア地域。被災地では、災害発生直後から、世界各国のセーブ・ザ・チルドレンのスタッフによる緊急援助チームが編成され、食糧や物資の配給、被災した子どもたちの保護、漁業や観光業などで生計を失った人たちへの支援を行っています。
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのスタッフが派遣されたのはスリランカ南部の町、マータラ。美しいビーチが広がるのどかな地域でしたが、津波は一瞬にして多くの人の命を呑み込み、生き残った者の人生もすっかり変えてしまいました。家を壊された多くの人たちが学校や寺院、またはグラウンドに設置されたテントなどに住んでいます。私たちはそうした避難キャンプを訪れ、米や乾燥麺などの食糧、石けんやタオルなどの日用品、鉛筆やノートなどの学用品を届けてきました。
避難キャンプを訪れると、子どもたちが笑顔で駆け寄ってきて、配給物資の積み下ろしなどを手伝ってくれます。しかし、その屈託のない笑顔の裏で津波によるトラウマを抱え、不便な避難所生活で相当なストレスを負っていることがわかります。ある村で出会った少年は津波で母親と兄弟を失ったといいます。彼が握り締めていた3枚の遺体の写真がとても痛々しく思えました。今回の津波で親を失った子どもの数はスリランカだけで3200人以上にもなるのです。
こうした子どもたちの心の傷を癒すには、思いっきり遊ぶことが一番の薬です。私たちはボールや縄跳び、ゲーム、塗り絵、絵本などを避難キャンプに住む子どもたちへ贈り、時には一緒に遊ぶことで、子どもたちが早く普通の生活に戻れるように支援しています。
一方、津波で多くの漁師が船や魚網を失い、ホテルやレストランなどで働いていた人たちも生計を失いました。セーブ・ザ・チルドレンでは、そうした被災者を雇用し、学校や道路沿いにたまった瓦礫やごみを撤去したり、家の再建に必要なブロックを製造するなど、短期的に現金収入を得てもらうプログラムも開始しました。
日本国内でも多くの団体・企業・個人の方々から被災地への支援金が寄せられています。被災地の復興には時間が必要なのです。セーブ・ザ・チルドレンとして今後も、子どもを中心に被災者らを支援し、復興に寄与していきたいと考えています。
執筆:社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 武田和代
テキスト形式のファイルはこちら
|