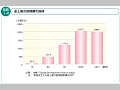本編 > 第I部 > 第1章 > 第2節 > (2) 主要な論点
(2) 主要な論点
以上の会議において繰り返し議論されたのがミレニアム開発目標(MDGs)の達成、開発資金の確保、援助の効率化、良い統治、援助の選択的実施、官民パートナーシップといった問題です。こうした点は、DACや世界銀行とIMFの年次総会といった開発に関する国際的な議論の場においても取り上げられ、開発を巡る主要な論点となっています。
図表I-6 国際的な開発目標の進歩表

ミレニアム開発目標(MDGs)の達成
一連の国際会議の合意文書では、繰り返しMDGsが国際社会共通の目標であることが確認され、被援助国、援助国、国際機関などが協力してMDGsを達成するための取組について議論しました。
第一に、MDGsの達成に向けてまず必要となるのは、MDGsの達成状況のモニタリングと途上国における統計整備です。全ての途上国において定期的にMDGsの達成状況を確認することが不可欠であり、このために、国連は、2005年より5年毎にMDGsの達成状況に関する包括的な報告書(国連事務総長報告書)を作成し、また、国レベルでのモニタリングを行うため、国別に「ミレニアム開発目標報告書」を作成することとしています。しかしながら、このようなモニタリングを適切に行うためには現時点の開発に関する国内統計は特に最貧国において完全とはいえず、国際社会は途上国の能力向上のための支援を強化する必要があります。
第二に、MDGsの達成に向けた具体的な戦略に関する研究が必要です。これは、国連、世銀が中心になって推進していますが、研究成果を各途上国におけるMDGs達成のための戦略立案に適切に活用していくことが重要です。
第三に、先進国、開発途上国を問わず世界中全ての人々がMDGsに対する理解と支持を深め、その達成に向けて様々な組織や団体が自発的に幅広い連携を行うことを確保することが必要です。このために、国連では、国連開発計画(UNDP)が中心となって「ミレニアム・キャンペーン」を行うこととしています。
開発資金の確保
MDGsの達成には現在の援助総額をはるかに越える資金が必要とされています。例えば、国連は年500億ドル、世銀は年400~600億ドルの追加的な資金が必要であると見積もっています。これに対し、最近の全世界から途上国へのODA額は、年500億ドル前後で推移しています。こうした状況を背景に、一連の会議では、資金の問題が活発に議論されました。その結果、途上国の開発を進めるためには、途上国の国内資金やODAのみならず海外直接投資等の民間資金や貿易などのあらゆる資金を動員することの重要性が確認されました。
従って、ODAが途上国の開発において果たしている役割を考える際には、途上国に対する資金全体の流れや貿易などの世界経済全体の動きの中で考えていくことが大切です。例えば、2001年カタールのドーハで開催された世界貿易機関(WTO)第4回閣僚会議において立ち上げられた新ラウンドが「ドーハ開発アジェンダ」と呼ばれているように、WTOへの途上国の加盟国が増加する中で貿易交渉における開発の視点がますます重視されるようになっています。
また、DAC諸国及び国際機関から途上国への資金の流れを見てみますと、長期的には、グローバル化の進展の中で対外投資が大幅に拡大しており、民間資金の占める割合が相対的に増大しています。しかし、96年を境にして、途上国への民間投資が急減しており、比較的安定した規模を保ってきたODAが占める割合が再び増加に転じています。加えて、ODAは、以下の理由により、途上国にとって極めて重要な開発資金となっています。
もとより途上国の貿易、投資の活性化のためにはWTO等における交渉を通じて国際的な貿易・投資システムの改善が図られることが重要ですが、それに加えて途上国の能力向上のための支援を行う必要もあります。わが国もODAを活用して途上国の貿易、投資を活発化するための制度構築や人材育成のための支援を行っており、ヨハネスブルグ・サミットにおいては、第10回国連貿易開発会議(UNCTAD)総会で行った公約を拡充し、貿易関連人材育成を2000年度から5年間で4,500人に対して行うことを表明しました。
また、一般的に、民間資金の投資先は、インフラ分野、中でも、通信、エネルギー等、利益が期待できる分野に偏りがちです。90年以降、民間資金の約80%は6つの上位中進国に流れており、貿易・投資の利益は国によって大きく偏っています。従って、教育、保健などのいわゆる社会セクター分野の支援や、道路・港湾など採算が合いにくく民間資金の期待できないインフラ分野などの、途上国の社会・経済基盤整備を支援するためには、民間資金のみでは不十分であり、より公共性、政策性が高いODAが依然重要な役割を担っています。
さらに、依然として産業基盤が脆弱で貿易による利益の確保すらままならない国や民間投資が十分に集まらない国にとって、公的資金は貴重な開発資金となっており、途上国の中には対外援助の総額が国家予算の半分以上に達する国もあります。
図表I-7 DAC諸国および国際機関から途上国への資金の流れ

債務問題
多くの途上国は、開発資金を確保するため、相当規模の対外借入を行ってきました。それらの国の大半は、借入に対する返済に充てる外貨を一次産品の輸出によって調達するしかなかったのですが、80年代以降の一次産品価格の下落やオイルショックによる輸入価格の高騰により対外収支が悪化し、多くの国は債務の返済困難に陥りました。
こうした経済状況を打破するため、80年代より、IMF・世界銀行の支援の下、肥大化した政府・公共部門の縮小と自由化・規制緩和を伴う構造改革を通じた経済体質の改善が多くの途上国において進められ、一定の成果を上げてきましたが、必ずしも所期の効果を上げられない国もありました。加えて90年代の冷戦構造の崩壊と民主化の進展に伴う政治の流動化・不安定化、民族紛争の激化が表面化し、この影響により経済情勢も急激に不安定化し、債務問題が再び表面化しました。こうした重い債務負担に悩まされている国は、重債務貧困国(HIPCs:Heavily Indebted Poor Countries)と呼ばれており、2002年時点でIMF及び世界銀行によりアフリカを中心に42か国がHIPCsと認定されています。
途上国の発展を妨げる債務負担は、人道的にも国際社会の平和と安定の確保の観点からも見過ごすことのできない問題であり、国際社会は、従来の取組に加え、99年、HIPC諸国の債務を持続可能なレベルにまで低減することを目標とした「拡大HIPCイニシアティブ」を承認しました。同イニシアティブでは、ODA債権については67%から100%削減に、適格な非ODA債権については80%から原則90%削減にそれぞれ削減幅が拡大されるといった合意がなされました。
一連の会議においては、この拡大HIPCイニシアティブの迅速かつ効果的な実施の重要性が繰り返し強調されました。また、G8カナナスキス・サミットでは、HIPC信託基金に最大10億ドルの資金不足が生じることを認識した上でG8の負担分を拠出することが決定されました。わが国は、公的二国間債権者として、同イニシアティブの下、既に決定時点に到達した26か国に対して48億ドルに上る債務救済を行うこととしており、G8諸国中最大(G8による債務救済額全体の約4分の1に相当)の貢献をしているほか、HIPC信託基金に対しても、2002年10月に、従来の2億ドルに加えて、5,600万ドルの貢献をすることを表明しました。
図表I-8 途上国の債務額の推移
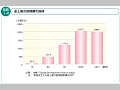
図表I-9 パリクラブ等における債務救済措置の変遷

援助の効率化
すでに説明したとおり、貧困削減は単に所得の問題だけでなく多面的な問題であるとして包括的な開発アプローチの必要性が指摘され、国連におけるミレニアム開発目標(MDGs)の策定や世界銀行による包括的開発の枠組み(CDF)や貧困削減戦略文書(PRSP)の動きに繋がっています。このため、経済協力開発機構の開発援助委員会(OECD-DAC)を始めとする国際的な開発に関する議論の場において、上述のPRSPをいかに実施し、MDGsを達成するかが議論されています。特に、援助吸収能力が極めて限られている途上国において、いかに援助効果を高めていくかとの観点から、これまでの援助手法を大幅に見直す動きが顕著になっています。より具体的には、[1]これまで各援助国が個別に実施してきたプロジェクト型の援助に対し、個々のプロジェクト・レベルでの成果は達成されてもマクロレベルの開発効果に繋がっていないのではないか、[2]援助を実施する際、指標の設定やモニタリング・評価を強化してより結果を重視したアプローチをとるべきではないか、[3]援助国や国際機関毎に異なる手続きは、途上国に過度の負担をもたらしているのではないかといった問題提起がなされています。
英、オランダ、北欧諸国などは、途上国側のオーナーシップ向上のために、対外援助を一つの基金(コモン・ファンド)にプールし、途上国の財政を直接支援(財政支援)するとともに、共同モニタリングを強化し、支援を行うすべての援助国の手続きを抜本的に見直すべきとの主張をしています。他方、日・米・仏・独等は、援助効率の観点からより協調的な援助を行うとの基本的方向性には賛同しつつも、プロジェクト型援助は有効であり、個々のプロジェクト型援助と全体の計画との整合性を高め、それぞれの途上国の特性に応じてプロジェクト援助やコモン・ファンドを含む多様な援助形態を適切に組み合わせていくことが重要との考え方に立っています。
もっとも、援助の現場では、先ほど述べた国々がそれぞれの主張に固執している訳ではなく、協調の努力が行われています。すなわち、行財政能力が不十分で、開発計画が十分に精緻でない途上国や、国家予算に占める援助の割合が小さい国においてはプロジェクト型援助が中心となっており、現在、コモン・ファンドや財政支援といった新しい援助手法が試みられているのはアフリカ諸国を中心に一部の国です。そのため、依然として多くの援助国や国際機関がプロジェクト型援助を行っていますし、また、わが国や米国も途上国側の十分なアカウンタビリティが確保されており、適切かつ効果的と考えられる場合は、タンザニアやウガンダのようにコモン・ファンドへの参加や財政支援を行っています。
囲みI-8 DAC援助手続き調和化タスクフォース
囲みI-9 援助のアンタイド化
囲みI-10 SPA(Strategic Partnership with Africa)
良い統治(グッド・ガバナンス)
良い統治とは、国の政治、経済、社会運営のあり方について、政府が開発の促進と国民の福祉向上を目指して努力し、効果的・効率的に機能しているか、また、そのために適切な権力の行使が行われているか、さらに、人権の保障が確保されているかなど国家のあり方を問題とする概念です。この概念は、民主的な政治体制(議会制民主主義)、法の支配、説明責任を果たす効率的な政府、政府による適切な情報公開、腐敗や軍事支出の抑制、市民社会の存在、男女平等な社会、人権の保障といった要素を含んでいます。良い統治は、途上国の開発を効果的・効率的に進める上で不可欠なものであり、また、開発の結果得られた「成長の果実」(富)が、貧困層も含めて国内に公正に再分配されるためにも必要なものであると考えられています。
一連の会議では、良い統治を巡り、議論が紛糾しました。つまり、先進国側が、開発援助が有効に使われるためには、良い統治が必要であるとして、援助供与の前提として途上国側の国内改革が必要であるとしたのに対し、途上国側は、良い統治を確保する上では人的資源の確保・育成や制度の構築といった能力の向上、さらには様々な分野における法制度の整備などが必要であり、そのためには援助が必要であると主張し、「援助が先か、良い統治が先か」を巡り交渉が一時中断する事態となりました。
援助の選択的実施
G8カナナスキス・サミットの過程で開発に関し最も大きな議論を生んだ論点の一つが「援助の選択的実施」の問題でした。G8アフリカ行動計画では、アフリカ開発のための新パートナーシップ(NEPAD)の目的を支援するため、良い統治、経済成長及び貧困削減に向けた政策の追求などを約束するアフリカ諸国に対しG8各国が支援を強化することが合意されました。
こうした考え方が出てきた背景には、次の2つの理由があります。一つは、良い統治が確保されていない国では援助が効果的に活用されてこなかったとの反省から、援助が効果的・効率的に活用される国、分野のみに援助を行うことは、援助効果の改善に繋がるという理由です。もう一つは、改革を行わない途上国は援助を享受できないか削減されるという方針を先進国が明示的に途上国側に打ち出すことにより、途上国側の改革を促すことができるという理由です。
2002年3月に米国が打ち出した50億ドルの開発援助増額イニシアティブ(ミレニアム挑戦会計)注)は、良い統治、人への投資(教育・保健)、健全なマクロ経済政策への公約を実行している国にのみ供与する旨表明している点で援助の選択的実施を明確に掲げています。
また、同年4月には、世界銀行が、開発委員会において基礎教育に関するファスト・トラック・イニシアティブ(FTI)を打ち出しましたが、これも援助の選択的実施に基づいています。同イニシアティブは、万人のための教育(EFA)行動計画に基づき、対外援助なしにはEFAの達成が困難な88の途上国から、一定の基準を満たす国を選択し、援助を集中させるものです。対象条件として、貧困削減戦略文書(PRSP)が2002年末までに完成しており、かつ教育分野の国家計画が存在する国と未就学の児童人口が多い国が考慮された結果、23か国がFTI対象国として選定され、現在、パイロット・フェーズが行われています(FTIの詳細については、第2章第5節(1)を参照)。
他方、こうしたアプローチに問題があることも指摘されています。援助が効果的に使われるか否かは、いくつかの指標のみで常に機械的に判断できるものではなく、結局は国毎、分野毎にケースバイケースで考慮しなければいけません。また、そもそもこうした手法により援助が供与されなくなったり削減される国が、援助を必要としていないわけではないことも明らかです。
従って、援助国の間では援助の選択的実施という考え方は一般論として共有されていますが、これまでのところ、具体的な支援強化対象国や支援内容については、各国がそれぞれの基準に基づいて個別に決定することとなっています。また、汚職や民主化等の良い統治(ガバナンス)に関して問題がある国、紛争状態にある国を始め、援助の選択的実施の対象にならないと判断された国に対しても、引き続き援助を行うべきであるという点について、援助国・国際機関の間で見解が共有されており、経済協力開発機構の開発援助委員会(OECD-DAC)と世界銀行が連携し、選択的実施の対象から漏れる可能性がある国々(Poor Performersと呼ばれる)に対する効果的な援助方法について議論がなされています。
わが国は、これまで92年のODA大綱の原則に基づき、開発途上国の民主化、市場経済化、基本的人権の保障状況等にも十分注意を払いODAを行ってきました。一方、わが国は援助を通じて開発途上国の能力向上を図ることも重要であると考えており、統治能力を始めとした能力向上のための支援も重点的に取り組んでいます。
官民パートナーシップ(PPP:Public-Private Partnership)の進展
開発における官民の連携が、ますます活発に行われるようになってきています。この背景として、第一にNGOを始めとした市民社会が開発途上国の開発の現場で、援助の担い手として益々重要な役割を果たすようになったことが挙げられます。また第二に、ヨハネスブルグ・サミットに約8千人ものNGOが参加したようにNGOが国際的な場で存在感を増していること、さらに、ODAを始めとした公的な開発資金が伸び悩む中、NGOを含む民間資金の動員が重視されるようになっていることがあります。
こうした中、各国政府は、国際会議の政府代表団にNGOや企業関係者を含めることで連携を強化するとともに、政府とNGOが対等なパートナーとして会議の周辺行事を開催したり、官民が共同でイニシアティブを発出するといったことが頻繁に行われるようになっています。また、2002年1月に正式に発足した世界エイズ・結核・マラリア対策基金には、最高意思決定機関である理事会に政府に加え、NGOや財団などが正式メンバーとして参加しています。
以上のようなNGOとの連携の強化に加え、最近は、民間投資や貿易が開発に果たす役割の重要性への認識が高まっていることから、その担い手である民間企業と政府がいかにパートナーシップを形成して途上国の開発を進めていくかが開発上の大きな課題となっています。2002年8月のヨハネスブルグ・サミットでは、官民パートナーシップに基づく膨大な数の開発関連事業が一つの冊子にまとめられ、約束文書として、会議の公式の成果物として採択されたことは既に述べたとおりですが、その中にはNGOのみならず民間企業がパートナーとして参加しています。また、サミット会場には企業関係者が多く参集し、周辺行事を通じて環境に優しい最先端の技術を紹介しました。

 次頁
次頁