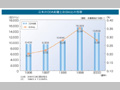第2章 > 第3節 > 2 2001年における重点事項
【地域別 ~アジアを中心とする世界との共生~】
〈アジア〉
アジア地域は、日本にとって歴史的・経済的・文化的に最も密接な関係にあり、その総合的な関係の深さによりODAの最重点地域となっている。現に2000年度の実績でも二国間援助の半分以上に当たる52.3億ドル(約54.8%)がアジア地域に供与された。
東南アジア諸国連合(ASEAN)地域については、アジア向け援助の59.2%を占め、特に重点を置いている。ASEANでは、新旧加盟国間の経済格差の是正が今後のASEANの統合強化や地域の安定を推し進めるための重要な課題となっている。こうした中、日本は二国間支援のほか、域内協力や南南協力の促進に積極的に協力するとともに、同地域において比較的開発の遅れているベトナム、ラオス、ミャンマーの各国について、長期的視点から市場経済化移行支援の実施、さらには貧困削減、基礎生活支援といった社会分野での援助を実施している。
特に、ベトナムの市場経済化に向けた政策提言を行う市場経済化支援計画策定調査(いわゆる石川プロジェクト)は、1995年8月から開始され、2001年3月をもって終了したが、日本の政策支援型援助の先駆けとなるものである。
1997年のアジア通貨・金融危機により深刻な影響を被り、日本を始めとする国際社会の支援を受けて経済建て直しの途上にあるインドネシアでは、最近になって実体経済が持ち直しの兆しを見せている。こうした中、日本は、2001年11月に行われた支援国会合(CG会合)の際に、インドネシア経済が安定的な回復軌道に戻り、更なる成長を実現するための中長期的視点に立った支援として、総額約417億円の新規円借款の供与を表明した。また、インドネシアにとって重要な政策課題について両国間で対話の幅を広げるために、日本の学識経験者で構成されるインドネシア経済政策支援チームを中心として、経済政策支援プログラムを実施していくことになった。
これらに加え、小泉総理大臣は、2002年1月のASEAN訪問の際、東アジア地域全体の開発について、未来のための協力として、ASEANに日本、中国、韓国を加えた枠組みで新たな開発政策を考える東アジア開発イニシアチブ(IDEA)の開催を提案した。
中国に対するODAについては、日本の厳しい経済・財政事情、中国の経済発展に伴う開発課題の変化や近年の日本国内における種々の批判を受け、対中ODAのあり方の見直しを行った。その結果、2001年10月に、より効果的・効率的な対中ODAの実現のため、今後5年間を目途とした対中経済協力のあり方の指針として、対中国経済協力計画(注1)を策定した。
南アジアにおいては、インド及びパキスタンに対し、1998年5月の両国による核実験以来、ODA大綱の原則に鑑み、新規の円借款及び緊急・人道的性格の援助並びに草の根無償資金協力を除く新規の無償資金協力を停止する措置をとってきた。しかし、米国同時多発テロ後の10月、核不拡散分野での進展、国際的なテロへの取組等、種々の要素を総合的に考慮し、両国への措置の停止を発表した(アフガニスタン周辺国支援に関しては、第1章2(3)を参照)。
〈アフリカ〉
アフリカは、世界で最も貧困人口の割合が高く、また、紛争や感染症、累積債務など困難な課題が集中している地域であり、日本は、その状況改善に積極的に取り組んできている(2000年の日本の対アフリカODAは、9.69億ドル、二国間援助の10.1%)。
日本は2回のアフリカ開発会議(TICAD)を開催し、アフリカ諸国の自助努力とそれを支援する国際社会のパートナーシップの重要性を提唱し、2001年12月には、TICADIIIに向けた準備として、TICAD閣僚レベル会合を開催した。具体的には、これまで日本は、1998年のTICADIIの際に発表した「今後5年間で教育・保健・水供給分野で900億円の無償資金協力を実施」するとの約束に従い、2001年12月までにアフリカ諸国に対し532億円を供与してきている。これにより、約31万人のアフリカの学童が教育機会を享受し、また、約270万人が安全な水の供給を受けるなど着実に成果を上げてきている。
日本のODA実績と対GNI比の推移
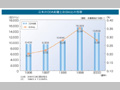
ケニア北部の難民キャンプを訪問する櫻田外務大臣政務官(4月)

【分野別 ~地球規模の課題への対応~】
〈感染症対策〉
国境を越えて広がりを見せるエイズ等の感染症は、開発途上国の人々の健康と労働能力に深刻な影響を及ぼし、開発の大きな阻害要因となっている。こうした認識の下、日本は保健医療分野を重点分野の一つとして取り組んできており、2000年ODA実績ではこの分野に対し、全ODA実績の約16%に当たる22.2億ドルを拠出している。
2001年は、4月にナイジェリアでエイズ、結核、その他感染症に関するアフリカ・サミット、6月に国連エイズ特別総会、そして7月にジェノバ・サミットが開催されるなど、感染症対策に関する議論が活発に行われた。
このうち、国連エイズ特別総会では、森前総理大臣が沖縄感染症対策イニシアチブ(注2)の意義、及び同イニシアチブに基づき(その時点で)既に約7億ドルの具体的な支援を実施してきたことなどの日本の取組を発表し、各国から高い評価を得た。さらに、日本は、ジェノバ・サミットの際に合意された世界エイズ・結核・マラリア対策基金(GFATM)に米国、英国、イタリア等とともに2億ドルの拠出を決定した(第1章6(5)を参照)。
〈地球環境問題〉
環境問題は、開発途上国の問題にとどまらず、国際社会全体で取り組むべき課題である。日本はこれまで環境分野で積極的にODAを実施してきており、2000年度では、日本の環境ODAは援助の約32%に当たる約4500億円を占めている。
地球温暖化問題については、2001年、気候変動枠組条約第6回締約国会合(COP6)再開会合及び第7回締約国会合(COP7)が開催された(第1章6(4)を参照)。日本は、1997年の気候変動枠組条約第3回締約国会合(COP3)の機会に打ち出した京都イニシアチブ(注3)に基づき、温暖化対策関連支援で毎年総額約24億ドルに上る二国間ODA事業を進めており、例えば、1998年度から3年間で約4600名の温暖化対策関連の人材を育成する等の具体的成果を上げてきている。
〈基礎教育〉
教育は国造りにとっての基盤であるにもかかわらず、世界では2000年時点でいまだ1億1000万人以上の子供が初等教育すら受けることができない状況にある。こうした中、日本は2000年のODA実績として8.9億ドル(6.4%)を教育分野に当ててきた。
その中でも、基礎教育分野では、2000年の世界教育フォーラムで採択されたダカール行動枠組み(注4)の目標を追求する最善の方法についてG8首脳に対し助言を行っていくため、2001年のジェノバ・サミットの際、G8の上級専門家からなる作業部会の設置が合意される等国際的な動きがある。日本はこれまでも学校建設等のハード面の支援のみならず、技術協力を通じたソフト面の支援も実施してきている。近年の支援例としては、2001年、ベトナムにおける初等教育セクターの包括的なプログラム作りについての開発調査の実施が挙げられる。これは、日本として初めて一国の教育計画策定(組織、制度構築等を含む)を支援する試みである。

 次頁
次頁