第4節 新たな領域における取組
衛星通信やインターネットの普及によって私たちの生活が大きく変わったように、国際協力が必要とされる領域も、小さな農村から宇宙やサイバー空間へと広がっています。また、海洋においても、海上テロや海賊対策といった新たな国際社会の課題に、より戦略的に対応する形での途上国支援が進んでいます。
1. 宇宙空間における取組
宇宙技術を利用した途上国支援には、様々な形があります。日本が取り組んでいる例では、自然災害管理、森林資源管理、流域管理、分析・計画立案能力の強化、地形図作成などがあり、衛星から送られる情報が、途上国の防災や環境保護、人材育成などに役立っています。災害が起きたときには、衛星から送られる広範囲の気象情報や被害状況が、避難指示や被災地の復旧活動に役立つ貴重な情報になります。また、気候変動に影響を与える森林面積や植生の変化も、衛星によって一目で把握することができ、政策や方針決定の参考にすることができます。
個別の支援例では、2010年の豪雨で、インダス川が氾濫し、建国以来最大の洪水被害に見舞われたパキスタンに対し、2011年7月、国連教育科学文化機関(UNESCO(ユネスコ))と連携して防災・災害復興支援無償資金協力「洪水警報および管理能力強化計画」を実施しています。この協力を通して、パキスタンにおける洪水予測システムの導入、洪水ハザードマップ作成およびそのための人材育成などを行っています。また、この事業には宇宙航空研究開発機構(JAXA)が協力し、衛星降雨データの提供、地球観測衛星「だいち(ALOS)」による地表の標高情報作成、2010年の洪水時の氾濫地域の検出などを支援しています。インダス川流域に位置する同国では今後も同規模の洪水被害が予想されるため、地域住民に対する洪水情報の確実な伝達、政府の洪水予測・警報能力の向上に役立つことが期待されます。
また、2011年に大洪水が発生したタイでも、JICAが1999年に策定協力したチャオプラヤ川流域マスタープランの見直し調査が、衛星による洪水の観測画像などを活用して進められています(タイ洪水についてはこちらを参照)。
災害への対応だけではなく、途上国の環境保護にも衛星画像が活躍しています。ブラジルのアマゾン森林保全・違法伐採防止のためのALOS衛星画像利用プロジェクトは、違法伐採の監視能力向上を目的とした事業です。衛星情報には雲の影響を受けない利点があり、画像を解析して広大なアマゾンのどの地域で森林が減少しているかを特定し、取り締まりに必要な情報を配信して違法伐採による森林減少を抑制します。日本の支援によって、これまでブラジル政府が対応できなかった通年のモニタリングが可能になりました。協力が始まった2010年8月から2011年7月の1年間で、アマゾン熱帯雨林の伐採面積(合法伐採、違法伐採をともに含む)は11%減少しています(アマゾン森林と衛星データについてはこちらのコラムでも紹介されています)。
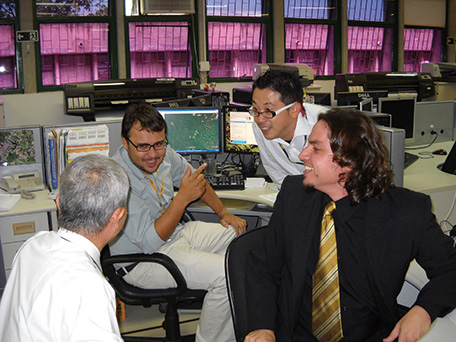
日本はブラジルとともに人工衛星を用いてアマゾン森林の違法伐採の発見に取り組んでいる(写真:JICA)
2. 海洋における取組
ODAを利用した海洋での途上国支援はこれまでにも各国に対して行われていますが、近年は、テロ対策や海賊対策など日本の国益に直結する海上交通路の安全確保の観点などから、より戦略的にODAを利用する形での支援が進んでいます。とりわけ、海の安全を守る海上保安分野については、2000年代まで支援の中心だったシンガポール・マラッカ両海峡周辺の東南アジア地域から、近年海賊事案が頻発している東アフリカ周辺のインド洋へと広がっています。
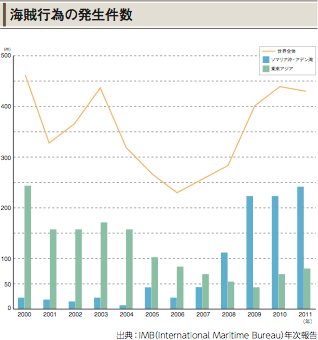
東アフリカ周辺(ソマリア沖、アデン湾)では、2007年まで50件以下だった海賊事案の発生件数が急増し、2009年以降は3年連続で200件を超えています。各国が軍艦・軍用機を派遣して商船の護衛活動と海上警戒監視活動を強化しており、日本も2009年から海上保安官が乗船した海上自衛隊の護衛艦2隻と哨戒機2機を派遣しています。ODAによる支援では、2009年に国際海事機関(IMO)が招集したジブチ会合で採択された「ジブチ行動指針」に基づき、IMOが設置した基金に1,460万ドルを拠出し、イエメン、ケニア、タンザニアに海賊情報共有センターを設置して周辺国間で海賊発生情報の共有を促すとともに、ジブチにソマリア周辺国(ケニア、タンザニア、セーシェル等)の海上法執行能力向上のための訓練センターを建設しています。また、JICAは、ジブチおよび周辺国の海上保安機関職員を招聘(しょうへい)して海上犯罪取締りに関する研修を実施しているほか、ジブチ沿岸警備隊の能力拡充のための支援を行っていきます。
こうした海上保安分野の支援は、海洋国家である日本の得意分野でもあり、特に海上保安の専門家である海上保安庁職員などの知識や経験を活かした技術協力支援に、途上国からの期待が寄せられています(コラム「国際航路を守るマレーシアの『海猿』たち」参照)。

マレーシアの海上保安機関の巡視艇(写真:JICA)

海上保安部本羽田特殊救難基地での研修(写真:JICA)

海上保安庁での研修で、火災発生時に空気呼吸器を装着する訓練に参加するアフリカ人研修生(写真:JICA)
3. サイバー空間の取組
急速に発展した IT技術は、いまや生活のあらゆる部分に浸透し、社会基盤として必要不可欠となっています。ITの重要性が増す一方、サイバー攻撃や情報漏洩(ろうえい)が国民の生活や経済活動に大きな打撃を与える可能性も大きく、サイバー空間における情報セキュリティ対策が差し迫った重要な課題となっています。
しかし、国境がないサイバー空間においては、日本国内の対策だけでネットワーク環境の安全を確保することはできません。たとえば、日本企業の情報セキュリティ対策がどれだけ進んでも、ビジネスパートナーである諸外国の企業から情報が漏洩するかもしれません。途上国のIT環境の安全強化を図ることは、日本の企業などのビジネスや投資環境改善に直結しています。
この分野での支援は、JICAがカンボジアやフィジーで行った、情報セキュリティ対策のためのコンピュータ緊急対応チーム(CERT)設立のための技術協力があります。加えて、途上国に対しては、業務の効率化や透明化などを目指す「電子政府」推進のためのセキュリティ強化研修など、日本での研修機会を数多く提供しており、各国の情報政策を担当する責任者や技術者から大きな信頼を得ています。サイバー空間の重要性は日ごとに増しており、今後、経済的な関係の強い途上国を中心に、情報セキュリティ能力向上やサイバー攻撃リスクを軽減するネットワーク構築等の支援を強化していきます。