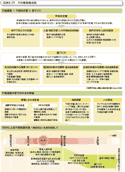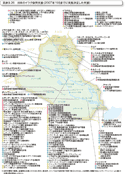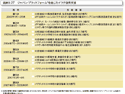冷戦後の国際社会においては、民族・宗教・歴史等の違いによる対立が世界各地で顕在化し、地域・国内紛争が多発するようになりました。こうした紛争では、被害者の大多数が子どもを含む一般市民であり、難民・国内避難民が発生します。このような難民・国内避難民の問題は、さらには人道問題や人権侵害の問題に発展します。また、紛争は長年の開発努力の成果を瞬時に失わせ莫大な経済的損失を生み出します。平和と安定は、開発と発展の前提条件であり、国際的な開発目標であるミレニアム開発目標(MDGs)達成にも、平和の構築が重要な役割を果たします。
国際社会では、2004年12月の「脅威・挑戦・変化に関する国連事務総長ハイレベル・パネル」報告および2005年3月のアナン国連事務総長(当時)報告「In Larger Freedom」を踏まえ、同年9月、国連加盟国の首脳は、国連首脳会合の成果文書において、平和構築委員会(注168)を設立することで意見の一致を見ました。これを受けて、同年12月20日、国連総会および安保理は、同委員会の設立を決定する決議をそれぞれ採択しました(総会と安保理の共同設立)。平和構築委員会は、持続可能な平和を達成するために、紛争状態の解決から復旧、復興および国づくりに至るまでの一貫したアプローチに基づき、紛争後の平和構築と復旧のための統合戦略を助言および提案することを主要な目的として、2006年6月に活動を開始しました。日本は同委員会の設立メンバーとしてその議論に積極的に参加してきましたが、日本の平和構築分野全般での取組が評価され、2007年6月には同委員会の第2代議長に選出されました。
また、様々な国際機関においても紛争地域における平和の構築に向けた支援に取り組んでいます。例えば、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR (注169))においては紛争により発生した難民・国内避難民に対する緊急援助、帰還支援等への取組を、UNICEFにおいては紛争地における子どもに対する取組を、紛争要因や紛争形態にあわせて実施しています。
日本は、2000年7月に「「紛争と開発」に関する日本からの行動-アクション・フロム・ジャパン」を発表し、紛争予防-緊急人道支援-復旧・復興支援-紛争再発防止と本格的な開発支援という一連の紛争のサイクルのあらゆる段階で被害の緩和に貢献するため、政府開発援助による包括的な支援を行っていくことを表明しました。また、2005年4月に開催されたアジア・アフリカ首脳会議において、小泉純一郎総理大臣(当時)は、アジア全体で取り組むべき問題として、経済協力、平和の構築、国際協調の推進をとりあげました。さらに、2006年4月から5月にかけて、エチオピアおよびガーナを訪問した際に、アフリカの平和と発展に向け、日本は積極的に支援していくことを表明しました。
→ 具体的な支援内容については、アフリカ(サブ・サハラ)の項を参照してください
日本は、政府開発援助大綱およびこれを受けた政府開発援助に関する中期政策において、平和の構築を重点課題の一つとして掲げています。「紛争の発生と再発を予防し、紛争時とその直後に人々が直面する様々な困難を緩和し、その後、長期にわたって安定的な発展を達成すること」を目的とし、各段階において継ぎ目なく支援を行い、平和と安定を確保します。具体的には、紛争下における難民支援や食糧支援等の人道支援に始まり、選挙支援など和平(政治)プロセスに向けた支援を行い、紛争の終結を促します。そして、紛争の終結後は、平和の定着に向けて、元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR (注170))への取組、治安部門の再建など、国内の安定・治安の確保のための支援を段階的に実施するとともに、難民や国内避難民の帰還、再定住への取組を進め、基礎インフラの復旧を行うなど、復興への道筋をつけます。さらに、定着した平和を確立し、次の紛争が起こらないよう、国家、経済、社会の再建に向けて、行政・司法・警察機能の強化、経済インフラや制度支援、保健や教育といった社会セクターへの取組を進めます。このような継ぎ目のない支援を行うため、国際機関経由の支援と、無償資金協力、技術協力、円借款という二国間の支援を組み合わせて対処しています。
日本は、これまでイラク、アフガニスタン、スーダン、カンボジア、スリランカ、コソボ、東ティモール、パレスチナ、ネパールなどにおいて平和の構築への具体的な取組を行ってきており、今後とも、同分野に政府開発援助を活用した取組を積極的に行っていきます。
平和構築分野の人材育成
2006年8月、麻生太郎外務大臣(当時)は平和構築に必要な文民専門家の育成を目的とした「平和構築分野の人材育成事業」を2007年度から試験的に立ち上げ、アジアにおける平和構築分野の人材育成を推進していくことを表明しました(注171)。2006年12月には、安倍晋三総理大臣(当時)からASEAN議長国であるフィリピンのアロヨ大統領に対し、また、2007年1月には東アジア・サミットにおいて、日本の東アジア協力のための取組の一つとして、「平和構築分野の人材育成構想」を表明しました。内閣においても「平和構築分野の人材育成に関する関係省庁連絡会議」が設置され、取組を強化しています。そして、この構想の主柱となる、外務省の行うパイロット事業が、広島大学が設立した広島平和構築人材育成センター(HPC (注172))を事務局として、2007年9月から日本人研修員、アジア人研修員を対象に開始しています。
 |
 |
日本を含む国際社会は、イラクの平和と安定の実現のために、イラクの国づくりへの支援を進めていく必要があります。イラクが主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建されることは、イラク国民にとって、また、中東および国際社会の平和と安定にとって極めて重要であり、石油資源の9割近くを中東から輸入する日本の国益にも直結しています。
日本はこれまで、自衛隊派遣による人的貢献と政府開発援助による支援を「車の両輪」としてイラク復興支援を実施しています。自衛隊による支援については、陸上自衛隊が2004年初めから2006年7月まで、サマーワを中心に医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備といった人道復興支援活動等に従事しました。航空自衛隊による国連、多国籍軍の人員・物資の輸送支援については現在も引き続き実施しています。
政府開発援助による支援については、マドリードにおける2003年10月のイラク復興国際会議の際に、当面の支援として、電力、教育、水・衛生、保健、雇用などイラク国民の生活基盤の再建および治安の改善に重点を置いた総額15億ドルの無償資金の供与、また、中期的な復興需要に対しては、電力、運輸等の分野でのインフラ整備に対する円借款を中心とした最大35億ドルまでの支援を行うことを表明しました。総額15億ドルの無償資金の供与については、既に使途をすべて決定し、現地で着実に実施しています。また、円借款に関しては、2007年7月までに、電力・運輸・石油・かんがい等の分野の10案件に対し、イラク政府との間で約21億ドルの交換公文の署名をしました。さらに、2007年2月、イラクの宗派・民族間対立の激化等の厳しい情勢の中で、イラクの国づくりに取り組んでいるイラク政府を支援するべく、基礎的生活分野、治安、人材育成等の分野での事業のため、新たに約1億ドルの無償資金の供与を決定しました。こうした支援は、経済・社会面での復興を支援するとともに、イラクの政治プロセスを後押しする役割も担っています。
図表II-26 日本のイラク復興支援(2007年11月までに実施決定した支援)
イラク政府機関などに対する日本の無償資金による直接支援は、総額約9億ドルに上ります。これまで順次決定してきた緊急無償資金協力案件のうち、警察車両供与、消防車両供与、サマーワ市ゴミ処理機材供与等の機材供与の9事業および移動式変電設備の供与、北部・中部主要病院整備計画等の施設整備の3事業は既に完了し、支援の成果が現地で実感されつつあります。
円借款による支援については、イラク側との協議や各種調査を経て、2007年7月までに、電力・運輸・石油・かんがい等の分野の事業を実施するために必要な10案件(約21億ドル)に関する交換公文をイラク政府との間で署名しました。
債務問題については、2004年にパリクラブにおいてパリクラブ諸国保有分におけるイラク債務(総額約362億ドル)の80%を3段階で削減する合意が成立したことを受けて、2005年11月に日本が有する約76億ドルの債権(日本は第1位の債権国)を3段階に分けて合計80%削減する内容の交換公文が日本・イラク間で署名されました。債務削減スケジュールは国際通貨基金(IMF (注173))支援プログラムと連動しており、2007年10月現在、第2段階まで進展しています。
復興が着実に進展するためには人材育成が重要であるとの考えから、日本は、研修事業を通じて様々な分野において、イラク人の行政官や技術者のキャパシティ・ビルディング支援を行ってきています。2007年11月までにエジプトやヨルダンといった周辺国や日本において研修を受けたイラク人は約2,000名に上ります。
具体的には、日本はエジプトと協力し、イラクの医療分野の復興を支援しました。特に、小児科などの需要の高い分野での人材育成に重点を置き、カイロ大学を中心としたエジプトの医療機関において、500名近いイラク人医療関係者の研修を行っています。また、ヨルダンにおける第三国研修では、電力、統計、水資源管理、上下水道、博物館・遺跡管理、IT教育の分野でヨルダン側の各関係機関の協力を得て、770名を超えるイラク人関係者が研修を受けています。さらに、イラクで大きな課題となっている国民和解を促進するべく、2007年3月、イラクの国民融和担当国務大臣を含む、イラク各宗派・民族の代表の参加を得て国民融和セミナーを開催しています。
サマーワを中心とするムサンナー県では、自衛隊の活動と連携し、総額2億ドル以上を投入して草の根・人間の安全保障無償資金協力や緊急無償資金協力といった政府開発援助による支援を実施してきました。特に、安全な飲料水の提供、電力供給の安定化、基礎的な医療サービスの提供、衛生状態の改善、教育環境の改善、生活道路の確保、雇用機会の創出、安全な生活を送るための治安回復および人材育成を優先課題として取り組んできました。
電力分野では、2005年5月にサマーワ大型発電所建設計画に対する緊急無償資金協力の実施を決定しました。この協力により県全体の電力総需要(200mW)の約3分の1が供給されることになります。給水分野では、草の根・人間の安全保障無償資金協力により、県民一人当たり毎日約5リットルの安全な飲料水を提供しています(注174)。
政府開発援助と自衛隊との具体的な連携事例としては、政府開発援助により供与した医療機材の使用方法を自衛隊医務官が指導したり、自衛隊が砂利舗装した道路を政府開発援助によりアスファルト舗装したことが挙げられます。また、円借款により、サマーワにおける橋りょうの新設(1本)および架替え(2本)等や、ムサンナー県におけるかんがい施設の復旧等を支援することとしています。
日本はイラクの人道・復興支援のため、医療、教育、給水等の分野でNGOを通じた支援も行っており、その総額は2007年11月現在、約2,700万ドルに上ります。その中で支援総額の9割近くに当たる約2,490万ドルをイラクの復興支援事業に限定して、ジャパン・プラットフォーム(JPF (注175))に拠出しました。この拠出により、ジャパン・プラットフォーム傘下のNGOが2007年5月までに、イラク北部3県の国内避難民・帰還民・住民に対する緊急復興事業、バグダッドの小中学校修復事業、北部地域における医療支援等、合計17件の事業を実施しています。
→ ジャパン・プラットフォームについては第II部のこちらを参照してください
このほかにも日本政府は、ジャパン・プラットフォーム傘下に入っていない日本のNGOや国際NGOに対しても支援を行っています(注176)。日本のNGOを通じては、これまでサマーワ母子病院に対して新生児保育器などの医療機材やサマーワ看護高等学校に対して教育用機材の供与などを実施しました。また、国際NGOを通じては、バグダッドのヤルムーク教育病院に対して医薬品・医療品を供与したり、ムサンナー県では給水車をレンタルして水道管による給水を得られない地域の住民に給水する活動を行うなど、イラクの人道・復興のため、日本は積極的に支援しています。
図表II-27 ジャパン・プラットフォーム(*)を通じたイラク復興支援
日本の民間企業による病院支援
イラクには、1980年代に日本企業が医療機材の供与を行った13の地域拠点病院があり、その一部には円借款が供与されましたが、湾岸戦争や長年の経済制裁により、病院設備および医療機器の老朽化が激しく、基本的な診療も困難でした。これに対し、日本は、2004年にイラク保健省向けに緊急無償資金協力により、当該病院の修復を目的とした病院設備および医療機器の供給および据付を実施しています。ただこの修復は、治安状況の悪化により日本人がイラクへ入国できない状況であったため、関連設備機器の日本人技術者を含む関係者が隣国のヨルダンに常駐し、電話、FAX、電子メール等のあらゆる手段を駆使して現地イラク人技術者と連絡をとり合う「遠隔操作」により、修復を完成させました。その努力は、イラク保健省および病院関係者から「かつて病院を建ててくれた日本人が、再び病院の修復に貢献してくれた」と感謝されています。
日本は、イラク復興支援にあたり国際協調の促進が重要であるとの考えから、マドリード会議で設立が合意されたイラク復興信託基金に、4億9,000万ドル(注177)を拠出しました。この拠出を通じて、国連機関や世界銀行が実施する各種復興事業を支援しています。また、資金面での貢献だけでなく、同基金に対する最大の拠出国として、日本は同基金の援助国委員会の議長を2004年の1年間務めました。イラク復興信託基金への拠出以外では、日本は2億ドル程度の国際機関経由の支援を行っています。
日本は、イラク復興のための国際協調の促進に引き続き努力していきます。
イラクでは、2005年12月に実施された国民議会選挙の結果を受け、2006年5月に正式な政府が発足しました。2007年5月には、政治、治安、経済、社会等の広範な分野にわたる、イラク政府と国際社会の協力の在り方を定めた、「イラク・コンパクト」がエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された74の国・機関による閣僚級会合において採択されました。今後の復興プロセスにおいては、このような国際社会の幅広い支持の下で、イラク政府の、より主体的かつ自律的な取組を国際社会が支援していくことが重要です。
日本は、今後は円借款による支援を中心として、イラク政府の復興努力を支えていきます。また、資金協力との一層の連携を図りつつ、研修を通じた能力向上支援も継続していきます。このように今後とも日本は、イラク人自身による国家再建の努力への支援を積極的に進めていく方針です。