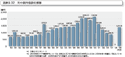政府開発援助(ODA)大綱では、日本と密接な関係を有し、日本の安全と繁栄に大きな影響を及ぼしているアジアを重点地域としています。その他の地域についても政府開発援助大綱の目的、基本方針および重点課題を踏まえ、選択と集中を図り、効果的で効率的な協力を進めていくこととしています。以下では、各地域別の日本の政府開発援助の取組状況について説明します。
日本の東アジア地域に対する2006年の二国間政府開発援助は、約13億4,353万ドルで、二国間援助全体に占める割合は18%です。
東アジア諸国は日本と政治・経済・文化などあらゆる面において緊密な関係にあり、東アジア地域の発展と安定は日本の安全と繁栄にとって重要な意義を有しています。日本は、東アジア地域に対して、政府開発援助によるインフラ整備や人づくり支援とともに、経済関係の強化などを通じて貿易や民間投資の活性化を促進するなど、政府開発援助と貿易・投資を連携させた経済協力を進めることにより、同地域の目覚ましい経済成長に大きく貢献してきました。政府開発援助の実施にあたっては、引き続きアジアを重点地域と位置付けています。
東アジア地域においては、韓国やシンガポールのように高い経済成長を遂げ、既に被援助国から援助国へ移行した国も現れています。その一方で、カンボジアやラオスなどの後発開発途上国(LDC (注1))が依然として存在しています。また、中国のように、近年著しい経済成長を成し遂げつつも国内格差を抱えている国や、ベトナムのように、中央計画経済体制から市場経済体制への移行の途上にある国もあります。日本は、このような各国の経済社会状況の多様性、援助需要の変化などに十分留意しつつ、援助を行っています。
日本は東アジア地域において、基本的な価値の共有に基づいた開かれた域内協力・統合をより深めること、また、相互理解を進め、安定を確保することを目標としています。民主化の定着や人権保護強化、法制度整備、経済成長促進のためのインフラ整備などの協力や、金融、エネルギー、防災、感染症対策といった機能的な協力を推し進めることは、まさにこうした目標の達成に向けたものです。加えて、相互理解のためには人同士が交流することが重要であり、特に青少年交流の促進や、日本語・日本型教育支援を行い、知日層の育成に努めています。また、東南アジア諸国連合(ASEAN (注2))の統合促進やメコン地域開発などを通じて、東アジア地域内での格差を是正することは、地域の安定につながり、ひいては日本の利益となります。このような観点から、アジア地域において様々な地域協力に取り組んでいるアジア開発銀行(ADB (注3))と連携を強化していくことも重要です。
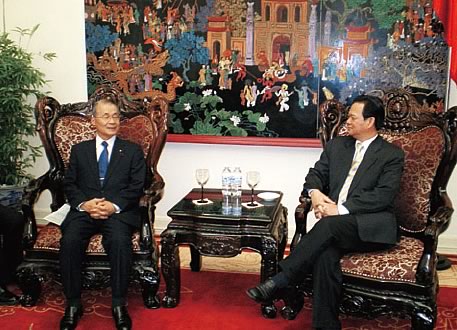 |
インドネシアは、日本の戦略的パートナーとして政治・経済面でも非常に緊密な関係を築いています。2007年8月には、日・インドネシア経済連携協定(EPA)に署名しました。今後は投資環境の整備やエネルギー関連協力を一層進めることとしています。また、スマトラ沖大地震・インド洋津波の記憶も新しいところですが、防災分野での協力、マラッカ海峡における海賊対策やテロ対策も行っています。
また、CLV(カンボジア、ラオス、ベトナム)などメコン地域で地域経済の統合と連携の促進を目指し、社会経済基盤の整備や制度の構築、地域ネットワーク構築を強化しています。一方、現在ベトナムとの間で経済連携協定交渉を進め、法的枠組みの整備などを通じた、貿易・投資の拡大に向けた取組も行っています。このような取組を進めることで、民主主義、法の支配、市場経済といった基本的価値の共有を推し進め、貧困の削減を図り、ASEAN域内の格差を是正することにより、域内統合を支援しています。
このほか、フィリピンのミンダナオや、東ティモール、インドネシアのアチェにおける平和構築への取組を進め、地域の安定を図ることも重要です。
新興援助国として台頭しつつあるマレーシアやタイを拠点とした南南協力の促進や、政府開発援助卒業国であるシンガポールと共同で開発途上国への技術協力を行う日・シンガポール・パートナーシップ・プログラム等も推進しています。
2005年12月の第1回東アジア首脳会議(EAS (注4))以降、地域協力・地域間協力は一層ダイナミックに動きつつあります。2007年1月14日および15日に、フィリピンのセブにおいて、第2回EASや第10回日・ASEAN首脳会議等一連の首脳会合が開催されました。安倍晋三総理大臣(当時)は、一連の会合で、オープンで活力があり、イノベーションに富む東アジアの構築に向け、普遍的価値の共有を基礎に地域協力を進めるという基本理念を表明しました。また、そのため、具体的な東アジア協力として、防災、鳥インフルエンザ対策、メコン地域に対する政府開発援助の拡充、平和構築分野での人材育成等を表明しました。また、同年から3年間で20億ドル規模のエネルギー関連政府開発援助を実施して、東アジア地域のエネルギー・アクセス改善を目指すことや、省エネルギー対策に協力することを中心とするエネルギー協力イニシアティブを発表しました。既に9.5億ドル(注5)の協力をインドネシア、ベトナム、フィリピン等に行っています。さらに、東アジア地域を中心に、5年間で毎年6,000人程度の青少年を日本に招く350億円規模の交流計画を発表しました(「21世紀東アジア青少年大交流計画(注6)」)。これにより若い世代に知日層が形成されることが期待されます。
2015年までのASEAN共同体形成を最大の目標として、域内の開発格差の是正に向けて努力しているASEANとの関係では、後発地域であるメコン地域を支援の重点とし、(1)地域経済の統合と連携の促進、(2)日本とメコン地域との貿易・投資の拡大、(3)価値観の共有と地域共通の課題への取組-を3つの柱とする「日本・メコン地域パートナーシップ・プログラム」を表明しました。同プログラムでは、今後3年間、CLV(注7)の各国および地域全体に対する政府開発援助の拡充を表明しました。さらに、日・ASEAN経済連携促進のため総額5,200万ドルをASEAN事務局へ新規拠出することとし、このうちCLMV(注8)に対し約4,000万ドルの支援を表明しました。メコン地域の中でも特に貧しいCLVの国境地帯「開発の三角地帯」に対しては、その半分の約2,000万ドルの支援を行うこととしています。日本とASEANの経済連携を促進するためにも、ASEANの後発地域であるメコン地域の経済成長を支援し、域内全体において、日本との経済連携から利益を受ける環境をつくることが重要との考えに基づくものです。こうした日本の積極的な取組に対し、2007年1月12日の日・CLV外相会談においてCLV側から感謝の意が表明されました。
なお、ベトナムでは、2007年9月、日本の円借款により建設中のカントー橋の橋げたが崩落し、多数の死傷者が発生しました。ベトナム政府は、国家事故調査委員会を立ち上げ、事故の原因究明に取り組んでいます。日本政府は、ベトナム側の事故原因究明に係る作業に協力すると同時に、カントー橋崩落事故再発防止検討会議を設置し、今後の円借款事業に係る案件監理の改善点や事故再発防止策を検討しています。
日本の対中国政府開発援助は、1979年以来中国沿海部のインフラ整備、環境対策、保健・医療などの基礎生活分野の改善、人材育成など中国経済の安定的発展に貢献し、中国の改革・開放政策を維持・促進させる上で大きな役割を果たしてきました。その協力の大部分は円借款の形で中国に供与されました。このような対中国政府開発援助は、日中経済関係の発展を支えるとともに、日中関係の主要な柱の一つとして重層的な日中関係を下支えしてきたと評価しうるものです。この点、中国側からも、首脳レベルを含め、様々な機会に謝意が表明されてきました(注9)。
近年、中国の経済発展が飛躍的に進んだという状況を踏まえ、2005年4月の日中外相会談において、日中両国は、2008年の北京オリンピック前までに円借款の新規供与を円満終了することについて共通認識に達しました。
その一方で、中国における環境問題や感染症は、日本にも直接影響が及びうる地球規模の問題ともなっており、これらの問題をはじめとして日中両国民が直面する共通課題が数多く存在しています。また、日中関係の健全な発展を促進するという観点からは日中両国民間の相互理解の増進も重要な課題となっています。
このような状況を踏まえ、無償資金協力の対象は現在、(1)環境、感染症等日中両国民が直面する共通の課題の解決に資する分野、(2)日中両国の相互理解、交流の増進に資する分野-に絞り込みつつ実施しています。また、技術協力は、人と人との交流を通じ、日本の価値観、文化を中国に伝えるための重要な手段であるので、これらに加えて、市場経済化や国際ルールの遵守、良い統治の促進に資する案件を中心に実施しています。
内閣に設置された海外経済協力会議では、対中経済協力の在り方についても議論され、対中円借款終了後は、日本の国益を踏まえ、戦略的に支援を行う考え方が示されました。対中経済協力については、今後とも日中関係全体や中国を巡る情勢を踏まえつつ、日本自身の国益に合致する形で、総合的・戦略的な観点から適切に判断した上で実施する必要があります。
中国の新たな動き
中国は、以前から先進国から援助を受けながら他の開発途上国支援も行ってきましたが、近年、援助量が急激に増加しています。こうした変化は、日本が戦後、援助を受ける立場から行う立場へと変化してきたことと同じであり、また、国際社会全体の政府開発援助の量が伸び悩む中で歓迎すべきことです。ただ、現時点における中国の援助は、まだまだ外部にとって分かりづらく、またその援助のやり方についても国際社会において様々な問題が指摘されています。日本は、2007年4月の日中首脳会談において、安倍総理大臣(当時)から透明で国際的規範に沿った援助の重要性を指摘しました。これを受け、温家宝総理からは「国際ルールを遵守する。日本とも協力したい」との発言があり、双方が協力して第三国に援助を行う取組について検討を行うこととなりました。今後もより一層の対話・協力を進めるとともに、G8、OECD-DACの場などで、中国を含めた新興援助国との対話の重要性を訴えていきます。