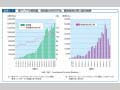本文 > 第I部 > 第2章 > 第2節 経済成長を通じた貧困削減~アジアの経験から~
第2節 経済成長を通じた貧困削減~アジアの経験から~
MDGsの目標の第一番目には「極度の貧困と飢餓の撲滅」が掲げられています。日本はMDGs目標1の達成にあたっては、経済成長を通じて開発途上国の人々、特に貧困層の所得向上を図ることが極めて重要であると考えています。
そして、第1節でも述べたように、経済成長のためには人材育成を含む制度・政策整備といった投資環境改善や基礎インフラ整備を強化し、海外からの直接投資を誘発し、貿易を拡大させることが必要です。
日本は、インフラ整備などによる経済成長が貧困削減において重要であるという点を従来より主張し、日本のODA政策に取り入れてきました。ODAが経済成長の基盤づくりに寄与した結果、貧困削減が進み、MDGs達成の軌道に乗った好例が東アジアです。日本のODAによる支援は、東アジア諸国の経済発展に関して、国際金融市場が未発達の時期、あるいは当該国の国際金融市場へのアクセスが限定的であった時期に、これらの国の成長基盤となる経済インフラの整備を助けたという意味で非常に大きな貢献でした。さらに、日本のODAによる人材育成とが相まって、日本の民間セクターからの直接投資や、それにより引き起こされた輸出の増加や市場の形成により、東アジアの経済は大きく成長しました。その結果、民間経済活動の拡大は、雇用の増加を通じて、貧困層の所得向上に貢献しました。企業や国民からの税収により、東アジア諸国は、保健や教育といった公共サービスの供給を強化し、人材育成を通じて貧困削減に結びつきました。
図表I-7 東アジアの貿易量、貿易量の対GDP比、直接投資の受入額の推移
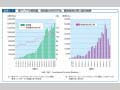
日本は、こうした東アジアの開発経験を世界に発信することを意図し、東アジア開発イニシアティブ*1(IDEA:Initiative for Development in East Asia)を提唱しました。IDEAの閣僚会議およびシンポジウムでは、東アジアの開発に貢献した要素として、[1]オーナーシップ、[2]開発における政府の主導的役割、[3]民間投資の誘致、[4]インフラ、政策・制度整備および人材育成などの重要性が指摘されました。特に、インフラ整備は、ODAの供与によるものを含めて、自国の経済発展における政府の最も重要な役割の一つとして指摘されました。そして、道路、橋、発電所、かんがいなどといった伝統的な「ハード」インフラの整備とともに、通信、マーケティング・ネットワーク、技術支援など「ソフト」インフラの強化についても重要であると指摘されました。
さらに、アジアにおける開発経験の成功は、2005年7月のG8グレンイーグルズ・サミットで採択されたアフリカに関する成果文書でも言及されており、アジアの経験が他の地域の開発のためにも有益であることが広く認知されています。
MDGsは、教育や保健といった課題ごとに目標を定めていますが、MDGsに盛り込まれていない経済成長に資するインフラ整備などは、MDGsの各目標達成のために極めて重要な要素となっています。
民間セクターからの投資を促す上でインフラ整備は極めて有効な手段です。民間企業の事業展開にとって投資効率の向上は収益につながります。道路、鉄道、港湾、空港といった物流の確保、電気、通信、ガス、水道の安定した供給などは、民間企業の収益に直接的に影響するため、民間企業はインフラが整備された地域に参入してきます。このような民間企業の参入による資金流入は経済成長の重要な要素です。
また、インフラは、水、電力、交通などのインフラ・サービスの提供によって、そこに居住する住民の生活の質を向上させる効果もあります。開発途上国の貧困層の大部分は、安全な飲料水、電気、道路へのアクセスに欠いている状態です。その状態は貧困の一つの側面であり、MDGsにも取り上げられています。例えば、一つの橋の建設により医療機関へのアクセスが容易になったり、子どもが学校へ登校できるようになる効果があります。

大ファリドプール農村インフラ整備事業(バングラデシュ)。農村インフラ整備のための土木工事、また必要な機器の調達のための資金の供与を行った。 (写真提供:JBIC)
経済インフラの建設・維持管理には、莫大な費用と利益回収のための時間がかかるため、民間企業が建設し、その費用を回収することは難しく、事業実施に伴うリスクも大きくなる傾向があります。そのため、民間企業の投資が期待できないような案件については、依然として、ODAを通じたインフラ整備支援の必要性があります。
しかしながら、1990年代には、アジア、ラテンアメリカ諸国において民間セクター主導のインフラ整備が各地で進められ、インフラ整備に向けられるODA額は減少の一途をたどりました。1997年のアジア通貨危機以降、1990年代末から民間セクター主導のインフラ整備が減少したため、開発途上国においては一般的にインフラ整備・維持管理に必要な資金が十分手当されない状況が生じています。例えば、ラテンアメリカ諸国における民間のインフラ整備は1998年の約700億円の投資をピークに2002年には約200億円と激減しています。(注1)
国際協力銀行(JBIC:Japan Bank for International Cooperation)、世界銀行、アジア開発銀行(ADB:Asian Development Bank)が共同で行った研究によれば、東アジア地域においても依然インフラ整備の必要性は高く、2006年から2010年の5年間に道路・水道・通信・電力などのインフラ建設・維持管理に年間2,000億ドル以上の資金需要があるとされています。(注2)
また、「アフリカ委員会報告書」*2によれば、アフリカには年間200億ドルのインフラへの投資が必要であり、先進国は現在のアフリカへのインフラ整備に加え、2010年まで年間100億ドルの追加投資をすべきであり、さらに2015年までは年間200億ドルの追加投資が必要であると報告しています。
このような状況から、インフラに関する開発援助の役割については、近年、世界的に見直される動きが出ています。例えば、2003年9月の世界銀行・IMF(International Monetary Fund:国際通貨基金)合同開発委員会で、世界銀行は「インフラ・アクション・プラン」を発表し、インフラ整備の重要な意義を踏まえて、今後、インフラ分野の支援を大幅に強化することを目指しています。ミレニアム・プロジェクト報告書においては、インフラ整備が、MDGs達成のために重要であり、特に農村部の小規模インフラの整備を推進するべきであると指摘しています。2005年7月に開催されたG8グレンイーグルズ・サミットで採択された「G8アフリカ行動計画の実施に関する進捗報告書」においては、インフラ整備の不足が投資、経済成長、貿易の主要な障害であるので、この障害を取り除くためにはインフラへの投資の大幅な増加が必要であることが確認されました。

国道5号線改良事業(ベトナム)。 (写真提供:JBIC)

JBIC、世界銀行、ADBの共同研究のシンポジウムの様子(写真提供:JBIC)
以下では、日本のODAによる大規模なインフラ整備が民間資金の流入を促し、経済成長に貢献した例としてタイの事例を取り上げます。
タイは、現在、社会・経済の様々な面で大きな変化を遂げています。同国の貧困率は1990年の27.2%から、2002年の9.8%と低下し(注3)、経済的にも2002年の経済成長率は5.3%、2003年は6.9%、2004年は6.1%と高い成長率を維持しており(注4)、近い将来、中進国入りする可能性が高いと言われています。
このようなタイの経済発展と貧困削減に対して、日本のODAはインフラ整備、政策・制度整備、人材育成などを通じて大いに貢献してきました。日本のタイへの援助は、1968年から始まり、日本はタイに対する最大の援助国の一つとなっています。(注5)
囲み I-1 インフラに関する議論・研究の概要
「東部臨海開発計画」に対する支援
現在、バンコク首都圏に次ぐ第二の産業エリアへと発展した東部臨海地域の開発に対して、日本は積極的な援助を行いました。この地域の開発は、1980年代から1990年代前半にかけてタイの最優先課題として位置付けられていました。東部臨海開発計画(注6)と呼ばれるこの計画において、日本は、[1]重化学産業の振興を目指すマプタプット地区の工業団地および工業港の建設、[2]レムチャバン港の建設(注7)およびレムチャバン地区の工業団地建設、という2つの事業を中心に、両地区の主として工業用水需要に対応するための水資源開発・導水事業、地域内の交通需要に対応するための鉄道網・高速道路網の整備、といった全16件におよぶインフラプロジェクトに対し、合計約1,800億円の円借款を供与しました。(注8)

現在のマプタプット港の様子 (写真提供:JBIC)

マプタプット工業団地 (写真提供:JBIC)
図表I-8 タイの一人あたりGDP変化

囲み I-2 東部臨海開発計画の概要
1981年に設立された東部臨海開発委員会に約10年間役員として従事し、その後タイの経済社会開発委員会(NESDB:National Economic and Social Development Board)の長官も務めたピシット・パッカセム博士は「東部臨海開発計画における日本の貢献は非常に大きいと感じる」と語っています。(注9)
日本の支援により建設されたレムチャバン工業団地は、多数の自動車メーカーと部品メーカーが進出し、自動車産業の一大集積地になっています。そして現在、自動車産業はタイ経済の主な牽引役に成長しています。また、日本の支援により建設されたレムチャバン港は、今や、タイ国内で最大の規模に拡大し、タイの貿易促進に大きな役割を果たすようになっています。同港は、日本の東京港を抜いて、世界で第19位の貨物取扱量を誇っています(2004年現在)。

ピシット・パッカセム博士。日本側のインタビューに答えて「東部臨海開発計画」について語っている様子。
タイの東部臨海開発計画は、日本のODAによるインフラ整備が、タイの投資環境整備と民間活動の活性化を通じて持続的な経済成長を可能とし、貧困削減に貢献しています。
column I-2 タイで花開いたわが国の港湾・臨海開発技術~財団法人 国際臨海開発研究センター元理事長 竹内良夫氏

「レムチャバンは、キャリアアップの機会を見出す絶好の土地だ」

「レムチャバンの企業は福利厚生がしっかりしており、平均賃金も高いのでできるだけ長く働きたい」

「レムチャバンは、子供を持つ共働き夫婦にとっては、働きやすい環境である」
「小規模灌漑計画」などによる農業振興
日本は、タイに対し、上記のような大規模なインフラ整備への支援と並行し、農村における小規模なインフラ整備への支援を技術協力と組み合わせた形で実施し、地方の農業の開発と貧困削減に貢献してきました。
タイでは、1980年代に入って工業化が急速に進んだものの、依然として全人口の約6割が農業に従事しており、農業が経済の基盤となっていました。特に東北部は、タイの面積、人口の約3分の1を占めているにもかかわらず、一人当たりの地域総生産(GRP:Gross Regional Products)が低く、貧困問題が深刻化していました。

小規模灌漑計画によって建設されたバン・ヤン・ク貯水池施設(写真提供:JBIC)
こうした状況から日本は、農村開発支援を通じて貧困層の生活水準向上に貢献するため、1978年から1985年にかけて、タイ東北部、北部の農村地域において、4,000か所に及ぶ小規模用水施設(貯水池、堰、水量調節施設など)の建設を支援しました。これによりかんがい用水の安定供給による稲作の増産、乾期における作物栽培、農繁期における雇用の増加といった効果が得られ、貧しい地域における人々の収入向上に貢献しました。
農村部の貧困層の所得向上の鍵となる農業振興のためには、このようなかんがい施設の整備などに加え、農業金融、農業経営に対する助言、流通インフラ整備など様々な支援を組み合わせることが効果的であることが少なくありません。こうしたことから日本は、東北部農民の農地開発、農業用機械の購入、営農経費などの支援のため、タイの公的機関である農業・農業協同組合銀行(注10)(BAAC:Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)を通じたツー・ステップ・ローン(注11)を供与し、農民自身の自助努力による農業生産性向上支援を行いました。BAACは貸付にあたり、農業経営に関する助言も行っており、各農家に対してきめの細かい業務を展開しています。このような活動の結果、農民の努力により、かんがい用水と耕運機を用い、乾期にも作付け可能な生産性の高い農業へと転換することに貢献しました。そして、BAACによる貸付の返済状況も良好です。
さらに、日本は、東北部に対し、余剰生産物の市場へのアクセスを確保するための道路網を整備するとともに、電力供給支援も行い、生活向上のための支援も行いました。
また、日本の円借款により購入したミシンを使用して裁縫作業を中心とした家内工業が発達し、女性の雇用機会も増進されました。こうした資金協力による一連の事業に加え、日本は農業関係の政府系金融機関の専門家を派遣し、農業金融の審査方法を指導したり、優良種子増殖のための専門家や地方配電網のメンテナンスのための専門家などを派遣し、インフラ整備の効果を一層高めることに貢献しました。
タイ政府による全国農民アンケート調査によれば、農家所得は向上したと報告されています。

 次頁
次頁