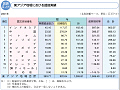本編 > 第II部 > 第2章 > 第2節 > (1)東アジア地域
第2節 各地域へのわが国援助の現況
各地域に対するわが国の援助政策、重点課題については、既に第I部第2章第2節で紹介したので、ここでは2001年度における主な実施状況を中心に紹介します。
(1)東アジア地域
東アジア地域においては、所得水準、市場経済化の段階、社会・自然状況等異なる開発ニーズに対応する支援・協力を行ってきています。最近では、ASEAN加盟国間の「経済格差の是正」が重要な課題と認識され、こうした課題に対してより配慮した支援を行っています。
カンボジア、ラオス、ミャンマー、べトナムといった比較的開発が遅れた国々については、引き続き市場経済化への移行のための支援や法整備といった知的支援を実施するとともに、ラオスとタイとの国境を繋ぐ「第二メコン国際架橋」に象徴される経済社会インフラに対する援助や貧困削減、基礎生活分野支援といった社会開発分野における援助を実施しています。特にべトナムに対しては、2001年12月の支援国会合において有償資金協力(約743億円)を中心とした、約916億円の支援表明を行いました。
一方、より発展の進んだ諸国については、円借款を通じて経済・社会インフラ整備を引き続き支援するとともに、特にアジア通貨・経済危機後のより強靱な経済体制の構築に向けた各国の努力に対する支援策を実施しており、通貨危機の影響を最も大きく受けたインドネシアに対しては、2000年4月及び2002年4月にインドネシア債権国会合で合意された計約3,537億円(円借款分、暫定額)の債務繰延を実施することとしました。また、インドネシア及びフィリピンに対して、特別円借款を活用し、それぞれ400億円を越える規模のインフラ整備支援を実施しました。
中国については、2001年10月に策定された「対中国経済協力計画」を踏まえ、我が方重点分野との整合性などを総合的に検討した結果、2001年度円借款の規模は1,614億円で、前年度比約25%の減額となりました。その半分以上(金額ベースで約54%)が環境分野、約19%(金額ベース)が人づくり分野を対象としています。
また、こうした各国の開発ニーズや要望を踏まえた二国間援助と共に、ASEAN諸国間の格差是正やASEAN統合といった観点から域内協力や南南協力を積極的に推進してきています。11月の日・ASEAN首脳会議において、ASEAN諸国内における感染症対策への取り組みを支援するために、「日・ASEAN感染症情報・人材ネットワーク」を小泉総理より発表しました。また、第三国研修制度や第三国専門家制度の拡大を図りつつ、「21世紀のための日本・シンガポール・パートナーシップ・プログラム」を更新し、専門家の共同派遣、第三国研修のコース数や費用負担等に関する中期的な目標・計画を設定し協力を実施しています。
2001年のわが国の東アジア地域への二国間援助は約28億1,200万ドルで、二国間援助全体の37.7%にあたります。
図表II-11 東アジア地域における援助実績
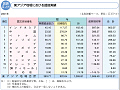
コラムII-5.「アリガト、ジュパン」

 次頁
次頁