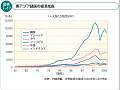本編 > 第I部 > 第2章 > 第2節 > (1) 東アジア諸国への総合的な協力
第2節 アジアを中心に世界に展開するわが国ODA
注)
Point
1. わが国は、貿易・投資と連携したODAを進めることで東アジア地域の目覚ましい発展に貢献。
2. アフリカ地域では、アフリカ自身のイニシアティブである「アフリカ開発のための新たなパートナーシップ」(NEPAD)を支えていく。このため、わが国は、2003年、第3回アフリカ開発会議(TICADIII)を開催する予定。
3. その他の地域についても、それぞれの地域のわが国にとっての重要性、開発ニーズなどを踏まえ、必要な協力を実施。
(1) 東アジア諸国への総合的な協力
東アジア諸国は、わが国ODAの半分以上が実施されてきた地域です。わが国は、歴史的、地理的な関係のみならず、政治・経済両面においても、密接な相互依存関係を有する東アジア地域を重視し、ODAによる経済インフラ整備等を通じた民間投資や貿易の活性化を図るなどODAと投資・貿易が連携した経済協力を進めることで同地域の目覚ましい発展に貢献してきました。実際、同地域は高い経済成長を成し遂げ、今ではシンガポールや韓国のように被援助国から援助国へと移行した国も現れています。その一方で、中国の著しい経済成長が大きな要因となり、対中ODAを見直す動きが見られます。
2002年1月、小泉総理がASEAN諸国を訪問した際、シンガポールにおける政策演説において、21世紀にわが国とASEAN諸国とが目指すべき関係を「率直なパートナー」として「共に歩み共に進む」と表現し、今後、わが国は、ASEAN諸国との一層の経済連携を進め、地域協力を深化させていく方針を明らかにしました。わが国の対東アジアODA戦略も今後はこの方針に沿って進められていきます。わが国は、その一環として、東アジア地域の発展とそれに果たしたODAの役割を検証し、同地域の開発の将来像を描くため、8月には、ASEAN諸国及び中国、韓国とともに東アジア開発イニシアティブ(IDEA)閣僚会合(外相及び開発担当大臣が出席)を開催しました。
図表I-16 わが国二国間ODAの10大供与相手国・供与額

図表I-17 東アジア諸国の経済成長
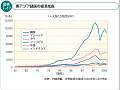
(イ)対中国ODAの新たな方向
中国がより開かれ、安定した社会となり、国際社会の責任ある一員となること、また、日中間に友好な二国間関係が存在することは、わが国のみならずアジア太平洋地域の平和と繁栄にとり極めて重要です。わが国の対中ODAは、70年代末に中国が改革開放政策に転換して以降、この政策を支持する一環として実施され、安定的な日中関係を下支えする基盤を構成してきました。対中ODAは中国経済・社会の発展に大きく貢献しており、中国側は、様々な場でわが国ODAに対して高い評価と感謝の意を表明してきています。しかし、わが国の厳しい経済・財政事情や中国の国力増大、すなわち、経済力・軍事力の向上やビジネスの競争相手としての存在感の増大といった変化を背景に、わが国国内において対中ODAに対する厳しい批判があるのも事実です。
これらに応えるべく、外務省は対中ODAについて国民各層に存在する意見を幅広く聴取するため、2000年7月に「21世紀に向けた対中経済協力のあり方に関する懇談会」(座長:宮崎勇元経済企画庁長官)を設置し、提言を受けました。また、与党内でも、自民党対外経済協力特別委員会において対中経済協力に関して議論が行われ「中国に対する経済援助及び協力の総括と指針」が出されました。こうした議論などを踏まえて、政府は、2001年10月、「対中国経済協力計画」を策定し、新たな対中ODAの方針を打ち出しました。
この計画に基づき、2001年度より、円借款について、従来の多年度供与方式からロングリストに基づく単年度供与方式に移行するとともに、従来の支援額を所与のものとせず、「案件積み上げ方式」を導入しました。また、この計画は、[1]わが国国民の理解と支持が得られるよう、わが国への影響等を含めて国益の観点に立って個々の案件を精査すること、[2]環境問題等の地球規模問題への対応、内陸部の民生向上・社会開発、相互理解の増進などを対中ODAの重点分野とする一方、沿岸部の経済インフラの整備は基本的に中国が自ら実施することなどを掲げています。
2001年度の対中国円借款については、この「案件積み上げ方式」に基づき個別案件とわが国の重点分野との整合性などを総合的に検討した結果、その規模は前年度比約25%の減額となり、また、その半分以上(金額ベースで54%)が環境分野を対象としたものとなっています。
今後とも、対中ODAにおいては、「対中国経済協力計画」で挙げられている重点分野への支援をより一層重視し、適正規模の実施を図り、国民の支持と理解を得られる対中ODAを実施していく考えです。
囲みI-11.対中国経済協力計画(概要)
コラムI-4 対中ODAプレスツアー
コラムI-5 安徽省金寨県果子園小学校建設計画
(ロ)経済連携、政策支援の強化
97年、東南アジア地域は未曾有の経済・金融危機に見舞われ、現在は、高度成長型の成長戦略からより安定的で危機に強い経済・社会体制の構築を目指し経済構造の変革や国内・域内格差の縮小に取り組んでいます。とりわけ低所得国から中所得国、さらには高所得国に移行しつつあるASEAN諸国は、経済成長を維持しつつ統合を強化することにより地域的競争力を高める努力を行っています。このため、わが国は、ODAを積極的に活用して、加盟国の増加に伴い顕在化したASEAN域内の格差を是正すると共に、貿易・投資を円滑化するための制度整備、人材育成、経済社会基盤への支援、さらには経済構造の変革に向けた政策形成を支援することが最も重要な課題となっています。その際、東アジアにおける経済連携強化等を十分考慮する必要があります。
域内格差の是正とASEAN統合イニシアティブ
ASEAN諸国においては、加盟国の増加や各国の有する地理的条件等の相違により、加盟国間の経済格差が広がっています。具体的には、ASEAN域内には、経済開発協力機構の開発援助委員会(OECD-DAC)の分類で中所得国であるマレーシア、タイ、フィリピン、低所得国だが発展過程にあるインドネシア、ベトナム、依然として後発開発途上国(LDC)であるラオス、カンボジア、ミャンマーといった具合に国により経済の発展段階が大きく異なっています。そのため、わが国は各国の実状に応じてきめ細かい対応をしています。
ASEAN自身も域内の格差の是正と、その地域的競争力の向上が急務であると認識しており、2000年11月、第4回ASEAN非公式首脳会議においてASEAN統合イニシアティブ(IAI)を打ち出しました。IAIは、人材育成、IT、インフラストラクチャー及び地域経済統合を重点分野とし、特に開発が遅れているASEAN新規加盟国、すなわちカンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム(いわゆるCLMV諸国)におけるプロジェクトとして、現在、具体的な協力案件についての検討が進んでいます。わが国としては、ASEAN諸国自身のオーナーシップに基づく域内開発の試みであるIAIの進展を歓迎しており、IAIプロジェクトへできる限りの支援を行うことを表明しました。わが国は、CLMV諸国等において地方の農林水産業をはじめとする地場産業の振興や地域総合開発に対する調査協力、さらには後述のメコン地域開発への協力などを行っています。また、域内格差については、日・ASEAN包括的経済連携構想を進めていく上でも配慮されることになっています。
囲みI-12 日・ASEAN包括的経済連携構想
メコン地域開発
カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの5か国と中国の雲南省を流れる全長約4,900kmのメコン河は、流域面積が日本の国土の2倍以上(79.5万km2)、流域人口は約2億5千万人にも及び、その流域はさまざまな資源に恵まれています。この地域の開発は、経済面のみならず地域の安定のためにも極めて重要です。「メコン地域開発」とは、メコン河流域のこれらの国・地域を国境をまたいで広域的に開発しようとする試みです。これを推進することで、流域諸国間の関係が強化されるとともに、流域に所在するASEAN新規加盟国の経済水準の底上げを通じたASEANの内部格差の是正、ひいてはASEANの統合強化や日・ASEAN包括的経済連携構想にも好ましい環境が作られます。
わが国は、93年に「インドシナ総合開発フォーラム」の設置を提案し、95年に東京で同フォーラム閣僚会合を開催するなど、国際的な取組を主導してきました。また、ODAによる具体的な支援としては、タイ、ラオスの両国を結ぶ第2メコン国際橋の建設のために両国に対して円借款を供与したのをはじめ、インドシナ地域を横断する「東西回廊」関連のさまざまなインフラ基盤(道路、橋梁、港湾等)の整備を支援してきました。
わが国は、流域諸国やアジア開発銀行(ADB:Asian Development Bank)をはじめとする主要ドナーと協力して開発を推進していく考えです。2001年7月、わが国はADBと共同で関係国に調査団を派遣し、その結果を踏まえて、同年11月のASEAN+3首脳会議及び日・ASEAN首脳会議で、「東西回廊」の経済回廊化および「第2東西回廊」(バンコク-プノンペン-ホーチミン道路)の整備を今後の協力の柱としていくことを表明しました。経済回廊化については、具体的には、2002年12月に民間部門の関与促進を目的とした「東西経済回廊に関するワークショップ」を行ったほか、日・ASEANセンターによる観光ミッションの派遣を提案しました。また、わが国は、メコン川流域の持続的な開発のために設置されているメコン河委員会に人材を派遣し、わが国の流域管理に関する経験を伝えるなど、積極的な協力を行っています。
図表I-18 メコン地域開発

政策支援
ASEAN諸国の市場経済体制への移行や経済のグローバル化への対応を支援するため、わが国は、東南アジア諸国の経済政策の立案や制度づくりのための協力を行っています。
こうした支援は政策支援と呼ばれ、その特徴は、わが国と相手国の閣僚等を含む有識者が緊密な調査や意見交換を行い、共同作業を通じて相手国政府に対して政策提言を行う点にあります。政策支援は、相手国の経済政策や制度作りを支援することが最大の目的であり、支援を通じた相手国の政策立案能力の向上とともに、その成果が相手国の主要政策に反映されることが期待されています。
わが国が本格的に取組を開始した政策支援は、95年に始まった「ベトナム市場経済化支援計画策定調査」です。石川滋一橋大学名誉教授が中心となって作業を進めたため通称「石川プロジェクト」と呼ばれている同プロジェクトでは、「マクロ経済」、「財政・金融」、「産業政策」、「農業・農村開発」などのテーマごとに日越で共同研究を行い、その成果はベトナム政府の第6次5か年計画(96年~2000年)、第7次5か年計画(2001年~2005年)、10か年の中長期計画に反映されるなど、ベトナム政府の政策形成に大きな影響を与えました。
ベトナムでの経験を踏まえて、現在、わが国はミャンマーの経済改革を促進し、ひいては民主化の環境整備に資することを期待して「ミャンマー経済構造調整政策支援」を行っています。また、2002年3月からは、インドネシアの地方分権やマクロ経済運営等について提言するため「インドネシア経済政策支援プログラム」を開始し、2002年6月に「財政の持続可能性」と「国際競争力の強化」を柱とする提言を行いました(詳細は、第II部第2章(3)(ロ)参照)。
(ハ) 東アジア開発イニシアティブ(IDEA)~地域開発協力の未来像の構築と東アジアの経験の世界への発信
IDEAは、東アジア地域の経済連携と地域協力の推進を基本目標として、東アジア地域の開発課題についての現状認識を共有するとともに、今後の地域開発協力の向かうべき方向性を模索することを目的としています。併せて、東アジアの開発モデルを世界に発信していくことも意図しています。その際、ODAの供与国と受益国といった二分論ではなく、わが国と中、韓、ASEAN諸国が率直かつ対等なパートナーとして、開発問題を地域の平和や安定に直結する共通課題として議論し合うことを目指しています。
2002年8月に東京で行われた第1回IDEA閣僚会合では、各国よりわが国ODAに対する感謝の意が示されるとともに、次のような参加国の共通認識が示されました。

写真 IDEA閣僚会合
[1]開発を国家的課題として推進する各国の自助努力が重要であり、それを強化していくためには、開発の主体となる人材の育成や政府の能力開発が鍵となる。
[2]地域の発展に向けてODAのみならず貿易と投資、更には金融とも連携した成長志向の包括的開発を一層推進していくことが重要である。このようなダイナミックな資源動員を持続的な経済成長につなげるため、民間資金と有機的に連携した戦略的なODAの活用が期待される。
[3]グローバル化に対する負の側面への対応として、社会的弱者に一層配慮していく。また、平和や安定のためにも効果的な開発のための環境整備(グッド・ガバナンス、制度・インフラ整備、紛争予防)に取り組むことが地域共通の課題である。
[4]地域諸国の発展段階はそれぞれ異なるが、各国が有する能力に応じて協力していくことが有効である。地域諸国の中には、適切な技術水準を効果的に移転する南南協力を行う国も出てきており、こうした域内協力の支援を重視していく。
[5]ODAによる経済インフラ整備が貿易や投資の呼び水となるなど、東アジアの開発が官民の資金の連携の中で進んだことを考えれば、今後、政府間協力と表裏一体で官民連携を促進することが有効である。
囲みI-13.IDEA閣僚共同声明の骨子
この声明の中で提唱された東アジアの経験や知見を国際的に発信するため、わが国は、ヨハネスブルグ・サミットの機会に、川口外務大臣が出席してIDEAに関するシンポジウムを主催しました。そこでは、ODAを活用し経済インフラ整備に努めながら貿易・投資との連携を深めてきた成長志向の東アジアの開発手法が、アフリカ政府関係者からも注目されました。このような積極的な発信と国際社会との知見の共有は、IDEAプロセスの特色の一つとして今後も続けられることになります。
2003年には、アフリカとの新たな開発の方向性について検討する第3回アフリカ開発会議(TICADIII)が日本で開催されます。そこではアジア・アフリカ協力も重要な論点になります。わが国としては、IDEAを通じて東アジア諸国と深めつつある協力関係を、わが国が主導したもうひとつの国際的イニシアティブであるTICADプロセスにも活かしていきたいと考えています。

 次頁
次頁