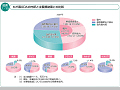本編 > 第I部 > 第2章 > 第1節 わが国ODAの全体像
第2章 戦略を持ったわが国ODAの展開

ODA写真館[2]:ブルジュ・バラージネ障害者地域福祉評議会へのマイクロバス供与計画(レバノン:無償資金協力)
Summary
国際的に開発問題への関心が高まっていく中、わが国も限られたODA資金をより有効に活用するため、ODA戦略をこれまで以上に明確化し、重点や優先順位を定めていくことが必要となっている。
これまで述べたように国際的に開発問題への関心の高まりや国内的な事情を踏まえ、わが国としては限られたODA資金をより有効に活用するため、ODA戦略をこれまで以上に明確化し、重点や優先順位を定めていくことが求められています。
わが国のODAの特徴を一言で言えば、地域別にはアジアを重視し、開発アプローチとしては、経済成長を通じた貧困削減と人づくりや制度づくりを重視し、それらの実現のため途上国の自助努力(オーナーシップ)を尊重して協力するということです。その際、わが国の経験やノウハウを活用していくことが大切です。また、最近では、ミレニアム開発目標(MDGs)を始めとした国際的な開発目標の実現に力を入れており、さらに、平和と安定へのODAの活用といった新しい取組も活発に行っています。
ここでは、わが国ODAの全体的特徴を俯瞰した後、地域別のODA戦略について解説し、さらにODAの一層の活用が期待される平和構築分野(平和の定着と国づくり)での取組について説明します。また、わが国が重視する人間の安全保障の推進やMDGs達成に向けた努力、さらに、益々重要性を増している国際連携の強化についても併せてわが国の取組の現状を説明します。
第1節 わが国ODAの全体像
Point
1. わが国は、地域的にはアジアを、開発戦略としては経済成長を通じた貧困削減と人・制度づくりを重視した援助を実施。
2. 平和と安定へのODAの活用や人間の安全保障、ミレニアム開発目標(MDGs)といった新しい取組も重視。
基本的なODA政策の枠組み
わが国は、92年、わが国ODAの基本理念や原則、重点課題等を明らかにした政府開発援助大綱(ODA大綱)を策定・公表しました。ODA大綱では、人道主義、相互依存、環境保全、平和国家としての使命を掲げるとともに、途上国の自助努力支援を基本とし、途上国の健全な経済発展を実現するためにODAを実施することを基本理念としています。
また、99年、政府はODA大綱に基づき向こう5年程度を目途に中期的な政策・プログラムの方向性を示した政府開発援助に関する中期政策(ODA中期政策)を策定・公表しました。中期政策では、経済成長等を通じた貧困削減を開発援助の主たる目的とし、各国、国際機関、NGO等が連携して援助を進めていこうとする援助協調の流れが強まる中、経済・社会インフラ整備支援とのバランスに配慮しつつ、貧困対策や社会開発分野及び人材育成や地球規模問題等への支援を重点課題の第一に掲げ、また、96年のDAC新開発戦略、人間の安全保障の視点の重視、国民参加型の協力の推進、紛争・災害と開発等の新たな要素を加えました。
さらに、そうした基本政策の下に、わが国は主要被援助国に対する援助の目的、重点分野等を示した国別援助計画注)や感染症、環境といった特定の課題に対する分野・課題別政策イニシアティブといった国毎、分野毎のわが国の援助計画や方針を順次策定しています。
なお、外務省は、2002年12月、ODA改革の一環として、ODA大綱について策定後10年間に生じた内外の情勢の変化を踏まえ、見直しを行うことを発表しました。
図表I-10 わが国ODAの政策的枠組み

地域別・分野別・形態別実績からみたわが国ODAの特徴
2001年のわが国ODA実績を見ると、二国間ODAの約6割にあたる42億ドルがアジア地域に振り向けられています。こうしたアジア重視の傾向は、ODA大綱、中期政策にも明示されたわが国ODAの基本方針であり、年によって多少の増減はあるものの、一貫してわが国ODAの最大の特徴の一つとなっています。
図表I-11 わが国二国間ODAの地域別配分

図表I-12 わが国二国間ODAの地域別配分の推移

図表I-13 わが国が最大または二番目の援助供与国となっている国一覧

また、2001年の分野別実績では、経済インフラ及びサービスが最大のシェアを占め(34.9%)、次に社会インフラ及びサービスが多く(17.3%)、その2分野でわが国ODAの過半が占められることがわかります。わが国は、従来、円借款を中心とした経済インフラの整備を積極的に行ってきましたが、こうした経済成長への支援に加え、最近の国際社会における貧困問題への直接支援の機運の高まりも踏まえて保健や教育といった社会セクターの支援を強化しており、経済・社会両セクターに対する支援に重点を置いたODAを実施しています。
また、援助形態別の実績を見ると、2001年は、二国間ODAが4分の3、多国間ODAが4分の1を占めており、二国間ODAが中心であることがわかります。その理由としては、わが国は、自ら策定した援助プロジェクトを実施することにより、わが国の政策の実現あるいは、いわゆる「顔の見える援助」を目指しているということが挙げられます。もちろん、国際機関経由のODAは、特に緊急人道支援など二国間ODAでは実施が困難な場合や国際機関の有する能力、知見を活用することができるという長所があります。
図表I-14 わが国二国間ODAの分野別配分の推移

図表I-15 わが国ODAの内訳と主要援助国との比較
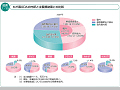
二国間ODAの援助形態の内訳は、無償資金協力が約4分の1で残り4分の3を技術協力と政府貸付等がほぼ二分しています。政府貸付等の約7割は経済インフラにあてられていますが、最近は、円借款による人材育成や貧困対策を重視した経済インフラ整備など対象分野の多様化が進んでいます。
コラムI-3.円借款で人づくり

 次頁
次頁