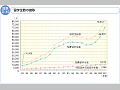本編 > 第II部 > 第2章 > 第1節 > (3)人材育成・知的支援
(3)人材育成・知的支援
わが国では、「国づくりは人づくりからはじまる」と言われています。これは、わが国自身の発展の経験に裏打ちされた信念でもあり、人づくりへの支援はわが国援助の重要な柱の一つとなっています。具体的には、人づくりの基礎となる基礎教育は勿論のこと、国づくりに直接貢献する人材育成も途上国にとって極めて重要な課題です。また、グローバル化に適応するために必要な制度の整備や能力の向上など人を基礎とした体制の強化が求められています。
このような人づくりへの支援は、わが国への研修員受入や専門家派遣などわが国と相手国との人間同士の相互交流を広げるなど、「顔の見える援助」の代表例の一つでもあります。
(イ)人材育成
わが国は、人材育成への支援として、留学生受入れ、行政実務者の能力向上支援、職業能力開発・向上支援など技術協力を中心とした支援を行っています。また、人材育成支援の実施に際しては、より低コストで質の高い支援が実施できるようITを積極的に活用しています。
留学生や研修員の本邦受入れ事業は、途上国の人々がわが国の経済・社会に直接触れ、わが国国民との交流を深めるよい機会を提供しています。わが国は、「留学生受入れ10万人計画」に基づき、2001年5月現在で約7万9千人の留学生を受け入れています。具体的には、留学生受入れの牽引力としての国費留学生受入れの計画的整備(2001年5月1日現在で約9千人)を進めているほか、私費留学生・就学生に対する学習奨励費の給付(約1万人)や、授業料を減免する学校法人への援助、短期留学生推進事業などの支援、留学生宿舎の整備、留学生に対する教育・研究指導など、留学生受入れ環境の整備を図っています。
また、99年度からは、途上国政府による組織的・計画的なわが国への留学生派遣事業に関し、途上国における事前教育、わが国への渡航費、滞在費、学費等に対する無償資金協力を行う「留学生支援無償」を通じて留学生の受入れを行っています。2001年度は、留学生支援無償によりカンボジア、ベトナム、ラオス、ウズベキスタンから各20名ずつ、計80名(約8億円)の留学生を受け入れました。
円借款による人材育成の活用も図られており、これまで途上国政府の人材育成・留学生派遣事業を支援する「留学生借款」を通じて、インドネシア、タイ、マレーシアの3か国に対し約592億円の円借款を供与しており、これによる留学生総数は、今後の留学予定者も含め約3,800人に達しています。また、その他にも、2001年度には、中国の内陸部の6地域64大学に対して、人材育成プロジェクトを対象とした約300億円の円借款を供与しました。
図表II-10 留学生数の推移
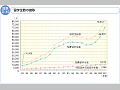
わが国によるアジア諸国の市場経済化への改革努力の支援策の一つとして、経済実務に携わる人材育成を主な目的とした「人材協力センター(日本センター)」の設立が挙げられます。日本センターは、[1]経済実務人材の育成、[2]日本語学習、[3]日本文化の紹介などによる相互理解の促進の3つを軸として、無償資金協力と技術協力プロジェクトを組み合わせて実施する事業です。2001年5月にはラオス、カザフスタン、ウズベキスタンに日本センターを開所したほか、ベトナム、モンゴルなどにおいて開所に向けて準備が進められています。
途上国における職業能力開発分野での支援についても、関連施設の設置・設営に対する協力や、専門家派遣、研修員受入れ等を行っています。現在、技術協力センター事業により、パラグアイ、セネガルなど計7か国に対し、職業能力開発施設の設置・運営等を行っているほか、専門家派遣等を含め、12か国に対し協力を実施しています。わが国は、また、途上国の自助努力への支援の基本理念のもと、途上国における職業能力開発分野での支援についても、関連施設の設置・運営等に対する協力や、専門家派遣、研修員受入れ等を通じて行っています。現在、専門家派遣、研修員受入れ、機材供与の協力を有機的に組み合わせ、総合的に協力を行う技術協力プロジェクト(旧プロジェクト方式技術協力)により、ベトナム、チュニジア、パラグアイなど8か国に対し協力を行っているほか、個別専門家派遣等による協力を含め合計23か国に対して職業能力開発分野における技術協力を実施しています。例えば、電気・電子分野の人材育成を担う「チュニジア電気電子技術者育成計画(2001年~)」に対する協力は、電気・電子産業に携わる中堅技術者の質の向上と、量的にも近年の技術革新等に伴う産業界の需要を満たすために実施しているプロジェクトの一例です。
また、ITを活用した支援策としては、「JICA-NET」が挙げられます。これは、東京・沖縄に設置されたコア・センターと途上国に設置するサテライト・センターを衛星回線等で結び、遠隔教育の実績を通じて、技術協力を効率的に実施可能とすることを目指しています。2001年度には、インドネシア、フィリピン、マレーシアの3拠点にサテライト・センターを設置し、現在はタイ、ベトナム、ラオスに設置すべく取り組んでいます。
なお、国際機関については、UNDPや世銀等が開発支援のための人材育成事業を行っている他、地域・分野には、アジア開発銀行(ADB)やアジア生産性機構(APO:Asian Productive Organisation)、コロンボプラン等が関連事業を展開しており、わが国は国際機関のこのような活動を支援しています。
人物II-2.シニア海外ボランティア:浅妻金平さん(ドミニカ)
(ロ)知的支援
わが国は、途上国の政策・制度づくりなどソフト面への支援需要に応えるため、政策アドバイザーなどの専門家派遣、諸制度を整備するため研修員受入や開発調査を活用した支援を実施しています。
こういった政策支援のうち、市場経済化や経済自由化における政策提言を行うものとして、「ミャンマー国経済構造調整政策支援(2000年~)」があります。この支援は、ミャンマーの経済構造調整に向けた自助努力を支援するため、日・ミャンマー両国の産・官・学のメンバーにより構成される合同タスクフォースが「財政・金融」、「産業・貿易」、「IT」、「農業・農村開発」などの分野について調査・検討を重ね、具体的な政策提言を行っていくものです。また、その他にも2001年には、既往継続案件として「チリ国地域経済開発・投資促進支援(99年~)」、新規の案件として「インドネシア経済政策支援(2001年~)」などを実施しています。
また、急速な経済成長を遂げているASEAN各国に対しては、産業構造の強化を目的として、産業の担い手である中小企業に対しての継続的な支援を実施しています。具体的な例として、インドネシアでは、わが国が派遣した大学教授などで編成された中小企業振興政策支援チームが2000年7月に中小企業振興政策提言をインドネシア政府に提出しました。この提言の内容を具現化するため、2001年度には、専門家を派遣して中小企業金融政策の強化や貿易研修センターの地方展開などの輸出振興、鋳造技術向上などの裾野産業育成への支援など中小企業育成・強化のための技術協力を実施しました。このような支援に併せ、対インドネシア支援国会合(CGI)の枠組みを活用して、世銀、アジア開発銀行(ADB)など他ドナーとも中小企業振興に向けた取組の連携を図り、当分野支援をさらに充実したものとしています。
さらに、タイにおいても、2000年度から2002年度にかけて、金融制度面での支援、中小企業支援、自動車部品メーカーの巡回指導等の裾野産業育成支援のための技術協力を実施しています。
このほか、途上国において財政、金融、産業といった重要政策の立案策定、制度づくりに携わる人材育成のために、わが国の学者や実務家を長期又は短期で派遣しアドバイスを行ったり、研修員受入れやワークショップの開催、相手国政府に研修等の必要機材の供与を行っています。2001年度は、前年度よりの継続案件としてカンボジア、ブルガリア、ベトナム、ヨルダンに対して法制や税制の整備を支援し、産業政策に対するアドバイスを行いました。
また、貿易・投資関連の人材育成については、2000年2月の国連貿易開発会議(UNCTAD X)において、小渕総理(当時)が2000年度から5年間で2,500人の貿易関連キャパシティー・ビルディングを行うとのイニシアティブを打ち出し人材育成に取り組んできましたが、2002年8月のヨハネスブルグ・サミットにおいて同イニシアティブをさらに拡充し、同期間で4,500人の人材育成を行うことを表明しました。2002年にはジュネーブにおいてアフリカ諸国を対象としたワークショップをWTOとの共催で行うとともに、2003年2月にはエジプトにおいて第三国研修を活用したセミナーを開催しました。
このほかにも、WTOルールの確立と自由貿易の推進を目的としてAPECに加盟する途上国に対するWTO協定への理解促進のためのキャパシティ・ビルディング支援を行っています。
また、アジア等の途上国とわが国の間の経済活動を円滑にするためには貿易投資環境の整備のための制度・ルール整備支援が重要であるとの認識のもと、知的財産権、基準・認証制度等のソフトインフラ分野においても、専門家派遣や研修、開発調査等を通じた技術協力を行っています。
囲みII-1 ミャンマー経済構造調整政策支援の概要
(ハ)民主化支援
わが国は、96年のG7リヨン・サミットに際して「民主的発展のためのパートナーシップ(PDD:Partnership for Democratic Development)」イニシアティブを発表し、法・司法制度や選挙制度の整備、司法官・行政官の育成、人権の擁護、さらにはメディア支援、民主化を支える市民社会への基盤づくりといった分野で途上国の自助努力(オーナーシップ)を積極的に支援していくとの方針を明らかにしました。
わが国は、そのような取組をさらに充実させるために、2001年度より無償資金協力の一環として「ガバナンス無償(10億円を計上)」を新設し、統治・行政能力向上及び民主的な制度構築に資する立法、司法、行政各機関の施設整備や資機材供与を行っています。
法・司法整備支援及び行政支援では、主としてカンボジア、ベトナム、ラオス、モンゴルなど東アジア地域の国に対して、各種法制度整備に向けた研修員受入れ及び専門家派遣などの技術協力を中心に行っています。例えば、2001年度には、法整備支援としてベトナムに対し40名の研修員受入れ及び30名の専門家派遣、カンボジアに対し16名の研修員受入れ及び25名の専門家派遣などを行っています。
また、途上国における国家警察の文民組織化努力は、民主化を大きく促進するものとして、わが国はそのような努力を側面から支援しています。インドネシアでは、法治国家への移行を目指した司法改革の一環として、国家警察が国軍から分離・独立し、文民警察組織を構築するという民主化改革を推進しています。わが国は、このようなインドネシア政府自らのオーナーシップに基づく民主化努力を積極的に支援するため、「インドネシア国家警察改革支援」を進めてきています。2001年度には、国家警察長官政策アドバイザーなどの専門家派遣やインドネシア警察行政セミナーへの研修員受入れを行うとともに、2002年1月に調査団を派遣し、今後の協力内容について検討しています。
途上国における民主主義の定着のためには、国民の政治参加を促す選挙の実施が大前提となることから、わが国は選挙実施への支援を重視しています。2001年度は、二国間援助及び国際機関を通じて、東ティモール等合計16か国に対し、選挙要員派遣や資金協力、資機材供与などを行いました。加えて、民主主義の土台となる市民社会を強化し、政治への国民参加を促進するため、選挙啓蒙活動や指導者育成、メディア支援などNGO等が実施する支援を草の根無償資金協力により16件実施しています。そのほかにも、2001年度は、ペルー、タジキスタン、アフリカ諸国の国会議員など合計43名をわが国に招いて民主化セミナーを実施しています。
コラムII-3 インドシナ諸国における法整備支援

 次頁
次頁