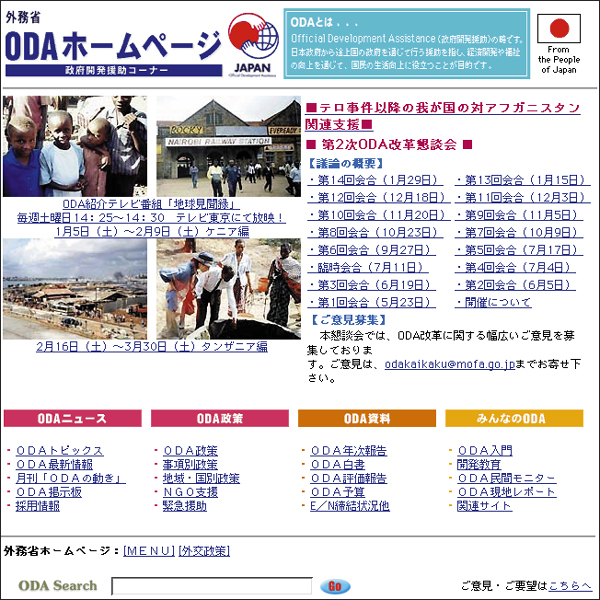本編 > 第II部 > 第2章 > 第4節 実施・運用上の留意点に関する取組の現況
最後に、ODAを実施・運用する上で留意すべき点として、ODA中期政策が掲げている国別援助計画の策定、事業評価、開発人材の育成、ODA広報と国民参加の促進、情報公開等について、2000年度のわが国の取組状況を概説します。
ODAの効果を高めるためには途上国ごとの開発課題を把握し、各国の状況を十分踏まえた上で援助を行うことが重要です。わが国は、このような観点から「国別援助計画」を順次策定しており、これまでに12か国(注)について策定・公表しました(仮)。国別援助計画は、ODA大綱及び中期政策の下に位置付けられ、主要な被援助国に関し、向こう5年程度の具体的な援助の目的、重点課題・分野、援助手法などを示したものであり、円借款、無償資金協力、技術協力といった異なる援助形態を一体的にとらえるとともに、他の援助国・国際機関の動向や民間セクターやNGOとの連携をも視野に入れたものとなっています。また、その策定に当たっては、政府部内での議論のみならず、NGO、経済界、学界等の国内各界や途上国政府、市民社会との意見交換を重視しています。
ODA事業の適時・適切な評価の実施と評価結果のフィードバックの重要性については、第I部第4章第2節(3)で概説しましたが、改めて2000年度以降の評価活動改善のための努力について整理すれば次の通りです。
まず、2000年3月に提出された、「『ODA評価体制』の改善に関する報告書」の提言に基づき、同年7月、評価体制の一層の充実について、より具体的・集中的な検討を図るため、ODA関係省庁の参加も得て外務省内に「ODA評価研究会」が立ち上げられ、2001年2月には、その検討結果がODA評価研究会報告書として外務大臣に提出されました。また、2001年1月には、評価の結果を以後の政策に活かしていくため、外務省の経済協力局長を委員長とした「ODA評価フィードバック委員会」が設置され、また、同年5月にはODA事業の事前・中間・及び事後の段階での一貫した評価プロセスを構築していく一環として、JBIC及びJICAにより、従来の事後評価の公表に加え、「事業事前評価表」が公表されました。ODA関係省庁間の連絡・調整も定期的に行われることとなり、2001年7月には「ODA関係省庁評価部門連絡会議」が設置され、以後、定期的に会合が開かれています。なお、政府部外の動きとしては2000年9月に日本評価学会が設立され、今後、本格的な評価研究とODA評価専門家の育成が期待されます。
ODA事業での環境配慮については、すでにJICA、JBICにおいて分野別環境配慮ガイドラインが策定されていましたが、現在、JBICにおいて国際金融業務(旧日本輸出入銀行が実施していた業務)と海外経済協力業務(旧海外経済協力基金(OECF:Overseas Economic Cooperation Fund)が実施していた業務)で共通な「統合ガイドライン」の策定作業が進められています(注:2002年4月に公表)。
第I部第4章第4節でも触れましたが、今後のわが国ODAのあり方を中長期的に考えた場合、新たな開発援助ニーズに対応していける人材を育成していくことが重要です。そうした人材を育成するためには国内での人材の養成を拡充するとともに、他の援助国・機関との人的交流、人の派遣を積極的に行っていくことも効果的です。他国との人事交流や国際機関への人の派遣については、これまでも行われてきており、2000年度においては、JICAからカナダ国際開発庁(CIDA:Canadian International Development Agency)や米国国際開発庁(USAID)への職員の派遣(2人)または受け入れ(2人)を行っています。また、国際機関との交流についても、JICAから国連開発計画(UNDP)、世界銀行、国連東チモール暫定行政機構(UNTAET)等へ8名を派遣、JBICからも16名を派遣し、3名を受け入れました。
さらに、JICA専門家に政府の専門家のみならず多くの民間の人材を活用するため、一般公募制度による人材募集を行い、2000年度は保健医療、理数科教育、ICT等の専門家を計40人採用しました。また、わが国の高等レベルでの開発教育への取組としては、2000年度より政策研究大学院大学(GRIPS)と国際開発高等教育機構(FASID)との連携による大学院レベルの開発援助人材の育成コースが開設され、実践的な開発援助教育が行われていることはすでに第I部で述べた通りです。
第I部第3章第3節で述べた通り、ODAが国民の税金等を原資として行われている以上、ODA事業を続けていくためには、広報や開発教育の推進を通じてODAに対する国民の理解と支持を得るよう努力しなければなりません。同時に国民参加型のODAを一層推進することにより、ODAを国民に身近なものとすることも大切です。
国民参加型の国際協力の代表例として、青年海外協力隊(JOCV)やシニア海外ボランティア制度があります。2000年度は、それぞれ65か国に対し1,365人(JOCV)と27か国に対し323人(シニア・ボランティア)が新たに派遣されました。なお、青年海外協力隊関連の記述が、2002年4月から使用される小中学校の国語、社会、英語などの教科書の多くに採用されています。
また、第2次ODA改革懇談会の中間報告発表(2001年8月)後、ODAに関する市民対話の一環として2001年8月から10月にかけて、計4回にわたりODAタウンミーティング(注)が開催され、懇談会委員の代表と一般の市民との間で率直な意見交換が行われました。さらに、第I部第3章第3節でも触れました通り、99年度からODAの透明性と情報公開の拡充努力の一環として国民からの公募により選出されたモニターをODA事業の現場に派遣する「ODA民間モニター制度」を開始し、2000年度は、同制度により104名の方が10か国に派遣されました。
ODA事業を継続する上で、国民からの理解と支持は不可欠であり、そのために政府としてもODAに関する情報の一層の公開に取り組んでいます(政策や事業の透明性向上については、第I部第4章第2節(1)及び(2)を参照)。ODA関連のホームページにおいても情報公開の充実化が図られており、外務省、JBIC及びJICAのホームページでは、ODAに関するあらゆる公開情報を迅速かつタイムリーに掲載するとともに、各ホームページともODAをわかりやすく紹介しています。(第V部資料編第12節参照)
また、わが国ODA事業の透明性を高める措置の一環として、円借款案件のより効果的・効率的な実施(案件の発掘・形成・採択)に資するため、円借款を供与する可能性のある案件のリスト(ロング・リスト)を順次確定・公表することとしていますが、2001年12月現在、ロング・リストが確定・公表された国数は4か国(ベトナム、チュニジア、モロッコ、中国)となりました。さらに、JBICでは、情報公開を進めるため、JBIC内に情報・資料センターを開設し、各種広報資料の閲覧体制を拡充しました。なお、外務省ホームページに、無償資金協力案件の応札額、契約額、有償資金協力案件の応札額、応札企業名などについての入札関連情報が掲載してあります。
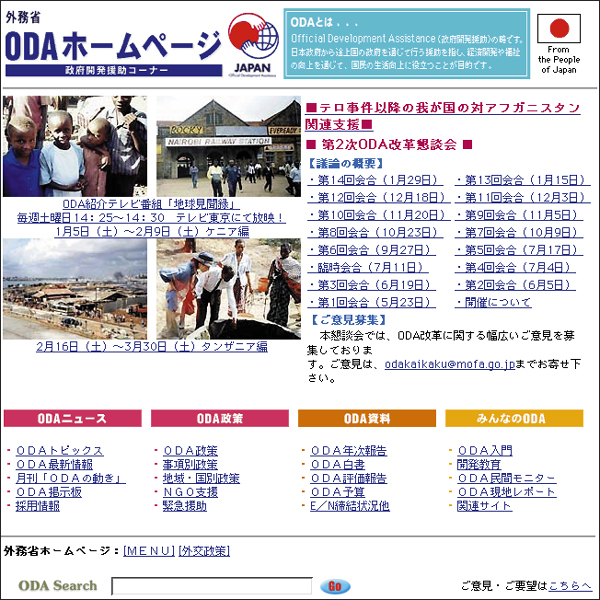
ODAホームページ
2000年4月より、わが国は、ODAの適正実施の観点から、ODA事業の調達に係わる不正防止のための新たな措置を導入しました。これは、国籍を問わずコンサルタント企業や施工・調達業者がわが国ODA事業の調達に関して不正行為を行った場合、それらの企業などを日本のODA事業の契約者として不適格とし、入札・契約から原則として2週間から最長2年間の間排除するものです。この措置により、ODAを巡る不正行為がなくなり、より透明で公正な調達手続きが徹底されるよう政府としても厳格に対応していくことにしています。なお、2000年10月にはエジプトに対する無償資金協力事業の請負業務に関する不正行為について、また、2001年7月にはインドネシアに対する円借款事業の調達に関する不正行為について、右措置に基づきそれぞれに関与した企業を一定期間ODA事業の受注から除外する措置をとりました。
日本のODA供与対象国が150を超える中で、着実に援助活動を続けていくためには、援助活動に従事する関係者の安全確保が欠かせません。援助関係者の安全対策は、ODA大綱上も実施体制等の強化を図る上で重要な課題として位置付けられ、従来からできる限りの措置を講じてきています。しかしながら、援助関係者が活動する途上国の治安状況はさまざまであり、また刻々と変化しているのが実情です。安全を脅かす要因も、テロや暴動、内戦などの極限状況から日常の一般犯罪に至るまで多様です。99年8月には、キルギス共和国でJICAから派遣された4人の資源開発調査団員が武装勢力に誘拐されるという深刻な事件が発生したほか、2000年以降もソロモン諸島、ジンバブエ共和国や象牙海岸共和国において、また、最近では米国の同時多発テロ事件に伴う南西アジア、中東地域における緊張の高まりに伴い、援助関係者が一時的に国外に退避するといった事例が発生しています。
これらの事件等を教訓としながら(注)、外務省は、技術協力の実施機関であるJICAや円借款の実施機関であるJBICと緊密に連携を取りつつ、援助関係者の安全確保のためにさまざまな対策を実施してきています。
具体的には、(1)専門家・協力隊員の派遣に際しては、派遣先の国内治安状況等の安全確認を行い、安全に懸念のある国については派遣決定前に現地での安全確認取り付けを条件とするほか、派遣前の研修において安全対策についての講義を実施し、(2)調査団の派遣等に際しても、安全対策の基本や海外の治安状況等に関し、渡航前の説明を行い、(3)在外公館、JICA事務所等の無い国への専門家や調査団の派遣に当たっては、派遣前のブリーフィングの実施は勿論のこと、当該国と管轄する日本大使館及びJICA事務所での情報収集を行うとともに、通信手段の確保という観点から、インマルサットを携行させています。併せて、(4)在外公館、JICA事務所等のない国に派遣中の専門家については電話・ファクシミリ又はEメールを使い、後述の安全対策アドバイザーが派遣期間中も随時現地情勢について連絡をとるようにしています。
このほか、(5)JICA本部より毎年、特に安全に懸念のある国の中から14~15か国を選び安全確認(対策)調査団を派遣し、治安状況、犯罪の趨勢を調査の上、安全確保の方法等について現地大使館をはじめ当該国治安当局や他ドナー援助機関の関係者と協議しています。さらに、(6)JICA在外事務所においても大使館をはじめ関係者と協議の上、任国の治安情勢を分析し安全対策関連のマニュアルを作成するほか、緊急連絡網を随時更新したり、住宅の防犯設備の設置、警備員の傭用、緊急警報装置の設置を行う等安全対策に努めています。
次に円借款に関しては、JBICとしても円借款事業に関する調査のために雇用した外部企業・団体職員及び個人の安全対策については、JICAに準じた形で対応しているほか、(7)事業実施にかかる契約を受注した本邦企業に対し、危険度が高まりつつある地域の現状を把握し必要に応じて安全情報を提供するとともに、(8)本邦受注企業が当該国からの撤退が必要となった場合には、契約先である現地機関との交渉を支援することにより、企業の安全確保を支援しています。さらに、(9)円借款受注本邦企業に対しては、在外公館への在留届の提出の推奨、安全情報に係る情報ソースの案内、基本的な安全対策上の留意点の紹介、といった内容を含む文書をJBICより送付しており、安全対策の喚起にも努めています。
また、安全対策の実施体制面では、(1)JICAによる現地での治安関連情報の分析能力強化のための安全対策クラークの配置拡充、とりわけキルギス事件の教訓を踏まえ、日本大使館、JICA在外事務所の所在しない国への現地安全対策連絡員の配置促進、(2)JICA本部における治安関連情報の分析能力の強化と現地との連絡強化のための安全情報室の設置や安全対策アドバイザーの配置を行い、こうした措置を通じて安全・治安状況の見直し体制そのものを強化しながら安全対策の一層の改善・強化に努めています。

 次頁
次頁