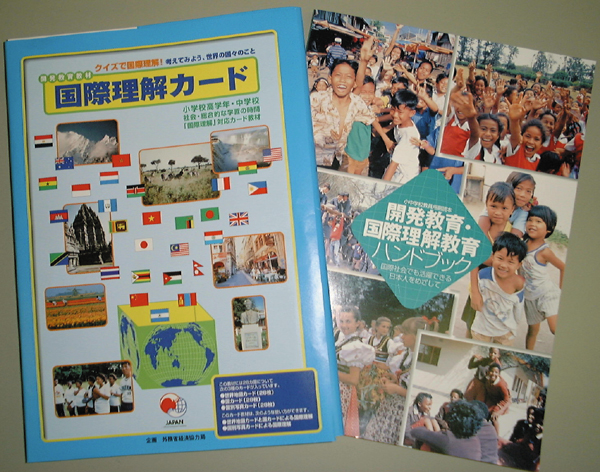本編 > 第I部 > 第3章 > 第3節 双方向の交流(パブリック・プライベート・インターアクション)
国民各層が途上国の状況と開発援助について認識を深め、併せODA事業への積極的な参加を促していくためには、ODAに関する透明性の向上に努め、積極的に情報公開を推進していくとともに、教育の現場をはじめとして国民各層にODAの意義と役割を幅広く伝えていく必要があります。
政府は、ODA事業の入札プロセスに関する一層の情報公開を推進するとともに、事業実績や、評価結果に関する情報をインターネット上のホームページで迅速に公表するなどの努力を行っています。JBIC及びJICAは、2001年度から従来の事後評価の公表に加え、個別のODA事業の実施に先立ち当該事業の必要性、事業の成果見通しや目標等をまとめた「事業事前評価表」を作成し公表するなど、ODAの透明性向上を図るために事業の事前・中間・事後にわたる一貫した評価制度の確立へ向けた努力が続けられています。
もとより、政府側からの一方的な情報提供だけでなく、国民の側からの意見をどのようにODA政策や事業に反映させていくかも併せて重要です。2001年5月に開始された「第2次ODA改革懇談会」では、外務省ホームページを通じて懇談会の議論の概要を紹介するとともに、ODA改革についての意見を幅広く募集しています。また、同年8月の「中間報告」の発表を踏まえ、4回にわたりタウン・ミーティングを開催し(東京、神戸、仙台、福岡)、中間報告の概要を報告するとともに、ODAについて国民との直接対話を行いました。
(トピックス11参照)
(トピックス12参照)
ODAの意義については、特に若い人たちに知って頂くことが重要であり、開発教育の推進が重要な課題として挙げられます。この観点から、政府やJICA、JBICは各地で開発教育セミナーの開催や学校での授業の実施、教材・資料、広報ビデオの配布など情報の提供に努めています。特に、ODA開発教育教材を全国の小中学校に配布してきたほか、2001年度には、さらに充実した内容のODA開発教育キット(国際理解カード、教員用副読本、ビデオの3点セット)を全国各3,000の小中学校に配布しました。
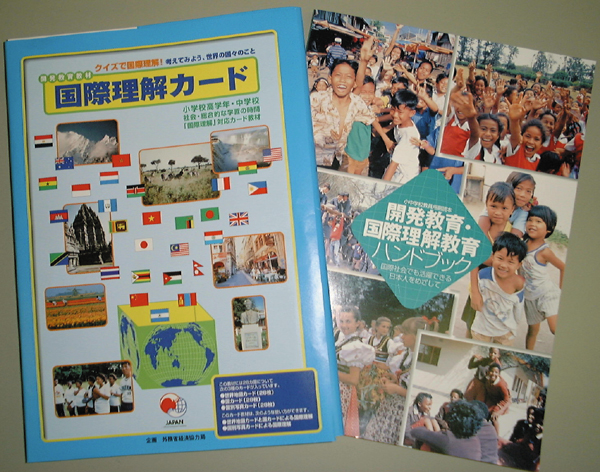
2001年度作成の開発教育キット
また、国民にODAの役割と重要性につき認識と理解を深めてもらう最も効果的な方法は、「百聞は一見にしかず」、すなわち、実際にODAの現場を自らの目で見てもらうことです。この観点から、全国各都道府県から公募の上選出された一般のモニターが、途上国における日本の経済協力プロジェクトを視察するという「ODA民間モニター制度」が99年度より導入されており、国民が直接現場を体感できる機会となっています。また、JBICにおいては、NGO及び地方自治体等との連携をさらに深めるため、円借款業務についての講習やサイト視察、具体的な協力促進についてのワークショップの開催等を行っていく予定です。
政府としてもODA事業に関する情報公開の強化に取り組んできましたが、より透明性の高い、効率的なODAの実施が求められていることを踏まえ、政府と国民の間で双方向に開かれた交流に努めていきます。

 次頁
次頁